「荒れ」と向き合う詩の授業≪実践編≫(2)
子どもたちの「自尊感情」を高め、少しでも「荒れ」が見られる学校の現状を改善しようと、全校全職員で「詩の指導」に注力することが決まったA小学校。その指導法については、校長から「先生方の創意工夫で」という指示のみでした。
前回私の学級では「作戦(1)」を実践し、確かな手ごたえを得ました。今回は「作戦(2)+(2')」実践してみます。
大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長 杉尾 誠
いよいよ、詩作指導実践初日
先生方の貴重な反省を心に刻み、いざ私も担任する教室へと、大量の「作戦(2)」の資料を携えて、詩作の指導に向かいます。
作戦(2)「好きな詩をひたすら視写」
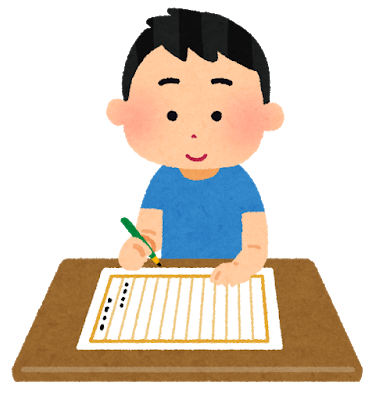
前回の「作戦(1)」で「詩のシャワー」をたくさん浴び、「詩」というものが〈何だか心地よいもの〉と捉えることができるようになった子どもたち。その中でも一番人気だった児童詩を、ありとあらゆるところから集めてきて、オリジナルの「児童詩集」を作り、印刷して全員に配付しました。
その詩集と、「詩作用紙」も同時に配付し、それぞれの心に響いた詩を視写するように指示しました。【学ぶことは真似ること】という格言があるように、詩を書くことを学ぶには、まず詩がどのような形式で書かれているか、どのような心情をもって書かれているか、その世界観を真似して書いてみることが大切だと考えました。
そもそも、学習に向き合うことが難しい子どもたちでしたが、明確な指示のもと、学習課題の道のりがはっきりしている場合は、落ち着いて取り組むこともできるようでした。本時では、読むことに熱中しすぎて書き出しが遅い子は数名いましたが、不満や反抗などの声はほとんどなく、穏やかに、そして和やかな雰囲気で視写に取り組んでいました。また、「先生、もう1枚書いていい?」の声には最大限の賛辞で応え、新しい用紙を手渡しました。
作戦(2’)「好きな詩をひたすら視写+α」
何気ない発言のようですが、この子どもは、自分の詩の世界観を構築しようと、大切な一歩を踏み出し始めているのです。「もちろん、あなたがそう思うならいいですよ」と答えると、その子ではなく「え、いいんや!」とあちらこちらから声が沸きました。どうやら、同じことを考えながら視写している子が、かなりいたようです。
それからというもの、用意した詩作の紙があっという間になくなり、急いで職員室へ増刷に走るなど、おおいに視写が盛り上がってきました。いや、厳密には視写と呼べる一線は、すでに越えていました。素敵な既作の児童詩から、新たにまた素敵な児童詩がたくさん生まれたのです。
詩作指導実践初日の成果
こちらの意図を越えた子どもたちの頑張りに、指導者としてこの上ない喜びを感じました。いや、実際には子どもたちの方がもっともっと、〈不人気〉だったはずの国語の学習で、この上ない達成感を得ていたのでしょう。掲示されたそれぞれの作品を味わいながら談笑し合う姿が、私にそう確信させてくれました。
(続く)

杉尾 誠(すぎお まこと)
大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長
子どもたちの「自尊感情」を高めるため、「綴方」・「詩」・「短歌」・「俳句」などの創作活動を軸に、教室で切磋琢磨の日々です。その魅力が、少しでも読者の皆様に伝われば幸いです。
同じテーマの執筆者
-
兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)
-
京都教育大学附属桃山小学校 教諭
-
さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当
-
戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表
-
小平市立小平第五中学校 主幹教諭
-
西宮市立総合教育センター 指導主事
-
明石市立高丘西小学校 教諭
-
木更津市立鎌足小学校
-
東京学芸大学附属大泉小学校 教諭
-
愛知県公立中学校勤務
-
大阪大谷大学 教育学部 教授
-
神奈川県公立小学校勤務
-
寝屋川市立小学校
-
明石市立鳥羽小学校 教諭
-
千代田区立九段中等教育学校
-
大阪府泉大津市立条南小学校
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない



















 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望








