震災を知らない世代に向けた授業の実践(6) ~小学生でもできることを知る①(さいたま市立植竹小学校 教諭 菊池健一さん)
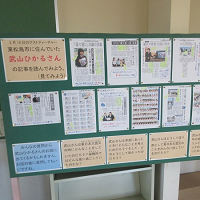
東日本大震災を取り上げた授業を、さいたま市立植竹小学校 教諭 菊池健一さんが連載形式で紹介します。第6回では、ゲストティーチャーを招く前に、震災の語り部について取り上げた新聞記事を読んで理解を深め、質問したいことを考える事前学習をします。
当時小学生だったゲストティーチャー
学年掲示板を活用した武山さんコーナー
前回は、東日本大震災の被災地である宮城県を取材した新聞記者に、被災地の様子や被災地で暮らす人々についての話をしていただきました。子どもたちは、被災地の様子について記者の話を通してさらに詳しく知ることができました。
次に招聘するゲストティーチャーは、宮城県東松島市出身で震災当時小学校4年生だった、武山ひかるさんです。武山さんは現在、群馬県の大学生として勉強をする傍ら、様々な場所で語り部として震災について話をしています。当時、小学生だった武山さんは避難所生活の中で、何か自分にできることはないかと考えましたが、子どもはおとなしくしていければならないという雰囲気の手前、何もできなかったそうです。また、同級生や親友の保護者の方が亡くなったことをなかなか教えてもらえずに、もやもやした気持ちで過ごされたということも様々な場所で話されています。そのような中、中学生になったころから、避難所の管理など自分にできることを自ら実践されてきました。高校生になると震災の語り部活動をスタートし、多くの場所でご自分の経験を語っておられます。昨年行われた東京オリンピック・パラリンピックの聖火ランナーにも選ばれ、東松島市代表として、震災の復興に協力してくれた人々への感謝の気持ちを持ちながらランナーを務められました。
これまでの学習で、児童は東日本大震災がどのような震災であったのかを詳しく学習しました。また、家族や担任から当時の様子についての話も聞き、被災地への関心も高めてきました。その経験をもとに、話を聞く前に、武山さんを取り上げた新聞記事をいくつか読みました。
その中で、
「武山さんはどうして高校生から語り部を始めたのだろう」
「どんな気持ちでいろんな人に震災の時のことを話しているのかな」
「武山さんはどうして、東京オリンピック・パラリンピックの聖火ランナーになったのだろう」
「聖火ランナーとして走っている時に、どんなことを考えたのかな」
「震災の時に僕たちと同じぐらいだった武山さんは避難所でどんなことを考えたのかな」
「避難所での生活はどんなものだったのかな。楽しいことはあったのかな」
と、実際に聞いてみたいことが子どもたちから沸き起こってきました。
子どもたちが武山さんに聞いてみたいと思い、ワークシートに書いたことを事前に武山さんにも伝え、お話に盛り込んでもらうことにしました。
事前学習で武山ひかるさんについて知る
児童の考えた質問を掲示
武山ひかるさんに教室に来ていただき、直接子どもたちに体験を語ってもらいます。そこで、子どもたちは武山さんの新聞記事を読んだり、武山さんが聖火リレーを走る動画を視聴したりして、武山さんへの関心を高めました。武山さんに関する事前学習から児童は実際に話を聞いてみたいことを考えました。
「武山さんは津波に襲われたときにどんな思いだったのだろう」
「武山さんは、小学生だったから不安じゃなかったかな」
「避難所での生活が長かったと言っていたけれど、どんな生活だったのだろう」
「武山さんの家族はどうしていたのかな?助かったのかな?」
「友達が亡くなったということが書いてあったけれど、どんな気持ちになったのだろう?」
など、友達同士で話し合いました。
児童から出てきた疑問などは武山さんに事前にお伝えしておき、お話の中に盛り込んでもらうことにしました。
また、今回の学習はテーマに防災を取り上げていますが、あくまでも「国語科」で意見文を書く学習に位置付けています。そこで、武山さんの話を聞いて大切なことをメモするように指導しました。メモすべきこととして、以下の3点を児童に知らせました。
・武山さんの震災当時の様子やその時に思ったことや感じていること
・震災の時に命を守るために大切なこと
・武山さんがみんなに伝えたいと思っていること
以上の3点を示して、授業に臨むことにしました。
武山さんとの連携で児童の心を揺さぶる
児童が事前に考えた武山さんへの質問を読むと、当時の様子についての質問が多くありました。おそらく、児童は保護者へのインタビューや新聞記者の話などを通して、震災当時のことに関心をもったのだと思います。特に、お話を伺う武山さんは児童と同じぐらいの年齢だったので、もし自分だったらどうなっていたかを知ることができると考えていたのではないかと思います。武山さんにはその点もお話に盛り込んでいただくことにしました。
しかし、児童に学んでほしいことはそれだけではありません。武山さんが子どもの立場で「震災でみんな大変な中、自分にできることは何か」を考え行動したり、現在でも、震災の怖さや防災の大切さを伝えたりしている姿勢についても学んでほしいと思います。そして、学びを通して積極的に家族と防災について考えられるようになっていけると確信しています。武山さんのお話から子どもたちがどんなことを感じるか楽しみです。武山さんと当日の話について打ち合わせ、授業に臨みました。
(実際の授業の様子は次回レポートします。)
文・写真:菊池健一
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 教育つれづれ日誌
教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望










