「先生、あのね」子どもの声を見逃さないアンケートの誕生(前編)
人間関係や学業不振など、子どもたちは様々な悩みを抱えています。社会の変化とともに、その悩みは多岐にわたり、私たち大人が子ども時代のそれとは様変わりしてきています。そんな子どもたちに、少しでも寄り添ってあげる方法はないかと考え、生まれたのが「先生、あのね」です。
東京都品川区立学校 平野 正隆
成長への一歩を
悩みをもつことは、素晴らしいことだと思います。「悩み」は「成長」するための道標となるからです。しかし、それをどう解決すればよいかが分からず、未来を見通せない状況が続けば、悩みはストレスに変わります。ストレスの正しい解消法が分からなければ、成長に向けた一歩を踏み出す勇気すら失ってしまいます。悩んでいることを話せる人、一緒に解決方法を考えてくれる人がいれば、きっと「悩み」は成長へ導いてくれることでしょう。私は、教師として、その選択肢のひとつになれればと思っています。
相談アンケートにひと工夫
各自治体や学校では、相談ダイヤルを設置したり、相談アンケートを定期的に実施したりしています。もちろん、そういった組織的な対策は大切ですが、もっと気軽に話せる環境づくりはできないかと私は考え、まず学校で月1回実施している相談アンケートにひと工夫加えました。
もともとアンケートの質問は「困っていることはありますか」「身近に困っている人はいませんか」「相談したいことはありますか」といった内容でした。もっと肯定的に子どもたちの変化に気付きたいと考えた私は、そのアンケートの裏面に「最近、楽しかったことや嬉しかったことはありますか。最近気付いた友達の良いところはありますか。あれば1つ書いてください」という質問を載せ、記述式でそれにも答えてもらうことにしました。すると、いつもその質問に必ず書いてくるような子が、「ない」と答えるときがあることに気付きました。そんな時は、その子を注意深く観察しながら、他にも何か変わったことがないかを見たり、直接声をかけて話を聞いたりしました。
新たな2つの壁
この方法を数年続けていましたが、当初私が考えた「気軽に話せる環境づくり」とは少し違いました。「担任しているクラスの子ども達と、もっと気軽に話せるようにすることが根本的な解決につながる」そう思った私は、新たな2つの壁にぶつかりました。
一つ目は、積極的に関われる子はいいが、そうでない子が話したくても話せないでいることです。もっと言えば、「話したいけど話せない子」と「話したいわけではない子」の違いも難しいと感じていました。
二つ目は、次の授業の準備などで、一人ひとりとうまく時間をつくれないことです。もちろん、「先生、相談があります。」と言われれば、なんとしてでも時間をつくりますが、それだけでは何も変わらないと感じていました。
「ちょこあいす」がきっかけ
そんなとき、ふと思い出したのが、教員一年目の初任者のときのことです。当時、私は一年生の担任をしていました。国語の授業で「せんせい、あのね」という作文の指導をした際、「せんせい、あのね あさごはんにちょこあいすたべたよ」といった、他愛ない話題を書いた子がいました。それを読んで、みんなで笑い合ったのを今でも忘れられません。環境さえ整えば、子どもたちは何かしらの発信をしてくれるのではないでしょうか。
「先生、あのね」誕生
「環境さえ整えば」そう思った私は、学年に関わらず、担任・( 教科担任として )担当した子に、単元テストのあとに学習の振り返りを兼ねてアンケートを実施し、その設問の一つに自由にコメントできる「先生あのね」を実施することにしました。
下の写真は実際のアンケートです。

平野 正隆(ひらの まさたか)
東京都品川区立学校
研究会での実践報告や校内での若手教員育成などの経験を通して、自分の経験や実践が広く皆様のお役に立てるのではないかと考えております。大人・子どもに関わらず、「明日から頑張れそうです」「明日が来るのが楽しみです」と言ってもらえるのが私の喜びです。
同じテーマの執筆者
-
京都教育大学付属桃山小学校
-
兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)
-
帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師
-
陸中海岸青少年の家 社会教育主事
-
兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭
-
岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任
-
福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝
-
前 山形県立米沢工業高等学校 定時制教諭
山形県立米沢東高等学校 教諭 -
大阪市立堀江小学校 主幹教諭
(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -
戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表
-
静岡大学教育学部附属浜松小学校 教諭
-
佛教大学大学院博士後期課程1年
-
札幌大学地域共創学群日本語・日本文化専攻 教授
-
明石市立高丘西小学校 教諭
-
名古屋市立御器所小学校 教諭
-
高知大学教育学部附属小学校
-
ユタ日本語補習校 小学部担任
-
木更津市立鎌足小学校
-
北海道公立小学校 教諭
-
東京学芸大学附属大泉小学校 教諭
-
東京都東大和市立第八小学校
-
浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授
-
東京学芸大学附属大泉小学校 教諭
-
沖縄県宮古島市立東小学校 教諭
-
岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭
-
神奈川県公立小学校勤務
-
寝屋川市立小学校
-
鹿児島市立小山田小学校 教頭
-
仙台市公立小学校 教諭
-
東京都内公立中学校 教諭
-
目黒区立不動小学校 主幹教諭
-
東京都公立小学校 主任教諭
-
尼崎市立小園小学校 教諭
-
ボーズマン・モンテッソーリ保育士
-
埼玉県公立小学校
-
大阪府泉大津市立条南小学校
-
岡山県和気町立佐伯小学校 教諭
-
合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員
関連記事
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない



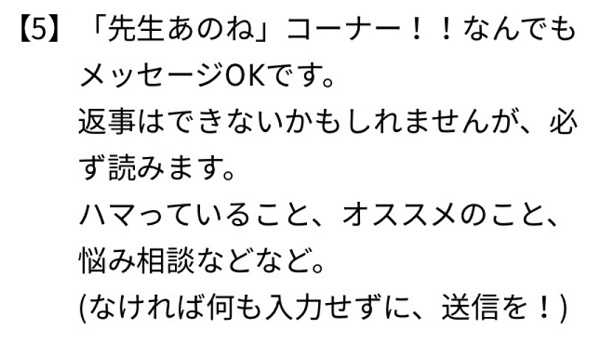






































 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望






