東日本大震災を伝える命と絆の授業(8) 震災を学ぶレポート最終回(さいたま市立植竹小学校 教諭 菊池 健一さん)
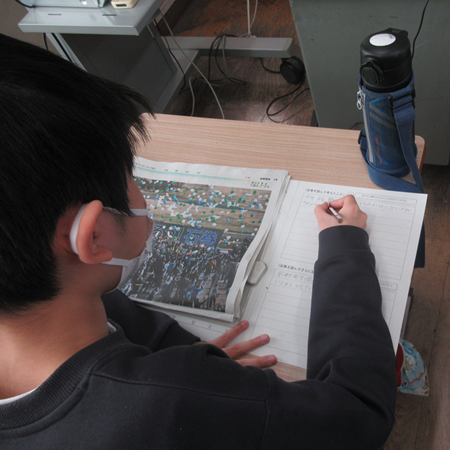
東日本大震災を題材にした授業について、さいたま市立植竹小学校の教諭・菊池健一さんが全8回にわたり連載します。震災から14年。菊池さんは記憶の風化を防ぎ、命の尊さや絆の大切さを子どもたちに伝える授業実践に取り組んでいます。
震災を学び、命と絆について考える活動レポートが最終回を迎えました。第8回では、新聞を教材に子どもたちが命の尊さや防災、他者とのつながりについて深く考えた様子を紹介します。記憶の風化を防ぐ、これからの教育のあり方をあらためて見つめ直します。
3.11の新聞スクラップ

新聞をスクラップする児童
毎年、震災を取り上げた授業のまとめとして、3月11日と12日の新聞を読む活動を行っています。子どもたちは普段から新聞を使った学習に取り組んでいます。毎日、担任が新聞記事を紹介し、子どもたちに情報提供するほか、各授業でも新聞を使って学習に活用しています。新聞は子どもたちと社会をつなぐツールであり、各教科の架け橋として有効な学習材でもあります。これまで新聞を使って学習してきた成果を生かして、今回の震災を取り上げた学びにもつなげました。
2学期にゲストティーチャーとして被災地の方を招き、その方について新聞で学ぶという活動も行いました。新聞には「記録性」があり、震災当時のことを詳しく学ぶことができます。子どもたちは震災について過去の記事や現在の記事から多く学んできました。
「とても大きな震災だったんだね」
「新聞の見出しの大きさから、どれだけ大きい出来事だったか分かるね」
「この記事を書いた記者さんはどんなことを考えたのだろう…」
そんな思いが高まっていました。
今回、地域の新聞販売店に協力いただき、3月11日と12日の新聞を児童の人数分提供いただきました。現在の学習指導要領の理念として「社会に開かれた教育課程」と掲げられています。このように地域の方が子どもたちの豊かな教育活動に協力してくださっていることを改めてありがたいことだと感じています。
子どもたちは早速いただいた新聞に目を通し、スクラップを始めました。
「やはり3.11の新聞には東日本大震災の記事がたくさんあるね」
「ゲストティーチャーとして私たちに話をしてくれた石巻の佐藤美香さんの記事があるよ」
「この記事の写真は、ゲストティーチャーとして来てくださった読売新聞社の関口記者が撮った写真だよ」
「たくさんの人が黙祷をしているね」
など、感想を話しながらスクラップを進めていきました。
子どもたちにとっては、3年生の頃から学んできた東日本大震災の集大成となります。一人ひとりがそれぞれに防災について、命の大切さについて、近くにいる方との絆の大切さについて考えてきました。そのまとめとして、記事を読んだ感想やこれからさらに知りたいと思うことをまとめる活動を行いました。
子どもたちの感想から
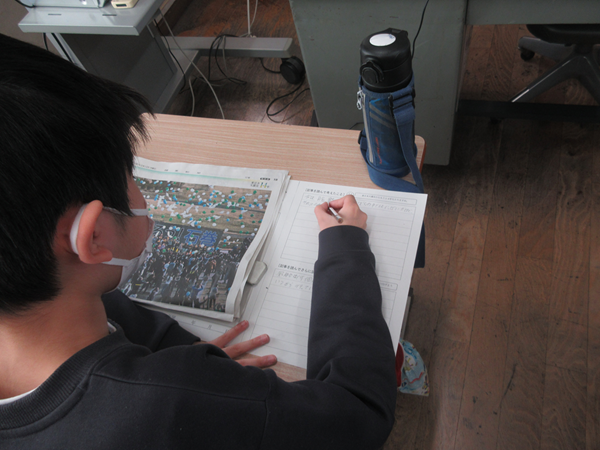
記事を読んだ感想を書く児童
子どもたちがスクラップをしたワークシートには、主に「記事を読んで(記事の写真を見て)考えたこと」そして「今後さらに知りたいと思うこと」が書いてあります。子どもたちが考えたことの中には以下のようなものがありました。
「あらためてたくさんの命が震災で奪われてしまったのだということを知った。これからも防災のことを学んでいきたい」
「2学期にお話を聞いた、石巻の佐藤美香さんの記事を読んで、14年たっても震災の傷はいえないと思った。娘の愛梨ちゃんの成長を本当に見たかったのだと思う」
「記事を読んで、佐藤美香さんが話してくれた『当たり前は当たり前ではない』ということを思い出した。これからもそのことをずっと忘れないでいたい」
「被災地の人は今も傷を負って生きていることが分かった。まだ訪ねたことのない被災地にいつか行ってみたいと思う」
など、自分が学んだことにも触れながら感想を書いていました。
また、さらに知りたいことについては、以下のような記述がありました。
「家族を亡くした方にどのように寄り添えばよいのかを学びたい」
「地域で役に立つために防災について学びたい」
「授業で学んだ、石巻のことについてさらに詳しく調べていきたい」
など、これからもたくさん学びたいという気持ちが表れていました。
私との学びはこれで終了してしまいますが、中学校や高校に進んだ後にも震災のことについて興味をもち続けてほしいと感じています。
震災学習のまとめ

石巻の日和幼稚園のバス事故の慰霊碑
今回の取組を通して、大きく二つのことを感じました。一つはやはり、子どもたちが震災を身近に感じられる工夫をすることが大切だということです。これまで取り組んできた、被災地の方や被災地を取材した記者などから話を聞くという活動は学習をするうえで大変効果的でした。教師自身の私もたくさん学び、授業に生かすことができました。今ではZoomなどを使えば、場所が離れていても授業に登場いただくことができるので、授業の可能性がさらに広がりました。
二つ目は、様々な教科や領域を横断的に行う授業をデザインすることの大切さです。震災を通して学ぶことで、子どもたちは教科等の学習が有機的につながり、また、実社会とも学習内容がつながることを実感できると考えています。そのような授業を仕組むマネジメント力が必要だと感じています。今後も、震災を取り上げた取り組みを継続し、その成果を発信していきたいと考えています。
(今回で、8回にわたりレポートが終了です。ありがとうございました。来年度もまた新たな取り組みにチャレンジします。)
文・写真:菊池健一
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 教育つれづれ日誌
教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望









