最初の読みを次につなぐ物語授業づくり──「感じた」から始まる国語の学び
物語を読んで感じたことは、子どもにとって大切な出発点です。
ただ、そのままにしてしまうと、学びは広がりません。
第2回では、最初の読みを次の時間へつなぐための考え方について、日々の授業を振り返りながら整理します。
明石市立高丘西小学校 教諭 川上 健治
最初の一段目が、学びの質を左右する
前回、子どもの読みが深まらないのは能力の問題ではなく、「階段(=橋渡し)」が用意されていないからだ、という話を書きました。今回は、その階段のいちばん下、つまり最初の一段目について考えてみたいと思います。
ここをどう位置づけるかで、その後の学びの質は大きく変わってくると思います。
物語の授業では、単元のはじめに「読んで感じたことを書く」場面がよく設定されます。いわゆる「初発の感想」ですよね。
子どもたちはとても率直に、自分の思いを言葉にします。「かわいそうでした」「悲しかったです」「ひどいと思いました」。拙い言葉だったとしても、そこには、その子なりの実感が確かにあります。だからこそ、この最初の段階は大切だと感じている先生も多いのではないでしょうか。
ただ、ここで一度立ち止まって考えてみたいのです。その「感じたこと」は、次の学びへとつながっているでしょうか。それとも、その場で完結してしまってはいないでしょうか。
石丸(2014)は、現在の国語授業の実態について、「教師が範読をし、子どもたちが受動的にそれを聞き、その後、おきまりのように初発の感想を書いてというのんびりとした展開になることが多い」と指摘しています。
さらに、通読段階で広く行われている初発の感想についても、形式に多少の違いはあるものの、子どもたちが能動的に活動するものにはなっていないのが現状であるとして、批判しています[i]。
「感じたこと」よりも大切な、「ズレ」に気づくこと
私は、この最初の段階で大切なのは、「感じたこと」そのものよりも、「自分がそう感じたということに気づくこと」だと考えています。
自分の受け止めを言葉にし、友だちの受け止めと比べる中で、「自分の読み方は一つの見方にすぎない」と気づいていく。そして、友だちとの意見と比較し、自分とのズレに気づきます。その気づきが、次の学びの出発点になります。
感想発表で自他の感想を比較し、ズレを見出していくことは、広岡の論を援用した吉川の説明的文章の学習指導過程の第一次に相当します。吉川(2021)は、第一次について「広岡の『ズレの感知』に対応させて『既有知識とのズレを知る』となっている」[ii]と述べています。これは説明的文章の学習指導過程として提唱されたものですが、文章を読む最初の段階としては文学作品での読みにも援用できる論であると考えられます。
また、このズレを「知る」ことは、大島(2019)の言う「個人的興味の発現」[iii]につながります。従来、国語科単元学習で重視されてきた児童の「興味・関心」を起点に出発する活動に代わるものだと考えます。そして、この「ズレ」が、第二次の中心課題になっていくための架け橋となってくるはずです。
初発の感想を、問いとして次の時間へ手渡す
ところが、授業の中では、この初発の感想がそのまま「正解」として扱われてしまうことがあります。「いろいろな感じ方があっていいですね」。この言葉は子どもを安心させ、教室を温かい雰囲気にします。しかし同時に、読みを前に進める力を弱めてしまうこともあります。なぜなら、「ズレ」から引き起こる「問い」が残らないからです。
初発の感想は、本来、次の学びへ向かうための材料です。まだ言葉になりきらない違和感や、どこか引っかかる感じ。それらは、すぐに整理される答えではなく、しばらく手元に置いておくべきものだと思います。ところが、「感じたね」で終わってしまうと、その材料はその場で使い切られてしまいます。
では、初発の感想をどのように扱えばよいのでしょうか。私が大切にしているのは、「感じたことを問いとして保留する」という考え方です。
例えば、『ごんぎつね』で最後に撃たれたごんに対して「かわいそうだった」という感想が出たとします。ここで、その気持ちをすぐに理由づけたり、整理するのではなく、「本当に、ずっとかわいそうな存在だったのでしょうか」「〇〇さんは、ここをごんはうれしかったと表現していますね」といった問いやズレをそっと差し出します。
すると、子どもの中で、自分の直観が揺さぶられ始めます。この揺らぎが生まれたとき、読みは次の段階へ進み始めます。「あっそんな読み方もあるんだ」という感覚が芽生えるからです。まだ、なぜそう読めるのかを、自分の言葉で明確に表現できるわけではありません。なんとなく言わんとしていることが分かるという感覚です。
ここで起きているのは、新しい知識を学ぶことではありません。これまで自分がもっていた見方や考え方を、もう一度見つめ直そうとする動きです。
この段階では、まだ「誤解」や「葛藤」、「思いやり」といった抽象的な言葉を教える必要はありません。むしろ、そうした言葉が与えられていないからこそ、子どもたちは本文の中を行き来しながら、自分なりに意味を探し始めます。ここで行われているのは、「概念」を理解することではなく、その準備段階です。
また、この最初の段階は、子どもたちがどのような読み方をしているのか、どのような力を使って文章を読んでいるのかを見取る大切な場面でもあります。それは、評価のためだけではありません。この先の授業で、どのような読み方を意識させ、どのような問いを用意すればよいのかを考えるための、大切な手がかりになります。
初発の感想を大切にするとは、感じたままにしておくことではないと、私は思っています。揺さぶり、保留し、問いとして次の時間へ手渡すことです。最初の読みで生まれた違和感が、次の時間にも子どもの中に残っている。その状態こそが、学びが動き始めている証だと感じています。
次回は、この保留された「直観」を、どのようにして作品の「概念的理解」へと「橋渡し」していくのかについて書いていきます。
参考資料
- [i] 石丸憲一「文学の授業における、いわゆる三読法を見直す:通読段階での読みの指導を中心に」創価大学教育学部・教職大学院『教育学論集』、第65巻、2014年、p.23
- [ii] 吉川芳則『論理的思考力を育てる!批判的読み(クリティカル・リーディング)の学習モデル―説明的文章の授業が深まる理論と方法―』明治図書、2021年、p.40
- [iii] 大島純、千代西尾祐司『主体的・対話的で深い学びに導く学習科学ハンドブック』北大路書房、2019年、p.54

川上 健治(かわかみ けんじ)
明石市立高丘西小学校 教諭
クラスの全員が楽しく学び合い「分かる・できる」ことを目指して日々授業を考えています。また、様々な土台となる学級経営も大切にしています。
同じテーマの執筆者
-
兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)
-
帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師
-
京都教育大学附属桃山小学校 教諭
-
さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当
-
兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭
-
岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任
-
福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝
-
大阪市立堀江小学校 主幹教諭
(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -
大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長
-
戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表
-
佛教大学大学院博士後期課程1年
-
小平市立小平第五中学校 主幹教諭
-
西宮市立総合教育センター 指導主事
-
長野県公立小学校非常勤講師
-
木更津市立鎌足小学校
-
北海道公立小学校 教諭
-
東京都東大和市立第八小学校
-
東京学芸大学附属大泉小学校 教諭
-
愛知県公立中学校勤務
-
大阪大谷大学 教育学部 教授
-
東京都品川区立学校
-
岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭
-
神奈川県公立小学校勤務
-
寝屋川市立小学校
-
明石市立鳥羽小学校 教諭
-
仙台市公立小学校 教諭
-
東京都内公立中学校 教諭
-
目黒区立不動小学校 主幹教諭
-
東京都公立小学校 主任教諭
-
尼崎市立小園小学校 教諭
-
千代田区立九段中等教育学校
-
埼玉県公立小学校
-
大阪府泉大津市立条南小学校
-
岡山県和気町立佐伯小学校 教諭
-
合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない





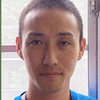




















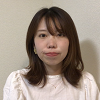











 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望





