「振り返り」に値する中味(授業)が大事 子どもの声を授業に反映させる(先生の通信簿)編(9)
「子どもにとって中味のある授業」を創ること。それは、授業を創る主体が誰かということと深くかかわってくるのではないかと思います。授業を創るのは、教師だけではありません。そう、子どもが授業の主人公です。子どもが授業をどう見ているかをキャッチして、子どもの声を次の授業に反映させていく、そういう教師の姿勢が必要ではないでしょうか。そのための手立ての一つ。「先生の通信簿」について綴ってみたいと思います。
浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授 川島 隆
評価されるのは、誰?
あっという間に、7月を迎え、1学期も終盤を迎えようとしています。
前号では、「魔の6月」の話でしたので、7月は、何て言えばいいかって言ったら、「評価の7月」でしょうか。
ちょっと待ってください。
「評価」とは、誰が誰を対象にするものでしょう?
「先生」が、「子ども」を評価するものって考えるでしょうか。
これには、子どもも賛成するでしょう。
評価の代表的なものと言えば、「通信票」
それをつけるのは、先生ですから。
受け取るのは、子どもですから。
国際的な評価で言うと
PISAは、皆さんよく御存知だと思うのですが、この調査にしても、評価する対象は、子どもになります。
義務教育修了段階(15歳)において、これまでに身に付けてきた知識や技能を、実生活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用できるかを測定するものです。
簡単に言えば、子どもの学力の国際比較って言ってもよいでしょうか。
この調査結果が教育施策にも影響を及ぼすのですから注視せざるを得ません。
評価されるのは、子どもだけではない!
でも、こんな調査があるのを御存知ですか?
PIAAC(ピアック)という調査です。
PISAやTIMSSと同じように、OECDが主体となって実施している国際調査ですが、調査対象は、成人、参加する各国の成人(この調査では16~65歳)が持っている「成人力」について調査するものなのです。
知識量を問うものではありませんが、課題解決力や思考力を測定する、言わば大人の学力と言ってもよいではないかと思います。
私たち教員が求めているのは、むしろ大人になって、社会に出てどれだけ自己の力を発揮し、目の前の課題を解決しながら生きていけるか、社会貢献していけるか、ということではないかと思うのです。
ですから、大人の私たちの学力がいかほどかを評価することは、とっても意味深いのではないかと思います。
無論、このPIAACを持ち出すまでもなく、「教職員評価」や「学校評価」等の評価も1年の節目ごとに、職員室で登場してきているのではないかと思います。
また、それらには違った意味合いがあると思います。
つまり、評価の対象は?
つまりは、評価の対象というのは、子どもだけではなく、大人であっても、その対象となっているのだと思います。
1学期の節目を迎える今、子どもの評価をしていく私たち。
その評価者は、適切な力を持って評価にあたっているのか。
そして、その子どもの評価は、適切なのか。
ちょっと厳しいようですが、そんな見方も一方で必要ではないかと思うのです。
自分が受け身的に「評価」されるのは、誰しもいい気持ちがしません。
ならば、私たち自らが主体となって評価をされてはどうでしょうか?
子どもに先生を評価してもらう!
そこで、私が学級担任のころ、取り組んでいたのが「先生の通信簿」です。
終業式の日、子どもたち一人一人に通信簿を渡す時間がありますよね。
それぞれに一言伝えたいし、子どもの声も聴きたいので、少し時間がかかります。
すると、結構な待ち時間が生まれます。
そんな時間を活用して、子どもたちに、こう言うのです。
「今から、みんなに『先生の通信簿』をつけてもらいたいと思います」
「どんな観点から評価してもらっても構いません」
「先生も、みんなの評価をしているのですから、先生にも、みんなから『先通信簿』をくださいね」
「正直に書いてください。このことが成績に影響することはありませんから」
子どもたちは、「え~」と反応しながらも
「川島先生は、授業中、結構……なんだよね」など
結構前向きに受け止めて書き進めていきます。
子どもたちが帰った教室で
終業式の日。子どもたちが下校していなくなった教室。
子どもたちの荷物もほとんどなく、少し寂しげな教室で子どもたちが書いてくれた、作ってくれた『通信簿』を一人で読むのが楽しみでした。
「国語 分かりやすさ 物語の人物の気持ちを考えたり、ローマ字では書き方を教えてくれて分かりやすい」
「社会 教え方 『なぜ?』とか『どうして?』という疑問をみんなで解決できていい」
「体育 分かりやすさ お手本を見せてくれて分かりやすいけど、一人一人じっくり教えてほしい」
こんな感じで、子どもたちの率直な意見、評価は、結構心に響いてくるのでした。
この子は、こんなふうに考えてくれていたのか。
この授業は、子どもからすると、楽しくなかったのか。こんな受け止めをしていたんだ。
私の知らなかった子どもの思いが伝わってきます。
そして、2学期からは、「こうしなきゃ」と正直思わせてくれるものです。
子どもたちの思いに応えるべく頑張らなくっちゃと元気をもらったりします。
むすびに
子どもたちと中味の濃い授業を創っていくためには、先生だけでなく、子どもの声を反映させていく必要があると思います。
その一つが子どもたちによる、授業評価であり、先生の通信簿。
令和の日本型学校教育に示される「一人一人の子供を主語にする学校教育の実現」の一歩につながっていくのではないでしょうか。

川島 隆(かわしま たかし)
浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授
2020年度まで静岡県内公立小学校に勤務し、2021年度から大学教員として、幼稚園教諭・保育士、小学校・特別支援学校教員を目指す学生の指導・支援にあたっています。幼小接続の在り方や成長実感を伴う教師の力量形成を中心に、教育現場に貢献できる研究と教育に微力ながら力を尽くしていきたいと考えております。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない



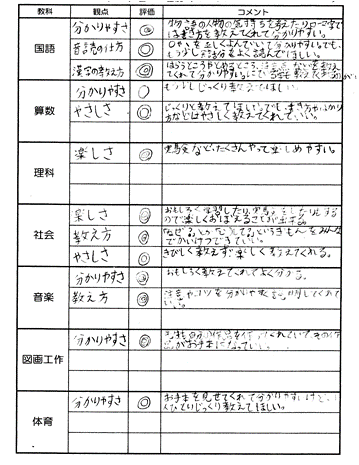
 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望









