スポーツは全ての人のために―発達性協調運動障害の視点から運動発達支援へ―
東京都立南花畑特別支援学校 主任教諭・臨床発達心理士・自閉症スペクトラム支援士(standard) 綿引 清勝
「手と知能の、どちらか片方では価値がない。 ―――フランシス・ベーコン」
これは、シーラ・A・ヘンダーソン先生が運動発達における問題点――理論的問題の文頭で引用していた言葉ですが、障害のある子どもたちの中には、運動能力を十分に獲得することが難しい子どもがいます。
「走り方がぎこちない」、「上手に泳げない」、「ボールを遠くに投げられない」、「ダンスでは、周囲とは全く別な動きになってしまう」こういったことは、体育の時間に目立つことが多いですが、体育の場面以外にも運動の困難さは「姿勢が悪い」、「書字が苦手」、「蝶結びができない」、「ハサミがうまく使えない」といった手指を使った活動場面にも見られます。
このような身体の動きをコントロールするのは協調(coordination)と言われる脳の機能が大きく関係しています。ところが、動きのぎこちなさが発達の問題であるという理解はまだまだ弱く、本人の努力不足や保護者の育て方といったことに問題の焦点が向けられてしまい、苦しい思いをしている子どもや保護者は少なくありません。
協調とは見る、触るといった感覚、筋肉や関節の感覚、平衡感覚など、様々な感覚の情報を整理し、運動として身体を動かす脳の機能ですが、運動やスポーツに限った話ではなく、衣類の着脱、食事の時の箸の使い方といった日常生活動作や書字、ハサミの使い方、折り紙などの手指を使った細かい作業、そして、縄跳びやボール運動に加え、姿勢の保持、物を運ぶ、ボディ・イメージなど学校生活や日常生活の多岐に渡り重要なキーワードとなっています。ゆえに、この協調機能のつまずきが、体育の授業のみならず、社会性や気持ちの安定、自尊感情などとも大きく関連しているという理解が必要です。
運動とスポーツとは
運動と体育やスポーツがほぼ同じような意味で使われていることがありますが、「運動(=motor skill)」を厳密に定義すると走る、跳ぶ、投げるといった粗大運動(=gross motor skill)と、文字を書くことや紐を結ぶといった細かい動きの微細運動(=fine motor skill)に分かれます。
一方で、スポーツとは陸上、サッカー、バレーボールなど一般的によく知れている競技的なものだけでなく、山登り、釣り、ハイキングなど、様々な身体活動の総称で、必ずしも競技性をもったものだけを指すのではありません。例えば、ボルダリングやキャニオニングといった人工的な建造物や自然を生かした活動が含まれます。ですので、運動の困難さがあったとしても、可能であれば何か一つでよいのでスポーツを享受する心が育って欲しいと願っています。
生涯スポーツを獲得することは、相手と競わなくてもよいのです。他者と比較するから劣ります。自分自身と向き合い、何ができるようになったか?そして、何にチャレンジしたか?を大切にしていけるとよいのですが、そのためには、キーパーソンが必要になっていくでしょう。ですので、学校教育はその役目を大きく担っているのではないかと考えます。
トップアスリートを育てるのではなく、一人一人の心を拾い、生涯スポーツの措置を養う。それは通常の学校でも特別支援学校でも同様です。ゆえに、体育を担当する教員の責任は大きく、「できたorできない」で判断するのではなく、子どもたちの「何ができるようになったのか」を丁寧に見ていく必要があります。
発達性協調運動障害とは
では、どう丁寧に見ていけばよいのでしょうか?その視点の一つに協調運動に対するつまずきの理解が挙げられます。
以前、「不器用なこどもたち」でその定義や概要に触れましたが、協調運動の困難さによる発達障害として、「発達性協調運動障害(deveropmental coordination disorder;DCD)」があります。このDCDの割合は、6~10%と言われており、決して少ない割合ではありません。実際に通常学級の先生方に意見を聞くと、「たしかに協調運動のつまずきが気になる児童・生徒はいる」という回答が多く聞かれます。ところが、「発達障害者支援法」の条文には具体的に表記されていないこともあり、この診断名を知らない教員は、まだまだたくさんいるのが現状です。ですので、本来運動のつまずきは、学校生活全般に影響することが考えられることから子どもたちの支援を考えていくにはとても大切な視点のはずが、残念ながら見落とされてしまうことがあります。
発達障害があっても、周囲の理解や支援と本人の努力が実を結んだ事例として、トム・クルーズ氏のLD(読み障害)は、広く知られてきました。実はDCDにもこのようなケースは話題として挙がっており、その代表が映画「ハリー・ポッター」で知られるラド・クリフ氏です。彼は、蝶結びができずに苦しんだことをはじめ、学校では何をやってもうまくいかないことが、とても辛かったと述べており、このことは、いくつかの文献やインターネットなどでも取り上げられ、少しずつではありますが、DCDが知られていくきっかけとともに、同じような苦しさをもった人たちには、大きな励みになっていると言えるでしょう。
DCDは、他の発達障害との併存についても様々な報告がされており、「不器用なこどもたち その2」でDAMP症候群(Deficits in Attention, Motor control and Perception)と呼ばれるADHDとの併存診断について概説させていただきました。また、自閉症との関連についても古くから注目されており、レオ・カナーやハンス・アスペルガーの論文においても、自閉症児の動きのぎこちなさについて指摘されていたようです。
筑波大学の澤江幸則先生は、著書の中でアスペルガー氏の論文から以下の内容を引用していました。
「…彼の動きは、自然ではなく…ひとまとまりの動きとして運動システムが適切に協調しながら展開することはなかった
不器用な子どもは、たちの悪い(atrocious)書き方で、…ペンが彼の言うとおりに動くことはなかった」
以上のように、特にアスペルガー氏の報告においては、ぎこちない動きや奇妙な姿勢をアスペルガー症候群の主要な症状として主唱されていたようです。
自閉症児の運動発達から
自閉症児の運動のつまずきは上述した通りですが、私がこれまでに出会ってきたASDの方全てが運動のぎこちなさが見られるわけではなく、必ずしもそうではないケースがいくつかありました。ゆえに、運動のつまずきをASDの主唱とすることは、もう少し多角的に考えていく必要があると感じています。
一方で、運動を苦手とする子どもたちが多いことは否定できません。運動発達は一定の指標に沿って、連続的・段階的に進んでいきますが、どうやらASD児の運動発達は必ずしも定型発達児とは合致せず、独自の道筋をたどっていくようなことが仮説的に考えられるようです。
この点については、澤江先生が「ASDに見られる不器用さは、必ずしも運動発達上の障害を根底にしたものではなく、ASDの中核症状、とくに社会性の障害がその背景要因として位置付いているのではないかと考えられるのである」と述べられているように、運動のつまずきがあるからASDであると一義的に捉えるのではなく、その関連性を考慮しながら彼らの運動に対するつまずきを理解し、支援を考えていく必要があるのではないでしょうか。
ある広汎性発達障害の児童は、ボール運動の投動作に苦手意識をもっていましたが、現在ではだいぶ気持ちが変わってきました。それは、単純に技術を習得して上手になったからということだけが理由なのではなく、自分でもやればできるんだという経験や結果よりも改善に取り組んだプロセスの大切さに気付けたからだと捉えています。そのためには、運動のステップを丁寧にルーティーン化し、スモールステップを踏みながら成功体験を重ねることが必要で、障害特性に応じた環境調整や教材の工夫が求められます。
アダプテッド体育・スポーツの視点から
過去の投稿の中でアダプテッド・スポーツというキーワードを取り上げてきました。詳細については過去の記事にある「運動会にアダプテッド・スポーツの視点を取り入れる」をご参照ください。
そこでは、活動に参加する人たちの実態に応じて、競技内容やルールを工夫することの大切さを書かせていただきましたが、実際に行われているスポーツ大会などでは、競技性が上がるほど「人がスポーツに合わせる」という状況が起こっていきます。
これは、学校教育の中ではどうでしょうか?体育の授業において、授業内容が集団に応じて工夫されているのか?授業者の思いに児童・生徒がこたえるように設定されているのか?なかなか難しい側面があります。
しかしながら、なんでもかんでもアダプテッド・スポーツだと言って新しいルールや競技内容に変えていく必要があるかと言えば、必ずしもそれが正解ではないと言えるでしょう。バレーボールを例にすると、成人男子のネットの高さは2m30cmです。これは成人男子の公式よりも低い高さですが、これ以外に大きくルールが違うことはありません。その理由は、「いずれ健常者と一緒に活動するときに、それまでの経験が生かせるように」という社会参加の視点があります。
つまり、ここで最も重視されなければいけないのは、「その人自身に活動をどうかえすか」という視点であり、「またASDであっても、その認知特性や社会性発達レベルに応じて、必ずしもASDの定番とされている「絵カード」を使う必要はない。ホワイトボードに文字だけの情報で十分な子どももいれば、絵カードでなく実物を呈示する方がよい子どもだっている。指示を出す際においても、抽象表現を避けた方がよいか、単語だけで指示した方がよいかなど、子どもの言語理解の特性を知ることでadaptationの内容は異なる。それは、その子どもの認知や社会性、運動などの様々な発達特性の実態を把握するという試みの必要性を示唆するものである。そう、adaptationとは、スポーツや体育に参加する「その『人を知る』ことから始まるのである。」と澤江先生が述べられているように、本人のニーズに対して、先を見据えてどうこたえていくかということが大切です。
まとめにかえて
今回は最後の投稿ということで、改めて運動の支援について書かせていただきました。これまでのまとめという視点から、内容が重複するところもありますが、やはりまだまだ社会全般で理解が必要なところだと感じています。
私の周りにも「体育が苦手」、「体育が嫌い」という方が結構います。私も種目によって得意・不得意があり、ボウリングは今でも苦手でアベレージは60程度です。頑張ってはいるのですが、なかなか上達しません。
ただ、友人とボウリングに行くこと自体は楽しいと思えます。スコアがもっと出せればいいなぁという憧れはありますが、スコアのためにボウリングをやっているわけではなく、友人と活動をつなぐツールになっています。ですので、ぼちぼちと楽しみながら余暇として取り組めているのかと感じます。また、簡単な登山やスノーボードも年に数回程度ですが、自然を感じる楽しみとして生活に根付いています。
一方で、競技として柔道をやっていましたが、引退してからこの10数年は、一度も柔道着に袖を通すことはありませんでした。毎日嫌というほど練習していましたが、今は残念ながら生活の中には運動習慣として根付いているとは言えません。ただ、少し形を変えて、「やるスポーツ」から「みるスポーツ」へと変わり、オリンピック中継などは毎回録画するほど楽しみにしています。
スポーツは一部の競技者のためにあるのではなく、様々な形で全ての人にあるべきものだと考えていますが、そのためには、やはり他者に認められる経験や達成感が必要だと思います。そのために、学校教育では何が求められ、何ができるのかを今後も模索していきたいと思います。
近年、運動発達への理解や関心が高まり、様々な著書が発刊され、シンポジウムなども開催されてきました。また、兵庫県立リハビリテーション中央病院 子どもの睡眠と発達医療センターの中井昭夫先生を中心に、世界的にも最も広く使われ国際ガイドラインでも推奨されているMovemento Assessment Battetry for Children 第2版(M-ABC2)の日本語版も開発が進んでおり、アセスメントとしてもこれまで以上に浸透していくことが期待されています。私のような体育教師は、これまでの体育のあるべき論を捨て、もう一度子どもの実態やニーズに立ち返ることで、子どもたちが「楽しい」と思える授業づくりから一人一人の特性に応じた運動発達支援を考えていかなくてはならないでしょう。
さて、この一年半、つれづれなるままに特別支援教育について思うことを書かせていただきましたが、本稿をもって筆を下ろさせていただくこととなりました。様々な出会いの中で私自身大きな学びがありました。また、学会や研修会等でお声かけいただけたことは、とても嬉しく感謝しております。今日まで拙文にお付き合いいただけたことを、心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。
参考文献
・阿部俊彦監修、清水由、川上康則、小島哲夫編著、「気になる子の体育 授業で生かせる実例52」、学研
・中井昭夫(2015)、「チャイルドヘルス 子どもの保健と育児を支援する雑誌」、pp.6-9、診断と治療社
・リサ・A・カーツ著、七木田敦、増田貴人、澤江幸則監訳、泉流星訳(2012)、「不器用さのある発達障害の子どもたち 運動スキルの支援のためのガイドブック」、東京書籍
・澤江幸則、川田学、鈴木智子編(2014)、「<身体>に関する発達支援のユニバーサルデザイン」、金子書房
・澤江幸則、木塚朝博、中込四朗編著(2014)、「身体性コンピテンスと未来の子どもの育ち」、明石書店
・辻井正次、宮原資英編著(1999)、「子どもの不器用さ その影響と発達的援助」、ブレーン出版

綿引 清勝(わたひき きよかつ)
東京都立南花畑特別支援学校 主任教諭・臨床発達心理士・自閉症スペクトラム支援士(standard)
東京都内の知的障害特別支援学校で中学部、高等部を経験後、現在は小学部の自閉症学級を担任。自身の実践を振り返りながら、子ども達が必要としている支援とは何かを考えていきたいと思います。
同じテーマの執筆者
-
東京都立白鷺特別支援学校 中学部 教諭・自閉症スペクトラム支援士・早稲田大学大学院 教育学研究科 修士課程2年
-
富山県立富山視覚総合支援学校 教諭
-
北海道札幌養護学校 教諭
-
東京学芸大学教職大学院 准教授
-
東京都立城北特別支援学校 教諭・臨床発達心理士
-
福島県立あぶくま養護学校 教諭
-
東京都立港特別支援学校 教諭
-
京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会
-
福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士
-
信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭
-
在沖米軍基地内 公立アメリカンスクール 日本語日本文化教師
-
静岡市立中島小学校教諭・公認心理師
-
寝屋川市立小学校
-
目黒区立不動小学校 主幹教諭
-
合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない



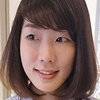




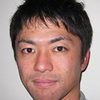






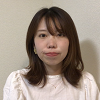


 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望









