オリンピック・パラリンピック教育を愁う
3月になりました。年度のまとめと新年度の準備など、慌ただしい日々が続いているかと思います。久しぶりになりますが、今回は最近の教育課題から自分が感じている違和感について、つれづれなるままに思いを綴らせていただきました。
東京都立南花畑特別支援学校 主任教諭・臨床発達心理士・自閉症スペクトラム支援士(standard) 綿引 清勝
1 はじめに
2020年に東京でオリンピック・パラリンピックが開催されることになり、今まで以上にスポーツや運動に対する関心も高くなってきていると感じています。教育現場においても、チャンピオンシップスポーツだけでなく、不器用な子どもたちに対する相談も増えてきており、学校や家庭など、様々なところで課題意識が出てきたことは、とても嬉しく思うとともに、自分自身もっと勉強をして、実践力を高めていかなければならないと背筋が伸びる思いです。
さて、このような教育現場の現状において、東京2020大会に向けた様々な取り組みが学校教育の現場に求められています。これは、我々教育現場の人間にとってこの東京2020大会に向けて子どもたちへ何を教えるのか?何を伝えていくのか?ということが大きく問われていると言えるでしょう。
今回寄稿しようと思ったきっかけは、大坂なおみ選手のグランドスラム優勝でした。私はスポーツを見ることは好きなので、サッカーや野球などはよくTV観戦し、録画もします。今回の大坂選手の試合もTV観戦をしていました。息をするのを忘れてしまうような緊張感のあるラリーが繰り返される中、双方ともに素晴らしいパフォーマンスが繰り広げられています。あれだけのパフォーマンスを発揮するためには、どれだけの時間と労力を費やしたのだろうかと考えると、ただただ、尊敬の念も含めて素晴らしいという言葉しか出てきません。そして、優勝の瞬間には、私自身同じ日本人選手が優勝したということも含めて、とても嬉しい気持ちになりました。興奮して、眠れなくなるほどです。
そこから数日間、TVやインターネットなど、様々な形で優勝についての報道がありました。ところがそこでの内容が、これまで感じていたオリンピック・パラリンピック教育に対する違和感の根っこの部分と重なり、やっと自分でもその理由が理解できたように感じました。
2 無意識に潜む差別感と教育実践の矛盾
東京2020大会へ向けて、学校の教育内容にもオリンピック・パラリンピック教育が教育課題の一つとして入ってきています。これは、日本のスポーツ教育の理解・推進には大きな追い風になるでしょう。しかしながら、ちょっと引いて考えると学校には○○教育という言葉がたくさんあります。安全教育、防災教育、健康教育、交流教育、情操教育、ICT教育など、探せばまだまだ出てきますが、こういった教育課題を解決しつつ、さらにオリンピック・パラリンピック教育を題材として扱い、新学習指導要領に準じて教育活動を行なっていくということは、人によっては多忙感を感じることもあるかもしれません。言い換えれば、学習指導要領が新学習指導要領へ移行することに伴い「主体的・対話的で深い学び」を実現するという喫緊の教育課題と並行して○○教育にも取り組んでいくというミッションには温度差があると言えるのかもしれません。
このような教育課題の解決は、多忙感が先にきてしまうと「大変だからやりたくない」という気持ちが出てしまい、建設的な取り組みは想起しづらいでしょう。あるいは、管理職からのトップダウンだとしても「やらされている教育」では、結局のところ時間数をどう消化して報告書を作成するかという消極的な方向で議論が展開されてしまい、教育活動の本質から外れる危険性も考えられます。オリンピック・パラリンピック教育が現場に降りてきた際に、私が感じた最初の違和感は正にそこでした。
ただでさえ、日々の教育活動で余裕がない教員集団にとっては「じゃあ何やる?」、「何やっていいかよくわからないから、とりあえずパラリンピアンを呼んでパラリンピックの種目の体験でもやっておけばいいんじゃない?」といった声が聞こえてきそうです。こういった消極的な発想の「根幹」がのどの奥に突き刺さった小骨のようにずっと気になっていました。すなわち、オリンピック・パラリンピック教育におけるねらいがズレてしまって、教育的な意味や意義が適切に押さえられていないのではないかという違和感です。
この違和感を踏まえて大坂選手の話題に戻すと、グランドスラム優勝に伴い、「アジアで男女初の世界ランク1位」という大きな見出しがたくさんありました。確かに、テニスプレイヤーとしては快挙です。しかしながら、日本を代表するプロテニスプレヤーには国枝慎吾選手がいます。彼は車椅子テニスの選手ですが、シングルス・ダブルスの世界ランキング1位だけでなく、男子における歴代の世界大会優勝回数も記録を保持しており、間違いなく世界の超一流プレイヤーです。
ゆえに、ネット型スポーツとしての「テニス」という大きな括りにおける「テニス」と「車椅子テニス」という分け方、つまり「健常者のスポーツ」と「障害者のスポーツ」という分け方は、我々が無意識的にもっている差別意識が目の前のスポーツの捉え方に隠れていることを示唆しているのではないか?という疑問が出てきます。そして、この問いがオリンピック・パラリンピックに対する違和感の根幹にあるのではないかと感じました。
3 オリンピック・パラリンピック教育で目指すもの
大坂選手の優勝の話題から見えてきたこの問いは、我々の社会全般に問いかける大きなテーマだと考えています。「一緒(多数)と違う(少数)」を議論することの難しさや、それ自体に触れることを避けようとする空気など、周辺の問題も含めてとても大切なことだと感じる一方で、筆者のようないわゆる「大人たち」は、そこを学校教育では学ばずにきています。つまり、今の社会の姿がこれまでの公教育の成果だとするならば、今回のようなテニスの問題をこれからの子どもたちに問いかけ、問題解決の姿勢を育てていく必要があると言えるでしょう。そして、こういった発想と自覚を教育現場がもてるようになれば、必然的に「オリンピック・パラリンピック教育で何を学ぶか」という問題は実にシンプルで、現代のような無意識的な差別意識についても、障害の有無では無く、一人一人の人間と向き合うことの大切さを知ることの本質が見えてきます。
それが見えてくることによって、障害とは個人の特性や優劣を議論することではなく、その特性が周囲の無理解や誤解といった「障壁」によって生じる困難さ(=生きづらさ)であることが理解されていくことにつながるのではないでしょうか。そして特別支援教育における「特別」をともすれば「当たり前」にしていくことの道筋を深く議論し、考察していくことが、ひいては「健常者と障害者」、「教師(正しい)と子ども(間違い)」という偏見もなくなっていくように思います。
そのような流れの中においては、「オリンピック・パラリンピックを教える」ことが大きな目標でなく、「オリンピック・パラリンピックを介して共生社会の実現のために何が必要かを自分たちで考える」ことにつながっていくのではないでしょうか。そしてその題材として、オリンピックとパラリンピックを扱っていくことで、これまで知らなかったパラリンピアンのパフォーマンスや障害とは何かということを知り、直接的なスポーツの体験を通じて具体的な関わり方や、ノンバーバルなコミュニケーションのあり方を考えるきっかけが生まれてくる。その結果、このような経験を経て、我々の世代では理解し、生活の中で実現しきれていない多様な人間の理解やインクルーシブ教育の理解・促進にもつながっていくのではないかと考えます。
4 インクルーシブ教育の実現に向けて
昨年の秋に、インクルーシブ・バレーボール大会を企画・運営しました。一昨年の秋から始めて、第二回になります。成人の知的障害者の方と学校の教員、大学生など合計で約30名の参加がありました。内容は、様々な参加者の属性に応じて3チームを編成し、チームビルドからゲームまでを行いました。ここでのポイントは、単に参加者間で一緒にチームを編成して勝敗を競ったり、障害者スポーツの体験をしたりするのではなく、チームビルドから丁寧にコミュニケーションを図っていくことです。また、ゲームも参加者の実態に応じてアダプテッド・ルールを取り入れ、ゲームでも技術的な差から極端な結果に偏りそうな場面では、その場でルールの調整を行いながら大会を実施しました。
ですので、ウォーミングアップを兼ねたチームビルドも、実に1時間半程度時間をかけて、じっくりと行いました。その結果、大会の雰囲気は誰もが楽しめる穏やかな雰囲気で実施ができただけでなく、参加者のアンケートを見ると一般参加者の回答の中には、「これまでスポーツに苦手意識がありましたが、最初のウォーミングアップが一番楽しかったです」といった意見や「はじめて成人の知的障害の方と交流をしましたが、皆さん自分よりもバレーボールが上手で驚きました」というような参加者の意識変容に加え、知的障害の方からは各家庭に戻ってからも「すごく楽しかったみたいで、帰宅してからもずっと興奮してバレーボールの話をしていました」といった報告や「普段接する機会がない学生さんとの関わりがすごく嬉しかったみたいでした」といったバレーボールを介した活動の広がりについての肯定的な効果が得られました。この結果からは、ゲームで勝敗を競う以外にも、スポーツを楽しむことはできるということができます。
本来、スポーツには全ての人を包み込む懐の深さがあります。一方で、「スポーツが苦手」「スポーツが嫌い」といった方にもたくさん出会ってきました。大人だけでなく、運動欲求が強い子どもたちにもそのようなケースがたくさんありました。なぜ、そういった状況が生じてしまうのでしょうか?
「みるスポーツ」「やるスポーツ」「つくるスポーツ」において、我々には何が有用なのでしょうか?
こういったインクルーシブの活動における参加者の変容や意見を間近で感じながら、オリンピック・パラリンピック教育をとおして、これからの時代を担う子どもたちへの教育の重要さを感じるとともに、スポーツを介した様々な関わりの中から、多様な人間の理解へつながっていくことを心から願っています。

綿引 清勝(わたひき きよかつ)
東京都立南花畑特別支援学校 主任教諭・臨床発達心理士・自閉症スペクトラム支援士(standard)
東京都内の知的障害特別支援学校で中学部、高等部を経験後、現在は小学部の自閉症学級を担任。自身の実践を振り返りながら、子ども達が必要としている支援とは何かを考えていきたいと思います。
同じテーマの執筆者
-
東京都立白鷺特別支援学校 中学部 教諭・自閉症スペクトラム支援士・早稲田大学大学院 教育学研究科 修士課程2年
-
富山県立富山視覚総合支援学校 教諭
-
北海道札幌養護学校 教諭
-
東京学芸大学教職大学院 准教授
-
東京都立城北特別支援学校 教諭・臨床発達心理士
-
福島県立あぶくま養護学校 教諭
-
東京都立港特別支援学校 教諭
-
京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会
-
福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士
-
信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭
-
在沖米軍基地内 公立アメリカンスクール 日本語日本文化教師
-
静岡市立中島小学校教諭・公認心理師
-
寝屋川市立小学校
-
目黒区立不動小学校 主幹教諭
-
合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない



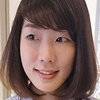




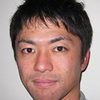






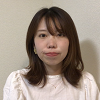


 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望









