New Education Expo2017から学んだこと
6月1日~3日に東京でNew Education Expo2017が開催されました。
6月16日~17日には、大阪でも開催されるとのことです。
私は6月2日に参加しました。
現場の小学校の教員の目線、教員養成系短大の教員の目線で紹介をしてみたいと思います。
帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師 鈴木 邦明
「はじめに」
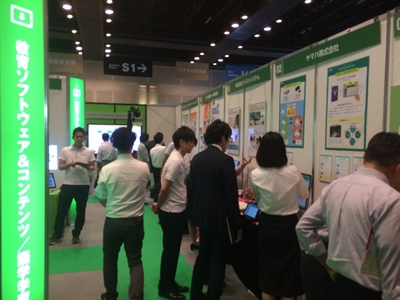
私はこれまでこういった催しにあまり参加ができていませんでした。
小学校の教員だったということもあり、平日は基本的にはほとんどの時間で授業がありました。
自習にしたり、他の人に任せたりしてまで、外部の催しには行こうとは思っていませんでした。
立場上、少し難しい状況の子どもを担任していることもあり、そういった子どもが私のいない時にトラブルを起こすようなことになってはすまないという思いがありました。
また、様々な事務仕事などもあり、時間的にも精神的にも余裕がなかったというのが実際の所でした。
「豊富で多様な展示物」
今回、初めてNEEに参加し、本当に驚きました。
まず驚いたのは、出展している企業などの多さと多様さです。
内田洋行を始め、ICT、教材、教室環境、業務改善などハードからソフトまで本当に多くの企業が出展していました。
スペースの関係で教材もたくさんのものが置いてある訳ではなかったのですが、その中でも私が注目したのが、ボーネルンドの「マグ・フォーマー」と内田洋行の「中型定規」です。
ボーネルンドの「マグ・フォーマー」は、その使い勝手の良さに驚きました。
私は、小学校の算数の授業で似たようなことを紙を使って取り組んでいました。
繋がり方の不十分さや手先の不器用な子どももいることなどからうまくいかないこともありました。
このマグ・フォーマーは、作りがしっかりとしている上、磁石の力を使ってつながる形になっているので、非常に動きもスムーズです。
子どもがイメージしたものをそのまま形に表現することができます。
小学校以前の幼児教育においても遊びながら図形の感覚などを養うのに良いと思いました。
また、私がもう一つ感じたことは、算数以外での活用法です。
理科の授業の中などでもうまく活用することで、子どもの理解が進むのではと思いました。
これに関しては、まだ考え中です。
良いアイデアがある方や実際に使って授業をしてみたいという方がいましたらご連絡ください。
担当者に取り次ぎます。
「使い勝手の良い道具」
教材で気になったものの2つ目は内田洋行の「中型定規」です。
通常、教室に置いてある「1m定規」「三角定規」「分度器」の中型版です。
定規は60㎝、三角定規は長い一辺が40㎝位でした。
きっとこれまでもカタログの中で見ていたのだと思います。
しかし、カタログを見ているだけでは、この教具の良さは実感できないと思います。
実際に私も、これまでこの教具に注目したことはありませんでした。
この定規を手に取ってみると、ちょうど子どもが前に出て黒板に図を書いたりする時に最適なサイズなのです。
普段、子どもに前に出てきてもらい、定規(大型のもの)などを使わせて何かを書いてもらうと、非常にやりにくそうにやっています。
子どもが扱うには、定規などのサイズが大き過ぎるのだと思います。
今回、展示されていた「中型定規」は、絶妙な大きさになっていました。
こういったことを感じられるのは、実際に展示会などに参加し、実物に触れたからだと思います。
「セミナーでの学び」
私は6月2日に行われた2つのセミナーに参加しました。
「これからの大学生に必要な「情報活用能力」~教育機関は社会のニーズにどう応えるか~」
「大学におけるアクティブ・ラーニングのデザイン」
現在、私が興味を持っている内容です。
上のものは、私の高校時代(神奈川県立平塚江南高校)の一年生の時の担任だった武沢護先生(早稲田大学客員教授、高等学院教諭)が登壇するということもあり、色々な意味で楽しみにしていたものです。
現在の大学における情報教育のあり方について、様々な事例から学ぶことができました。
歴史的経緯を踏まえた話はとても勉強になりました。
また、東大の山内先生と東工大の中野先生も興味深いものでした。
アクティブ・ラーニングの歴史から始まり、分類などをとても分かりやすく話してくれました。
特に印象的だったのが、山内先生が聴衆からの質問に答えた時の言葉です。
質問は「東大や東工大だから学生の意欲が高く、良いアクティブ・ラーニングの授業ができるのではないか。あまり意欲的ではない学生を相手にする時にはどうしたらよいか?」というものでした。
それに対する山内先生の言葉は次のものでした。
『「学ぶこと」と「自分の人生」をつなげることが大切』
学習に対して意欲の高くない学生は、その学習の意味を理解できていないということになります。
どうしてその学習をするのか、その学習がその人の人生にどの様な影響があるのかということを丁寧に説明することが大事なのだそうです。
山内先生が看護学校で非常勤講師として、教育学を教えていた時の話をしてくれました。
看護学校の学生にとって、教育学はそれ程重要なものではありません。
意欲も高くありません。
そういった状況において、始めの3回位のふりかえりのレポートにおいて、非常に丁寧な返答を書き、その中でその学びの必要性を説いたのだそうです。
数回したら学生の態度が一変したそうです。
この話はアクティブ・ラーニングだけに関することではないと思います。
どういった子どもが相手であっても、その学びの意義や意味をしっかりと伝えることなしに良い学びはできないのだと思います。
本当にその授業が必要であるということを伝えることが出来ていれば、授業中に学生が寝るようなことはないでしょう。
テストで落第することもないでしょう。
子ども達の様々な問題は、こちら側(教師の側)の問題であり、改善していくべき部分が見えている状態なのだと思います。
そこに対して、どう取り組んでいくのか(無視するのか、必死で改善策を考えるのか)が教師としては試されているのだと思います。
私自身、反省することがたくさんあります。
本当にたくさんの学びがあります。
「内田洋行教育総合研究所のこと」
私はこの「教育つれづれ日誌」を書いて5年くらいになります。
学びの場.comのページを見たり、執筆仲間の文を読んだりはしていました。
しかし、内田洋行教育総合研究所についてはあまり知りませんでした。
今回、ブースがあり、そこにいくつかのパネルが展示されていました。
様々な調査研究などをしていることや組織などについて知ることができました。
担当者の方ともお話しする機会もありました。
とても良かったです。
ちゃんと「学びの場.com」のパネルもありました。
ちょっと嬉しい気持ちになりました。
「終わりに」
始めに書いたように私はこれまでこういったイベントにはあまり積極的に参加はしていませんでした。
今回、実際に参加してみて、できるならこういった場に、現場の教員が参加できたら良い学びができると感じています。
教具の所の「中型定規」で紹介したように「実感を伴った理解」ができます。
できるだけ現場の教員が参加しやすい形での開催になればと願います。
また、自分のすべきこととして、なかなかこういった場に参加ができないような教員のために今回文章を書いているように「つなげていく」ことが役割なのではと感じました。
実際、ボーネルンドのマグ・フォーマーをSNSで紹介した所、研究者仲間の大学の教員が興味を持ち、担当者との橋渡しをしました。
今回のような企業の催しもそうですし、様々な学校がやっている研究授業、講習会などにも積極的に参加していくつもりでいます。
そこで学んだこと、感じたことを様々な形で情報発信していきたいと思っています。
若い教員がそういったものを少しでも参考にしてくれたらと思います。

鈴木 邦明(すずき くにあき)
帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師
神奈川県、埼玉県において公立小学校の教員を22年間務め、2017年4月から小田原短大保育学科特任講師、2018年4月から現職。子どもの心と体の健康をテーマに研究を進めている。
同じテーマの執筆者
-
兵庫県公立小学校勤務
-
兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)
-
大阪府公立小学校教諭
-
特定非営利活動法人TISEC 理事
-
兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭
-
岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任
-
福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝
-
大阪市立堀江小学校 主幹教諭
(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -
戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表
-
佛教大学大学院博士後期課程1年
-
明石市立高丘西小学校 教諭
-
木更津市立鎌足小学校
-
北海道公立小学校 教諭
-
東京都東大和市立第八小学校
-
東京学芸大学附属大泉小学校 教諭
-
東京都品川区立学校
-
岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭
-
神奈川県公立小学校勤務
-
寝屋川市立小学校
-
仙台市公立小学校 教諭
-
東京都内公立中学校 教諭
-
目黒区立不動小学校 主幹教諭
-
東京都公立小学校 主任教諭
-
尼崎市立小園小学校 教諭
-
埼玉県公立小学校
-
大阪府泉大津市立条南小学校
-
岡山県和気町立佐伯小学校 教諭
-
合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない































 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望








