がんばれ三宅島!(第3回) ~三宅村立小学校教育IT化プロジェクトに密着取材~

今回は現地の三宅村立小学校の先生から、これまでの取り組みと、今後の抱負について寄稿いただきました。
都立秋川高校への避難
避難生活での取り組み
児童数は0名となりましたが、いつ避難解除され、学校が再開されるかわからない状況であったため、学校は3校合同体制を継続し、所属の教職員は学校再開に向けた諸条件の整備や管理等に努めました。特に、災害に見舞われた子どもたちや保護者が、避難先で自分自身を守り、お互いを助け合っていくことのできる力を育むこと、さらには全国各地に避難した三宅島の子どもたち(保護者や地域も含めて)の心の絆を保つことは大きな課題であり、下記のような取り組みに努めてきました。
1.兼務校とのかけ持ち勤務
三宅村立小学校の教員が、三宅島の子どもの在籍する学校に兼務して授業等を行いました。また、家庭訪問や学校訪問を繰り返し行い、子どもたちが新しい生活にうまく適応できているかなどにも留意してきました。
2.交流行事の実施
転出した児童やその保護者、さらには三宅島の住民がふれあい、交流できる場を設け、島民としての絆を深めることに努めました。具体的には、「小中高合同運動会」「全校遠足」「小中高合同文化祭」「スケート教室」「島民ふれあい集会」「避難先地区別懇談会」「高遠体験学習」などを 行ってきました。
3.三宅島児童・生徒一時帰宅
全島避難後、帰宅の機会がない三宅島の児童・生徒に、故郷への思いをより深めることができるよう島の様子を見せる機会を設けました。またその際、島の復旧に向けて献身的な努力をする人々の姿を目の当たりにすることにより、避難先での生活におけるさまざまな障害を乗り越えていくことのできる勇気やたくましさを育んだりすることにもつながりました。
4.火山と共に生きる子どもサミットへの参加(平成14年度)
北海道有珠山山麓の虻田町から「火山と共に生きる子どもサミット」への参加について呼びかけがあり、短期間で噴火を繰り返す北海道有珠山と三宅島雄山の山麓に住む子ども同士が交流する機会を設けました。この交流によって、復興への意欲をより高めたり、将来にわたって火山と共生する知恵と勇気を共有したりする貴重な機会となりました。
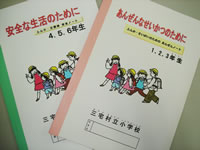
「噴火・災害時安全ノート」
三宅島の火山ガスは人体に有害な二酸化硫黄を多く含んでおり、島内での生活については、二酸化硫黄の健康影響を考慮し、その濃度レベルに応じた安全対策が求められています。そのため、現地視察などを重ねながら、児童が三宅島の特性や災害について理解を深め、自らの安全な生活について考えたり、身を守る行動をとったりすることができるような「噴火・災害時安全ノート」を作成しました。
学校の再開とIT支援プロジェクト
平成17年2月に避難指示がようやく解除され、いよいよ4月から学校が再開されることとなりました。しかしながら、人体に有害な火山性ガスの噴出が続いている中での学校再開であり、子どもたちは全国各地に避難をしていたことから、全員が転校生という特異な状況の中での学校の出発となりました。加えて、校舎は増築・改築工事の途中であり、視聴覚室や図工室、保健室、図書室などがなく、子どもたちを取り巻く教育的な環境は、必ずしも十分なものではありませんでした。
こうした現状に、当時静岡大学に勤務されていた堀田龍也助教授(現・メディア教育開発センター)が中心となって手をさしのべてくださったのが「三宅村立小学校教育IT化支援プロジェクト」です。プロジェクトチームは、6月と7月の2回にわたって来島してくださり、職員室内ネットワークの構築、教室内IT環境の設定、校内無線LANの設定、インターネット百葉箱の設置、学校Webサイトの開設など、都内の平均的な小学校の環境を遙かにしのぐ充実した環境を整えてくださいました。
IT支援を受けて…
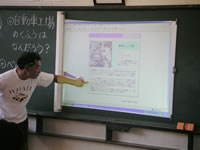
コンテンツを活用した授業の様子
プロジェクトの支援により、次のようなことが可能になりました。
1.いつでもどこでもインターネット
校内ネットワークが整備されたことにより、手軽に校内のどこからでもインターネットでの調べ学習などができるようになりました。各教科等における情報検索ひとつとっても、図書室が工事中の本校にとってその役割は大変重要です。 学習コンテンツを活用した授業も展開できるようになり、休み時間には自由に計算ドリル等に取り組む子どもたちも見られるようになりました。 また、夏から秋にかけて三宅島に接近した台風について、体感だけでなく屋上に設置していただいた「インターネット百葉箱」を利用して数値的に検証したりすることもでき、支援していただいたことが子どもたちの知的好奇心の喚起や、「よくわかる」「おもしろい」といった満足感につながっています。 さらには、この春まで在籍していた学校のホームページを閲覧したりする子どもなどもおり、避難生活の中で培った人間関係や思い出などを一層大切にするためのツールにもなっています。
2.校務の効率化
開校当初、職員室内のネットワークが構築されていなかったため、教職員が自席でインターネットや共有文書を開くことができず、印刷なども順番待ちの状況でした。しかし、今回のIT支援によって、例えば印刷待ちの時間を子どもとのふれあいや教材研究等に利用することができるようになるなど、教職員の職務の効率化が図られるようになりました。 また、職員室のPCの環境が同じになったため共通の話題も増えてきました。学校Webサイトの情報などを元に児童理解に関するコミュニケーションを深めたりするなど、よい意味での教員の仕事の透明性が高まっています。
3.「今」を知らせる学校Webサイト
人体に有害な火山性ガスが噴出している中、4年半ぶりに島での学校再開を果たした三宅村立小学校。全国各地から様々な支援をいただいたことや、帰島したくてもできない島民の方々もいる状況を考えると、子どもたちが安全に楽しく学校生活を過ごしている様子を積極的に発信していくことは、公立学校としての説明責任を果たしていく上でとりわけ重要です。 学校Webサイトで学校や子どもたちの「今」を発信することによって、保護者の方々との連携も少しずつ深まってきました。また、学校Webサイトを発信する過程で、教員や子どもたちが身の回りの事象を改めて見直したり、新たな価値に気付いたりすることが増えています。
これから…
三宅島の子どもたちに確かな学力を
三宅島の子どもたちに情報社会で生き抜く力を
三宅島の復興の象徴に
学校Webサイトの取り組みを、「三宅島のよさ」をアピールするよい機会ともとらえて情報の発信をするとともに、これらの取り組みをより効果的・継続的に行っていくことができるよう関係機関等との連携に積極的に取り組んでいきたいと思います。
(文: 三宅村立小学校(三宅村立坪田小学校所属)大塚昌志先生)
参考: 三宅村立小学校 http://schoolweb.ne.jp/miyake/miyake-e
学びの場.comでは、今後も引き続き三宅村立小学校を応援していきます。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 教育つれづれ日誌
教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望










