【先生たちの復興支援】さいたま市立海老沼小学校 教諭 菊池健一さん(第1回) 「3月11日に向けて児童の関心を高める」

今回は、さいたま市立海老沼小学校 教諭 菊池健一さんの授業実践を4回にわたってご紹介します。
この3月で、東日本大震災から5年になります。まだ、5年しか経っていないという印象がありますが、現在担当している小学校3年生の児童は、当時3歳から4歳であり、その時の記憶があまり残っていない子もいます。震災当時のことを尋ねてみても、「よく覚えていない」という答えが返ってきました。「風化」という言葉がありますが、被災地でないところでは震災がもう過去の出来事のように思えることがあります。
しかしながら、被災地では未だに行方不明になっている方が2500人を超えていたり、集団移転も計画通り進んでいなかったりと、被災地の復興にはまだほど遠い状況です。被災地の方達のためにできることを日本全体で考えていく必要性を感じます。
また、東日本大震災を通して、私達は人と人とのつながりの大切さについて改めて感じることができました。これからの社会を担っていく子ども達には、東日本大震災について自分事として捉え、自分の生き方や、被災地の方のためにできることを考えたりしてほしいと考えています。
そこで、担当する児童に東日本大震災について関心を持ってもらうために、新聞を活用した取り組みを行いました。まずは、震災関係の記事を取り上げた毎朝の新聞トークと新聞スクラップです。以下のような話題の新聞記事を取り上げました。
- 今でもまだ発見されていない行方不明の方が2500人以上もいることを取り上げた新聞記事
- 原発の汚染水を処理するためのタンクが1000基以上作られている新聞記事
- 被災地の方の集団移転が計画の3割しか済んでいないことを取り上げた新聞記事
- 被災地の小学生の現在の様子を取り上げた新聞記事
- 原発の影響で閉校してしまった小学校の新聞記事
児童は、これまであまり東日本大震災について関心を持って考えたことがなかったようですが、毎日、朝の時間に震災の話題を取り上げることによって、次第に興味関心が高まってきました。
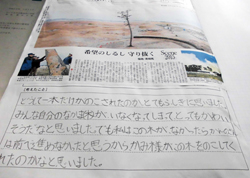
児童のスクラップノート
廊下に設置した新聞コーナー
掲示には記事の解説や、教師からのメッセージも付けるようにして、興味を持った児童がさらに震災について調べたり、話を聞いたりしやすいように工夫しました。児童の中には、学校図書館で震災に関する本を借りたり、家族に震災当時のことを聞いたりする子もいました。
これらの取り組みによって、児童の東日本大震災に関する興味関心が高まってきました。3月11日に向けて、児童は自ら震災に関連する情報に触れていくようになると思います。これからも、新聞トークや新聞スクラップ、そして新聞コーナーを通じて、東日本大震災についての情報を提供していこうと考えています。
文・写真:菊池健一
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 教育つれづれ日誌
教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望










