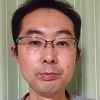『僕たちは希望という名の列車に乗った』 無意識のうちに政治的タブーを犯した高校生たちが辿る道とは?
映画は時代を映し出す鏡。時々の社会問題や教育課題がリアルに描かれた映画を観ると、思わず考え込み、共感し、胸を打たれてしまいます。ここでは、そうした上質で旬な映画をピックアップし、作品のテーマに迫っていきます。今回は『僕たちは希望という名の列車に乗った』と『長いお別れ』をご紹介します。
舞台はベルリンの壁建設前の東ドイツ
ドイツが東西に分離されていたことを、知らない人達が増えてきた。歴史の授業で聞いたとしても、そのことの意味は当事者でないとなかなか理解できないのかもしれない。だがアメリカとソビエト社会主義共和国連邦(現ロシア)の冷戦時代に築かれた東西を分けたベルリンの壁が1989年に取り壊されるまで、ドイツは社会主義陣営に属するドイツ民主共和国(東ドイツ)と、自由主義陣営に属するドイツ連邦共和国(西ドイツ)に分かれていた。特に1961年に壁が建設された後は東と西の間の通行は本当に不可能になり、壁を越えて越境しようとした者は容赦なく射殺されるなどの悲劇が生まれたのだ。
『僕たちは希望という名の列車に乗った』の舞台は1956年の東ドイツ。まだ壁が建設される前の話だ。もちろん西ドイツに行くのに検閲などはあるが、まだ親戚の墓参りがあるから西ドイツに行きますという言い訳が通用する時代だった。実際、映画の主人公、高校生のテオとクルトは列車で祖父の墓参りに行く体裁で(もちろん墓参りもちゃんとするが)西ドイツへ行き、自由主義を味わい、若者らしく冒険気分で映画館に忍び込んだりする。
が、その映画館で彼らはとあるニュース映像を見てしまう。それが東ドイツ同様、ソ連の強い影響下に置かれたハンガリーが、自由を求めて蜂起した様子を写したもの。
ハンガリーの衝撃映像が脳裏に焼きついたクルトは、自分たちの街に戻ってからその様子を同級生に話す。そして同級生パウルのおじさん、エドガーのところで禁じられている西ドイツのラジオをこっそり聞かせてもらうことに。するとハンガリーの武装蜂起で何百名もの市民が命を落とし、ハンガリーを代表するサッカー選手のプスカシュも命を落としたとの放送が。そのことに大きなショックを受けてしまう高校生たち。
翌日、教室でもハンガリーの悲劇話が話題となり、クルトは思わず「ハンガリーの死んだ同志のために黙祷を捧げよう」と提案を。多数決の結果、2分間の黙祷を捧げることとなり、歴史の授業で最初の2分間、生徒たちはだんまりを決め込んでいく。だがこのわずか2分間の生徒たちの行動が、本当に純粋な気持ちで起こした出来事が、なんと社会主義国家への反革命行為と見なされてしまうのだ。
結託したクラスを解体しようとする郡学務局
この映画の恐ろしいところは、若者たちが何気なく起こした行為が、想像もしえない波紋を巻き起こしていくところ。最初はふざけているのか!?と学校側の怒りもそこまでではない。特にシュヴァルツ校長はなるべく事を穏便にすまそうとする。だが学校から郡学務局に報告が行き、女性局員ケスラーが動き出してからは、事態が急速に動き出す。結束の固い生徒たちに亀裂が生じるよう、わざと嘘をついて「✕✕はあなたのことを首謀者と告白したわ」などと言ったり、子供には隠していた親の真実などをあえて知らせることで動揺させたり。来春卒業試験を控える彼らに試験を受けさせないだの、首謀者の名を言えば退学はさせないだの、このままクラス全員でごまかしを続けるのならばクラスを解散させると脅しまで行っていく。ありとあらゆる卑怯とも言える手で彼らの精神をメッタメタに追い込んでいくのだ。
もともと東ドイツは建前的には第二次世界大戦に脅威となったナチに抵抗した社会主義者の国として、建国されたものだ。だが郡学務局が取った行動は、生徒たちも劇中で思わず叫んでいるが「まるでゲシュタポ」だ。それこそ建前が揺らぐような行動を間違いなくしており、そしてその人民への締め付けは東ドイツが西ドイツに併呑されるまで続くこととなるのである。
そういった社会主義の怖さはスティーブン・スピルバーグ監督作で60年代に東ドイツで暗躍したアメリカ側の交渉人となった弁護士の姿を追った『ブリッジ・オブ・スパイ』を観ると、より立体的に伝わるのではないかと思う。
親世代への「反抗」が成長を促していく
ちなみにもう少し当時の世界状況を説明しておこう。50年代は実は社会主義にまだまだ勢いがあった時代だったのだ。様々な映画にも登場するソ連の人工衛星スプートニクの打ち上げが成功したのが1957年だ。同時に50年代のアメリカでは赤狩りなどが盛んになり、チャールズ・チャップリンなどが国外退去させられるなど、特に映画界では激しいバッシングが起きていた時代。人々が社会主義と自由主義のどちらが良いのか、自分の考えを明確にすべき時代になっていた。
そんな中でアメリカ映画では若者たちの旅立ちや反抗をテーマにしたマーロン・ブランド主演『乱暴者』やジェームズ・ディーンの『エデンの東』『理由なき反抗』などが公開され、それらのアメリカ映画や勢いを得たロックン・ロールの影響でドイツ、オーストリア、スイスなどに「ハルプシュタルケ(ドイツ語で非行青少年)」と呼ばれる若者が56年〜58年に多く見受けられるようになってきた。
特にドイツでは、当時の親世代はナチスに積極的であれ消極的であれ、支持をしていた「うしろめたい」世代だ。
一方、ハルプシュタルケを含む若者世代はそんな親世代に反抗するかのような意志を表示していく者たちが多かった。それは逆にいえば親世代にとっては脅威であり、だからこそ東ドイツではなんとしてもその反抗の芽を摘み取りたいという気があったのだろう。また東ドイツは若い国家だったということもあり、「青年を手に入れたものが、未来を手に入れる」という教育スローガンを掲げ、若者の教育に心血を注いでいた。特に歴史と公民の授業は重要視された。
テオやクルトたちは、よりによってその「歴史」の授業で黙祷を捧げたからこそ、より厳しい監視下に置かれることになったのだろう。
つまりこの映画は、そういった親世代への子供たちの毅然とした反抗を描いた映画でもあり、反抗を経て大人になっていく成長物語でもある。
しかもここで描かれているのはすべて実話。この映画の原作を書いたのはクルト役に相当するディートリッヒ・ガルスカだ。
だからこそのリアリティも胸を打つし、素晴らしい成長物語として心にも刺さるのだ。そしてそんな子供たちに様々な複雑な思いを寄せる大人たちの愛の物語でもある。
こういったように様々なテーマを味わうことができる素晴らしい作品なのだ。
そして同時に人生には必ず何かしらの選択が訪れる時が来るということ。自分の生き方を決めるために歴史などを含めて様々な学業があることを忘れてはならないのだ。
私も中学・高校の頃は「なんでこんなにいろんな勉強をしないといけないのだ。必要な科目以外、勉強しなくて良くない?」なんてことをよく考えたりしたものだが、とんでもない!!別に受験のために勉強をしているわけではない。自分にとって良い人生とは何なのか、それを探るために様々な勉強や学生生活があるといっても過言ではない。そのことをこの映画はよく示してくれる。
「仲間を密告してエリート街道を進むのか」それとも「信念を貫いて大学進学を諦めるのか」。生徒たちが起こした2分間の黙祷がどのような結末にたどり着くのか。
それは映画を観る楽しみにしていただきたいが、ひとつ言えるのはこの出来事は当時の彼らをとても不安にさせただろうし、様々な憤りや、行く宛のない怒りを覚えさせたことだろう。だがそれも今となってみれば彼らを人間的に成長させるには大きく役にたったはずだ。その時には悲観しかできないような事だって、それは必ず人を成長させるための大きな礎となる。
人生にはムダなことなんて何ひとつない。
そんなことも感じさせてくれる快作だ。
- Movie Data
監督・脚本:ラース・クラウメ 原作:ディートリッヒ・ガルスカ 出演:レオナルド・シャイヒャー、トム・グラメンツ、レナ・クレンク、ヨナス・ダスラー、イザイア・ミカルスキほか
配給:アルバトロス・フィルム/クロックワークス
- Story
1956年、東ドイツの高校に通うテオとクルトは、西ベルリンの映画館でハンガリーの民衆蜂起を伝えるニュース映像を見た。自由を求めるハンガリー市民に素直に共感した2人はクラスメイトに呼びかけて2分間の黙祷を。だがそれが社会主義国家への反逆とみなされることに。かくしてクラスの皆は1週間以内に首謀者の名を言えと国から詰め寄られる。
文:横森文
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
子どもに見せたいオススメ映画
『長いお別れ』
核家族化が進んで、祖父や祖母と一緒に暮らす人がどんどん少なくなっている。淋しい話だ。以前は姑と嫁問題などがあまりにも多くて、祖父や祖母と離れて暮らすのを良しとする傾向があったが、孤独死などの今あふれる問題を見ているとそれは本当に正解だったのかなあ…とふと疑問に感じてしまう。今回紹介する『長いお別れ』はそんな現代に一石を投じる作品となっている。
かつては学校の校長を務めたこともある厳格な父親・昇平。その昇平の70歳の誕生日を祝うために実家に集まった長女・麻里と次女・芙美は、昇平に認知症の症状が現れ始めたことを母親・曜子から知らされる。やがて日に日に父としての記憶や夫としての記憶を亡くしていく昇平。しかし、そんな父親の中には、家族の誰もが忘れてしまっていた思い出だけが息づいていた…。
長い時間をかけていろんなことを忘れていく昇平と、そんな父親と否応なしに向き合ううちに、自分たちのことも見つめ直していくことになる娘たち。その描き方のバランス感がとても良い。特に前向きな母親・曜子の姿が素晴らしく魅力的。自分が年をとっても曜子のように、大好きな人に寄り添うことができるだろうか。娘たちにも波紋を広げていくことになる。
しかもだ。認知症になる話となると、「しんどい」だの「辛い」だの、暗い側面から描くことが多い日本映画界だったが、今回はとてもポジティブに物事が展開するのが良い。認知症の患者を介護して支えていくのは、もちろん生半可ではない大変さがあるが、それも人間のひとつの面としてとらえ、特別視しないのがたまらない。
そうなのだ。どんな人でも必ず年をとり、例え認知症にならなかったとしても、どこかに体の不調が出て、誰かに厄介にならなければならない日は必ず訪れる。健康だったり若かったりするとそのことを忘れがちだが、順番にそれは訪れるもの。人は決してひとりでは生きていけないし、誰かと寄り添って生きていく動物なのだ。そのことを真摯に伝えてくれるのが本作。特に高校生に本作を観て、自分の家族のこと、将来のこと、様々なことに目を向けて、いろいろ考えてほしいステキな1作である。
監督・脚本:中野量太 原作:中島京子 出演:蒼井優、竹内結子、松原智恵子、山崎努ほか 配給:アスミック・エースほか
(C)2019「長いお別れ」製作委員会
文:横森文 ※写真・文の無断使用を禁じます。

横森 文(よこもり あや)
映画ライター&役者
中学生の頃から映画が大好きになり、休日はひたすら名画座に通い、2本立てなどで映画を見まくっていた。以来、どこかで映画に関わっていたいと思うようになり、いつの間にか映画ライターに。『スクリーン』、『DVD&ブルーレイでーた』、『キネマ旬報』など多数の雑誌に寄稿している。 一方で役者業にも手を染め、主に小劇場で活躍中。“トツゲキ倶楽部”という作・演出を兼ねるユニットを2006年からスタートさせた。
役者としては『Shall we ダンス?』、『スペーストラベラーズ』、『それでもボクはやってない』、『東京家族』等に出演。
2022年4月より、目黒学園で戯曲教室やライター講座を展開。
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 教育つれづれ日誌
教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 震災を忘れない
震災を忘れない



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事