夫婦の不仲が子どもに与える影響とは?子どもの心を守るためにできること

私、アグネス・チャンがこれまで学んだ教育学の知識や子育ての経験をもとに、学校や家庭教育の悩みについて考える連載エッセイ。夫婦の関係は家庭の雰囲気に大きく影響します。親のちょっとした言い合いで、子どもが不安やストレスを感じることも。今回は「夫婦の不仲が子どもに与える影響とは?子どもの心を守るためにできること」をテーマに考えました。
子どもの前で悪口を言っていませんか?
両親の仲が悪いと、子どもは自分のせいだと思い込んでしまうことがあります。これは子どもにとって避けたほうが良い状態です。パパもママも同じように愛している子どもにとって、両親の不仲は辛いものです。
場合によっては一方の親が子どもの前で、配偶者の悪口を言うことがあります。私の場合、両親は特に仲が悪かったわけではありませんが、何か問題が起きると母はいつも父のせいにしていました。私は父が大好きだったので、「なぜそんなことを言うのだろう?」と感じていました。確かに父にはお人よしすぎる面がありましたが、それも父の長所であり優しさでもあります。そうした愚痴は、家庭の雰囲気が悪くなる原因ともなります。
配偶者に不満があったとしても「パパは君のことを大切に思っているよ」「ママはパパに出会えて、君が生まれたことを感謝しているんだよ」と、良いところを探してでも伝えることが大切です。そうした言葉を意識して口に出していくうちに、自分自身でもそう思えるようになり、夫婦の関係も少しずつ改善していくかもしれません。
子どもの前で夫婦喧嘩をすること
子どもの前で喧嘩をすることは子どもが恐怖心だけではなく、親や自分自身を否定するような感情を持つことにつながります。繊細な子は「自分がダメな子だから両親が喧嘩している」と悩み、単純に考える子は「どちらかの親が悪い」と決めつけてしまいます。複雑に考える子は「両親に問題がある」と捉えて親が嫌いになり、早くこの家から出たいと考えるかもしれません。両親を愛している場合は、自分では解決できない無力さに苦しむでしょう。
夫婦関係はそれぞれ違うので、誰が悪いのかは簡単に決められません。場合によっては許しがたいこともあるでしょう。しかし、不倫や暴力、依存症など深刻な問題は別として、日常の不満程度であれば子どもの前では平和な関係を保つようにしていたほうが子どもの心を守ることができます。
子どもの前では仲良くいられるようにお互いに努力を
「我慢せずにありのままの自分を出すほうが良い」という考え方もありますが、もし感情的になりやすいのであれば、そのままの自分ではなく冷静な自分を意識してください。夫婦喧嘩は子どもの心や脳にダメージを与えることがあるので、暴言を吐いたり、物を投げたり、無視するようなことは絶対に避けてください。家庭内で腹の立つことがあっても許せるものは許して、たとえ許されないことがあっても子どもの前では仲良くいられるようにお互いに努力しましょう。
人間の記憶は不思議なもので、同じ環境で育っても記憶に残ることは子どもによって違います。両親が衝突したことばかり覚えている子もいれば、仲良くしている姿だけを覚えている子もいます。子どもの記憶が辛いものばかりにならないためにも、子どもの印象に残るような激しい喧嘩をしたり、怒鳴ったりしないように気を付けたいものです。
子どもが寝ていると思っても、意外と耳を澄ませて聞いている場合もあります。どうしても言い争いになりそうなときには、子どものいない場所で話し合うのはどうでしょうか。例えばカラオケボックスのような場所なら、周りを気にせずに存分に話ができます。
そうやって隠していても子どもは不仲を察してしまう場合もあります。しかし、親が努力していることは認めてくれるはずです。「パパとママが仲良く振舞うのは僕たちに対する愛情なんだな」と敏感な子であれば分かります。もし気が付かなくても、「家族が仲良くて幸せ」と感じるでしょう。それは、親の不仲を見続けるよりもはるかに良いことです。
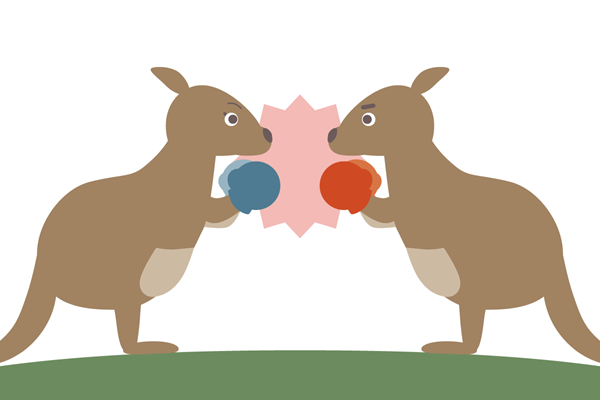
©学びの場.com
特に幼い子どもの場合、ストレスによってホルモンバランスが崩れると、成長に影響します。脳や身体が発達する大切な時期に、ストレスホルモンが過剰に分泌されてしまうと成長が遅れてしまう可能性があります。食が細くなったり、睡眠が浅くなったり、びくびくした神経質な子どもになることもあります。思春期の子どもにとってもストレスは体調を崩す原因になります。家庭の和やかな雰囲気は子どもの成長に欠かせないものなのです。
努力しても状況が改善しない場合や、子どもが親の帰宅を恐れるような場合は離婚も選択肢の一つになるかもしれません。しかし、離婚によって子どもに会えなくなるようなケースもあるので慎重に考えるべきです。そこまで深刻ではない場合はお互いに歩み寄ることも大切です。子どもに悪い影響を与えないような家庭を作ることも親の責任です。子どものために平和で安心できる家庭を作る努力を続けていきましょう。

アグネス・チャン
1955年イギリス領香港生まれ。72年来日、「ひなげしの花」で歌手デビュー。上智大学国際学部を経て、78年カナダ・トロント大学(社会児童心理学科)を卒業。92年米国・スタンフォード大学教育学部博士課程修了、教育学博士号(Ph.D.)取得。目白大学客員教授を務め、子育て、教育に関する講演も多数。「教育の基本は家庭にある」という信念のもと、教育改革、親子の意識改革について積極的に言及している。エッセイスト、98年より日本ユニセフ協会大使、2016年よりユニセフ・アジア親善大使としても活躍。『みんな地球に生きるひと』(岩波ジュニア新書)、『アグネスのはじめての子育て』(佼成出版社)など著書多数。2009年4月1日、すべての人に開かれたインターネット動画番組「アグネス大学」開校。2015.6.3シングル『プロポーズ』release!!(Youtubeで公開中)
ご意見・ご要望・気になることなど、お寄せください!
「アグネスの教育アドバイス」では、取り上げて欲しいテーマ、教育指導や子育てで気になることなど、読者の声を随時募集しております。下記リンクよりご投稿ください。
※いただいたご意見・ご要望は、企画やテーマ選びの参考にさせていただきます。
※個々のお悩みやご相談に学びの場.comや筆者から直接回答をお返しすることはありません。
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 教育つれづれ日誌
教育つれづれ日誌 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望・気になること
ご意見・ご要望・気になること









