「州議会選挙に合わせて選挙制度の学習を」 カナダ・バンクーバーより
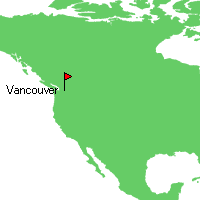
カナダ人は一般的に参選意識が強い。息子たち小学校4年生は、毎年1月ごろに州議会について学習するが、今年は丁度良いタイミングで州議員選挙が近づいてきたため、4月から社会の授業で選挙制度について学んでいる。投票日が近づくにつれ、子どもたちの興奮度もアップ。党首による公開討論も「見なきゃ」と大張り切り。さて、クライマックスを迎えた選挙当日は......?

名簿対照係がチェック
まず議員の役割をはじめ、州議会について説明があり、その上で、国民が政治に参加するという意味での選挙について、そして選挙制度そのものについて学んだ。それから、担任教師が州議会にどんな政党があるか紹介した。
「今は4人ずつのグループに分かれて、政党についてインターネットでリサーチしてるんだ」という。グループごとに2つの政党を選び、それぞれについて自分たちの住んでいる地域の候補者名、主張などを調べる。それを模造紙にまとめて発表を行った。

僕の名前はここ!

選挙人名簿で確認
また家庭でも、お父さん、お母さんがどの政党を応援しているのか、その理由についても聞いてくるようにと言われたらしい。「アーロンのところは(野党の)NDP党だって。今の(与党の)自由党が教育予算を減らしたから、BC州では先生の数が足りないんだよ。僕たちは十分な教育を受ける権利があるのに」と、友達の話をする。
カナダ人は一般的に、参選意識が強く、多くの家庭で各人が応援している政党を持っている。保護者が応援している政党について聞くことにより、影響を受けてしまって、公正に自分の頭で判断しない危険性はありそうだ。しかし、だからこそ、教室では各政党を応援するグループに分かれ、お互いにその政党の良い点を出し合うことで、自分たちで判断するように勧めている、と担任のマックロイ先生も工夫している。

投票用紙。 学校のある選挙区の 候補者の名前が並ぶ
カナダでは州の教育省が初等、中等教育は管理している。カリキュラムがあり、各学年で何を学ぶかは決まっているが、市町村レベルで共通に使用する教科書はない。それどころか、科目によっては教師手作りのプリントのみが多いようだ。基本的にどのように教えるかは、各教師に委ねられている。すなわち、一応、何年生で何を学ぶかといった規定はあるが、共通の教科書を用いるわけではないので、教師次第なのだ。
授業時間数も各学年、教科に対して何時間と厳密に時間割が決まっているわけではない。選挙について学習したのは社会の授業としてだが、新聞を読んで要旨をまとめる宿題などは、ランゲージ・アート(国語)の要素が強いし、社会、国語と明確な時間分けをしなかったのも、“日本人の母”としてはおもしろいと思った。
投票日が近づくにつれて、子どもたちの興奮度もあがってきた。党首による公開討論についても、先生から聞いていたらしく、「見なきゃ」と大張り切り。4年生には内容が難しすぎるのではないか、どれだけ理解できたのかと思ったが、後で、選挙運動の一部として、選挙権者が各政党、候補者の主張を聞く機会を提供するための手段、場であると紹介したのだと、マックロイ先生から聞いた。

誰に投票しようかな

これから投票
しかし、こんな風に、選挙について学んでいたら、選挙権のある年齢になったら、ちゃんと投票するだろうなぁと思わせる一こま。教科書がないので、きちんとそれぞれの学年で学ぶべきことを教わっているのか、今までずっと心配だったが、認識を改めさせられた。
ちょっとがっかりしたのは、どの政党を応援しているか、子どもたちに聞いたとき。「そりゃ、NDPだよ」と多数が断言する。なぜかと思えば、自由党は学校におやつを持っていくことを禁止すると公約をしているからだとか。やっぱり4年生。まだまだ子どもだ。
関連情報

http://gogo.chips.jp/kakibito/
海外書き人クラブお世話係 柳沢有紀夫さん の本もご覧ください!
『オーストラリアの小学校に子どもたちが飛び込んだ.』
カナダ・バンクーバー発 西川桂子
地図画像著作権:白い地図工房&学びの場.com
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事














 算数の教え上手
算数の教え上手 学校の危機管理
学校の危機管理 科学夜話
科学夜話 今どきの小学生
今どきの小学生



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事
