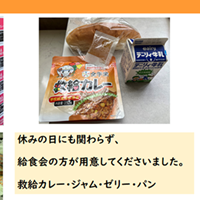色が変わる不思議な団子を作ろう! 【作ってみよう!食と科学】[大学・教育学部]

食育は家庭科や総合的な学習の時間だけが受け持つものではありません。理科、社会科などどの教科でもアイデア次第で楽しく展開できます。教材開発のノウハウや子どもたちの興味・関心を高めながら、望ましい食生活習慣を育てていく授業作りのヒントを、武庫川女子大学・藤本勇二先生主宰、食で授業をつくる会「食育実践研究会」がご紹介します。第214回目の単元は「色が変わる不思議な団子を作ろう!」です。
「作ってみよう!」編では、実際に作りながら学べる内容をご紹介します。授業や家庭での実践に役立つ調理のポイントや、食に関する学びを深めるヒントもあわせてお届けします。
授業情報
テーマ:食と科学
学年:大学教育学部
重曹と紫芋粉で色の変化を実験
団子を団子粉から作ったことはありますか。また、紫色や青色の団子を食べたことがありますか。
色が変わる団子は、少ない材料で簡単に作ることができ、水溶液の性質に気づくと同時に、色が変わる不思議を楽しむことができます。第6学年「水溶液の性質(酸性、アルカリ性)」の学習にぴったりの調理を紹介します。
色が変化する団子を作ってみましょう。
今回は、重曹と紫芋粉を使って作る様子を教育学部の学生がレポートします。
以下、学生の視点からお届けします。
用意するもの 材料(3人分)
・団子粉・・・120g ・重曹・・・ 2つまみ
・絹ごし豆腐・・・100g ・砂糖・・・ 3g
・紫芋粉・・・小さじ1杯 ・水・・・小さじ
・トッピング・・・お好みでどうぞ。
〇手順
①団子の生地を作る。

手のひらで押しながらよく混ぜる
(1)団子粉、砂糖、絹ごし豆腐を量って、ボールに入れます。
(2)指でくずした後に、手のひらで押しながらよく混ぜます。
混ぜるときのポイントは、だまができないように、豆腐を崩しながらひとまとまりになるまで混ぜることです。
②分ける
-

団子生地を3等分する
-

きれいな紫色になるまでしっかりこねる
(1)①で作った団子生地を3等分にします。分ける時のポイントは、均等にすることです。また、机にラップを敷くことで作業しやすくなります。
(2)2つ分には紫芋粉を加えます。白色のかたまりと紫色のかたまりができます。ポイントは、紫芋粉をまんべんなく混ぜ、ひとまとまりになるようによくこねることです。きれいな紫色になるまでしっかりこねましょう。
③大変身
(1)重曹を水に溶かします。重曹2つまみを少量の水と混ぜます。重曹が溶けきるまで少しずつ水を加えます。1滴ずつ確認し、水を入れすぎないようにしっかりと溶かしきりましょう。重曹が水に溶けきっていなかったり、重曹の量が少なかったりするとうまく反応せず、色の変化が小さくなったりまばらになったりします。そこで、色の変化に注目しながら、重曹の量や水の量を変えて実験してみるのも楽しいです。
(2)ボールに入れた紫色の半分の生地に水に溶かした重曹を、しっかり混ぜ込みます。まんべんなく色がつくように力をいれてこねましょう。こねていくとどんどん色が変わってきます。
科学の原理
紫芋粉には、アントシアニンが含まれています。
アントシアニンは、酸性では赤色に、アルカリ性では緑色(青色)に変化します。
重曹(炭酸水素ナトリウム)は、アルカリ性の白い粉末状の物質で、酸を中和する作用があります。
紫芋粉を混ぜた団子生地に、水に溶かした重曹(pH8.0~9.0の弱アルカリ性)を混ぜることで、生地の色が変わります。
④団子状に丸めて、ゆでる。
-

団子状に丸める
-

団子が浮いてきたら2分間茹でる
-

白➡紫➡青の順番に別々に茹でる
(1)団子の形を整えます。指の腹や手のひらで丁寧に転がすことを意識すると、きれいな丸になります。ハートや星、猫など形を変えてもかわいく、おもしろいです。
(2)丸めた団子を沸騰した鍋に入れて茹でます。団子が浮いてきたらそのまま2分間茹でます。必ず白➡紫➡青の順番に別々に茹でるようにすることがポイントです。
白や紫の団子では、茹でた後のお湯に変化はありませんが、青色の団子をゆでた後のお湯は青く色づいているのが印象的です。
⑤完成
-

きなこやあんこなど好みの味付けでどうぞ
-

団子の形を変えても楽しいです
お皿やお椀に盛り付けます。器を変えてみると雰囲気が変わり、より楽しめますね。
きなこやあんこなど好みの味付けをしておいしくいただきましょう。
【色が変わる団子作りを振り返って】
・だんごグループ担当だったので、家で一度作ってみました。そのときは、団子粉と豆腐がうまく混ざらなくて固まりにくかったですが、学校でやったときは上手にまとめることができました。手の温度やこねる力も、関係するのかなと感じました。色が変わる瞬間を見ましたが、紫芋粉と重曹が反応しているのを感じました。目で見て感じられるのは、子どもにとっても「化学反応ってすごい!」と実感させることができると思いました。調理実習全体を通して、どのグループも使う食材が少なくてびっくりしました。学校でも、学習したことを生かしながら、「食育」の授業の一貫として取り上げることができると考えました。
・初めてだんごを作ったが、美味しくできた。材料が少なく、生地を作るときに水を混ぜなくてもできたことに驚いた。豆腐の水分が、生地を固めることに関係していると考えた。紫芋粉と重曹を混ぜることで色が変わるとき、少しずつじわじわ変化しているのが面白かった。変化を目の当たりにできるのは、化学変化に興味を持たせるきっかけとなると思う。茹でているときに団子が浮いてくるのは、なぜなのか疑問に感じた。重さは同じだが、形が変形したからだと考える。私たちのグループは、団子を星やハートの形にして茹でて食べた。団子をこねたり、茹でたりする工程を通じて、様々なことを感じられる実験だったと思う。
紫芋のように、酸性やアルカリ性によって色が変わる食品
【酸性】
・柑橘類の果物の汁 ・酢 ・炭酸水 など
【アルカリ性】
・卵白 ・にがり など
酸性・アルカリ性の性質を生かした生活の知恵として、掃除用品があります。アルカリ性の重曹は、油汚れや茶渋などの酸性の汚れを落とすのに効果的です。
また、酸性のクエン酸は、水垢やせっけんカスなどのアルカリ性の汚れに効果的です。
授業の展開例
〇他にも身の回りの食べ物で、どんなふうに色が変わるか実験して、調べてみましょう。
〇調べたものの色の変わり方を分類してみましょう。
青田花怜・伊勢真由子・大黒史織
武庫川女子大学教育学部

藤本勇二(ふじもと ゆうじ)
武庫川女子大学教育学部 教授。小学校教諭として地域の人に学ぶ食育を実践。文部科学省「食に関する指導の手引き」作成委員、「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」委員。「食と農の応援団」団員。環境カウンセラー(環境省)。2010年4月より武庫川女子大学文学部教育学科専任講師。主な著書は『学びを深める 食育ハンドブック』(学研)、『ワークショップでつくる-食の授業アイデア集-』(全国学校給食協会)など。問題解決とワークショップをもとにした食育の実践研究に取り組む「食育実践研究会」代表。'12年4月より本コーナーにて実践事例を研究会のメンバーが順次提案する。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事














 教育イベントリポート
教育イベントリポート 授業実践リポート
授業実践リポート 教育リサーチ
教育リサーチ



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望