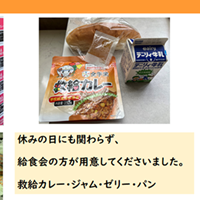自ら考え社会の課題に取り組む若者を育てる主権者教育(後編) 若者に社会を変える成功体験を
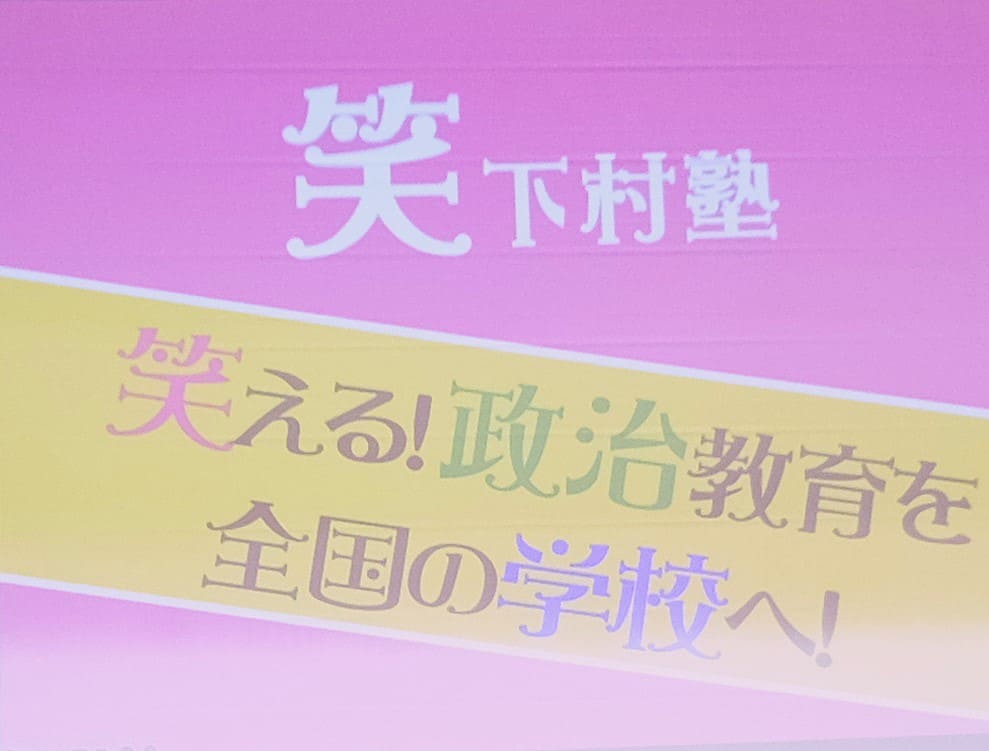
前編では、株式会社笑下村塾が群馬県の委託を受けて今年度県内51校で開催した主権者教育「笑える!政治教育ショーin群馬」の様子を紹介した。後編では、今回取材した館林商工高等学校の伊藤匠未教諭と笑下村塾代表のたかまつなな氏に主権者教育についてお話を伺う。
投票行動から一歩先へ
―—出張授業の様子をご覧になっての印象はいかがですか。
伊藤匠未教諭(以下、伊藤) 社会は変えられるというメッセージ、そのために活用できる手段といった要素が、生徒にストレートに伝わっていると感じました。クイズ形式を取り入れたり、生徒が壇上に上がる場面もあったりして、全員が参加意識を持つように進行されていました。
本校の生徒はどちらかというとおとなしい生徒が多いのですが、今日は積極的に授業に関わっていました。やはり芸人のノウハウはすごいですね。
今日の授業では、自分と同世代の人たちの具体的な話題がたくさん取り上げられていたので、興味を持って参加していたように思います。

たかまつなな氏
―—非常によく練り上げられたプログラムだと感じました。
たかまつなな氏(以下、たかまつ) 伝えるべきメッセージをコンパクトに分かりやすくまとめ上げ、コンテンツの一連の流れをロジカルにかつテンポ良く構成しています。
「笑える!政治教育ショー」は、社会貢献意欲の高いお笑い芸人の方々が協力してくださっており、それぞれの方が実際にパフォーマンスをして感じたことをフィードバックしてくださっています。コンテンツの内容の更新だけでなく、順序や長さも見直して、教材をどんどんブラッシュアップしてきています。
――笑下村塾が取り組む主権者教育について教えていただけますか。
たかまつ 日本では主権者教育というと投票教育となってしまいがちですが、私たちは、改善すべき社会課題に遭遇したとき、それを自分自身の課題として受け止め、どうすれば解決できるかを主体的に考え、仲間とともに行動できる人材を育てていくことが主権者教育だと考えています。
つまり、若者をパートナーとして認め、若者に社会は変えられるという自信を持ってもらう取組です。社会に働きかける方法は投票行動だけではなく、署名活動や議会への請願、マスメディアの活用などさまざまな方法があることも知ってもらいたいですね。
学校ができるのはガイダンスのみ

伊藤匠未教諭
――そういう点から考えると、若者と社会との接点を形成することも重要ですね。
伊藤 高校生は、政治や経済をはじめとして社会について実践的に学ぶ機会が少ないのは確かです。政治経済の授業では、毎時間冒頭で、闇バイト問題やフェイクニュース、地元企業に関するものなど、身近なニュースを取り上げています。
学校としては、生徒が、主権者としていろいろな社会的課題に興味・関心を持つ動機付けをし、その課題について考えるときの切り口をガイダンスする中で、一人ひとりが主体的に行動することを促していきたいと考えています。
――公務員である学校の先生には選挙運動などの政治的活動の禁止制限規定があり、学校教育の中で主権者教育は扱い方が難しい面もあると思います。
伊藤 選挙がある際は、投票に行くように強く促したりはできませんが、自分は必ず期日前投票に行って、「意外と簡単にできたよ」と話すようにしています。有権者として投票に行くのであれば、それぞれの政党の考え方や政策などを理解したうえで投票してほしいですが、おっしゃるとおり、日本の実在の政党の主張や政策の是非といったテーマを授業で扱うのは難しい面がありますので、トランプ氏の主張など海外のものを取り上げたりしています。
投票行動には家庭の影響が強いようです。総務省が2016年10月に行った「18歳選挙権に関する意識調査」を見ると、子どもの頃に親が行く投票について行ったことがある人は、そうでない人と比べて投票した人の割合が20ポイント以上高いという結果があります。身近にいる大人の投票行動が若者に与える影響が大きいと感じます。
海外の主権者教育
教材スライド
たかまつ ヨーロッパにおける若者の政治参加の状況を取材したのですが、日本とは事情が大きく異なっていますね。
スウェーデンは、若者の投票率が8割以上と高いことで知られていますが、その基盤にあるのは、学校教育の中で実際の政党や候補者を取り上げた主権者教育を行っている点だと感じました。25歳以下のメンバーが6割以上いる団体へ年間約45.5億円の助成金を分配するなど、若者への支援も充実しています。
さらに、批判的思考力を育てる授業も行われており、生徒たちは、政治家が本当のことを語っているかどうかを一次資料にあたって確かめるという姿勢も身につけています。
小学校の教科書にも、すべての政党とその理念が掲載されていて、右派・左派のマッピングなども示されています。教育法の中で、現実の政治における政党の考え方を知り、それを批判的に評価する能力を養うことの重要性が掲げられているのです。
選挙というのは、投票所に行くことが目標なのではなく、投票行動を通して望ましい社会をつくろうという意思表示の場だと思うのです。自分の行動が社会を変えられると思うから、選挙に行くし、政治活動もするのです。
では、そうした期待をどのように育んでいくのか。社会を変える場を作ることです。そのポイントは、大人が若者の意見に耳を傾け、どうすれば変えることができるかを一緒に考えることだと思います。
たとえば、学校運営に子どもたちが参加し、具体的な変化を体験できる仕組みを制度化するのも一案です。ドイツのベルリン州では、授業の時間割など学校生活の多くのルールを決め、校長の選任まで行う学校会議に校長、教師、保護者代表に加えて生徒の代表も参加しています。全く同じ制度の導入は難しいでしょうが、その制度が根差している考え方は参考になるように思います。
若者に社会は変えられるという自信を持ってもらう

――そうした海外の主権者教育を踏まえると、今回の出張授業が生徒の中に撒いた主権者としての意識をどのように育て、引き継いでいくかも重要なテーマですね。
たかまつ 子どもの話は聞いた。しかし、フィードバックをせず、何も変わらない。それでは、社会の課題を自分の問題として受け止め、解決に向けて取り組んでいく若者はなかなか現れないでしょう。
自分たちの意見を言うと、周囲の大人たちがちゃんと受け止めてくれて、アドバイスしたり、励ましたりしてくれる。そういう成功体験を積み重ねることによって、子どもたちは主権者に育っていくのです。
――生徒による校則の見直しなど、以前より、学校の先生は生徒の意見を尊重するようになってきたと感じますが、いかがですか。
たかまつ こうして出張授業をしていても、学校の二極化が進んでいると感じます。不手際があっても出張授業の依頼や日程調整まですべてのやり取りを生徒に任せている学校もあれば、「うちの生徒たちにワークショップなどとても無理」と、生徒を全く信頼していない学校もあります。

――今日は「笑える!政治教育ショー」を中心にお話を伺いました。笑下村塾として今後力を入れていきたい取組がありましたら教えてください。
たかまつ リバースメンタリングの活動を広げていきたいと考えています。これは、自治体の首長と高校生が立場を入れ替えて、高校生が首長の相談役になり政策提言を行うというものです。
もちろん、ただ提言するだけに終わらせず、それを社会実装するところまで持っていくことを目指しています。今日の出張授業でも紹介した、群馬県でのeスポーツ大会の開催もその成果の一つです。
また、学校民主主義の法律化にも取り組んでいます。成功体験を積み重ね、それを多くの若者が共有する。そうやって、若者の社会参加を応援していきたいと考えています。
記者の目
笑下村塾が群馬県で出張授業を展開してから行われた選挙では、18歳有権者の投票率が8%上がったという。自分たちがアクションを起こせば社会を動かせる。そうした成功体験を提供し、社会参加の意欲を高めるのだろう。今回のような出張授業と教育現場との連携が今後ますます必要だと改めて実感した。
取材・文:学びの場.com編集部 写真:笑下村塾、学びの場.com編集部
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
「教育リポート」の最新記事














 教育イベントリポート
教育イベントリポート 食育と授業
食育と授業 教育リサーチ
教育リサーチ



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望