新人危機管理コンサルタント奮闘記(vol.4) 応急救護は難しい!?
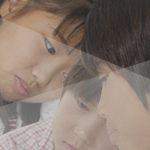
私達は、応急救護が必要とされる場面で、一体何ができるでしょうか? 今回は、子ども達にもできる応急救護について、新人危機管理コンサルタントの須藤綾子がお話します。
応急救護とは ~応急救護は誰にでもできること~
専門機関で応急救護訓練を体験するまでは、必要以上に「応急救護は難しい」と考えてしまいがちでした。医療の専門知識がなくてはいけないのではないか、素人が手を出してはいけないのではないか……。人の命に関わることですから、そのように構えてしまうのは、当然のことかもしれません。
しかし、実際に訓練を受けてみると、専門知識がなくても、誰でも出来ることなのだと感じました。
私達が生活をしている中で、身近な人が倒れたり、事故現場に遭遇したり、あるいは目の前で突然人が倒れたり、ということは有り得ないことではありません。さらに、災害が発生した時に、目の前で人が倒れているかもしれません。そんな時、皆さんはどうしますか?
慌ててしまい、パニック状態になってしまうこともあるでしょう。そんな時、誰でもできる応急救護があります。それは『救急車を呼ぶこと』。
そんなこと? と思われるかもしれません。人の命を救う為に行動を起こすこと、それこそが応急救護の第一歩なのです。
救急車を呼ぶ練習をしよう
心臓マッサージのような具体的な技術がわからなくても、倒れている人に近づくこと、声をかけること、救急車を呼ぶことは、誰にでもできること。子ども達にも出来ることですよね。電話をかけて、119番をする。通話が始まれば、相手の聞いてくることに答えればいいのです。
しかし、119番を知ってはいてもいざというときにかけられないのでは、困ってしまいますよね。そのためにも、ご家庭で119番をかける練習をしてはいかがでしょう。お子さんが119番通報をし、親御さんがそれに対して受け答えてみるという設定です。その逆をやってみるのもいいですね。
例えば、このような感じです。
親 : はい、こちら消防庁。消防ですか? 救急ですか?
子 : 救急です。
親 : どうしましたか?
子 : お母さんがお腹を押さえて倒れています。
親 : 何区(市)、何町、何丁目、何番、何号ですか?
子 : ○○○です。
親 : 電話番号を教えてください。
子 : ○×-○○○○-△△△△
親 : わかりました。
電話はすぐに切らない方がよいです。こちらの様子を伝えることができるし、様子が変わったら、電話でその様子を伝えることができるからで
救急車が来るまでにできることは?
もちろん、その先の手当てができるのであれば積極的に行動するに越したことはありません。しかし、何の訓練も受けていない人はどうしたらいいのかわからず途方に暮れてしまいます。そんな時でも、救急車が来るまで、倒れている人に声をかけ続けること、そっと身体に触れてあげること。このくらいはできるのではないでしょうか。
例えば、気分がすぐれない時やおなかが痛い時に、近くにいる人が『大丈夫? 少し休みなよ』というように優しく声をかけ、背中に手を当ててくれたらどう思いますか? きっと苦しくても安心すると思います。
今回の講習を通して、それだけでも何もしないよりはいいのだと感じました。もちろん、その先の手当てができるのであれば、それを行うことはもちろん必要なことです。
ここまでは、訓練をしたことがない人にでもできることです。でも、訓練を受けているのと受けていないのとでは、実際にその場面に遭遇した時の体の反応が変わってきます。
まずは気持ち、そして正しい知識と技術で救護を
以前、駅で人が倒れている場面に遭遇しました。その時の私は、周りの人が倒れている人に声をかけたり、駅員さんを呼びに行ったりする姿をただ見ていることしかできませんでした。もしもまたそのような場面に遭遇したら……。今度は一歩踏み出そうと思います。応急救護講座を受け、インストラクターの資格まで取ったことが「できる」という気持ちに繋がりました。
私達が行っている防災キャンプでも、災害時に子ども達が救助隊になり、建物内で被災した大人を救出しに行くというプログラムを実施しています。子ども達は、大人が考えている以上にテキパキと動き、教えてもらった知識、技術を使い、目の前に倒れている人を助けようと一生懸命です。子ども達にでもできること。決して難しいことではありません。
皆さんも機会がありましたら、ぜひ、応急救護研修会に参加してみてはいかがでしょう。様々なところでこのような研修会を行っているようですから、親子で一緒に参加してみてもいいですね。
何よりも大切なことは、倒れている人を助けようとする気持ちを持つことです。その気持ちと、一歩踏み出す勇気。ひとりでも多くの人に応急救護を広め、「決して難しいことではない」「人を助けようとする姿勢が必要」だということを伝えていきたいと思います。
(文:須藤綾子)
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事














 算数の教え上手
算数の教え上手 世界の教育事情
世界の教育事情 科学夜話
科学夜話 今どきの小学生
今どきの小学生



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事
