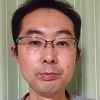ブルース・リー並みのアクションをこなした柴崎コウ
香港映画界のトップスターであるチャウ・シンチーが製作総指揮に入った本作は、日本でも大ヒットした『少林サッカー』にインスパイアされて作られたもの。少林拳を世に広めたいと思い中国で修行を積んで帰ってきた凛が、ひょんなことから大学のラクロス部の助っ人となる展開。となると、どうしたって『少林サッカー』のサッカーがラクロスに変わっただけの映画ではないか……、あるいは『少林サッカー』的な映画を思い浮かべることだろう。
でも本作のタイトルは『少林ラクロス』ではなく、あくまでも『少林少女』。メインは凛の成長物語であり、未知数の“気”の力を持つ彼女を倒そうとし、汚い手で彼女を闇の世界に引き摺りおろそうとする、常に最強を目指す男(仲村トオルが好演)との戦いを中心に描いている。
そこで凛役の柴咲さんに求められたのがアクションだった。なにしろ凛は少林拳の使い手で、少林拳の師匠たちも恐れを成すほどの強い“気”が出ているという設定。当然、少林拳を習うことに。しかし今の日本映画の慌ただしい製作状況では、たいていの場合、役者が練習するといっても3か月間できればいいほう。下手をすれば、「どうせ難しいところはスタントマンにまかせればいい……」と、付け焼き刃でアクションを練習し、こなしていく役者も多い。ましてや女優さんならなおさらだ。
なんと彼女の『少林少女』の役作りは1年! これまでも『日本沈没』や『どろろ』などでワイヤーアクションに挑み、アクションシーンをこなすのは好きだと明言してきた彼女だが、1年間を体作りに費やしたのは尋常ではない。しかも彼女はものすごく体が硬かったのだという。彼女いわく「立位体前屈をしたら指が床に届かないどころか、むしろ逆に手がどんどん床から遠ざかっていくような硬さだった」という。それが1年の歳月をかけて手がぺたりと床に着くまでになった。
それだけではない。今回は観た人が「これなら女性である彼女が大の男たちをなぎ倒すのもわかる!」と納得できるような技を出したいと、付け焼き刃のアクションとしてではなく、武道としての小林拳を鍛練したのだ。その結果、カンフー系アクションに目ざとい人であれば思わず「おおっ!」と乗り出すような、ハンパでない腰を落とした構え方、軸足がキッチリした蹴りのひとつひとつなど、説得力あふれるアクションに行き着いている。なにしろ指導に当たった人が「瞬間的にはブルース・リーなど、神の領域に達したアクション映画のスターと同等のレベルに達した部分がある」と驚嘆していたくらいなのだから。
プロの役者だから危険なアクションも自分で挑む
もちろんそんなアクションに挑んでいるのだから、怪我もハンパではなかった。
例えば一度ワイヤーアクション中にタイミングがあわず、彼女は顔から落下して鼻を強打した。その瞬間、彼女いわく「折れたかと思った」ほど、ものすごい激痛だったそうだ。けれども現場では、彼女はそんなことは一切漏らさず、動揺するスタッフに「大丈夫でーす」と(わざと)のん気な素振りで返答し、氷でちょっと冷やした後、すぐに撮影を続けた。
またラクロスシーンの撮影では、肉離れを。ちょっと足を引き摺っているのは誰の目にも明らかだったが、彼女はあえて何も言わずに撮影にのぞんでいた。
さらに実際に顔面を足で蹴られるという、信じられないような撮影もあった。カンフー映画の都・香港映画界でも、主人公の顔や頭部などを蹴る場合は手に靴を履かせて蹴ったように見せるのが普通だ。それなのにこの映画では「本物のアクションを見せたい」という思いから、実際に蹴るというやり方を取り入れたのである。しかもそれを柴咲さん自身が「是非、挑戦したい!」と言ったというから驚きだ。やり直しなども含め、彼女は数回蹴られることになり、その結果、蹴られた部分は内出血で紫色に。しかし彼女はそれすらも秘密にし、メイクの方に相談し、目立たないようにごまかしてその後も撮影を続行したのだ。
それにしてもそこまでやってしまうのは何故なのか。たまたま柴咲さんにインタビューする機会があり、なぜそこまでしてアクションに挑むのかと問いかけると、彼女は「アクション映画に出るのなら、自分でやるのが当然じゃないですか……」とサラリと言ってのけたのである。彼女の価値判断でいくと自分でやらないなら、アクション映画になんか出るなということなのだそうだ。そして怪我など、彼女の中では取り立てて騒ぐようなことではないらしいのだ。
そう、彼女は本当にプロ中のプロの俳優なのである。プロだから、アクション映画に出るなら、役作りの一環としてアクションをこなすのは当然と考え、できればスタントを使わずに自分でこなそうとするのである(実際、90%以上は彼女自身が演じている。わずかなシーンしかスタントマンは使われなかった)。だからむしろ自分が思ったように動けなくて、悔しくて泣くこともしばしばだったとか。
最近、こんなプロ意識が世の中から欠如している気がしてならない。
筆者は仕事柄タクシーを利用することが多いが、平気で「道を知らないので教えてください」と言う運転手が増えた。中には、ナビゲーターがついているのにそれを使うこともなく堂々と行き方を聞いてくる強者もいる。ただ「駅に行ってほしい」と言っているだけなのに、だ。
タクシー運転手だけではない。どの業界でもプロ意識の欠如は目立つ。最近多い食品業界のトラブルにしろ、住宅問題のトラブルにしろ、そういうプロ意識の欠如が招いた結果ではないだろうか。プロだからと思うからこそ安心してまかせていた部分が、どうにも不透明になり、まかせられなくなりつつある。残念なことに、一部の教育現場でもしばしば同様の事件が起きている。
あるいは事件ではないが、小学生の子どもを持つ友人のほとんどが「学校教育だけでは足りないから」と、こぞって子どもを塾に通わせている実態はどういうことだろう? 学校が教育のプロとして、保護者から信頼されていないということか。
プロだからこそ一般の人が「すごい!」と思うことも当然のようにやらなければならないことがある。柴咲コウさんの姿を見ていると、そんな風に思えてならない。それぞれの現場で、仕事をプロとしてこなすことの意義をもっと考える必要があるのではないだろうか。
相手の立場を考え“赦す”ことの大切さ
ついつい映画のメイキング話ばかりに話が及んでしまったが、作品自体も素晴らしいテーマがある。中でも感動的なのは“赦す”ということ。実はそもそも少林拳というものは、戦いのための武術ではなく、防御から成り立ってきた武術だからだ。戦うことを良しとするものではないからこそ、映画のオチ(ネタバレになるのでくわしくは言えない)が効いてくる。同時に、戦うばかりでなく人を赦すことの素晴らしさも胸に響いてくるのだ。
誰にでも間違いはあるし、行き過ぎた言動が誤解を生むことはよくある。けれどもそれを責めてばかりでは始まらないのではないかと思う。
またタクシーの話で恐縮だが、ある知人がタクシーで激怒した話をしていた。それは自分の指示通りにタクシーが走ってくれなかったからということであった。でもよくよく聞けば、その知人は何度も行き先を変更し(ちなみに知人は酔っていたらしい)、その挙句、タクシーが行き先を間違えたというのだ。これは知人のほうが明らかに悪いといえよう。どんなにプロの仕事をしている運転手でも、行き先をサンザン変更されていたらうっかりミスをすることもあるはず。しかも酔っていたら、本人はちゃんと告げたつもりでも伝わらないこともあろう。
でもその知人は赦そうとしなかったのだ。彼の頭には自分にも非があるはずだという考えは一切ない。
それはどうなのか。人を責めるのは簡単なことだが、自分にも非があるのではないかと考えてみることも必要ではないだろうか。相手の立場に立って物事を見てみれば、おのずと自分のしている事が正しいかどうか、わかると思うのだが。このように最近は相手の立場に立てない人が本当に多くなったように感じる。『少林少女』で柴咲さんが怪我を負っても何も言わなかったのは、プロ意識に加えて、自分が怪我をアピールすることで周囲の空気がどうなるかを考えてもいたからだろう。
時には自分の道理を引っ込めても他者の言葉に耳を貸すことは大事だ。自分のためにではなく友情のために動くことは素晴らしいことなのだ。最初は少林拳を広めたいという欲求だけで動いていた凛が、友情のために、ラクロス部の仲間たちのために動き始めたように。この映画は実にさまざまな感動を秘めている作品である。
- Movie Data
- 監督:本広克行
エグゼクティブ・プロデューサー:チャウ・シンチー
脚本:十川誠志、十川梨香
出演:柴咲コウ、仲村トオル、キティ・チャン、ティン・カイマン、ラム・チーチョン、岡村隆史、江口洋介ほか
(C) 2008 フジテレビジョン ギャガ・コミュニケーションズ S・D・P ROBOT クロックワークス
- Story
- 日本で少林拳を広めるため、本場中国で修業をしてきた桜沢凛。だが日本に戻ると祖父が開いた道場は潰れ、門下生も散り散りに。そんな中、ひょんなことから凛は国際星館大学のラクロス部の助っ人になる。だがこの大学には強さを極めようとする学長・大場がいた。凛のすさまじい“気”を感じた彼は彼女との対決を望むが……。
構成・文:横森文
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
子どもに見せたいオススメ映画
『スパイダーウィックの謎 』 さまざまな教えを発見できるアドベンチャー
原作:トニー・ディテルリッジ、ホリー・ブラック
出演:フレディ・ハイモア、サラ・ボルガー、メアリー・ルイーズ・パーカー、ニック・ノルティほか
(C) 2007 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
構成・文:横森文 ※写真・文の無断使用を禁じます。

横森 文(よこもり あや)
映画ライター&役者
中学生の頃から映画が大好きになり、休日はひたすら名画座に通い、2本立てなどで映画を見まくっていた。以来、どこかで映画に関わっていたいと思うようになり、いつの間にか映画ライターに。『スクリーン』、『DVD&ブルーレイでーた』、『キネマ旬報』など多数の雑誌に寄稿している。 一方で役者業にも手を染め、主に小劇場で活躍中。“トツゲキ倶楽部”という作・演出を兼ねるユニットを2006年からスタートさせた。
役者としては『Shall we ダンス?』、『スペーストラベラーズ』、『それでもボクはやってない』、『東京家族』等に出演。
2022年4月より、目黒学園で戯曲教室やライター講座を展開。
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 教育つれづれ日誌
教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 震災を忘れない
震災を忘れない



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事