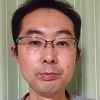2013.02.12
『遺体 明日への十日間』 東日本大震災の遺体安置所となった中学校体育館での群像劇
今回は、テレビ・新聞などでは報道されなかった、東日本大震災の遺体安置所での人々の様子を描いた『遺体 明日への十日間』です。
舞台は、大混乱の遺体安置所となった中学校体育館
3月11日。この日のことを一生忘れることはないだろう。14時46分18秒。その時、私は東京にいた。偶然だが、翌日の用事のために私はホテルを2日間確保していた。そのホテルに入った瞬間、地震が来ることを示すらしいサイレンのような音がそのホテルに鳴り響いた。「え?」と思った瞬間に、あのマグニチュード9.0の揺れ……。一気にエレベーターが止まった。隣のビルは外壁が崩れかけ、すぐに警察が隣のビルを囲って接近できないようにした。
しばらくして地震の震源地がわかった。私のパートナーの親戚たちは、岩手県の海沿いの町にいた。そこで子どもの頃の数年間を過ごした彼は、「津波が心配だな」とポツリと呟いた。そしてその嫌な予感は残念ながら的中し、彼は祖母を含む4人の親戚を津波で失ってしまった……。
恐らくこの記事を読んでいる方の中にも、あの3月11日という日が忘れられないという方は多いと思う。特に津波などで家族や親類を奪われたという方にとってはなおさらだろう。そんな人には、今回紹介する『遺体 明日への十日間』は、とんでもなく胸が詰まる作品になるかもしれない。
しばらくして地震の震源地がわかった。私のパートナーの親戚たちは、岩手県の海沿いの町にいた。そこで子どもの頃の数年間を過ごした彼は、「津波が心配だな」とポツリと呟いた。そしてその嫌な予感は残念ながら的中し、彼は祖母を含む4人の親戚を津波で失ってしまった……。
恐らくこの記事を読んでいる方の中にも、あの3月11日という日が忘れられないという方は多いと思う。特に津波などで家族や親類を奪われたという方にとってはなおさらだろう。そんな人には、今回紹介する『遺体 明日への十日間』は、とんでもなく胸が詰まる作品になるかもしれない。
この映画で舞台となるのは、岩手県・釜石市にある廃校となった中学校の体育館だ。ここは、東日本大震災で犠牲になった釜石市民の遺体が次々に運ばれる場所。映画はこの遺体安置所となった体育館にかかわることになる様々な人達を追っていく。いわば群像劇でもある。
中心となるのは西田敏行演じる地区の民生委員・相葉常夫。かつて葬祭関連の仕事をしていた相葉は、遺体がひっきりなしに運ばれる体育館の様子を見て唖然とする。未曾有の出来事ゆえに皆もどうしてよいかわからず大混乱。とにかく亡くなった方達をどんどんこの中に運び込んでいくしかない。
だがその扱いはとても人間のソレではなかった。津波で海水と泥にまみれた遺体を、青いビニール・シートに寝かせていくのだが、すき間があればどんどんそこに置いていくため、方向も置き方もメチャクチャ。さらに手などが死後硬直で上がったままの人や、膝などが曲がってしまっていてうまく寝かせられない人もいる。すると、現場で働く人達はとりあえず遺体を寝かせようと、その硬直した足や手をバキバキと折っていくではないか。
まさに地獄絵図のような光景。葬祭業をしていた相葉にとっては、その死者に対する態度が許せなかった。いてもたってもいられなくなった相葉は、そこで旧知だった市長に、ボランティアでこの安置所の世話役をしたいと頼み込むのだ。
だがその扱いはとても人間のソレではなかった。津波で海水と泥にまみれた遺体を、青いビニール・シートに寝かせていくのだが、すき間があればどんどんそこに置いていくため、方向も置き方もメチャクチャ。さらに手などが死後硬直で上がったままの人や、膝などが曲がってしまっていてうまく寝かせられない人もいる。すると、現場で働く人達はとりあえず遺体を寝かせようと、その硬直した足や手をバキバキと折っていくではないか。
まさに地獄絵図のような光景。葬祭業をしていた相葉にとっては、その死者に対する態度が許せなかった。いてもたってもいられなくなった相葉は、そこで旧知だった市長に、ボランティアでこの安置所の世話役をしたいと頼み込むのだ。
死者の尊厳を重んじることで、生者の尊厳を取り戻させる
かくして相葉はまず、遺体をあちらこちらに運び込むのではなく、整然と並べるよう指示する。また遺体をまっすぐに寝かせたい時には無理して骨を折るのではなく、ゆっくりと筋肉の硬直をマッサージすることで自在に伸ばすことができることなど、遺体をどう扱ったらいいのか、そのやり方を遺体安置所で働く人達に教えていく。
つまり、相葉が伝えたのはたとえ亡くなろうと、遺体は人間であるということ。人間としての尊厳に敬意を払いながら、接しなければいけないということなのだ。だから相葉は相手が口をきけない遺体だとしても、あたかも生きている人間かのように話しかける。
そういった彼の遺体への接し方、ちょっとした態度が、安置所にかかわる人達の姿勢をも変えていくことになる。
あまりにも辛くて自暴自棄に陥ってしまった人や、何をしてよいかわからず、ただオロオロするばかりの市役所職員など、絶望に近い状況になってしまった人達が、相葉の態度を見て、死者の尊厳を常に重んじながら接するようになっていく。たとえば、最初は呆然とするばかりだったし、「遺体に声を掛けるなんて…」とためらっていた市役所の女性職員は、相葉の真似をして声を掛けていくうちに、遺体の立場になって物事を考え、「どうせなら祭壇を作った方がいいのでは」と、自らアイディアを出し提案するようになっていった。
つまり、相葉が伝えたのはたとえ亡くなろうと、遺体は人間であるということ。人間としての尊厳に敬意を払いながら、接しなければいけないということなのだ。だから相葉は相手が口をきけない遺体だとしても、あたかも生きている人間かのように話しかける。
そういった彼の遺体への接し方、ちょっとした態度が、安置所にかかわる人達の姿勢をも変えていくことになる。
あまりにも辛くて自暴自棄に陥ってしまった人や、何をしてよいかわからず、ただオロオロするばかりの市役所職員など、絶望に近い状況になってしまった人達が、相葉の態度を見て、死者の尊厳を常に重んじながら接するようになっていく。たとえば、最初は呆然とするばかりだったし、「遺体に声を掛けるなんて…」とためらっていた市役所の女性職員は、相葉の真似をして声を掛けていくうちに、遺体の立場になって物事を考え、「どうせなら祭壇を作った方がいいのでは」と、自らアイディアを出し提案するようになっていった。
あるいは自暴自棄だった男が、もう一度踏みとどまってこの死体安置所で働く決意をする。家族を失って悲嘆にくれる者も相葉のおかげで多少なりとも弔いができたと喜んだ顔を見せる。
そう、相葉は死者に対して尊厳を重んじて接することで、何もかも失って人間としての尊厳を失いそうになっていた生者にも尊厳を取り戻させ、希望の光となっていくのだ。
そう、相葉は死者に対して尊厳を重んじて接することで、何もかも失って人間としての尊厳を失いそうになっていた生者にも尊厳を取り戻させ、希望の光となっていくのだ。
一方、驚くような現実も本作は伝える。これだけ身を粉にして働く相葉に対して、「ボランティアは食事を自分で調達する」のが原則だと、握り飯の一つも配られないのだ。彼だって被災者だから昼食などを自分の力で用意できるはずがない。地方から来ているボランティアとはまるで状況が違うのだ。それでも頑張って通っているのに、マニュアルだけに従い、現実を何も考えない担当者のやり方に、メチャクチャ腹が立った。それこそ、法律やルールって何だと思ってしまったし、相葉が動くまで誰も責任を持って何かを貫く覚悟がないことにもいら立った。だが、「たった一人の一生懸命なボランティアにも何もしてあげられない……」、こうしたことは実際、多く起こっているのだろう。怒りと虚しさを同時に感じるシーンでもあった。
それら現場の様子が、とてもリアルに本作では描かれていくのだ。
それら現場の様子が、とてもリアルに本作では描かれていくのだ。
役者たちの生な反応を活かした演出
監督と脚本を手がけた君塚良一氏は、『踊る大捜査線』の脚本家としても知られているが、彼も東京で震災に遭ったものの、仕事に追われすぎていて震災に関して何もできないジレンマを感じながら日々を送っていた。そんなある日、一人のジャーナリスト・石井光太氏が書いたルポルタージュ本『遺体 震災、津波の果てに』を読んで、君塚氏は衝撃を受け、これを映画化しなければいけないと思ったのだという。
つまりここに登場する相葉など、多くのキャラクターには実際のモデルがいるのだ。そしてこの劇中で起きた出来事は真実そのものなのである。
この状況をリアルに再現するために、君塚監督は役者たちに対して感じたままに行動してほしいと伝えたという。つまり一応脚本はあるのだが、もし自分が喋れないと感じたら喋らなくてよいし、逃げ出したいと思ったら逃げ出してもOK。何か言いたいことがあるなら自由にそこに台詞を重ねてもいいという演出を行ったのだ。
つまりここに登場する相葉など、多くのキャラクターには実際のモデルがいるのだ。そしてこの劇中で起きた出来事は真実そのものなのである。
この状況をリアルに再現するために、君塚監督は役者たちに対して感じたままに行動してほしいと伝えたという。つまり一応脚本はあるのだが、もし自分が喋れないと感じたら喋らなくてよいし、逃げ出したいと思ったら逃げ出してもOK。何か言いたいことがあるなら自由にそこに台詞を重ねてもいいという演出を行ったのだ。
こうして生まれたのが監督の目指したリアルな世界観だった。相葉役の西田が遺体安置所に足を踏み入れた途端、思わず「なんだこれ」と呟くが、これは完全に西田のアドリブだったそうだ。また相葉は死者に対する思いなどから、遺体安置所を土足のままで歩き回れないと裸足で歩く。それも西田が出してきたアイディアだそうだ。遺体安置所は畳の上にあるものという感覚なので、どんなに泥だらけでも畳の上は土足では歩けない、だから裸足でずっといたい……と言ってきたのだという。そういう役者たちの生な反応を、この映画は実にうまく切り取っているのだ。
君塚監督はこの作品に対してすべてを背負う覚悟があるという。この映画を作ることで傷口に塩を塗り込むような痛みを覚える人も必ずいる、とわかっていた。それでも監督はこの報道されなかった現実を絶対に伝えなければならないという強い信念を持っていたそうだ。つまり本作は劇映画ではあるが、記録を残すという重要な役割を担うと監督は考えていたのである。
確かに3.11の出来事は決して風化させてはならない。人間は忘れることで生きていく動物ではあるけれど、後世に教訓として残すことも人間の大事な任務だ。そして何気ない日常が、実はとても大切な時間であり、何もないことのありがたみを日々感じていなきゃいけないことを、この映画を観るとつくづく感じてしまう。恐らくこの映画ほど、観終わった後に語り合える映画もないだろう。生徒たちと共に観られるチャンスがあるならば、是非この現実を観てほしいと思う。
ちなみに私はこの映画をパートナーと共に観た。彼も相当に覚悟して観たようだったが、たとえば後味が悪いとか、そういう嫌な思いには一切駆られなかったと言っていた。それだけこの映画が、監督が熱い思いを込めながらも決して押し付けにはならず、客観的に描かれている証拠なのだと思う。まもなくあの日から2年が経とうとする今だからこそ、しっかり観ていただきたい作品だ。
確かに3.11の出来事は決して風化させてはならない。人間は忘れることで生きていく動物ではあるけれど、後世に教訓として残すことも人間の大事な任務だ。そして何気ない日常が、実はとても大切な時間であり、何もないことのありがたみを日々感じていなきゃいけないことを、この映画を観るとつくづく感じてしまう。恐らくこの映画ほど、観終わった後に語り合える映画もないだろう。生徒たちと共に観られるチャンスがあるならば、是非この現実を観てほしいと思う。
ちなみに私はこの映画をパートナーと共に観た。彼も相当に覚悟して観たようだったが、たとえば後味が悪いとか、そういう嫌な思いには一切駆られなかったと言っていた。それだけこの映画が、監督が熱い思いを込めながらも決して押し付けにはならず、客観的に描かれている証拠なのだと思う。まもなくあの日から2年が経とうとする今だからこそ、しっかり観ていただきたい作品だ。
- Movie Data
- 監督・脚本:君塚良一/原作:石井光太/出演:西田敏行、緒形直人、勝地涼、國村隼、酒井若菜、佐藤浩市、佐野史郎、沢村一樹、志田未来、筒井道隆、柳葉敏郎ほか
(c)2013フジテレビジョン
- Story
- 東日本大震災の発生直後、定年まで葬祭関係の仕事に就いていた相葉常夫は、仕事柄遺体に接していたことが多かったこともあり、遺体安置所でボランティアとして働くことに。遺体の一人ひとりに話しかける相葉の姿を見るうちに、膨大な遺体に戸惑うばかりだった市役所職員たちも、一刻も早く家族の元に遺体を戻したいと奮闘することになる。
文:横森文
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
子どもに見せたいオススメ映画
『横道世之介』
青春時代のコミュニケーションの大切さを描く
この映画は長崎から大学に入学するために上京してきた一人の青年・横道世之介の姿と、世之介にかかわっていく人々の姿を追ったドラマだ。マイペースでお人好しなキャラから、次々と友人や知り合いを作っていく世之介。彼を見ていると決して器用タイプの人間ではないが、どんな人ともきちんと向き合っていくことで、財産ともいうべき人とのつながりを獲得していく人間であることがわかる。このコミュニケーション能力の高さが、彼とかかわる人達のその後の人生にも少なからず影響を与えていく。
この映画はそんな世之介の青春時代、1987年頃の世界と、現在が交錯していく所がポイントだ。それにより、人と人とのコミュニケーションがちょっとした出来事を起こしていく様子が伝わってくる。人は人によって影響を受け、変わっていくことを思い知らされる。そう、この映画はいわばコミュニケーションの大切さを描いた作品になっており、コミュニケーションが苦手と言われる若い世代に特に観てほしい作品となっている。中でも、高校生が観るのがベストだろうと思う。
また、青春時代はわずか一瞬であり、だからこそ大切な次期であることもこの映画を観ると伝わってくる。二度と帰らない10代の終わりから20代最初の、人間形成の最終段階をどう生きるのがベターか。この映画を観て改めて考えてほしい。声高に主張してくる作品ではないが、ラスト、胸に響いてくる傑作だ。
監督・脚本:沖田修一/原作:吉田修一/脚本:前田司郎/出演:高良健吾、吉高由里子、池松壮亮、伊藤歩、綾野剛、朝倉あき、黒川芽以、柄本佑、佐津川愛美ほか
(c)2013『横道世之介』製作委員会
(c)2013『横道世之介』製作委員会
文:横森文 ※写真・文の無断使用を禁じます。

横森 文(よこもり あや)
映画ライター&役者
中学生の頃から映画が大好きになり、休日はひたすら名画座に通い、2本立てなどで映画を見まくっていた。以来、どこかで映画に関わっていたいと思うようになり、いつの間にか映画ライターに。『スクリーン』、『DVD&ブルーレイでーた』、『キネマ旬報』など多数の雑誌に寄稿している。 一方で役者業にも手を染め、主に小劇場で活躍中。“トツゲキ倶楽部”という作・演出を兼ねるユニットを2006年からスタートさせた。
役者としては『Shall we ダンス?』、『スペーストラベラーズ』、『それでもボクはやってない』、『東京家族』等に出演。
2022年4月より、目黒学園で戯曲教室やライター講座を展開。
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 教育つれづれ日誌
教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 震災を忘れない
震災を忘れない



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事