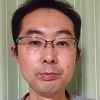映画監督・周防 正行 新作『終(つい)の信託』を語る。 世の中には白黒つけられないものがあることを、子どもたちに教えてほしい。

新作映画『終の信託』を撮られた監督・周防正行さん。今回は、「映画と教育」コーナー特別編として、周防監督へのインタビューをお送りします。終末医療問題、検察官の密室での取り調べといったテーマを扱いながら、映画は何を描き出し、訴えているのか。作品の魅力や見所と共に、映画ライター・横森文さんがお話を伺いました。

『終の信託』は不思議な映画だ。それは観る人が現在置かれている状況や立場、経験などによって、かなり鑑賞後の感想が異なるものになってしまうから。例えば筆者などはとても深いラブストーリーであると同時に、人として大切なものは何か? を問われているような気がした。しかし、別のライターさんによると、ラブストーリーではなく“尊厳死”を大きなテーマとして感じたという。それだけいろんな解釈ができる作品であり、だからこそ面白い。
今回はちょっといつもと形を変え、周防監督へのインタビューを通し、この作品の魅力や見所を綴っていきたい。
まぎれもないラブストーリー

ただラブストーリーだと確信したのは、実は撮影をしている時。江木がクルマの中で自分の死期が迫っていることを自覚し、綾乃に「最期の時は早く楽にしてほしい」と依頼するシーンです。綾乃はその依頼を引き受けつつも、「でもあなたがいなくなったら、私はどうしたらいいの」と返す。通常、医者はそんなことを言いませんからね。あそこで改めてやっぱりラブストーリーなのだと思いました。またそう綾乃に切り返された時の江木役・役所広司さんの何とも言えない表情がいいんですよね。
一方、小説では綾乃に質問を浴びせかける検察官の違法な部分というのが、実は彼の背景も含め丁寧に描かれていますが、映画は検察官の裏の話をあえて排除しています。それは僕が『それでもボクはやってない』の時とは違い、司法そのものではなく、司法に縛られている人間側を描きたいと思ったからなのです。
刑事罰に問うことで、何が起こるか

周防 世の中には割り切れないものがあって、割り切れないものは割り切れないものとして、人々は引き受けるべきだと僕は考えます。映画では、意識を失い延命治療によって生かされている江木に対して、綾乃が安楽死をさせようとする。それを検察官は法律で割り切ろうとしてある断定をするわけです。裁判というのは白黒をつけるものですから。
ところが、裁判制度にはもう一つの基準が用意されています。それは「疑わしきは被告人の利益に」というもの。疑わしい場合は無罪にしましょうってことです。裁判というとただ白黒つけるものだと思われがちですが、実際はグレーなものは白、つまり無罪にしましょうという、曖昧さを許容するシステムになっているのです。それはなぜかというと、人が人を裁くことの難しさを知っているからでしょう。僕はそういう緩さ・寛容さが、今の世の中からどんどん失われてきている気がします。凶悪犯罪は別として、何か少しでも罪を犯した人を徹底的にバッシングする風潮があるでしょう? それはどうなのかと。数年前、管制官の指示ミスで飛行機がニアミスした事件を覚えていますか。
うすぼんやりとですが記憶にあります。
周防 この時、その管制官が刑事罰を問われたのです。これは、実は世界的な常識でいくとあり得ないこと。飛行機のニアミスのような公共の事件の場合、事故はなぜ起きたのか、それを追究する方が後々の事故の回避などに繋がり、公共の利益になります。しかし刑事罰に問う、つまり管制官個人に罰を背負わせることにすると、関係者は皆、自分も罰を背負いたくないから自分に有利なことしか言わなくなるのです。裁判は、真相の解明よりも、自分はいかに罪がないかを言い募る場となってしまうのです。
海外では裁判をすることで公共的に不利益を及ぼすくらいなら、刑事罰には問わず、「何でも言ってください」と関係者たちに接していきます。日本では列車事故でも何でも刑事罰に問うことが圧倒的に多い。それが本当に社会の利益になるかどうかを考えなければいけないはずなのに。罪を犯した人を徹底的に追及することで何が導かれるか? という視点が欠けていると思うのです。このように、社会が寛容さを失うことによって何が起こるのか、そういう部分を教育関係者の皆さんには観てほしいと思います。
今の社会は寛容さを失っている

周防 いじめの内容がエスカレートしてきていますから無理もないと思いますが、学校現場でも警察を介入させてしまいがちですよね。この場合、やはりいじめた子の刑事罰を問うことになります。それが正しい解決法であるとは誰にも断定できないと思いますが、世間の風潮は「いじめた方がとにかく悪い」と、ただただ罰する方向へ向かっているように感じます。
これは、マスコミがいじめ、いじめと騒ぐことも一因ではないでしょうか。マスコミはいじめ問題が生じると、自分たちはいじめ問題に全く関わっていないようなスタンスで報道しますが、マスコミが騒ぐことによって、世間が煽られ過剰なバッシングが起き、一つ間違いを犯した人をボコボコにして立ち上がれなくしてしまうという現象があると思います。いじめ問題に限りませんが、マスコミは報道によって弱い者いじめをしていないかどうかを考えてほしいと思います。
マスコミだけでなく、裁判官であろうと警察官であろうと、人間がやることには間違いがあるものだと、我々は覚えておかないといけないでしょう。映画では、主人公・綾乃がした行為を「医者にあるまじき行為だ」と、社会はたたき切っていいのか? と投げ掛けています。何でもかんでも刑事罰に問う世の中であれば、誰もが自らの保身に走り、どんなことも無難な方向にしか行かなくなるものです。裁判制度でさえ「疑わしきは被告人の利益に」という寛容な基準があるのに、今の社会にはそれが欠けています。余裕、寛容、許容する心を、世の中は持ってほしいと思いますね。
学校教育にもそれは言えますか?
周防 恐らく、学校の授業では正解があったほうが、教えることに関しては楽だろうと思います。しかし現実には、正解がなかったり、白黒つけられなかったりするものがたくさんあります。教師の皆さんには、それを子どもたちにきちんと教えてほしいと思います。物事の本質には、本当はいろんなことがいっぱい関わっているということを伝えてほしい。そして、それを許容する心も。もちろん教師だけでなく、すべての大人たちがこのことを認め、考えなくてはいけない問題だと思っています。
この映画にはある意味、明確な答えは出ない。白黒はつけられない。だがそれをどう判断するのか。どう自分の中に収めるのか。それはまさしく監督が問う、観る人の寛容さの問題そのものである。ぜひこの作品を観て、いろいろと考えていただきたい。
- Movie Data
- 監督・脚本:周防正行/原作:朔立木/出演:草刈民代、役所広司、浅野忠信、大沢たかお、細田よしひこ、中村久美ほか (C)2012フジテレビジョン 東宝 アルタミラピクチャーズ PG12
- Story
- 97年の天音中央病院。呼吸器内科のエリート医師・折井綾乃は、失恋して自殺未遂を。失意の綾乃を癒したのは、彼女の患者で重度の喘息を患って入退院をくり返す江木だった。以来、綾乃と江木は心の内を語り合い、医者と患者の域を超え深い絆で結ばれていく。そんな中、死期を悟った江木は綾乃に“終の信託”をする。そして実際に江木が心肺停止状態になった時、綾乃はついに決断を下す……。

周防 正行(すお まさゆき)
1956年、東京都出身。立教大学仏文学科卒。在学中に高橋伴明監督の助監督となる。1989年、『ファンタシイダンス』で一般映画監督デビュー。『シコふんじゃった。』(1992年)で日本アカデミー賞最優秀作品賞ほかその年の数々の賞を受賞。1996年、『Sall we ダンス?』で第20回日本アカデミー賞13部門独占。同作品は全世界で公開され、絵画でも注目されるようになる。2007年、『それでもボクはやってない』、2011年、『ダンシング・チャップリン』を発表、話題を呼ぶ。
インタビュー・文:横森 文/写真:言美 歩
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 教育つれづれ日誌
教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 震災を忘れない
震災を忘れない



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事