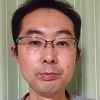世間の目から守る「容疑者家族の保護」
この『誰も守ってくれない』で監督と脚本を手掛けた君塚良一さんは、あの『踊る大捜査線』シリーズの脚本を手掛けた人だ。そんな人の監督作ともなれば、誰もがエンターテインメントな刑事ドラマを想像するだろう。もちろんこの映画もエンターテインメントであることは間違いない。けれども本作は君塚監督がもともと持っていた“社会派”の一面がとても強調された作品に仕上がっている。
ま、考えてみれば『踊る大捜査線』だって、エンターテインメントという枠の中で、警察官を“地方公務員でサラリーマン”という切り口から描き、リアルな組織問題や警察の抱える様々な内部矛盾などにメスを入れたのだから。本格的に社会派に挑めば、このくらいすごいものができても当然だろう。
ごく普通の一般的な4人家族の船村家。物語は、その家の長男がある日、小学生姉妹殺人事件の容疑者として逮捕されるところから始まる。ハンパじゃない残虐な事件。当然、容疑者家族にとってもそれは驚くべき話であり、とても自分の身内が起こした事件だとは信じられない。しかし、警察は容赦なくあがりこみ家宅捜索を始める。
なぜこんなことをするのか? それは執拗なマスコミや世間の目から家族たちを守るためだ。実際、人間は残酷なもの。人殺しを生みだした家族は、その容疑者同様の目を向けられるようになるから。布に液体が落ちて、その染みがどんどん全体に広がるように、ひとりが起こした事件は家族全員に広がり、全員にとっての事件となるのだ。実際、身内の事件がきっかけとなって婚約を断られたり、就職ができなくなったりと、家族がその重荷を背負ってしまうというのはよく聞く話だ。そう、この映画はそういった非常に難しい問題点を、逃げることなく真正面から描き出していく。だからスゴイ。
人間の心に潜む悪意を否定できるか?
映画の視点の中心となるのは、志田未来扮する妹・沙織と、佐藤浩市扮する彼女を守る刑事・勝浦だ。沙織には常にマスコミの目が食らいついていくが、実際はマスコミだけではない。ネットの無責任なユーザーたちも彼女に喰らいつく。格好の餌となった沙織は、不特定多数のネットユーザーたちによって常に追い回されるようになり、ついには写真がネット上に公開までされてしまう。
この映画で一番怖かったのは、そういった“世間の目”だ。マスコミは公のものである認識があるから、まだ歯止めが利くほうだ(それでも時々、節操のない行動に出ることもあるが)。しかし“世間の目”に歯止めは利かない。少なくともその事件が話題になっている間は、誰もがその事件のことをより深く知ろうとする。
そしてネット世界では情報を持っている者がキングになるという現象が、本作中には描かれている。自分の知識を自慢の種にしようとし、平気で何の罪もない少女の写真をネット上にさらしてしまう。その行為がさらにユーザーの暴走をエスカレートさせ、沙織にも罰を与えるべきだという意見がネット上に書き込まれていく。
背筋が寒くなるほどの世間の暴走……。はたしてそれでいいのだろうか。殺人者を育ててしまった家庭の人間は全員悪で、彼らはどうなっても知ったことではないというのか? そんな風に考えてしまってよいものなのだろうか? まだ14歳なのに突然両親と引き離され、さらにマスコミの追跡から逃れるために、見も知らぬおじさん(刑事)とずっと過ごさなければならなくなる苦痛。沙織が受ける仕打ちを観ていると本当に胸が痛くなる。
しかし本作には、演出的に彼女に同情するような場面はひとつもない。そこがすごいところだ。私のように素直に沙織側に寄って見れば、彼女の苦しみを通して人間の悪意の怖さ、集団の怖さ、そしてそんな中でも絆を紡ぎ合おうとする人間の素晴らしさを感じていくだろう。反対に、被害者家族の視線に立ったとしたら? はたして素直に人間の悪意を否定できるだろうか。「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」という言葉があるように、関わるものすべてが憎たらしく見えてしまうのは人間の心理でもある。そしてそれは人間の動物としての本能なのかもしれない。
考えてみれば、教室内でのいじめや全員による無視といった行為も、その心理と通じるところがあるのではないか。自分もいじめられた経験があるので、そう思わずにはいられない。自分と違うものが怖いから、自分を危険にさらすものが怖いから、逆にそれを破壊してしまおうとする衝動が、人間の心の中に湧いてくるのでは?
自分を本当に守れるのは自分だけ
だとしたら、人間はそれにどうやって立ち向かっていけばいいのだろう。
それはやはり、自分で強くなるしかないのだと思う。どんなに辛くてもどんなに苦しくても、傷を癒せるのは自分しかいないのだ。
劇中で勝浦刑事と沙織は、マスコミから逃れるために、海岸近くにあるペンションに身を寄せる。そこのペンションのオーナーは、自分の子どもを殺された経験がある。今でこそまるで仏様のようにニコニコしているオーナーー夫妻だが、その子どもを失った哀しみ、怒りを失ったわけではない(そのことがよくわかる印象深いシーンが登場する)。その思いは常に心の中には渦巻いている。だから沙織が世間を騒がせている犯人の妹だと知った時には怒りが爆発する。
そういうことなのだ。哀しみや怒りは消えない。だが時が経つに連れて、その逆巻く思いをせき止める精神の壁が強くなっていただけに過ぎないのだ。それが強くなることであり、傷を癒すということなのだろう。
そう、本当にタイトル通り、誰も真の意味では守っちゃくれないのだ。人間、いつどんな逆境に襲われるかわからないけれど、それを最終的に乗り越えていくのは自分。沙織の場合は勝浦刑事が世間から保護してくれてはいたけれど、それは一過性のもの。ずっと彼が付いていてくれるわけではない。任務が終われば、事件がある程度落ち着いてしまえば、沙織は嫌でも学校に通い、自分の生活を取り戻していかねばならないのだ。
もしかしたら泣きたくなるような罵倒を浴びせられるかもしれないし、深刻ないじめを受けるかもしれない。でもそれを「お兄ちゃんがこんなことしなければ」なんて恨んだって仕方ないのだ。前を向いて、懸命にポジティブに生きていかねばならない。少なくとも沙織は一連の出来事を通し、誰も頼りにはできないことはもちろんだが、懸命に生きていく勇気のかけらくらいはもらえたであろう。
そういった強さが今の時代、誰にでも必要なのではないだろうか。100年に1度と言われる不況、これまではニートで親のおかげで生活できていたという人にも、無理な時代がやってくる可能性も大きい。究極の格差社会がやってくるかもしれない。貧困のあまり自暴自棄になった人間が、とんでもないバカな出来事を巻き起こすかもしれない。本当にいろんなことが考えられる時代である。こんな時代だからこそ、子どもたちにはひとりで立っていられる“強さ”を教えなければならない。その必要性をこの映画は教えてくれる。
“強さ”は世界各国共通で持つべきもの、そういう普遍的テーマがうまく活かされたからこそ、本作はモントリオール世界映画祭最優秀脚本賞を取ることもできたのだろう。
- Movie Data
- 監督・脚本:君塚良一
製作:亀山千広
脚本:鈴木智
出演:佐藤浩市、志田未来、松田龍平、石田ゆり子、佐々木蔵之介、佐野史郎、木村佳乃、柳葉敏郎
(C)2009 フジテレビジョン 日本映画衛星放送 東宝
- Story
- 平凡な家庭の未成年の長男が小学生姉妹殺人事件の容疑者として逮捕される。東豊島署の刑事・勝浦と三島は、容疑者家族の妹・沙織を保護することに。執拗なマスコミから逃避行を続ける勝浦&沙織たちは、東京を離れて伊豆のとある場所を目指す。そこは事件に巻き込まれ幼い息子を失った夫婦が経営するペンションだった。
構成・文:横森文
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
子どもに見せたいオススメ映画
『ハイスクール・ミュージカル/ザ・ムービー』 進路に悩む卒業間近の高校生たち
出演:ザック・エフロン、ヴァネッサ・アン・ハジェンズ、アシュレイ・ティスデール、ルーカス・グラビール、コービン・ブルー、モニク・コールマン、オレーシャ・ルーリン、バート・ジョンソンほか
(c)Disney Enterprises, Inc.All rights reserved
構成・文:横森文 ※写真・文の無断使用を禁じます。

横森 文(よこもり あや)
映画ライター&役者
中学生の頃から映画が大好きになり、休日はひたすら名画座に通い、2本立てなどで映画を見まくっていた。以来、どこかで映画に関わっていたいと思うようになり、いつの間にか映画ライターに。『スクリーン』、『DVD&ブルーレイでーた』、『キネマ旬報』など多数の雑誌に寄稿している。 一方で役者業にも手を染め、主に小劇場で活躍中。“トツゲキ倶楽部”という作・演出を兼ねるユニットを2006年からスタートさせた。
役者としては『Shall we ダンス?』、『スペーストラベラーズ』、『それでもボクはやってない』、『東京家族』等に出演。
2022年4月より、目黒学園で戯曲教室やライター講座を展開。
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 教育つれづれ日誌
教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 震災を忘れない
震災を忘れない



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事