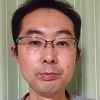『グリーンブック』 アカデミー賞・ゴールデン・グローブ賞獲得の間違いない名作!!
映画は時代を映し出す鏡。時々の社会問題や教育課題がリアルに描かれた映画を観ると、思わず考え込み、共感し、胸を打たれてしまいます。ここでは、そうした上質で旬な映画をピックアップし、作品のテーマに迫っていきます。今回は『グリーンブック』と『スパイダーマン:スパイダーバース』をご紹介します。
人種を分離していた60年代のアメリカ
1960年代。今から約60年ほど前のアメリカでは、差別が当たり前のように行われていた。例えばアフリカ系アメリカ人、いわゆる“黒人”と呼ばれる人達は“白人”と呼ばれる人達と同じトイレを使えなかった。他にも交通機関や水飲み場、学校や図書館などの公共機関、レストランなどなど、白人が有色人種とすべてを分離化することは合法だったのだ。それは1963年11月に就任したリンドン・ジョンソン大統領が大きく働きかけたことで成立することになった、公民権法が1964年7月2日に制定されるまで続いた(もちろん人種分離が合法ではなくなっただけで、根強い人種差別がなくなったわけではない)。
今回紹介する映画『グリーンブック』は、人種分離が合法だった1962年の物語だ。タイトルとなっている“グリーンブック”も、人種差別がひどい南部を旅する黒人が、トラブルなく泊まれる宿の紹介がされている本…のこと。なんだか聞こえはよいけれど、要は黒人はそこ以外に泊まるなということであり、しかもどのホテルも結構オンボロな建物ばかり。何がトラブルなく泊まれる宿なのか。まさに差別以外の何者でもない。でもそれが、1962年ではごく普通のことだったのだ。
この物語の主人公、ニューヨークに住むイタリア系アメリカ人のトニーも差別の概念が定着している。それが現れているのはこんなシーンだ。トニーの家にある日、黒人の修理屋2人がやってくる。トニーの愛妻ドロレスは差別意識のない人なので、冷たいものでもどうぞと修理屋たちにドリンクを振る舞う。が、その様子をチラッと見たトニーは、彼らが飲み終えたコップをまるで汚いものかのようにつまんで、ゴミ箱の中に捨ててしまうのだ。これではまるで彼らをバイ菌扱いしているのと一緒ではないか。
それでもトニーはまだ差別意識は少ないほうの北部の人間だし、一流ナイトクラブのコパカバーナで用心棒を務めているから、様々な人間にも出会っているし、訳ありな人間たちも知っているからまだ良いほうの部類なのだ。
そんな彼が新しい職として紹介されたのが、カーネギーホールを住処とし、ホワイトハウスでも演奏したことがある黒人の天才ピアニスト、ドクター・シャーリーの運転手兼ボディーガード。しかもアメリカ南部を回る演奏旅行を計画したドクター・シャーリーを、安全に次の演奏地へと遅れることのないように送っていく…というのがトニーの任務だった。
肌の色も受けてきた教育も、何もかも違う2人の男が育む友情
もちろん仕事の取り決めの際に面談があるのだが、このシーンがこれまた実に面白い。まるでアフリカの王様のような格好をしたシャーリーが、一段高いところにあつらえた玉座のような椅子に座り、トニーを見下ろすような形で面談が始まるのだ。一見してわかる立場の違い。さらにいえばシャーリーにはインド人の執事がいて、あらゆる身の回りの世話をやいてくれる。
ついでに言うとシャーリーは9歳でレニングラード音楽院の生徒となり、18歳でボストン・ポップス・オーケストラにてコンサートデビューを飾った。また音楽・心理学・典礼芸術の博士号を取得しており、複数の言語も話せる文字通りの天才であり、逸材なのだ。
それに比べ、トニーは腕っぷしは強いし、通称“トニー・リップ”と呼ばれるほど、出任せ&デタラメを吹聴するのは得意だが(つまり頭の回転はとてつもなく早い)、なにしろ学がないので、綴りなどは平気で間違ってしまうし、難しい言い回しは全くもってよくわからない。何か面倒臭いトラブルが生じれば、警官であろうと誰であろうとすぐに殴って解決するようなタイプだ。もちろん礼儀作法なんてものも知らない。だからピザを丁寧に切って食べるなんてことはせず、まるごと手で掴んでワシワシ食べる。食べて「不味い」と思ったら平気でペッと口から吐き出す。車の中から不必要なモノを窓からポイ捨てするのにも罪の意識はない。
当然こんな2人だから、トニーとシャーリーの相性は最悪だ。シャーリーが明らかにトニーとの会話を拒否しているのに、トニーは聞いていようがいまいがおかまいなしにベラベラベラベラ。シャーリーもそんなトニーに遠慮なく、これからいろんな方と会うのだからお行儀を良くしろだの、トニーが同じように集まっていたドライバー仲間たちと賭け事をしているとそんなことをするなと怒る。
落ちていた売り物のパワーストーンをくすねて「しめしめ」と思っていたトニーに、ちゃんと店に返してきなさいと子供にでも注意するかのように怒ったりも。そんな細かいことに口うるさく監視力の高いシャーリーに、もともとガサツに生きてきたトニーは、早くもうんざり気味だ。
そんな2人の心に変化をもたらすキッカケとなるのがシャーリーの奏でるピアノだ。無学でもシャーリーの音楽のすごさを、理論でなく肌身で感じ取ったトニーは、素直にシャーリーを褒め称える。彼の演奏を聞くことを楽しみにしていく。だから嫌がらせのようにゴミが放り込まれたピアノを用意するような主催側には、遠慮なく暴力で言うことをきかせる。お金のためではなく、本気で「彼を守りたい」と思い、本気でシャーリーのことを心配するようになっていく。
一方、幼い頃から普通の人とは違うエリート道を進んできて、フライドチキンすら食べたこともないというシャーリーに、トニーは下々の暮らしの楽しさを伝えていく。またクラシックやジャズなどを聞いてきたシャーリーだが、トニーのおかげでリトル・リチャードなど、一般に流行している曲などを知り、トニーを取り巻いてきた世界をも知ることになる。
そうなるとキチンと描かれていくのは立ち位置の変化。最初に出会った時は、玉座のような椅子から見下され、車の中では常に運転席と後部座席の関係にいた2人が、いつしかバーで隣同士に座っていたり、庶民らしいファーストフード店の外にあるベンチで同じような飲み物を飲んでいたりする。そういう2人の心の変化をとても自然にとらえていく。
これは2019年の現代にもあてはまる物語
もちろん2人の絆が次第に強まっていく展開は、誰にだって予想がつく。しかし本当の意味でこの作品がすごいのは、誰も差別の本当の理由をわかっていないということだ。
シャーリーは南部で演奏をしていく。彼の演奏を聞くために集まるのはハイソサエティな人々。いわゆるお金を持った白人層だ。彼らはわざわざ高いチケット代を求め、わざわざ彼を観るために車を走らせて集う。その素晴らしい演出に、遠慮なく絶賛の拍手を送って、総立ちになって惜しみない拍手をシャーリーたち演奏トリオに捧げる。しかしだ。それなのに主催者側が彼が黒人だというだけでトイレを貸さず、外の掘っ立て小屋のところでするように促す。しかも「あそこでしろというのですか?」と反論するシャーリーに主催者側が返す言葉は「誰も文句を言ってきたことがない」というもの。かと思えば、別の場所で。あるクラブで演奏するというのに、白人であるトリオの他の面々もトニーもそこにあるレストランで食事をしているのに、当のシャーリーだけは拒否される。もちろん理由は黒人だから。ちなみにこのクラブでシャーリーは物置部屋に自分の楽屋を用意されているのだが、その物置部屋でならば食事はできるとマネージャーは告げる。これにはトニーも怒りの声をあげるが、マネージャーは「ご理解ください。この土地の慣習なのです」と言う。慣習!? 演奏はしてくださいとお願いして、客たちもその演奏を楽しみにしているというのに?当時世の中は公民権運動が盛り上がっているという社会情勢だったが、黒人だからという理由で、分離することは当たり前であり、土地の慣習だからという。「じゃあ、お前の考えはどうなんだ!?」と言いたくなるではないか。誰もが差別しているから差別していいということなのか?
それこそ“教育”の問題にあるのではないかと思う。トニーが最初、黒人が使用したコップを廃棄していたように、黒人=差別して当然という図式を誰かが教え込むからそれが当たり前として成り立っていく。肌にいろんなカラーがあるのは当たり前、いろんな文化があるのは当たり前、人と人が違った考え方をするのは当たり前。違う考え方をしっかり取り込んで相手を見る。相手の物差しを持つことで初めて人は人を理解できるのだ。それは片方だけでは成り立たず、双方がそういう考えになって初めて成り立つ方式である。
だが1960年代のアメリカはそういう人達が少なすぎたせいで、なかなかこういった差別がなくならなかった。というより白人と有色人種を分離して何が悪いのかということすら、わからない人が多かったのだ。
トニーも最初はわかっていない人間だった。が、シャーリーと行動し、シャーリーの自分とは違うものの見方、自分とは違う世界を知るうちに、トニーはシャーリーという世界の物差しを持つことで、変わったのだ。そしてこれこそ、そういう変革こそ、無茶とも思える南部の演奏旅行を計画したシャーリーの思いだったのではないだろうか。自分の命をも賭けるような演奏旅行で、彼は問いたかったのかもしれない。忌み嫌う黒人の演奏なのにあなたたちはなぜ聞きたがるのか、そして聞きたがるのになぜ黒人への差別は辞めないのか…と。その答えはこの映画を観た人それぞれが考えるべき問題だろう。
ちなみにこれは実話の映画化だ。最初から最後まで徹頭徹尾、差別問題が描かれているのに、この映画を見て不快な気持ちにはならない。当たり前のように敷かれた差別を自覚すると共に、気持ち良いくらい差別なんてしてたまるものかという気持ちになれる。それは多分、私達もこの映画を観ているだけで新しい物差しを獲得してしまうからだ。そしてもうこの映画を知る前と知った後では考え方が変わってきている自分を自覚するからだ。
ぜひ、この映画を観て学校でも生徒たちと意見を交わしてみたら良いと思う。そうすることが、自分で考えるということが、差別そのものを無くすことに繋がると思うからだ。正直、差別は人種だけではない。女性と男性という性差別もあれば、学歴社会ゆえの学歴差別だってある。会社などでは考え方が人と異なるだけで差別されることもある…。つまりこの話は遠いアメリカの昔の物語ではない。今の日本に住む、私達の物語でもあるのだ。ゴールデン・グローブ賞など様々な賞を獲得しているのも当然だろう。(本作は、アカデミー賞/作品賞を受賞しました。)
- Movie Data
監督・製作・共同脚本:ピーター・ファレリー 製作・共同脚本:ニック・バレロンガ、ブライアン・カーリー 製作:ジム・パーク、チャールズ・B・ウェスラーほか
出演:ヴィゴ・モーテンセン、マハーシャラ・アリ、リンダ・カーデリー二ほか
配給:ギャガGAGA
(C)2018 UNIVERSAL STUDIOS AND STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC. All Rights Reserved.
- Story
ニューヨークの有名クラブで働いていたガサツで無教養なイタリア系用心棒のトニー。店の改装閉店で職を探した彼は、天才黒人ピアニストのドクター・ドナルド・シャーリーの演奏旅行に運転手兼ボディガードとしてついていくことに。そこでトニーはシャーリーを通して黒人の非情な扱いの現実を知り、その後の人生が変わっていくことになる……。
文:横森文
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
子どもに見せたいオススメ映画
『スパイダーマン:スパイダーバース』
この原稿を書いている時点では、まだアカデミー賞は発表になっていないが、『スパイダーマン:スパイダーバース』は長編アニメーション賞を間違いなく獲得するのではないかと思う。これまでスパイダーマンといえば白人の少年または青年のピーター・パーカーがスパイダーマンになるものが主流だった。ところがこの『スパイダーバース』ではブルックリンにある中学に通う13歳の黒人少年のマイルスが主人公。しかも今回はヴィランのキングピンが時空をねじ曲げたせい(亡くなった妻子を違う次元から連れてこようとしている)で、様々な次元のスパイダーマンがマイルスの住む次元の世界にやってきてしまう展開。その中には女性のスパイダーマンもいれば、日本の女学生とロボットによるスパイダーマン、さらにはブタだけどスパイダーマン(ピッグ?)など、本当にいろいろなスパイダーマンが登場するのだ。
そこから見えてくるのは、誰でもスパイダーマンになれる、つまり誰もがヒーローになれる…ということ。実際、マイルスの世界には先に別のスパイダーマンがいた。が、そのスパイダーマンが亡くなり、マイルスがその後を継いで新生スパイダーマンとなるのだ。最初はもちろんヒーローに対する責任感も、自信もなけりゃ、スパイダーマン得意のウェブスウィング(クモの糸を使ってビルからビルへと渡り歩く方法)もできないマイルス。本作はそんなマイルスの成長の物語であり、スパイダーマン=白人という勝手なカテゴリーをも破壊する。差別などは関係ない。本人のやる気さえあれば何にでもなれるということを、ダイレクトに伝えてくれるのだ。
さらに面白いのがマイルスは実写チックなアニメーションキャラだが、そこに日本のアニメ表現もカートゥーンもモノクロも、すべてのアニメ表現方法で描かれたキャラクターが入ってくること。どんな表現もアニメでありだと見せることで、人種の差別をも吹き飛ばす。画で納得させてしまうのである。
この映画は小学生には成長ドラマ&冒険アクションとして楽しめるし、高校生になればこのアニメに込められた差別などへの深い概念が読み取れてそこも楽しめるはず。ただのヒーローアニメではない面白味ある作品だ。(本作は、アカデミー賞/長編アニメーション賞を受賞しました。)
監督:ボブ・ペルシケッティ、ピーター・ラムジー、ロドニー・ロスマン 声の出演: シャメイク・ムーア、ジェイク・ジョンソン、ヘイリー・スタインフェルドほか(日本語版)小野賢章、宮野真守、悠木碧ほか
配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
文:横森文 ※写真・文の無断使用を禁じます。

横森 文(よこもり あや)
映画ライター&役者
中学生の頃から映画が大好きになり、休日はひたすら名画座に通い、2本立てなどで映画を見まくっていた。以来、どこかで映画に関わっていたいと思うようになり、いつの間にか映画ライターに。『スクリーン』、『DVD&ブルーレイでーた』、『キネマ旬報』など多数の雑誌に寄稿している。 一方で役者業にも手を染め、主に小劇場で活躍中。“トツゲキ倶楽部”という作・演出を兼ねるユニットを2006年からスタートさせた。
役者としては『Shall we ダンス?』、『スペーストラベラーズ』、『それでもボクはやってない』、『東京家族』等に出演。
2022年4月より、目黒学園で戯曲教室やライター講座を展開。
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 教育つれづれ日誌
教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 震災を忘れない
震災を忘れない



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事