小学校英語導入への課題と期待
授業と学校を変える「コミュニケーション」の力
宇都宮大学教育学部 渡辺浩行 教授
宇都宮大学教育学部 渡辺浩行 教授
コミュニケーションのための英語教育およびコンピュータを活用した言語教育(CALL)を実践・研究。大学では学生の指導のほか、英語教員の研修にも携わる。中学・高校・大学が連携した「英語教育のあるべき姿」について積極的に提言している。
これからの「小学校英語」を理解できる研修の場を
学びの場.com(以下学びの場) 先生は「小学校英語の必修化」についてどういう考えをお持ちですか。
渡辺浩行(以下渡辺) 前提としてお話しておきたいのは、「英語」と「コミュニケーション」は別物だということです。これは日本語も同じで、「コミュニケーションを伴った日本語」もあれば、「コミュニケーション抜きの日本語」というものも存在します。
私は、「コミュニケーションを伴った英語教育」については、小学校段階から導入する必要があると考えています。
ひとつめの理由は、現在の中学1年生英語科で扱っている言語材料が稚拙で、発達段階に合った年齢、小学校高学年かそれ以下にまで降ろしたほうがいいだろうということ。たとえば小学校低学年ならば、野菜や果物の名前といった簡単な言語材料でも子どもは喜んで授業に参加し、英語で積極的にコミュニケーションをしようとしますが、同じ授業を中学校で行うことはできません。できることは適切な段階でやっておいたほうがいいのです。
もうひとつの理由としては、東南アジアの国々の現状があります。小学校で英語教育を行っていない国は、すでに日本以外には1、2カ国しかありません。
小学校英語の是非については、「国語力を含めた学力低下の問題を優先すべきで、英語は中学校からで十分」といった意見もあります。私は、そうした考え方を持っている人にこそ、外を見てほしいと思っています。アジアの国々も、日本と似たような学力や教育上の諸問題を抱えているのです。しかしそうした障害をクリアし、研修を行って教員の指導技術を高め、小学校で英語教育を実践しているという現実がある。それと同じことが日本ではできないと考える根拠はどこにあるのでしょう。
学びの場 冒頭で、「英語」と「コミュニケーション」は別物というお話がありましたが、この点はどう捉えればよいのでしょうか。
渡辺 「コミュニケーション」というものは、日本語でも英語でも韓国語でも、言語を入れ替えても残っているものです。たとえば、隣の席の友だちが具合の悪そうな顔をしているとき、「大丈夫? 保健室に行く?」と声をかけられるのは日本語のコミュニケーションでしょう。でもその言葉が出てくる前に、相手の表情の変化を読み取ったり、その場の状況も踏まえて「何かしてあげたほうがよさそうだ、どうすればいいだろうか」と考えたりする過程がある。それは、日本語にも英語にも共通している部分なのです。
現在の日本語教育ですら、小学校から高校までを見通しても、こうした「コミュニケーション」という要素は薄い。これまでの英語教育も「コミュニケーション」に目を向けたものではありませんでした。
いまの小学校には、「コミュニケーションを伴った英語教育」を受けてきた教員は少ないですから、「小学校英語」という言葉から、従来の「コミュニケーションを伴わない英語教育」を連想し、不安を感じたり、反発したりするのは当然です。だからこそコミュニケーション・ベースの英語教育を学ぶ教員研修が必要なのです。研修なくして、指導力が身につくはずがありません。
学校間の「温度差・格差」を埋める手だてが必要
学びの場 研修の多くは自治体単位での取り組みになりますから、地域間の格差なども問題になりそうですが。
渡辺 新しいことを始めれば格差は生まれるのは当然です。小学校英語も、実践研究を行っているパイロット校では、ゼロからスタートして多くの苦労を経験しながら成果を上げています。一般の学校とこうしたパイロット校を比較すれば、「格差」があると言えます。
しかし、パイロット校が得たノウハウを地域の他の学校へ広めるような手だてがあれば、先行した学校と同じ課題を抱えて苦労するケースを減らすことができるし、より効率的に学校としての実践の質を高めることができます。こうなれば、「温度差」だとか「格差」を必要以上に問題視することもなくなるでしょう。
そこで重要になってくるのは、国や自治体が、英語を含めた教育に対する長期的な展望を持つことであり、ビジョンを実現していくために継続的な予算措置をとることです。しかし日本には、展望もなければ予算もない。これは教育行政の問題であり、突き詰めれば政治の問題と言えるのでしょう。
学びの場 「人・もの・カネ」をセットにして、実践を支える環境を整備していく必要がありますね。
渡辺 例えばICTの教育利用にしても、PCやネットワークといったものが入ってくれば、それを使いこなす人の問題が出てくる。人を育てて、ものを整備するためにはカネが必要であるというように、互いにつながっているんです。
英語教育では、カリキュラムや教材などが「もの」に当たりますが、これも早急に整備しなければなりません。学校独自にカリキュラムをつくるのは大変ですから、一定のモデルとなるようなものを自治体でつくって学校へ提供する必要があるでしょう。単につくるだけではなく、現場の声を反映したカリキュラムを開発し、学校で実施してみて、見えてきた課題をフィードバックして修正していくという継続的な取り組みが大切です。
学びの場 特区として取り組んでいる事例から、先進的なパイロット校、総合的な学習の一部として扱っている学校まで、英語活動の目的や内容はすでに大きく異なっています。必修化とともに足並みを揃えることはできるのでしょうか。
渡辺 導入後は、さまざまな英語活動のあり方が見られるでしょうね。中学校の授業を前倒しするような事例もおそらく出てくると思います。私は、子どもの実態に合わせて内容をアレンジしてあれば、それでもいいと考えています。文法的な指導なども、子どもの実態から必要と判断されるのであれば取り入れてもいいでしょう。
最初からパーフェクトな活動内容をつくることなど不可能です。大切なのは、ある程度の揺れや誤差は受け入れながら、次につなげること。英語教育に関するさまざまなプロジェクトなどを見ても、せっかく得た成果や課題が次につながらず、単発で終わってしまっている印象が強い。
教育に対する長期的な展望がないことが根本的な問題です。グランドデザインがないままに小手先で変化をつけようとするから、ひとつ案を出すたびにいろいろな方面から問題を指摘され、八方美人的な修正案をつくっているうちに、本当にやろうとしていたことが見えなくなってしまう。「ゆとり教育」などはまさにそうでしょう。
先生も子どもと一緒にコミュニケーションを学び実践する
学びの場 内容に揺れや誤差が出るとしても、小学校に英語が本格的に導入されることは大きな変化ですね。
渡辺 その通りです。そして導入する以上は、これまでの教育や、英語教育が抱えてきた問題を少しでも改善する方向に持っていきたい。そのとき、教育を動かしていく力になるのは、「英語」ではなく「コミュニケーション」という要素なのです。
私は指導者として古山小学校を何度も訪れていますが、先生方は、英語でのコミュニケーション活動を実践するようになって、子どもたちが変わったと話しています。そこで、ほかの教科でも「コミュニケーション」を重視するようになったと言います。
子どもたちがコミュニケーションする姿を見るということは、一人ひとりに目を向け、その変化を見取るということです。そこから、授業そのものを子ども中心に捉えようとする視点が生まれました。教師の指導テクニックよりも、子どもの変容を重視するようになってからは、先生自身が自らの授業を積極的に公開するようになりました。そして養護教諭の先生まで授業研究に参加し、それぞれの目で見た子どもの変化を報告し、オープンな議論ができるようになったそうです。
自分の授業を人に見せて指導技術を評価されるのを嫌がるといった、日本の学校現場が持っている風潮や文化も、「コミュニケーション」の導入によって一新される可能性があるのです。
私自身は、こうした変化が他の校種にも伝わることを期待しています。小学校英語という新しい要素が入ることによって、中・高・大学の先生も「コミュニケーション」の大切さに気づき、自分の授業を見直してくれるといいですね。
学びの場 これから英語必修化を前に、不安を感じている小学校教員も多いと思いますが。
渡辺 現場の先生方の多くは、自分に英語指導の知識がなく、言語習得のプロセスも知らないことを不安に思っているかもしれませんが、必要以上に心配することはありません。
知っているほうが望ましいことは事実ですが、「私たちは英語のプロではないのだから、知らない」という認識を持つことによって、かえって子どもの反応を注意深く見るようになるのですから。
そして、いま現在のこともそうですが、1年後、3年後も見据えながら、自分の英語でのコミュニケーション力を、子どもたちと一緒に磨いていってほしいと思います。子どもと一緒に学ぼうという前向きな姿勢を持っている人は、英語でコミュニケーションする力も自然と身につけていくものですよ。
小学校英語の必修化をめぐる動き
小学校での英語活動の必修化が話題になるのは今回が初めてではない。
2005年10月には中教審の答申に、「小学校段階における英語教育の充実」が盛り込まれたことが大きく報じられた。
翌年3月には、先の答申を受けた専門部会が「高学年で年間35時間程度」といった具体的な枠組みを検討していることが明らかとなり、賛否両論を呼んでいる。
今年8月には、指導要領改訂に伴う教育課程の再編成により、主要教科の時数増加とともに「小学校英語」のための時間枠を確保する方針を文科省が固めたとしてメディアに取り上げられた。
必修化に対しては、現状では否定的な意見が多い。学びの場.comが今年9月に行ったアンケートでも、「反対」が7割を占めた。理由としては、「既存教科の基礎基本の定着が最優先」「英語の前に国語力を育てるべき」といった声が目立つ。また、教員の英語指導力の不足、カリキュラムや教材の未整備など、「教えるための環境が整っていない」という現実もある。
「目的があいまいなまま導入しても、現場は混乱するだけ」という指摘も厳しい。そもそも「小学校英語」という言葉自体、目的や内容に対する共通理解がなされないまま、必修化の要・不要論とともに一人歩きしてしまった印象がある。
「小学校英語」の目的や内容に関しては中教審委員の見解も割れており、最近では「小学校段階における外国語活動(仮称)」という用語が使われるようになるなど、表面上の「英語色」は薄くなっている。この活動については現在、「教科としては位置づけず、数値的な評価も行わない」ものとし、「国が共通教材を提供することも検討中」とされているが、最終的にどのような形で学校現場に導入されるのか、先行きは不透明だ。
 初代文部大臣の森有礼は、近代学校制度の創設に尽力する一方で「英語公用語化論」を主張した。戦後、小説家の志賀直哉は、「60年前、森有礼が英語を国語に採用しようとした事」を想起しつつ、「不完全で不便な日本語」と別れて、フランス語を国語にしてはどうかと提言した(「国語問題」、1946年)。それから60年後、この国は「小学校英語」で揉めている。森や志賀の壮大さに比べると今回の構想はスケールこそ小さいが、検討すべき課題は山積みだ。ならばこの機に、学校教育での国語と外国語のあり方や、「コミュニケーション」をどう教え学ぶかといった大きなテーマを、社会全体でじっくり話し合うべきではないだろうか。導入の是非を論じるのは、それからでも遅くはない。
取材・文:栗林俊晴/写真:言美歩 ※写真の無断使用を禁じます。 | 
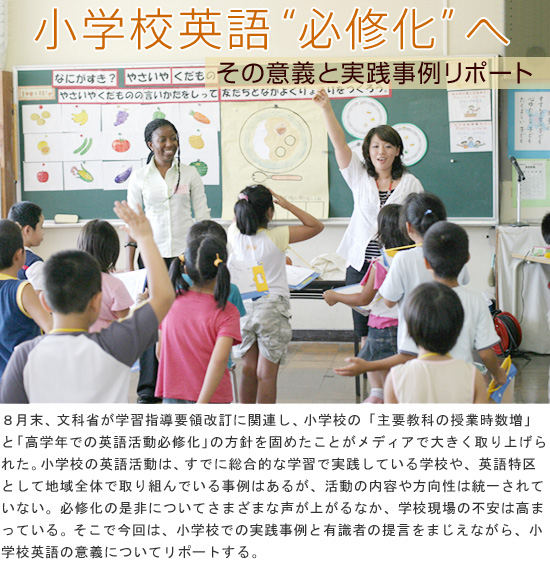





















 教育イベントリポート
教育イベントリポート 食育と授業
食育と授業 教育リサーチ
教育リサーチ













 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望

