ICT教育・初心者向け実践ガイド

ICT活用の授業に興味はあるけれど、どんなことから始めればよいかわからない、ICTでどんな授業ができるのか知りたい、といった疑問を持つICT初心者の先生方のために、中川一史・メディア教育開発センター教授のアドバイスと、手軽にトライできる活用法を合わせてご紹介します。
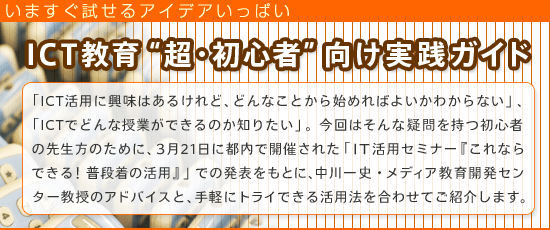 |
 |
| |
|
|
しかし「授業でのICT活用」となると、教師間でかなりの差が生じているという現状があります。ここでは、初心者の先生がこれからICTを活用していく際の工夫として、3つの点を提案したいと思います。 まず、「効果と手間のバランスを考える」こと。機器の準備に膨大な手間がかかるのに得られる効果は少ないという無理のある活用は定着しません。たとえば、プロジェクターや実物投影機のケーブルをあらかじめセットした状態でカートに置いて、使いたいときに手軽に持ち運んで使えるようにしておくなど、手間を軽減する配慮が必要。学校全体で初心者の先生をサポートしてあげるような体制づくりも求められます。 次に、「アナログとデジタルのよい関係づくり」。プロジェクターで画像を提示するだけでなく、手書きの書き込みを組み合わせることでよりわかりやすく伝える、情報の共有化と焦点化にはプロジェクターや電子情報ボードを使う一方、蓄積と整理は板書で行うなど、デジタルとアナログの特徴を理解したうえで、上手に役割分担することが大切です。  中川一史(なかがわ・ひとし) 独立行政法人メディア教育開発センター 教授。横浜市の小学校・教諭、横浜市教育委員会情報教育課・教諭、金沢大学教育学部教育実践総合センター助教授を経て現在に至る。専門は教育工学、情報教育。
|
|
| ||||||||
|
事例1「提示+書き込み」で、授業をもっとわかりやすく | ||||||||
|
 事例提供:綾瀬市立 土棚小学校 河崎睦 教諭 | |||||||
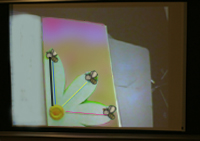 |
学習課題をつかむ 教科書の単元導入ページを実物投影機で提示。掲載されているイラストを指し示し、「3匹のハチのうち、どれが一番先にハチミツまで行けるだろう」と疑問を投げかけ子どもの関心を高める。ここで3本の直線の長さを比べるという学習課題を理解させ、「どうやって確かめたらいいかな」と発問し、子どもに意見を出させる。必要に応じて子どもにもスクリーンや投影機を使って発表させる。 | |
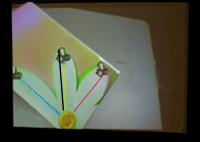 |
比較して理解する 画像を提示したスクリーン上で、1本の直線をペンでなぞる。教科書を回転させて、他の2本の直線と、ペンでなぞった線を重ねて長さを比べる。その都度、「青と黄色を比べると、青い線のほうが長かったね」とわかったことを述べ、子どもの反応を確かめる。 | |
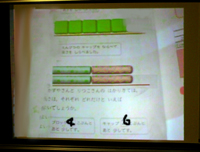 |
まとめを書き込む 教科書のまとめの欄をスクリーンに提示し、比較した結果を空欄に書いて見せる。子どもにも各自手元の教科書に同様の書き込みをするよう指示。机間指導で全員が正しく書いていることを確認する。 |
| 教科書を使った授業では子どもが下を向いてしまうが、プロジェクターで大きく提示することにより、全員が同じ方向を見ながら学習に集中することができる。「提示した画像の上から書き込む」という活用法は、テストの答え合わせやワークシートを使った学習にも応用できて便利。印刷物は暗く不鮮明に映ることもあるので、画面の見やすさを常にチェックするようにしたい。 | |
|
事例2デジカメ写真を題材に、学習のまとめを楽しく | ||||||||
|
 事例提供:前・金沢市立 三谷小学校 小林祐紀 講師 | |||||||
| 学んだことを振り返る まず、模造紙でつくった三角形と四角形のモデルを掲示する。単元の学習を振り返り、三角形と四角形がそれぞれ何本の直線で囲まれているかなど、図形の特徴を押さえ、板書する。次に「この教室のなかにも、三角形と四角形のものはあるかな」と投げかけ、黒板や三角定規など、子どもたちが見つけたものと図形をその場で発表させる。 | ||
| 写真を見ながら考える 「先生も学校のなかである形を見つけたよ」と子どもを引きつけ、事前に撮影したデジカメ写真をプロジェクターで提示。「どんな形が隠れているかな」と問いかけ、「2本の電柱と地面を囲むと三角形になる」、「ジャングルジムにはたくさんの四角形が隠れている」などの意見を引き出す。子どもにもスクリーン上に書き込みをしながら発表させる。 |
  |
デジカメで撮影し、発表する 子どもにスクリーン上に書き込ませて発表させる。 |
「みんなで学校のなかに隠れている形を探してみよう」と課題を提示。グループに分かれ、身の回りの図形をデジカメで撮影し、発表する活動へ移る。その際、「三角形と四角形を探す」という活動目的をしっかり理解させ、無関係な図形を撮影しないように誘導することが大切。発表は、撮った写真をプロジェクターに映して一人ずつ行うが、時間がない場合はグループでおすすめの1枚を選んで発表させる。 |
| 「教室外のものを、教室内に持ち込める」というのはICT活用の利点のひとつ。写真を使った活動は子どもも興味を持ちやすく、楽しみながら学習のまとめができる。提示する写真に無関係なものや人物が写っていると、子どもはそちらに注目してしまう恐れもあるので、トリミングなどの下準備も必要。 | |
|
事例3 準備不要の手軽さで、教科書ベースの授業が充実 | ||||||||
|
 事例提供:川西町立犬川小学校 鈴木誠 教諭 | |||||||
| 前時の学習を振り返る デジタル教科書の該当ページを提示し、「宇宙人からのメッセージを読みやすく書きかえる」という前時の学習内容をおさらいする。修正した箇所には画面上でラインを引くなどしてわかりやすく伝える。また、「方言と共通語」「常体と敬体」「敬語」「漢語」など、文章を修正する際の着眼点は板書で残し、この後の作業で子どもが随時参照できるようにしておく。 |
 デジタル教科書の画面を出力したワークシートも利用する。 「学んだことを生かして、別の宇宙人からのメッセージも書きかえてみよう」と本時の学習課題を示す。板書したポイントを再度確認し、作業の方向性を子どもたちに理解させる。デジタル教科書の画面を直接印刷したものをワークシートとして配布し、時間を区切って各自で作業させる。 |
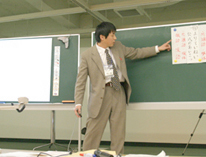 板書したポイントも確認しながらまとめる。 デジタル教科書の該当ページを提示。修正した箇所と書き直した文章を、電子情報ボード上で書き込んで発表させる。「常体をていねいな言葉に代えると読みやすくなる」など、板書したポイントとの関係についてもフォローし、共有を図る。 |
| 教科書の課題文を板書したり、事前に拡大コピーしたりする手間が省けるのは大きなメリット。反面、電子情報ボードの文字サイズは板書に比べて小さいので、後方の子どもには書き込まれた文章が読めない可能性もある。必要な場所はズーム機能で拡大提示するなどの配慮も必要。 | |
|
|
| 授業でICTを活用するメリットは? | ICTを活用すると子どもの学力は上がる? | ||
| 1つめは、「大きく見せられる」こと。教科書や資料集の写真なども拡大してわかりやすく伝えることができます。2つめは、「動く」こと。たとえば家庭科の調理や裁縫の手順などは、言葉や写真で説明するより動画で見たほうがずっとわかりやすいし、体育の跳び箱運動のフォームを動画で撮影し、その場で確認させるといった活動もできます。3つめとして、「やり直しや繰り返しが容易」という点があります。これにより、限られた時間でも子どもたちに試行錯誤する機会を与えることができます。 | 学校現場でのICT活用が進んでいるイギリスでは、教師のICT活用スキルと子どもの学力の関連を示すデータが出ています。わが国でも、文科省の委託を受けた外部研究機関などが検証を行っており、ICTを活用した指導と子どもの知識定着の相関性が実証されつつあります。授業のどの場面で、どのようにICTを活用すると、どんな学力が向上するかといった細かい点に関しては、今後さらに精査が必要です。 | ||
| 初心者におすすめの活用方法・機器は? | 活用するうえで注意したいポイントは? | ||
| 教科書や資料集などのアナログの素材を、プロジェクターなどで大きく写して説明するという使い方がもっとも手軽。これまでの授業スタイルを崩さずに、ICTのメリットを効果的に取り入れることができます。機器としては、操作の簡単な実物投影機やデジカメから入る先生が多いようです。具体的な活用方法については、今回紹介した模擬授業や、学びの場.comに掲載中の「ICT活用『日常化』へのヒント」などが参考になります。 | ICTを使うと子どもの意欲が上がるという捉え方がありますが、あくまでもベースにあるのは「学びそのものの面白さ」であり、そこにICTによる効果がプラスされることで意欲が高まるという点を見落としてはいけません。「ICTさえ使えば何とかなる」のではなく、きちんとした授業設計のなかで、使う場面や効果を見きわめたうえで活用するからこそ、授業改善という結果が出るのです。「教師が授業におけるICT活用をどうデザインするか」がもっとも大切なポイントと言えるでしょう。 |
| (取材・文:栗林俊晴/写真:言美歩 ※写真の無断使用を禁じます。) |
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事














 教育イベントリポート
教育イベントリポート 食育と授業
食育と授業 教育リサーチ
教育リサーチ



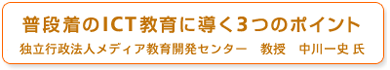
 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望

