企業は地域に対して何ができるか? 金富小学校と凸版印刷の共同プロジェクト

文京区立金富小学校では、総合的な学習の時間として、昨年11月より、同区内に拠点を置く凸版印刷株式会社と共同で、「プロジェクト金富~新入生へ学校のアピールポスターを作ろう~」(以下「プロジェクト金富」)という実験授業を行っている。
|
同プロジェクトは、凸版印刷が、財団法人コンピュータ教育開発センター(CEC)が公募した「情報経済基盤整備事業」に「私たちの生活と印刷」というテーマで応募したものが採択され、その実践授業対象校として、金富小学校に協力を要請したことに端を発する。 どのような経緯で、金富小学校に白羽の矢があたったのか、プロジェクトは実際にはどのように進行したのか、金富小学校の浅川宣夫校長先生にうかがった。 |
 |
■金富小と凸版印刷の出会い この「プロジェクト金富」は、「企業は地域に対し、何ができるか」という課題に対する答を模索していた凸版印刷と、「地域の企業と何か共同でできないか、と常にアンテナを張っていた」という浅川校長先生が、まさに出会うべくして出会ったと言うべきプロジェクトである。 「金富小学校は、5年前から地域をテーマとした学習には力を入れてきたのです。それが総合的な学習の時間に受け継がれていったのですが、都心の学校なので、山や川はない。周囲の企業や工場の見学はしていましたが、ただ見学だけではつまらない。何かもっと面白いことを、企業と共同でできないかとずっと考えていたのです」 |
|
具体的には、どのようなきっかけで、今回のような産学共同プロジェクトに結びついたのだろうか。 「日頃から、町内会をはじめ、地域のコミュニケーションは密に取っていまして、その都度、企業と交流したいということをふれ回っていたのが、回り回って繋がったのでしょう。直接企業に飛び込むのは難しいと思いますが、地域で、その企業に関連のある人が間に立ってくださるとスムーズに行くのではないでしょうか。
|
|
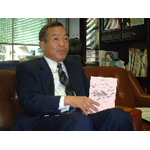 |
凸版印刷とのコラボレーションは、今回が初めてではなかった。 「凸版さんが100周年記念事業で、コンサートホールを建てられたのですが、今まで校内でやっていた音楽会を、そのホールでやらせていただきたいとお願いしたのが最初です。ピアノの調律までしていただき、ホールはもちろん無料で貸していただいたので、凸版さんの方では相当な負担になったのではないでしょうか。その後もホールを借りて『小中学生にクラッシックを聴かせよう』という企画を立てまして、一般の人からは多少入場料をいただきましたが、児童・生徒たちは無料で演奏を聴かせる、ということをやりました」 それらの活動により、交流の土台ができていたところに、今回のCECの実証実験の話が転がり込んで来た。 |
 |
■一過性のイベントならやりたくない 「こういう産学共同のプロジェクトというのは、言葉は悪いですが、打ち上げ花火のようなもので、そういう授業ならやりたくなかった。1回限りでなく、他の教科のように、一単元という枠のなかでどう構成していくか、きちんと計画した上で実施して、評価もしなければ意味がない。凸版さんにもそれを話し、理解していただけたので、やってみることにしたのです」 実施にあたって、5名の教師たちでプロジェクトチームを作り、凸版印刷との事前打合わせが続いた。授業のおおまかな構成は、「新1年生のために金富小学校をPRするためのポスターを企画し、版下を作り、印刷して、新1年生に配布したり、地元の町会や商店、企業に交渉してポスターを貼らせてもらったりする」というもの。同時に印刷のしくみも学ぶ。 |
|
|
■企業と学校の考え方には大きなズレが 「面白いことに、互いに出したものの内容は全く違った。学校と企業の考え方には大きなズレがある、と痛感しました」 そのズレとはこういうことだ。 「凸版さんは、あくまでも完成させることに重点をおいていました。それに対し、我々は、途中の試行錯誤に重きをおいていた。凸版側の提案は、印刷の知識や制作過程を順序だてて説明するものですが、こちらから出したのは、ポスターを作ろう、それだけです。その中で子どもたちがどのような課題を見つけて、それをどう解決していくかが一番重要なのです」 実際の授業の実施までの時間のほとんどは、そのズレを埋めて行くための作業であったと言っていい。 「最初は、凸版さんには数時間協力していただければいいと思っていましたが、結局20時間も費やしてもらうことになった。もちろん、こちらも時間をかけています。しかし、この授業がうまくいって、来年以降も続けていけるということになったら、今回のプロセスは、貴重なノウハウになるでしょうね」 |
 |
■主体的に総合学習をどうするか考えなければ 実際の授業の模様は、学びの場.comの「教えと学びの実験室」にも報告しているが、子どもたちは、たとえばインキを混ぜてイメージ通りの色を作る、という大人にとっては何でもないような作業の中でもたくさんのつまづきや、発見を経験する。机を汚さないように作業するにはどうするか、どうやったらローラーにまんべんなくインクをつけられるか。まさに、試行錯誤の連続だ。 「ただ作ればいいのだったら、極端に言えば、キットを買って来て組み立てさせるだけ、ということにもなりかねない。それでは総合的な学習の時間ではない。また、凸版さんからは、コンピュータで原稿を作るDTPを子どもたちにやらせては、という案もありましたが、私はバーチャルな世界ではなく、実体験にこだわりたかった。総合的な学習の時間から実体験をとったら何が残るでしょうか。 |
|
■関連サイト |
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事














 教育イベントリポート
教育イベントリポート 食育と授業
食育と授業 教育リサーチ
教育リサーチ




 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望

