「電気」って何だろう?
私たちの身の回りには、「電気」についての話がたくさんあります。
現在、学校の理科で「電気」を扱うのは小学校3年生からで、そこでは「電気」による現象を力、熱、電気の働きと関連付けながら学んでいます。中学校理科第2学年「電流とその利用」の単元には、「電気」という言葉はあまり多く出てきませんが、新学習指導要領ではその単元の中に「電気とそのエネルギー」の学習があり、ここでは「電気」の説明よりも熱などのエネルギーについて学習することが中心となっています〈表1〉。
|
小3
|
電気の通り道 ・電気を通すつなぎ方 ・電気を通す物 |
|---|---|
|
小4
|
電気の働き ・乾電池の数とつなぎ方 ・光電池の働き |
|
小5
|
電流の働き(小6から移行) ・鉄芯の磁化、極の変化 ・電磁石の強さ |
|
小6
|
電気の利用 ・発電・蓄電 ・電気の変換(光、音、熱などへの変換) ・電気による発熱 ・電気の利用(身の回りにある電気を利用した道具) |
|
中1
|
|
|
中2
|
電流 ・回路と電流・電圧 ・電流・電圧と抵抗 ・電気とそのエネルギー(電力量、熱量を含む) ・静電気と電流(電子を含む) 電流と磁界 ・電流がつくる磁界 ・磁界中の電流が受ける力 ・電磁誘導と発電(交流を含む) |
|
中3
|
残念ながら、電気の学習は中学生にとって苦手のひとつと言われています。小学生の頃には喜々として電気の勉強をおもしろいと思っていた子どもが、中学生になると「電気」の学習を苦手だと感じてしまう理由のひとつに、「電気」が「電流・電圧」や「回路」にいつのまにかすり替わっていることがあげられるのではないでしょうか。
電気について、昔の人たちはどのように研究をしたのでしょうか? 本稿では、紀元前から19世紀ころまでにかけての電気の研究の歴史をたどりながら、昔の人たちが電気について興味を持って調べた様子を振り返ります。電気のおもしろさや不思議さを現在の中学生にも感じて欲しいと思います。
電気の語源は宝石の「コハク」
コハクは、数千万年~数億年前、地上に繁茂していた樹木の樹脂が土砂などに埋もれて化石化した樹脂の化石です。世界最古のコハクは約3億年前のもので、イギリス最北地域のノーサンバーランド(Northumberland)や、シベリア(Siberia)で発見されています。
コハクは昔から宝石のひとつとして愛用されていますが、宝石は真珠やサンゴなど、一部が動物に属するほかはほとんどが鉱物で、コハクのように植物に属するものは極めて珍しいものです。コハクのもとになった樹脂というと、松ヤニを連想します。
しかし、実際にコハクのもとになった樹木は広葉樹から針葉樹までさまざまです。時代によっても、もとになった樹木の種類は異なり、現生の樹木もあれば、絶滅した樹木もあります。主なものは、新世代第三紀のおよそ3000万~6000万年前にヨーロッパ大陸の豊かな森林地帯に繁茂した「こはく杉」から滲み出した樹脂が、土中で硬化してできたもので、成分はコハク酸などの樹脂酸です。
コハクは透明から半透明で、色は乳白色、淡い黄色、黄褐色、蜂蜜色などがありますが、珍しい物として蛍光性をもった青、赤、紫、黒などのコハクもあります。
「コハクの中のハエ」は広く知られていますが、そのほかハチ、チョウ、アリ、クモなどが取り込まれているコハクが見つかっており、苔や各種の植物が含まれていることもあります。コハクの内部を拡大して見ると、閉じこめてられた数千万年前の世界をのぞくことができる珍しい宝石といえます。〈写真1〉に、コハクの一例を示します。
ウィリアム・ギルバートの電気の発見

〈図1〉ギルバート肖像画(ウィキメディア・コモンズより)
コハクを擦るとほこりなどの小さいものをひきつける現象はギリシャ時代に見つかっていましたが、結局2000年以上もの間、科学の研究対象にはなりませんでした。これを初めて研究したのがイギリスの物理学者ウィリアム・ギルバート(William Gilbert, 1540-1603)〈図1〉です。彼は、医師としての仕事のかたわら静電気、磁石の研究を約20年にわたり行い、実験を用いた近代的な科学の先駆けとして、その後の科学者に多大な影響を及ぼしました。
彼はいろいろな物を擦ってみて、硫黄、樹脂、ガラス、宝石類、皮、布、ロウなどにもコハクと同じ現象が起こることを発見しました。コハクを示すギリシャ語名elektronからelectricity(電気)という言葉を初めて作ったのも彼でした。
また、彼は鉄を磁化する方法や、地球自体が大きな磁石で、その磁極が地理上の南北両極の近くにあるなど多くの発見をしており、「磁気学の父」といわれています。
電気の引力と斥力の発見

〈図2〉ゲーリッケ肖像画(ウィキメディア・コモンズより)
ドイツのオットー・フォン・ゲーリッケ(Otto von Guericke, 1602-1686)〈図2〉という人が、1663年に静電気を大量に作り出すことの出来る摩擦起電機を発明しました。彼は、コハクが羽毛を吸い寄せることに興味を持ち、コハクを強く擦ってこれを他の物体に近づけると、パチパチと音を立てることや、暗闇の中でわずかに光ることを発見しました。
彼はもっと強い電気を作ろうと、コハクの代わりに硫黄を用いて直径25cmの球をつくり、これに軸をつけて回転させ、乾いた手を触れると強い電気が発生しました。 この装置は、何度でも電気を取り出せる機械としては世界初のものであり、彼はこれを使って電気には引力だけではなく、斥力もあることを発見しました。
静電気の発見と2種類の静電気
イギリスのステファン・グレイ(Stephen Gray, 1666-1736)は、1727年、電気が自由に伝わる物質と、発生した電気がその場所に留まる物質があることを発見し、物質を、金属などの導体と、樹脂などの絶縁体とに分類しました。彼は「導体にも絶縁体と同じように電気が発生するが、導体は電気を逃しやすいので電気現象は現れない。絶縁体では電気が動かないので電気現象が現れる」と考え「静電気」という概念を生みました。
フランスのデュフェー(Charles Francois Cisternay Dufay, 1698-1739)は、1733年、ガラス棒に帯電させた電気を同時に2本の金属棒に移したときは、この2本の金属棒が反発しあい、2本の金属棒の一方にゴム、もう一方にガラスで帯電させた電気を移すと、2本の金属棒が引き合うなどの実験から、電気には「ガラス電気」と「樹脂電気」の2種類があり、同種は反発し、異種は引き合うと考えました。
グレイは「全ての物質には、2種類の電気が同じ量だけあって、これが摩擦によって分離して静電気現象が起きる」と考えました。
これらの考えは、後述する通り、フランクリンによって修正されることになります。
静電気をためる装置(ライデン瓶)の発明

〈写真2〉ライデン瓶(ウチダ理化電子カタログ:型番2-131-0701 UG-9)
1746年、静電気をためる画期的な装置、ライデン瓶が発明されました。当時、静電気が時間とともに無くなっていくのは、電気素が空気や空気中の水蒸気に吸収されるためと考えられていました。
そこでオランダ、ライデン大学の物理学教授ミュッセンブルーク(Pieter van Musschenbroek, 1692-1761)は、電気を水の中に入れて空気に触れないようにすれば長持ちするだろうと思い、水を入れたガラス瓶にコルクで蓋をし、金属線をコルクを突き通して水に触れさせました。これが彼のつくったライデン瓶です。
たまたま訪れた友人にこの水入りガラス瓶を持たせ、起電機で加圧していったところ、ふいに友人はガラス瓶を持ったまま起電機からの金属線に触り、感電者となってしまいました。友人は「フランスをくれると言われても二度とごめんだ」と洩らしたそうです。
ライデン瓶は実用的なものではありませんでしたが、このような感電現象は興行的に使われました。イギリスではテムズ川の水をアースとして対岸の人を飛び上がらせていたといいます。水入りガラス瓶は、水の代わりに瓶の内外に金属箔を貼り付ける形に改良され、地名からライデン瓶と呼ばれるようになりました。
以後は起電機には必ずライデン瓶をつけることが常識とされ、ライデン瓶によってそれまでより強力な火花放電を起こせるようになりました。 後に、ボルタなどによって瓶に貼り付ける金属箔が錫箔に改良され現在の形になりました。〈写真2〉にその1例を示します。
ベンジャミン・フランクリンの実験
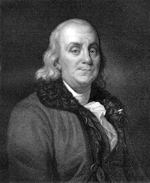
〈図3〉フランクリン肖像画(ウィキメディア・コモンズより)
フランクリンはアメリカ合衆国の独立宣言の草案作成に参画し、また大陸会議の駐フランス大使でもあって、合衆国の創立者の一人といえるすぐれた人物でしたが、むしろ当時のヨーロッパでは、電気の研究によって自然科学者としてよく知られていました。
彼ははじめ、静電気を蓄電したライデン瓶についての解析の実験を行ないました。フランクリンは、電気の素は1種類だけで、それは非物質的な流体で、あらゆる物体に含まれていると考えました。そして、それが過剰に存在する物体は「正(プラス)」に帯電し、不足している物体は「負(マイナス)」に帯電するというのです。
フランクリンは、デュフェーの提唱したガラス電気を「正電気」、樹脂電気を「負電気」と呼びました。この流体説は部分的には正しいものだったので、かなり長い間、広く受け容れられていたのでした。
この研究の過程で、彼は電気に関する基本的用語を少なくとも25個は作り、それを紹介しています。この中には「プラス」「マイナス」「陽」「陰」、のような現在用いている用語も含まれています。
また、フランクリンは、ライデン瓶の中で起る電気火花(スパーク)と稲妻が同じものであると考え、これを1752年の有名な凧の実験で確かめました。この実験で彼は絹の糸に金属製の止め金を固定して凧につけ、これを雷雨の中で飛ばしたのです。稲妻の中で絹糸は空中電気によって帯電し、金属の止め金に指が触れたとき、火花が飛びました。この止め金をライデン瓶につないで蓄電させたのです。
フランクリンはこの危険な実験から避雷針を1753年に発明し、これは合衆国全体に急速に広まりました。この研究を通じて、フランクリンは電気の理論的研究を進展させたばかりでなく応用電気学の分野、すなわち、現在電気工学として知られる分野を開拓したのでした。
ボルタの電池の発明

〈図4〉ボルタ肖像画(ウィキメディア・コモンズより)
1775年にイタリアのアレッサンドロ・ボルタ(Alessandro Giuseppe Volta, 1745-1827)〈図4〉は電気を自由に取り出すことができる電気盆を考案しました〈図5〉。
最初にお盆の中の絶縁物をこすってマイナス電気を発生させます。このマイナスに帯電したお盆の上に、絶縁物の柄を取り付けた金属板を近づけます。すると、金属板の盆に面した側にプラス電気が、金属板の反対面にマイナス電気が生じます(このような現象を「静電誘導」と呼びます)。このマイナス電気面に指を触れると、マイナス電気は体のほうに移り、金属板から指をはずすと、金属板にはプラス電気だけが残ります。こうしてプラス電気とマイナス電気が自由に作れるようになりました。
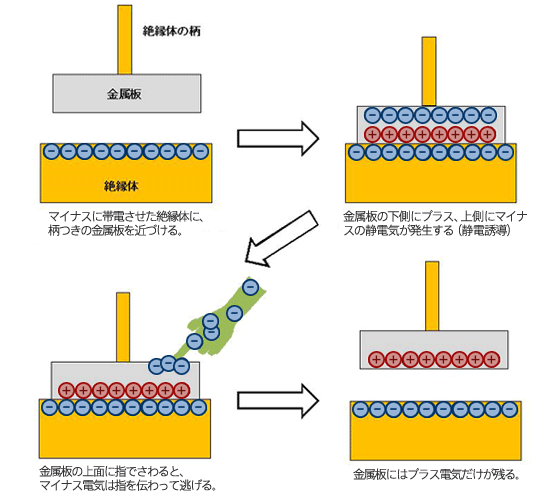
〈図5〉ボルタの電気盆(概念図)
また、彼は1778年コンデンサに関する論文を発表しました〈図6〉。
電気盆は金属板(盆)と絶縁体の重ねあわせでありましたが、ここでは、金属板、絶縁体、金属板、と3重に重ね、下の金属板はアースし、上の金属板は絶縁の取っ手を付けました。 上板に電気を加えてから引き剥がすと、この上板に検電器が強く反応し、これにより、引き剥がすという操作によって少量の電荷でも強い電気力が発生することを確認しました。 ボルタはこれを「コンデンサトーレ」と呼び、「コンデンサ」という名はここから始まったのです。
電気盆とコンデンサを区別したのは、電気の強さが帯電体の容量に逆比例し、導体の容量はその面積の増減に対応するといった蓄電気の一般性質をすでにボルタが理解していたからでした。コンデンサは、今日のあらゆる電気機器に使われている重要な部品です。
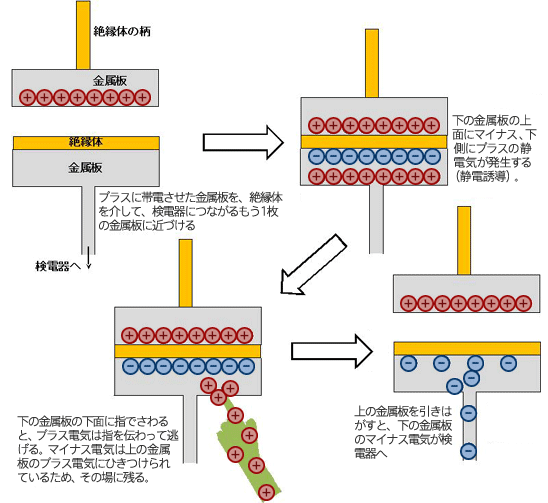
〈図6〉ボルタのコンデンサ(概念図)
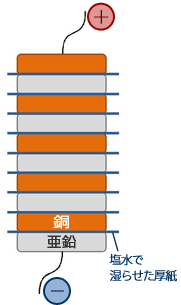
〈図7〉ボルタの電堆(概念図)
ガルバーニの論文発表当初こそ、ボルタも「正に大驚異というべきもの」と賛同していましたが、その後、2種類の金属を接触させて舌にのせると酸やアルカリのような特殊な感覚が生じるといった方法で追試するうちに、 動物に電気があるわけではなく、動物は検電器の役目になっていただけであったことを確認しました。この論争が、ボルタ電池の発明へとつながっていきました。
1800年、ボルタは蓄電池を発明します。これがまさしくボルタ電池です。銅と亜鉛の板に塩水で湿らせた厚紙をはさみ、これを直列に接続すると数に比例して効果が高まり、ライデン瓶のように一回の放電で消耗しないことも確認されました。 ボルタ電池については「この電堆(でんたい;電池のこと)は、わずかの液体で隔てた異種の金属を積み重ねたものであるが、それが生み出す効果が極めて異常であることを思えば、これこそ人類発明史上最大の驚異である。」と 当時多くの物理学者が喝采した大発見、大発明でした〈図7〉。
平賀源内のエレキテル
イタリアでボルタが活躍していた頃、江戸時代の日本では電気に関してどのような研究がなされていたのでしょうか。特筆されるのは、博物学者の平賀源内(1728-1780)が復元したエレキテルです。エレキテルは摩擦起電器のことで、オランダ語(ラテン語)のelektricteit(電気)がなまったものです。源内はこの静電気の発生装置を「ゐれきせゑりていと」と表記しています。
エレキテルはオランダで発明され、宮廷での見世物や医療器具として用いられていました。日本へは江戸時代に持ち込まれ、1751年(宝暦元年)頃、オランダ人が幕府に献上したとの文献があります。後の1765年(明和2年)に後藤利春の『紅毛談(おらんだばなし)』で紹介され、それを読んだ源内が、長崎滞在中の1770年(明和7年)に古道具屋、あるいはオランダ通詞の西善三郎から、破損したエレキテルを入手し、工人の弥七らとともに1776年(安永5年)に江戸で模造製作に成功したのです。
外部は木製の箱型、または白木作りで、内部に蓄電器があり、外付けのハンドルを回すと内部でガラスが摩擦され、発生した電気が銅線へ伝わって放電するというものでした。〈図8〉に、エレキテルを描いた絵を示します。
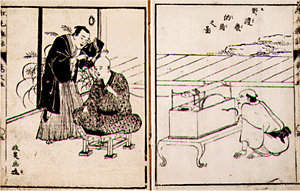
〈図8〉エレキテルを描いた絵(ウィキメディア・コモンズより)
源内は電気の発生する原理を陰陽論や仏教の火一元論などで説明しており、電磁気学に関する体系的知識は持っていなかったとされていますが、アメリカの科学者フランクリンが行った実験の情報が伝わっていたとも考えられています。日本でも見世物や医療器具として利用されていました。
しかし、寛政の改革による贅沢の禁止や出版統制などにより、電気に関する科学的理解・研究は後の開国以降や明治期まで停滞することとなりました。現在も源内製造とされるエレキテルは現存しており、1997年(平成9年)6月30日に国の重要文化財(歴史資料)に「エレキテル平賀家伝来」として指定されたものが、東京都千代田区の逓信総合博物館に収蔵されています。
これからの研究に若者の英知を

中村 日出夫(なかむら ひでお)
所属: 宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙教育推進室参事 独立行政法人国立科学博物館 学習課アドバイザー
1948年生まれ、神奈川県出身。1971年、千葉大学教育学部卒業。2年間の日本電信電話公社(現NTT)勤務の後、1973年より東京都北区立清至中学校教諭を皮切りに都内の中学校勤務を経て、本年(2008年)3月まで品川区立荏原第一中学校校長。4月より現職。教育委員会や文部科学省の委員や、理科教育に関する研究会役員も歴任。全国中学校理科教育研究会会長(2005~2006年)を経て、現在同会顧問。1987年、日本教育研究連合会教育奨励賞授賞。理科教育に関する数多くの研究成果や著書がある。第1級アマチュア無線技士資格を持つ。
構成・文:中村日出夫/写真1・図5・図6・図7:春名誠/イラスト:みうらし~まる
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事














 算数の教え上手
算数の教え上手 学校の危機管理
学校の危機管理 世界の教育事情
世界の教育事情 今どきの小学生
今どきの小学生





 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事
