危機管理とはなにか?

「学校の危機管理」って最近よく聞く言葉ですが、そもそも「危機管理」ってどんなことでしょうか?学校における不法侵入に対する危機管理を例に考えてみましょう。
危機管理はベルリン危機やキューバ危機から研究が始まったと言われている。元々は冷戦下における全面核戦争という危機を抑止するにはどうすれば良いのかという研究であった。それが現在までに企業経営などの組織運営、病院における衛生管理、工場における安全対策などさまざまな分野に適用され活用されている。
| =危機管理の基本= 危機管理は基本的に以下の流れで行われる。 (1)目的の明確化・・・危機管理の目的を明確にする (2)情報収集・・・危機の特定 (3)予防・・・特定された危機の予防 (4)準備・・・予防できない事態に備えての対応の準備 (5)対応・・・準備に基づく対応 (6)再発の防止・・・発生した危機の再発防止 |
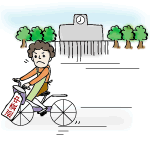
例えば学校における不法侵入に対する危機管理を考えてみよう。
(1)ではまず、何を何から守るのか目的を決めるので、この場合は「学校における子どもたちの安全を不法侵入者から守ること」と定める。
次に(2)で子どもたちの安全を脅かす可能性のある不審者の情報や学校の弱点を把握するなどの情報収集を行う。
(3)でその情報を元にPTAによるパトロールを行ったり、校門付近に先生方による見張りを立てたり、防犯カメラの設置などを行う。
(3)と同時に(4)において、実際に不法侵入者が入ってきた時、どうなるのかを考え、不法侵入者の動きを封じるための盾を設置したり、実際に子どもたちにけが人が出た場合に備えて救急道具を設置したり、マスコミが押しかけてきて子どもたちのプライバシーを侵害しないようマスコミ対応の訓練をしておくなどの準備をする。
万一、実際に不法侵入が発生した場合、その準備に沿って(5)の対応をしていくことになる。
最後に対応が終了したら、(6)としてその事件をいやな思い出だからと言って蓋をせずに、問題点を探し、同じ失敗をしないよう、事件記録の作成や、再発防止委員会を立ち上げて話し合うことになる。
大まかに言えばこの一連の流れが危機管理ということになる。
また、 危機管理には大きく3つの視点がある。一つ目は危機を起こさせない。(予防と回避)
二つ目に危機による被害を軽減する。(被害極限)
三つ目が二度と起こさせない。(再発防止)
この三つをバランスよく行えて良い危機管理といえる。防犯や安全対策との観点よりも大きな視点で生徒達の安全を確保できる枠組みである。防犯や安全対策という観点では子どもたちの生命の安全を確保すると言うことだけであるが、危機管理では子どもたちの生命だけでなく、精神の安定や不安の除去、それ以外に保護者の不安の除去まで大きな視点での対策をも考えることになる。
最後に皆さんにひとつ問題です。子どもたちの安全を守ることは学校の危機管理になるが、学校の危機管理は子どもたちの安全を守ることにはならない場合がある。それはどんな状況で何故であろうか。皆さんに考えていただきたい。答えは次回のコラムで・・・。
(イラスト:たかまひびき)
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
この記事に関連するおススメ記事

「おすすめ特集記事」の最新記事














 算数の教え上手
算数の教え上手 世界の教育事情
世界の教育事情 科学夜話
科学夜話 今どきの小学生
今どきの小学生



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事
