大人も「私とは何者か?」を問い続け、他者との違いを共創・成長につなげる New Education Expo 2025 リポート vol.6

今年で30回目を迎えた教育業界最大級のセミナー&展示イベントNew Education Expo 2025。vol.6では、アフリカ出身者として日本で初めて大学の学長に就任したウスビ・サコ氏による講演をリポートする。変化の激しい時代における自ら学び続ける力の大切さなど、文化や価値観の違いを超えた教育の本質が語られた。
学び続けることの意味~問いを立てる力を養うために~
京都精華大学 元学長、名誉教授/東京都公立大学法人 理事/東京都立大学 特任教授 ウスビ・サコ氏
マリから中国へ、そして京都へ留学
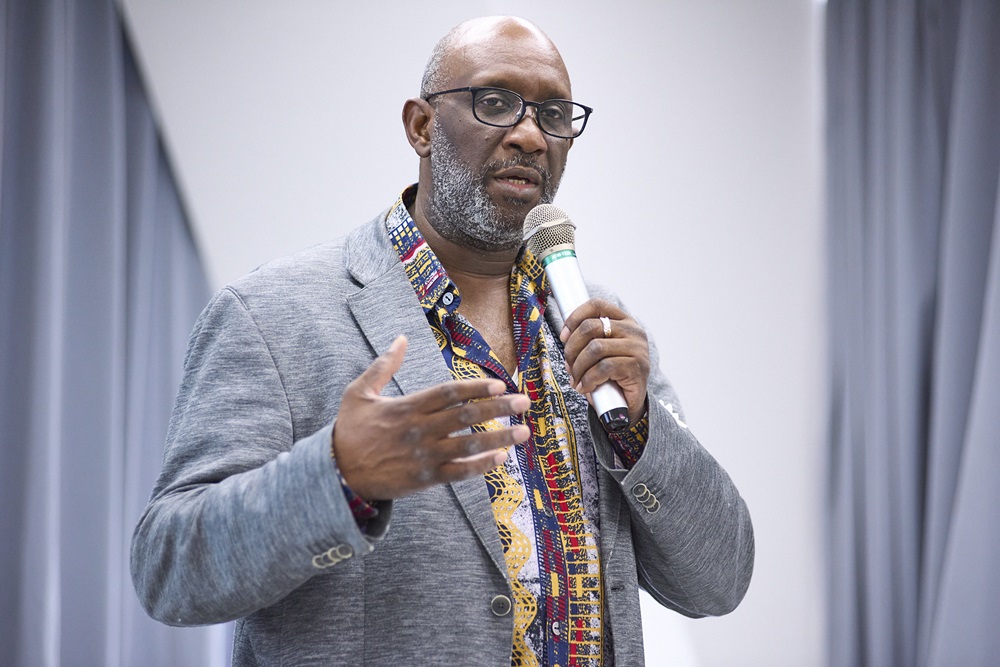
京都精華大学 元学長、名誉教授/東京都公立大学法人 理事/東京都立大学 特任教授 ウスビ・サコ氏
まずは、私のバックグラウンドについてお話ししたいと思います。私はマリというアフリカ西部にある国で生まれました。かつてフランスの植民地だったことから公用語はフランス語ですが、家では民族それぞれの言葉を使います。
マリの教育の特徴は「学問は学校で、倫理は地域や家庭で学ぶ」ということです。学校と家の役割が完全に分担されており、家では家族との会話を通して地域の生活や独特の挨拶の仕方などを学びます。
また、子どもは家族だけでなく隣人みんなで育てるという習慣が古くから根付いていて、学校から帰ると、多くの大人が家にいるのが当たり前でした。
マリは文字を持たず、口承で物語を伝えていく文化です。そのため、子どもは文字ではなく、耳で言葉を聞いて覚えていきます。
私がマリのいくつかの民族言語やフランス語、英語、ロシア語、中国語、日本語などを話すことができるのも、そのような口承文化で育ったことが深く影響しています。
そうした環境で子ども時代を過ごし、高校卒業と同時に中国に国費留学し、2つの大学で6年間、建築学を学びました。その後、京都大学大学院で建築の知見を深め、博士号を取りました。
1991年に来日して以来、京都に34年間住んでいますが、少子化と高齢化が進んだことから空き家が増えたり、マンションが建てられたりと、地域に大きな変化がありました。私の専門は空間人類学で、社会と建築の関係性をさまざまな角度から研究しています。その背景には、京都のコミュニティの変容を見てきたことが根底にあります。
本日は、社会の変化を見据えつつ、多様性とグローバル化の理解や共生社会の創造に必要なものについて、私の考えをお伝えします。
異文化体験から自分を再発見
日本で留学生活を始めた当初、私は多くのカルチャーショックを受けました。特に驚いたのが、「同じであること」を基本とする文化です。マリでは、年齢で人との関係を決めるような習慣がないため、同期や先輩、後輩という関係に大きな違和感を覚えました。
一方で、外国人市民として日本社会と共生するにはどうすればよいのかと考えるようになりました。考えた末に見えてきたのが、「日本社会や近隣住民と関わり、交流するプロセスの明確化とリテラシーが必要」ということでした。
また、当時は留学生へのオリエンテーションがほとんどなかったことから、留学生を支援する組織をつくり、日本社会を学ぶためのさまざまな活動を行いました。
その中で見えてきたのが、「他者と出会うことで、自分を再発見できる」ということです。コンフォートゾーンから離れ、他者や異文化と触れ合うことにより、自文化が見えてきたのです。そこから私の目的は、同化することではなく、共存による共生社会の実現であると強く感じるようになりました。
グローバル化と多様性

ここでグローバル化の概念について整理したいと思います。グローバル化を辞書で引くと、「ヒト、モノ、カネ、そして情報が国境を越えて自由に行き来し、それらの価値は一国の判断で決められないこと」とあります。
したがってグローバル化におけるポイントは、「新しい価値観を学ぶこと」といえるでしょう。
また、国際化は昔から存在していましたが、大きく拡大したのは20世紀後半以降のことです。アイディアや製品、文化の交換など、さまざまな変化をもたらしました。
そんなグローバル化する社会において、最も重要な要素となるのが「多様性」です。多様性を辞書で引くと「人種、性別、宗教、性的指向、社会的経済的背景、および民族性の個人間の違いが存在し、認識されること」とあります。
なお、日本における多様性としては、日本人間の問題なのか、外国人の問題なのか、それとも多様性そのものの捉え方の問題なのかという課題があります。
私は以前、「午前10時になったとき何を考えますか?」と色々な人に質問したことがあります。その結果、ある人はおやつの時間、ある人は仕事、ある人はお祈り…など実にさまざまな答えが返ってきました。つまり、文化を定義することは難しいといえます。
日本社会の現状
文化を辞書で引くと、「学習によって社会から修得した生活の仕方の総称」とあります。また、「人間相互の連帯感を生み出し、共に生きる社会の基盤を形成するもの」と書かれています。つまり文化とは、背景が違っても、お互いに合わせることができるものといえます。
そのような観点で日本における多様性・人種問題の価値観を見てみると、グローバル基準と大きくかけ離れているといえるでしょう。
私が京都精華大学の学長になった当初、毎週のように海外メディアからの取材を受けましたが、その背景には、日本で要職に就く外国人が2%未満であり、先進国としては極めて低いという理由が考えられます。また日本のテレビ番組では「黒人大学長」と紹介されたこともありました。
ここで、日本人社会と人権について考えたいと思います。人権を辞書で引くと、「すべての人が持ち、社会的地位の区別なく、人種、性別、国籍、出自、信条、政治的意見などの理由による差別は許されないもの」と示されています。
しかし、私の経験からもわかるように、「アンコンシャスバイアス」=無意識の偏見が各所で見られているのが実情です。これは日本だけでなく世界中に浸透しています。その理由として、他文化や自文化に対する知識不足、コミュニケーションスキルの問題などが影響しているといえます。
アイデンティティ・クライシスの時代
先日、学生に「自分の文化的アイデンティティ」についてアンケートをとったところ、「安定している」が23%、「守りたい」が37%で、「揺らいでいる」16%や「変わり続けるべき」23%よりも多いという結果でした。ですが、現代はグローバル化によって、自国の常識だけにすがることは難しく、ずっと一つの文化の中で過ごすというモデルは揺らいでいるといえます。
では、軸がなくなったアイデンティティをどう再構築すればよいのでしょうか?
これに対し、社会学者のリチャード・セネットは、「自文化をしっかりと見定めた上で、身のまわりにある異文化から理解していくことが重要」と示しています。
私自身も、長期にわたりアフリカの外に住んだことで、文化的アイデンティティとその表象が持つ意味の重要性を理解させられました。
ここ5年間を振り返ると、新型コロナウイルス感染症の拡大や、ロシアとウクライナの戦争など、今までの価値観では通用しない多くの出来事が起こりました。この先行きの見えない時代においては、学生だけでなく大人ももう一度社会について勉強する必要があります。
日本の学校教育に目を向けると、テンプレート化・フレーム化された教育が行われている印象があります。
授業でもクラブ活動でも「みんなと同じように」という意識が定着しています。また、先生は子どもに答えをすぐ示し、問いを立て、考える時間を十分に与えていないと私は感じます。それでは、教育の本質が失われてしまうでしょう。
また、日本では集団での協調を重視する慣習がありますが、せっかくの優れた才能が阻害されてしまいかねません。
ノーベル物理学賞を受賞し、アメリカで研究を行う眞鍋淑郎さんは、かつてインタビューで国籍を変更した理由を尋ねられて「(自分は)日本で調和の中で生きることはできない」と語られました。この発言からも、日本社会に同調圧力があることがわかります。
京都精華大学の取組
ここでは、京都精華大学で私が行った取組を紹介します。2018年に学長となって、まず初めに行ったのが教育の軸の設定です。「リベラルアーツ」「グローバル」「表現」の3つを掲げました。
また、自分自身について考える機会を与えたいという想いのもと、必修科目として「自由論」を設置しました。
さらに「ダイバーシティ推進宣言」を発表しました。この宣言は、多様なバックグラウンドを持つ人々が違いを認め合い、対等な機会が開かれることを目指すものです。ここでは、制度の整備だけでなく、学内のさまざまな場面で多様性に触れる機会を設け、共生の意識を育むことを示しました。
そして「違いとともに成長してほしい」という考えから、学籍簿の通称名の使用やマイノリティの社会包摂を視野に入れたアートマネジメント・プロフェッショナル育成プログラムの開設など多くの改革を行いました。2021年度以降、新入生の約30%は留学生となっています。
対話による共生(共創)社会の実現
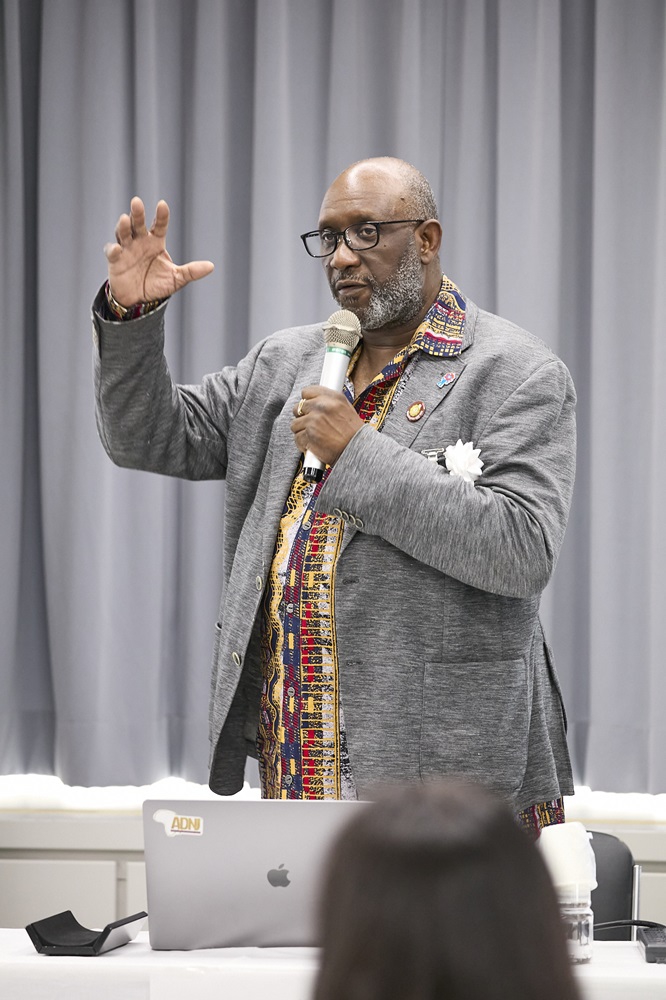
かつての日本社会は、消費が中心で、便利さだけが問われがちでした。そんな中、コロナ禍によって、新しい価値観や自分の原点について考える機会が増えた人も多いと思います。
その一方で、先行きが不透明で将来の予測が困難なこの世の中においては、多くの人が自分の変化を恐れているという印象を受けます。答えがなかなか見えず、不確定な社会的状況で求められるのは、自ら考え、問いを立てられる力だと私は考えます。その力を養うために、大きなカギとなるのが、リベラルアーツを学ぶことです。
リベラルアーツで特に重要となるのが、人間と人間を取り巻く環境を理解しようとする学問分野である「人文学」です。
人文学を学ぶ上で、有効な手法の一つとなるのが「ダイアログ(対話)」です。色々な人と話し、自分のことを相手に教えながらコミュニケーションすると、理解がより深まります。この手法は「ソクラティック・ダイアローグの方法論」とも呼ばれています。
大切なのは、自分のヴォイスを持ちつつ「私とは何者か?」と問い続け、自己の認識と他人を受け入れることです。なお「ダイアログ」はグローバル化が進む中で、世界中の人と触れ合う中でも、大変有効な方法といえます。
記者の目
近年、「ダイバーシティ」「多様性」は、さまざまな文脈で当たり前のように使われているが、本セミナーと通じて、改めてその言葉が意味するものや必要性について考えることができた。また、不確実性が高まるこの時代こそ、大人であっても学び続けることの重要性を再認識できた。今後も、西アフリカのマリ出身という視点を活かした、ウスビ・サコ氏ならではの取組に注目したい。
取材・文:学びの場.com編集部 写真提供:New Education Expo実行委員会事務局
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事














 授業実践リポート
授業実践リポート 食育と授業
食育と授業 教育リサーチ
教育リサーチ



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望



