海洋冒険家 白石康次郎氏の生き方に学ぶ 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校

世界で最も過酷なヨットレースに出場する白石康次郎氏を応援しよう、ということから始まった、横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校の4年2組の総合学習の取り組みを紹介します。
|
世界で最も過酷なレースと言われる単独世界一周ヨットレース「アラウンド・アローン」に日本から海洋冒険家の白石康次郎氏が出場する。 |
 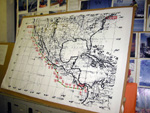 教室も廊下も「アラウンド・アローン一色」  座標を地図にプロットして…
 3年時で学んだ「空気の学習」の大きなボードも教室の壁に
 5月28日、白石氏来校   白石氏に贈ったテープ   |
白石康次郎氏の応援に取り組むのは、横浜国立大学附属鎌倉小学校のN先生と、4年2組の児童たちだ。鎌倉小学校は白石氏の母校でもある。 ■白石康次郎氏の軌跡を追って 「8月14日は随分進んでいるよね。どうしてだろう」 ■子どもたちの歌が白石氏の心に響いた! ところで、どのような経緯で、4年2組の子どもたちが、白石康次郎氏の参加するヨットレースを学習テーマとして取り上げることになったのだろうか。 「4年に一度のレースですから、どうせならひとりで参加するのではなく、子どもたちの夢を乗せて出航したい、という白石さんのたっての希望で、白石さんの所属事務所から依頼があったのが最初のきっかけです。でも、それだけで授業として成り立つかどうかは確信が持てなかった」 鎌倉小学校では、早くから総合的な学習を行ってきたが、先生が上からテーマを押し付けるのではなく、子どもたちの中で意識が高まって、自主的に「やりたい」と思うテーマを取り上げてきた。今回も、子どもたちの関心が高まらなければ無理だと思っていたのだ。 「しかし、4年2組の子どもたちは、3年時に1年かけて、空気の学習をやってきました。打診があった5月は、ちょうど4年生の1年間に、3年生で学んできた空気の学習をどうやって発展させようかと模索していた時期。子どもたちにとって、空気、つまり風の力で世界一周するヨットレースは、これまでの空気の学習を発展させるのにまさにぴったりだったんです」 さらに、ニューヨークに向けて下田を出航する直前の5月28日、白石氏本人が来校したことが、大きな転機になった。子どもたちは、事前に練習した「船乗りの歌」を歌い、応援のエールを送った。 みんなの歌声は、「持っていって南氷洋で聞きたい」という白石氏の希望で、テープにとることになった。それまで、合唱というと小さな声で恥ずかしそうに歌っていた子どもたちが、目を輝かせて練習に取り組み始めた。子どもたちだけで選曲し、伴奏も加え、時には音楽の授業でアドバイスを受けながらの練習が繰り返される。 授業のほかに、子どもたちはメールで白石氏に応援のメッセージを送ったり、海のこと、イルカのこと、船上での生活などについて質問を投げかける。白石氏からももちろんメールで返事が返ってくる。6月と7月には、洋上授業といって、船舶電話で、航海中の白石氏と直接話もした。こうした直接のコミュニケーションが、応援の機運をいっそう高めているようである。 これらの経験を通して、子どもたちに「夢を持つ人自身の存在を心の中に感じる」こと、また「その人の生き方に学ぶ」ということ、そして、自分も「世の中に役に立つ存在である」ということなどを学びとって欲しいとN先生。 そんなN先生の思いも、「子どもたちの夢」とともに乗せて、白石さんのヨットは世界一周の旅に出発する。
(取材・構成:学びの場.com) |
※当記事の情報は、公開当時のものです。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事














 教育イベントリポート
教育イベントリポート 食育と授業
食育と授業 教育リサーチ
教育リサーチ



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望

