ソーシャルスキルトレーニング(以下、SST)を活用した道徳授業を、東久留米市立神宝小学校の荒畑美貴子教諭が実践した。社会変化に伴い、ソーシャルスキルが不足する現代の子どもたち。また、教師の大量採用時代に差し掛かり、経験の少ない新任教師が悩みを深める昨今。理想の小学校教育像を追求する荒畑教諭の授業実践とインタビューを紹介する。
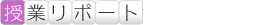
「上手な話の聞き方」を身に付けるSST活用授業
学年・教科: 5年生道徳(児童40名)
単元: 大切な友達のために
本時の学習: めざせ! 聞き方の達人(SST「上手な話の聞き方」)
ねらい: (1)友達の話を真剣に聞く方法を考えたり、見たり、試したりすることによって、話の聞き方のスキルアップにつなげる。(2)友達のことを互いによく理解し、信頼し、助け合うことの大切さに気付く。
指導者: 荒畑美貴子 教諭(学級担任)
使用教材・教具: プリント
「そうだねゲーム」でウォーミングアップ
この日の授業は取材が入ったため、子どもたちも少し緊張気味。荒畑教諭はすかさず、
「すっごく緊張しているようなので、最初にゲームをします。隣の人とじゃんけんをして、勝った人が先に質問者になります」
と呼び掛け、自然な形で「そうだねゲーム」に入っていった。といっても、実は最初から指導案に織り込んでいた導入の活動だ。子どもを前にして、荒畑教諭が実演してみせる。
「私が何か言いますから、全部『そうですね』と答えてください。絶対にそれ以外は答えてはいけません!」
クラスから「えーっ」という声も漏れるが、構わず続ける。
「今日の校長先生、素敵ですね」
「そうですね」
「副校長先生も素敵ですね」
「そうですね」
――ようやく子どもたちに笑いがこぼれる。友達同士のゲームに入ると、すっかり和気あいあいだ。
スキルを提示、反復練習、定着へ
教室の雰囲気が暖まったところで、荒畑教諭は本時の学習課題を板書し、子どもたちに復唱させる。
「友達の話を上手に聞くためには、どのようなことに気をつけたらいいか、考え、実行してみよう」
そして、気持ちよく聞くためのマナーについて意見を募る。子どもたちからは
「相手の目を見る」
「何でも『そうですね』って言うのは、やめた方がいい」
――しかし、後が続かない。
「出てこないかぁ……。じゃあ、策を練ろう。○○君、手伝ってくれる?」
荒畑教諭は一人の子どもを相手役に再度の実演。感情たっぷりに話してみせる。
「きのう私、すごく疲れちゃったんだよね。肉ジャガの材料買ってたら、『鍋にしよう』ってメールが入っちゃってさあ……」
「ふーん」
相手役の気のない反応に、クラスは大爆笑だ。そこで、荒畑教諭が
「どんなところを直したらいい?」
と問い掛けると、
「話をやめさせたいような感じだった」
「興味を持ってないみたいだった」
と、具体的な指摘が次々と挙がる。
ここで初めてプリントに注目させ、「話す人に体を向け、顔を見る」「話が終わるまで黙って聞く」など聞き方の6ポイントを提示。その上で、二人一組で一人が話し手、一人が聞き手になって、それぞれ1分間会話する。これを3人のパートナーと繰り返し、各ポイントが実行できたかどうかをA~Dで評価し、プリントに記入していく。子どもたちは回数を重ねるごとに、話し方にも聞き方にも、徐々に慣れていく。記入された評価を見ながら話し合う姿も見られた。
「聞いてもらえて、気持ちがよかった」
「大人としゃべっているような気分だった」
――最後の発表では、こんな感想も並んだ。荒畑教諭は
「これからも大切な友達のために、ぜひ話を聞いてあげてください。優しい感想が言えるようになるといいですね」
と呼び掛けて、授業を締めくくった。
終了後、児童に話を聞くと
「(話し方に気をつけたことは)あまりなかった。一対一だと緊張したけど、これからも少しは(授業でやったように)できると思います」
と、はにかんだ答えが返ってきた。
また、振り返りカードには、「話しやすかった」「楽しかった」「真剣に聞いてもらえて嬉しかった」といった感想が並んだ。
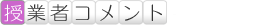
ベテランの体験を若手教師に伝えたい。
そして子どもに寄り添う教育を。
不登校児への対応から学ぶ
学びの場.com(以下、学びの場) SSTに取り組むきっかけは何だったのですか。
荒畑美貴子 主任教諭(以下、荒畑) 八王子市の小学校に勤務しているとき、教育相談部という研究の場で学ぶことができました。当時、不登校の子どもたちと関わっていたこともあり、SSTの大切さを痛感しました。勉強会では、東京学芸大学の小林正幸先生(現教授)をお招きして勉強しました。小林先生から、たくさんの示唆を受けることができ、感謝しています。
小林先生がご指摘の通り、今の子どもたちは社会的なスキルが育ちにくい環境にあると感じています。今年度5年生を担任させていただき、教育活動全般を通してSSTを取り入れてきました。その成果もあって、クラスもだいぶ落ち着いてきました。
学びの場 特別活動や生活指導を専門に研究してきたのですか。
荒畑 いいえ。むしろ学生時代からずっと勉強してきたのはシュタイナー教育です。でも、シュタイナー一辺倒ではありません。最近特に思うのですが、シュタイナーはたくさんの特徴的な教育技術を残してくれていますが、技術よりはまず、子どもたちの心に寄り添うことが一番大切だと言いたかったのではないでしょうか。また、子どもたちの人間としての成長過程を、とても大事に考えた教育家であると認識しています。さらに、教師の教育に対する姿勢や生きる姿勢の大切さも指摘していると思います。それらは、一朝一夕で培われるものではありません。
技術は、いかようにでも身につけることができます。しかし、教育の根底を支えるものを、教師は培っていく必要があると考えています。
いい公立学校が絶対に必要
学びの場 荒畑先生はTISEC(Towards Ideal School Education for Children=理想的な学校教育を求めて)を主宰されています。どういう思いからですか。
荒畑 最近の若い先生はとても勉強熱心なのですが、指導が主体となりがちであるように感じます。ですが、指導ばかりでは子どもは育ちません。それで壁に突き当たってしまうこともあるのではないかと思うのです。私の教師生活も残すところ10年ほどになり、何ができるかと考えました。これからは、若い先生たちを育てること、自分のやってきたことを若い先生たちに伝えることだが、自分の最後の仕事だと思い至ったのです。
学びの場 TISECのホームページには、臨時教員時代から先生が悩み、学んできた軌跡が赤裸々につづられていますね。やはり今、若い世代にベテランの教職体験を伝えなければいけないという危機感があるのでしょうか。
荒畑 危機感というより、使命感ですね。日本の将来を担う子どもたちの幸せのためには、いい公立学校教育が絶対に必要です。そのためにも若い先生たちには、私たちがそうしてきたように、必死で勉強してほしいと思います。表面だけの教育技術ではなく、教育を支える観念を学んでほしいと願っています。その助けとなるなら、協力は惜しみません。
東京都では10年で教員の半数が入れ替わると言われるほど、世代交代が急激に進んでいる。しかし最近、授業を参観していると、新任教諭が特定の教育技術に頼りがちなのが気にかかる。理想の教育とは目の前の子どもから学ぶものであり、授業の達人も新人時代から七転八倒の苦しみを経て指導力を高めてきたのだということを、荒畑先生のようなベテランの体験からぜひ学んでほしいものだ。
取材・文:渡辺敦司/写真:言美歩 ※写真の無断使用を禁じます。
【関連記事】
光村図書「子どもが光り輝く ソーシャルスキル教育 映像資料」
|

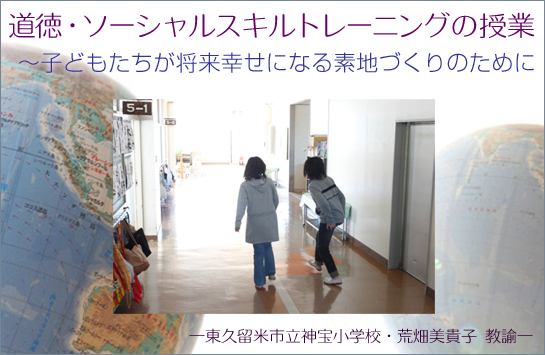















 教育イベントリポート
教育イベントリポート 食育と授業
食育と授業 教育リサーチ
教育リサーチ








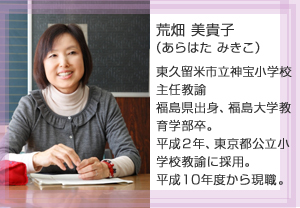




 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望

