算数・数学は難しい、嫌い……そんな子どもたちに向けて、自分の手を動かしながら算数・数学の面白さを知り、学べるワークショップが、理数の魅力と触れ合うための体感型ミュージアム『リス―ピア』にて開催された。小学校低学年から高学年まで、たくさんの親子が参加し、図形の等積変形から無理数の概念までを学習した。
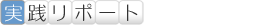
“感じる算数”と“考える算数”で「等積変形」から「無理数」までを学ぶ
対象学年: 小学生以上
教科・領域: 算数・数学 等積変形(学校では小学5年生)
教材・教具: 正多角形のジグソーパズル、電卓、実物投影機、ホワイトボードなど
本時の学習: 正多角形の対角線で作る正多角形
ねらい: 自分の手を動かして、正多角形を分割したパーツをすべて使って元の正多角形の対角線を1辺とする正多角形を作り、形を変形させても面積が変わらないことを実感する。また、図形と数を関連させて考えられるようにする。
指導者: 有田八州穂 教諭(多摩市立大松台小学校非常勤講師)
手を使って「感じる算数」
「ジグソーパズル、やったことある人は?」
有田先生の問いかけに、会場にいたほぼ全員の手が挙がった。
「今日は“正多角形の対角線で作る正多角形”という舌を噛みそうなテーマですが、最初にやるのはパズルです。ただ、いつものパズルと違って絵がついていないから少し難しいけれど、やってみよう!」
先生の説明後、参加者の手元には、正方形が2つ、正五角形、正六角形3つずつが印刷され、それぞれパーツごとに外せるようになっている厚紙が配られた。
「これからやるのは、“感じる算数”。自分の手を動かして、図形の面白さを感じてみてください」
と有田先生。その後、【図1】のように、正多角形(正方形・正六角形・正五角形)の変形にとりかかった。それぞれ、左の多角形の対角線が、右の多角形の1辺になっている。
会場では、苦戦する大人を横に、パパッと仕上げる子ども。そして子どもが親に教える光景も。
「形の感覚をつかむのは、算数の中でも面白い力。大人より子どものほうが早くできる場合もたくさんあります」
と有田先生。それぞれの形を、参加者が一人ずつ前に出て再現した。少し戸惑う子もいたが、全員が見事完成させ、会場から大きな拍手をもらっていた。
図形と数をつなげて考えよう
「さて、今までは“感じる算数”でしたが、ここからは“考える算数”です」
と有田先生。
「今日やっていることは、『等積変形』といって、面積を変えずに、違う形に変形させていくこと。今までは手を動かしたから、これからは頭で考えてみよう」
と続けた。
1辺が2cmの正方形の中に、1辺が1cmの正方形は4つ含まれる。そこから「辺の長さ」と「面積」の関係について考えていく。この大小の正方形の辺の長さの比は1対2。面積は1対4。
次に、先程のパズルをもとに考える(【図1】参照)。黄色の小さな正方形の対角線を1辺とする大きな正方形。面積は1対2。では辺の長さは?
「面積が2ということは、同じ数をかけて答えが2になるものだね。それってどんな数だろう?」
有田先生の問いに答えるべく、みんなで電卓を使って考えることに。1.41と1.45の間の数らしい、というところまで解明して、先生が種明かし。
「実は、同じ数同士かけて2になる数は、1.41421356……(ヒトヨヒトヨニヒトミゴロ……)と、永遠に続く小数で、『無理数』といいます」
なんと、中学で学習する無理数の概念が、図形の等積変形によって小学生にも提示された。
作って、考えて、算数って楽しい!
小学校低学年の参加者には、後半の考える算数は少し難しそうだったが、中・高学年の参加者は、前半に自分が変形した図形を見ながらホワイトボードで展開される無理数の概念を興味深そうに目で追っていた。
「図形を数で考えるというのはこういうことです。今日作ったパズルはみんな持って帰ってね」
という有田先生の言葉でワークショップは終了した。
参加者からは
「前に出て五角形を変形したのが面白かった。緊張したけど、できたから嬉しかった」(小1女子)
「パズルが面白かった。算数は苦手だけど、こうやって自分で作業できるのは好き」(小5男子)
など、楽しかったという感想が多く聞かれた。
【講師コメント】パズル問題で図形の概念を学びやすく
学びの場.com(以下、学びの場) 「感じる算数」「考える算数」という言葉と内容が印象的でした。
有田 算数イコール計算だと思ってしまう人が多いのですが、今日のように手作業を入れると、計算が苦手な子でも図形の魅力を感じられると思います。
今回扱ったのは、大きくは「等積変形」という概念ですが、私はこれを小学校4年生の面積の導入時に学習できればよいと思っています。「10平方センチメートル」といっても、いろんな形があることを最初に知れば、面積の概念が頭に入りやすくなりますし、なにより面白そう、と思えるはずです。
学びの場 学校の授業でもパズル的な要素を取り入れるとよいのでしょうか?
有田 そう思います。私は図形の授業の最初には、関連するパズル問題を必ず組み込みます。子どもたちにも好評です。手を動かす活動を入れることで、図形がより具体的に頭に入るようになるからでしょう。普段、計算問題などでは手を挙げられない子が、パズルだと意外と早くできたりして、面白いですよ。
最近は、図形の問題というとすぐに計算したがる子が多くいます。面積の学習では、公式にあてはめていち早く答えを出すことしか考えない。そういう子は融通が利きません。たとえば、ある子が「長方形の面積はタテ×ヨコで出す」と言ったので、私が「ヨコ×タテじゃだめなの?」と聞いたら、「だめ」と言うのです。公式だけで勉強すると、こうなってしまいます。これでは数学の面白さはまったく感じられないでしょう。小学校段階では、今日やったように、自分の手を動かして図形で遊び、親しむことが大事だと考えます。
学びの場 そうやって工夫した面白い授業は、子どもたちのモチベーションを上げますね。
有田 その通りです。以前、学級崩壊してしまった高学年のクラスを任されたことがありました。その時、私がまずしたことは、算数と理科の授業を面白くすることでした。そうしたらだんだんとクラスも落ち着いていきました。子どもたちは本来真面目なのです。学級崩壊にはさまざまな原因がありますが、一つには授業が面白くないということもあるのです。やはり教師は授業で勝負すべきなのだと、私は思います。
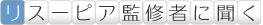
理科・数学の本当の面白さを届けたい。
学びの場.com(以下、学びの場) 「リスーピアが設立された経緯を教えてください。
岡部 リスーピアは昨今の理数離れへの対策として、2006年にパナソニック(株)が設立した理数の魅力と触れ合うための体感型ミュージアムです。パナソニックはご存じの通り製造業であり、このまま子どもたちの理数離れが進むと、将来的にも課題が出てくると考え、理数人口を増やしたいというねらいもあるとのことです。
学びの場 さまざまな設備がありますが、非常に面白く、科学への興味が増します。
岡部 ここは、理数に詳しい人のためにというよりも、むしろ理数に苦手意識を持つ人でも理数に親しめるよう、“驚き”を中心にさまざまな体験型設備が設置されています。まずツールに触れて理数の不思議に驚き、次にその原理・法則を楽しみながら学び、そして関連する身近な事例を知ることができます。
現場の先生方からは、この原理・法則が日常の中の現象に結びつけられている点がとても面白く、授業でもぜひ紹介したい、という声がよく聞かれ、好評です。
展示のほかに、今回のような、講師が理数の魅力を直接お伝えするワークショップも毎週開催しています。
学びの場 数学のワークショップの特徴は何でしょう。
岡部 今日の講座のように手作業を入れる点です。計算がテーマの時は、参加者が自分で何かを発見し、驚き、納得を得られるような仕掛けを入れています。
講師は、実験的なことをやってみたいと思っている、意欲的な方にお願いしています。ここでは、数学の実力は千差万別、年齢は小学生以上のさまざまな方が参加するので、授業内容や教材にかなりの工夫が必要になります。
学校現場では年間の指導計画に基づき、小学何年生にはこれとこれを教える、と決まっていますが、本来の数学的活動とは、年齢や学年を超えて一つの分野を広く捉えることです。ここではそれが実践できますので、子どもたちだけでなく、教える側の教師にとっても興味の湧く、チャレンジしてみたい施設だと思います。
記者は数学が大好き。久しぶりに図形の世界に入り、有田先生のガイドでとても楽しい時間を過ごした。パズルを前に四苦八苦する大人の横で、「できた!」と万歳する小さな女の子を見て、図形のセンスは、小さい子のほうがむしろあるのだなと感じた。数学は、学年が進むにつれて抽象化が顕著になってくる。特に中学では文字式が出てきて、そこでつまずいてしまう子も多い。だが、今日のように、小さい頃から形に対するセンスを十分に磨いておけば、抽象化の段階に進む時にも具体例がイメージしやすく、数学嫌いにならずにすみそう、いや、むしろ数学好きになれそう、と思った。
取材・文:菅原然子/写真:言美歩 ※写真の無断使用を禁じます。
|
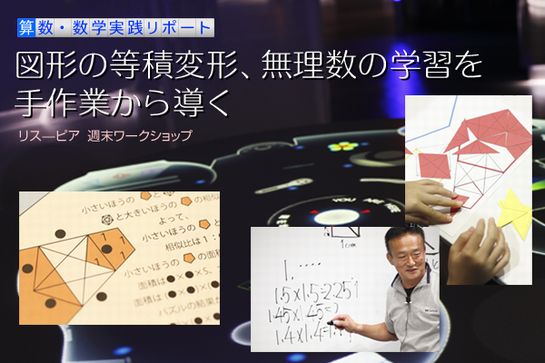
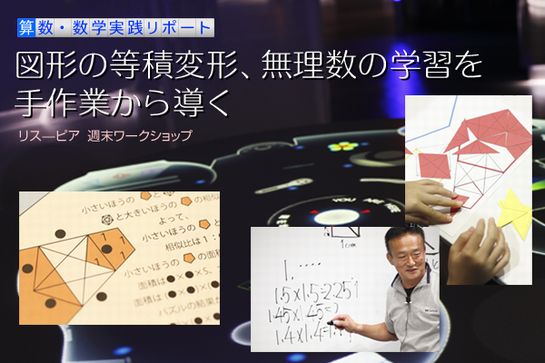















 教育イベントリポート
教育イベントリポート 食育と授業
食育と授業 教育リサーチ
教育リサーチ



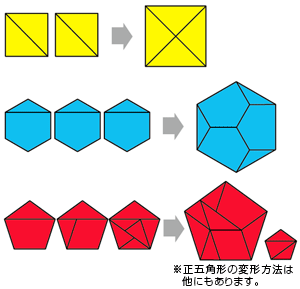




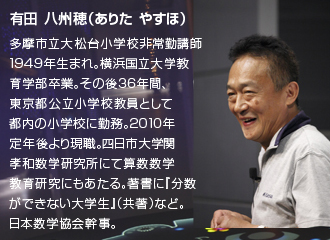


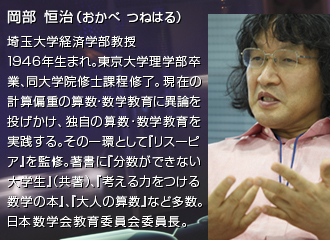

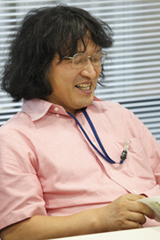

 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望

