家事育児分担シミュレーションを通じて、将来の自分の生き方や働き方を考える(後編) 生きることすべてが家庭科の学びの対象

共働き世帯が増加傾向にある昨今。その一方で、6歳未満の子どもを持つ日本男性の家事時間は諸外国に比べると著しく短い。その背景には"男は仕事・女は家庭"といった、「性別役割分業意識」があると思われる。
家庭科教育には料理や裁縫を学ぶ、かしこい消費者を育てるといったイメージがあるが、生きることすべてを学びの対象として、生きるための思想を探る教科でもある。今回は、将来のワークライフバランスを考える授業実践を取材した。後編では、授業者の佐藤誠紀教諭へのインタビューを紹介する。リアルな将来像からワークライフバランスを考えさせる
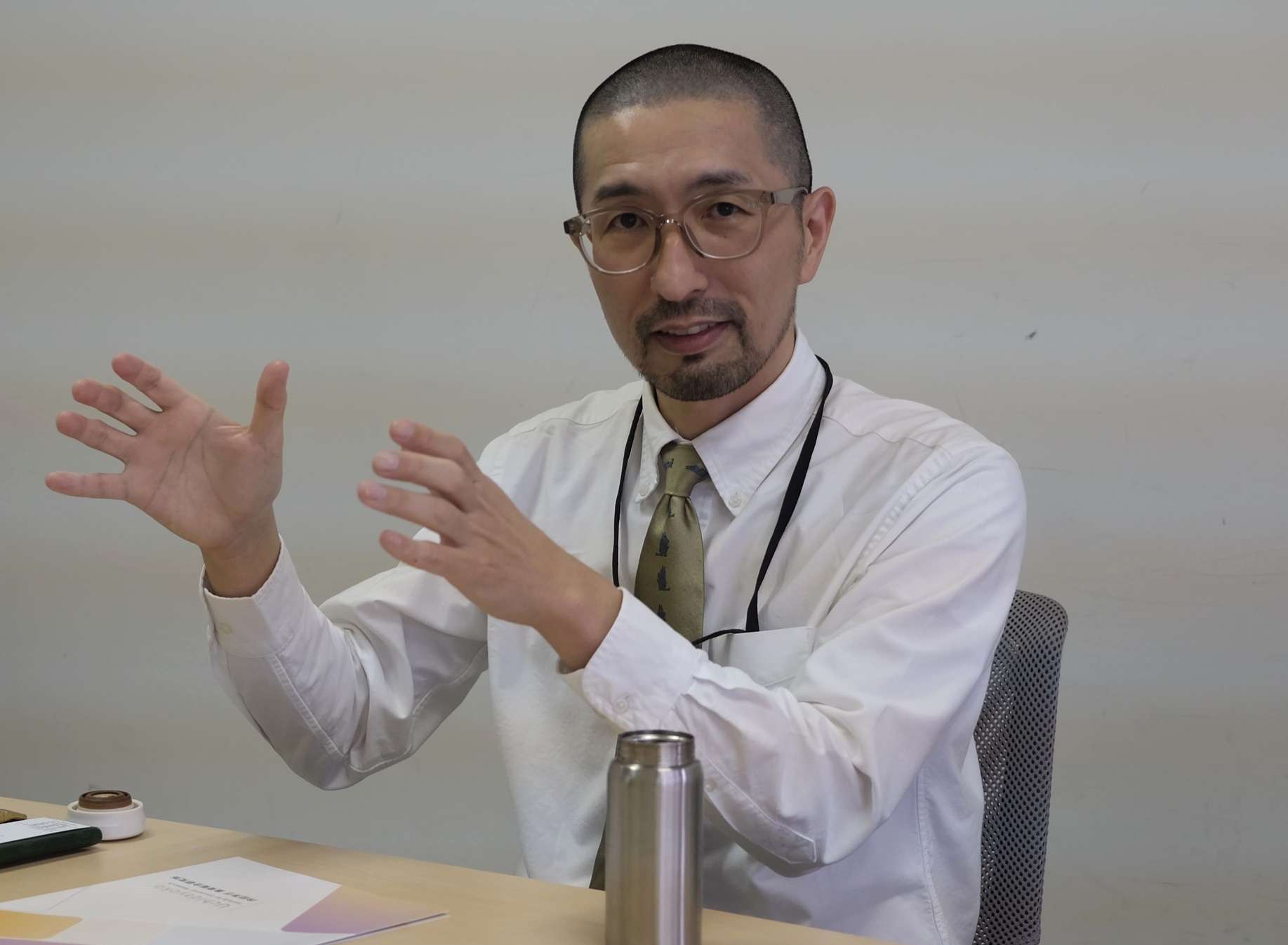
――「性別役割分業観」をテーマとした授業はいつから行っているのですか。
佐藤 誠紀 教諭(以下、佐藤) 男子部と女子部で分かれていたのを、2018年に共学化したときから行っています。それ以前は、前時の「理想のパートナー像」を考える授業までを行い、男子と女子それぞれのすれ違う意見を私が“仲介役”となって伝えていましたが、さらに踏み込んで「じゃあどうする?」と解決策を探る授業を行うことにしました。
――生徒たちの意識に変化は見られますか。
佐藤 大きな変化はないです。毎年、男女ともにまずは「人柄」がパートナーの条件のトップに来て、男女を比べると、女子は理想のパートナーに「経済力」を、男子は「容姿」を求める傾向があります。この、男子の傾向に、ちょっと・・・思うところもあるのですが、毎年気になっているのは、パートナーに経済力を求めることです。今年の男子生徒の感想では「自分は果たして結婚できるのか恐怖を覚えた」というものもありました。容姿や人柄などよりも、数字で比較できる経済力は、他者とはっきりと選別できる指標になります。
家計を支える経済力は重要です。ただ、その力が実際の生活にどう関わっているのかを考える機会があった方がいいと思い、今回の授業のような性別や収入をごちゃ混ぜにした家事分担のシミュレーションがあります。
ちなみに、本日の授業で発表してくれた男子生徒同士のペアでは、家事・育児の分担を決める際に、「どちらが料理をするか」で揉めたと話していました。そこには、「男は仕事 女は家事育児」という考え方が無意識にあるように感じられます。性別役割分業観 が良い悪いではなく、今ある問題に対してどう折り合いをつけるべきなのか、どのようすれば持続可能なのか考えていくきっかけになれば良いと思います。
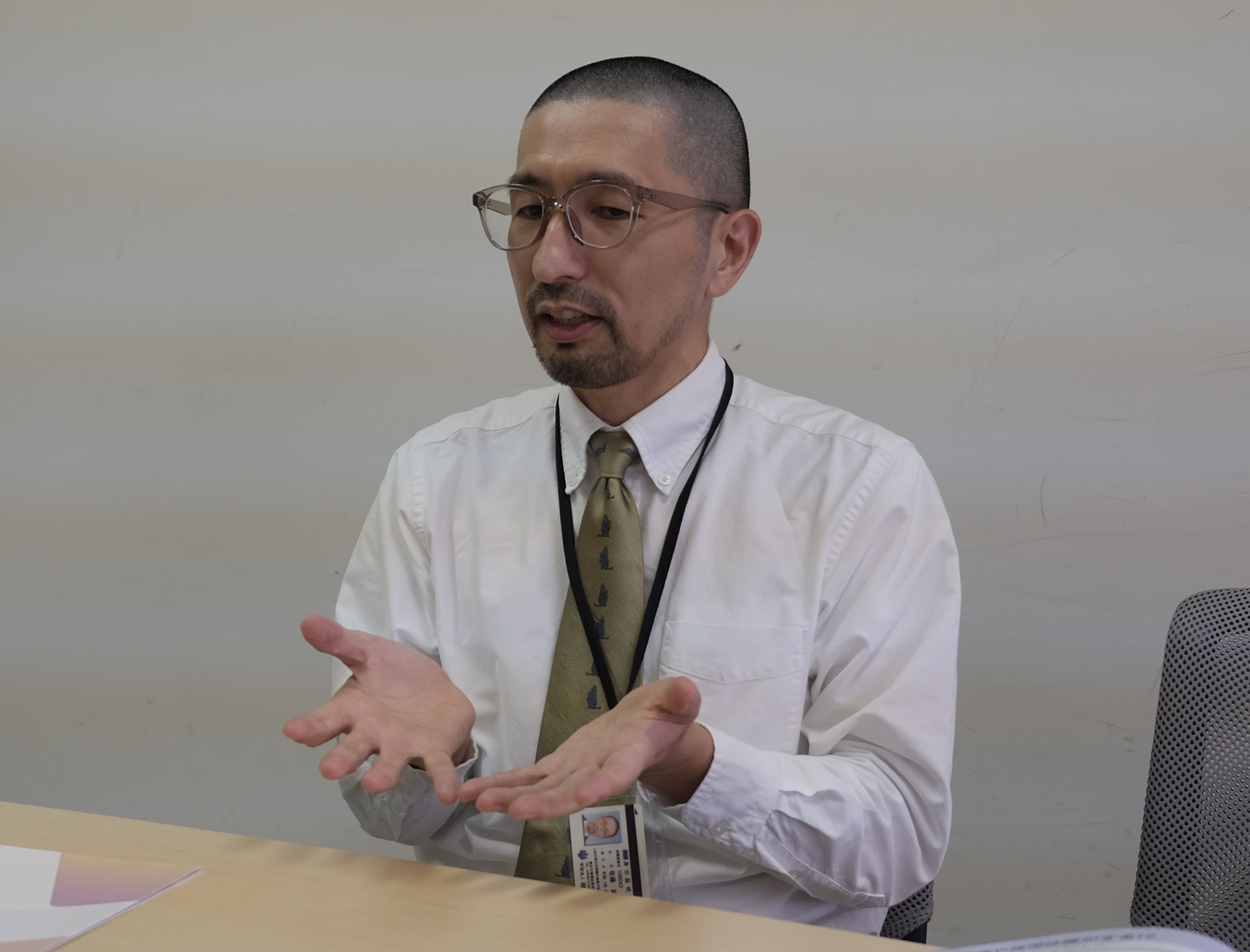
――本日の授業のねらいを教えてください。
佐藤 最終的なゴールは「ワークライフバランスの実現」です。家事や育児をどのように分担すれば実現できるのかを、生徒たちに学んでほしいと考えています。
――授業づくりで意識したポイントを教えてください。
本学習におけるポイントは3つあります。1つ目は「ワーク(仕事)」の具体的な設定です。経済的側面と時間的制約がトレードオフの関係にあることを理解するため、年収と残業時間を取り入れました。くじ引きで決めたのは、年収には実力だけでなく、人との出会いなど「運」も関係しているということを、生徒に知ってもらいたかったからです。
2つ目は「ライフ(生活)」における時間的制約の可視化です。法定労働時間と残業時間、通勤時間から「家事・育児ができない時間」を出し、1日の中で「ライフ」に使える時間が物理的にどれくらいあるのかを把握させました。多くの生徒は「仕事と家庭を両立したい」と考えていますが、実際にはそれが簡単ではないことを理解してもらえたと思います。
3つ目は「バランス」の模索のシミュレーションです。家事・育児を分担する作業は、限られた時間の中で仕事と生活をどう両立させるか、そのバランスを考えるシミュレーションとしました。また、家事・育児を一人ですべてこなすことの非現実性や、パートナーとのコミュニケーションの重要性を認識させたのも狙いの1つです。
実際に家事や育児をするときには、忙しい中で行うものです。現実を理解するために、まず収入を決め、そこから家にいられる時間を定めました。これにより、生徒たちは家事・育児の分担が性別ではなく、経済力によって決められている現実に気づけたのではないかと思います。
実際の社会では、男女に賃金差があり、平均的に男性の方が女性より高い現実があり、今日のクラスのようにはなっていない現実はありますが、共働き世帯が増えていること、これからの彼らのライフコースを考えると、いずれ今日の授業で見られたようなケースにあてはまることがあると思います。
「家事・育児の意思決定は、性別だけではなく、経済力も大きく関わっていること」について、生徒は理解してくれたと思います。理想のパートナーに経済力を求めると、家事育児の意思決定に関して相手に委ねてしまうことになりかねないことが、このシミュレーションで体験できると思っています。
すべての授業にジェンダー平等の視点を散りばめて

生徒の作品 答えは全員男子
――「SDGs目標5.ジェンダー平等を実現しよう」に関連して、他にも授業を行っていますか。
佐藤 授業の中で「ジェンダー」という言葉を使うことはほぼありませんが、家庭科においては、すべての授業にジェンダー平等の視点が散りばめられていると思っています。たとえば、調理実習や被服実習も男女一緒に行っていますが、そこに「男女差」は感じません。男子だから下手とか、女子だから上手い・サボらないということはなく、むしろ個人差のほうが大きいです。
毎年、ゴールデンウィーク中に自分が作れる料理を作って、写真付きのレポートを提出する」という課題を出しているのですが、レポートを見ていて毎年感じるのは、「男子だから」「女子だから」という先入観は意味がないな、と思ってしまいます。今年の生徒の課題ですが、どれが男子で女子だかわかりますか?
そういった日々の学びの積み重ねの中で、「男子はこう」「女子はこう」といった固定的な見方は、自然と薄れていくはずです。つまり、教員が「ジェンダー平等を実現しよう」とあえて言わなくても、生徒たちが自然と気づくことが理想です。
男性家庭科教員として目指すこと
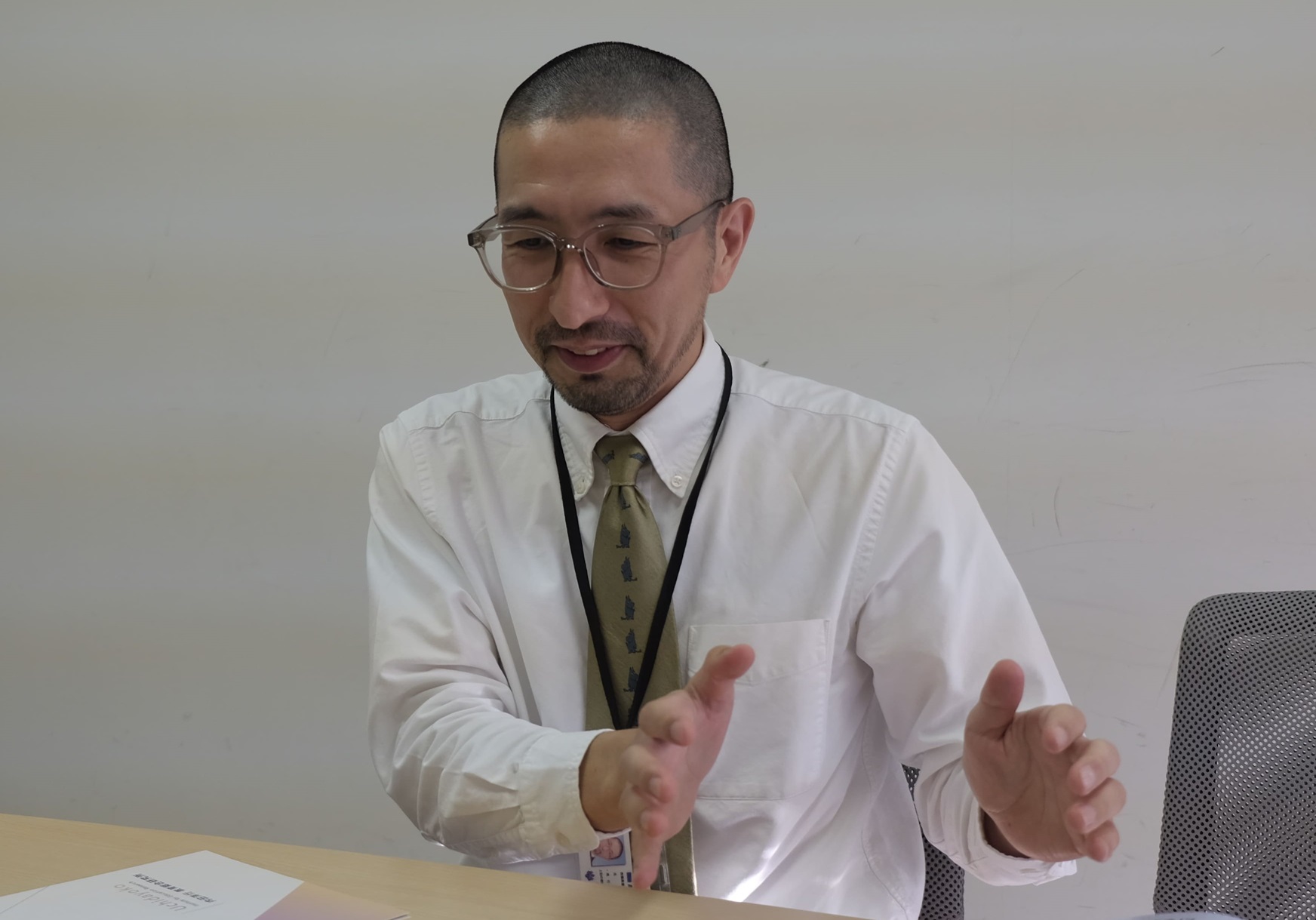
――家庭科教員を目指したきっかけを教えてください。
佐藤 私は現在47歳で、女子だけ必修だった家庭科が男女ともに必修化された世代です。男性の家庭科教員も一定数いて、メディアでクローズアップされることもありました。もともと学校の先生になりたいという思いがありましたが、そうした時代背景の影響もあって、「家庭科って面白そうだな」と感じたことが、目指すきっかけになりました。
あとは、私の親からは「あなたは長男なんだから」と言って、育てられました。親の期待に答えられなかったからなのか、そう言った価値観に反発して、そのアンサーとして家庭科の教員を選んだ背景もあります。
――男性の家庭科教員は全国でも1%未満といわれていますが、その立場から、どのようなことを目指していきたいですか。
佐藤 家庭科は、受験科目ではないので、学校の中でも目立つ存在とは言えません。だからこそ、多くの人に「家庭科って面白いよね」って思ってもらうことが大事だと思っています。当然ですが、家庭科教員として、今の授業を大切にすること。それと同時に、仲間を増やすためににも、学校の外に家庭科を発信する役割があると思っています。
――桐蔭学園高等学校は1学年に24クラスあるとのことですが、家庭科の先生は他にもいらっしゃるのですか。
佐藤 7人家庭科の先生がいます。学ぶことが多く、すごい授業をしている先生たちです。しかし、ジェンダーと家庭科の話になると、私の「男性家庭科教師」という肩書きが目立ってしまい、今回のようなお話は私宛にいただくことが多い現実があります。話が戻ってしまいますが、いつか私の肩書きに「男性」がなくなるくらい、男性の先生が増えて欲しいですね。
「仕事」と「家庭」の他にもう1つ、自分を支える何かを

2024年のダンスバトル(オーバー40歳の部)では年間チャンピオンに
――今後、挑戦してみたいことを教えてください。
佐藤 私は学生時代からずっとRepoll:FXというダンスチームで ストリートダンスをしています。20代、30代には、仲間と一緒に世界的なコンテストで上位に入ることもありました。40代後半になった今でも、コンテストに出続けることを目標に練習を続けています。
今の生活から、ワークライフバランスを考えると、「ワーク(仕事)」「ライフ(家庭)」の他にももう一つ、軸があってもいいと思うことがあります。趣味、友人、ボランティア、地域の町内会のつながりなど、なんでもいいので、ワークとライフ以外の「個人の活動」や「地域・社会とのつながり」があった方がいいと思うのです。
まったく家計にはプラスにはなっていませんが、私はダンスのつながりが続いたことで、結構助けられて生活しているという実感があります。時には面倒な事もありますが、緩やかな人とのつながりが続いていくと、人生がより楽しくなると思ってます。
だからこそ、生徒たちにも将来のライフプランを考えるときに、「仕事」と「家庭」だけでなく、もう1つ、自分を支える何かを持ってほしいと伝えていきたいですし、仕事にも家庭にも、ダンスにも全力で向き合っていきたいですね。
記者の目
筆者(40代)にとって高校時代の家庭科といえば、裁縫や調理実習といった内容が中心だった記憶がある。
しかし今回の取材を通して、現在の家庭科は当時とはまったく異なる学びに進化していることに驚かされた。さらに金融教育が含まれていることを考えると、これからの人生において大きな力となるはずだ。
取材・文・写真:学びの場.com編集部
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事














 教育イベントリポート
教育イベントリポート 食育と授業
食育と授業 教育リサーチ
教育リサーチ



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望


