AI時代の教育に必要な力とは? 親として今できること

私、アグネス・チャンがこれまで学んだ教育学の知識や子育ての経験をもとに、学校や家庭教育の悩みについて考える連載エッセイ。教育現場や家庭でもAIの使用が広がる中、どのようにAIと共存し、子どもたちに何を伝えていけばよいでしょうか。今回は「AI時代の教育に必要な力とは? 親として今できること」をテーマに考えました。
AIを使いこなす時代が来ています
我が家では、すでに次男と三男がAIに関わる仕事に就いています。スタンフォード大学時代にもAIを利用したプログラミングの開発や研究をしていました。現在も彼らはAIを使って、世の中を動かし始めているのです。
中国でも新しい教育方針として、小学校からのAI教育が義務化されました。世界的に、AIは避けては通れない重要課題となっています。これからの教育では、「AIにどう使われるか」ではなく、「AIをどう使いこなすか」が問われるようになるでしょう。
私自身も仕事や日常生活の中でAIを活用しています。たとえば、原稿のテーマについて相談すると「3月8日は国際女性デーです。女性の権利に関することはどうですか?」などと提案してくれたことがありました。他にも、アメリカの関税の問題のような社会的な話題から、家にある材料を使った献立、自分の身長と体重に合わせたダイエット方法まで、どんなことでも答えてくれるのです。しかも、「あなたの体重ではダイエットは必要ないかもしれません」ときちんとデメリットまで指摘してくれるのです。まずは一度使ってみると、その便利さが分かると思います。
しかし、これだけ有能だからこそ、AIには悪用される恐れもあります。実際に、香港ではAIで本人そっくりに生成した映像による詐欺なども発生しています。また、宿題やレポートをすべてAIに任せる子も出てくるかもしれません。テーマだけ伝えて、あとはAIに書いてもらうことも簡単にできてしまいます。完成したものは、もはや子どもが書いたのか、AIが書いたのか、見分けはつかないほどです。でも、それでは学ぶチャンスが減ってしまいます。宿題やレポートは教わったことを復習し、理解を深め、自分の考えをまとめるためにやることだからです。AIに任せれば楽ですが、それでは自分の力が伸びません。誘惑に負けず、自分で大事なことをつかもうとする子どもの自制心も大切です。
AIには無い人間らしさを育てることが大切です
文章や論文はAIがあっという間に書いてしまうので、これからは文章の上手さは重視されなくなるかもしれません。それよりも、物事の一番大切な部分を把握できているのかどうかが重要になります。試験の形式も文章力を問うものでなく、選択肢を選ぶことで本質を捉えているかを判断するようなものに変わっていく可能性があります。
もうひとつ大切なことがあります。それは、ビッグデータにないものを自分の中に持つことです。息子たちに「これからはママのような作家の仕事は必要なくなるんじゃない?」と聞かれたことがあります。私は「ママはAIデータが持っていないものが、まだ自分の頭の中にたくさんあるから大丈夫なのよ」と答えました。
AIはビッグデータをもとに知識を生み出し、そこから解決策を導きます。ですから、データに収まらない知識や考え方、創造力を持つ人間になることが大切なのです。
さらにAIは、感動や愛おしさ、寂しさ、緊張、恥ずかしさ、好き、嫌いなどの人間特有の感情や経験を持つことも難しいでしょう。たとえば、アメリカのAIに「きれいな顔を描いて」と頼めば、白人のモデルのような顔を表示します。なぜならビッグデータにそうした画像が多く含まれているからです。でも、私たちはモデルのような人だけを美しいと感じるわけではありません。「この人が好き」「この子が美しい」と思う人間らしい感情は、AIには理解できないのです。
正しさだけでなく、間違えることや嘘をついてごまかそうとすること、人を裏切ろうとすることのような複雑な感情もある意味で人間らしさです。子どもに失敗や負けるくやしさを経験させることも大切だと、私は思います。これまで、特にアジア圏の教育では「テストで100点をとる子ども」を育てようとする傾向がありました。しかし、正確さを育てても、ロボットにはかないません。「これって本当?」「僕は賛成できないな」と疑問を持つ子がこれからは必要とされるでしょう。
知識よりも愛やモラルで、子どもたちから尊敬される大人へ
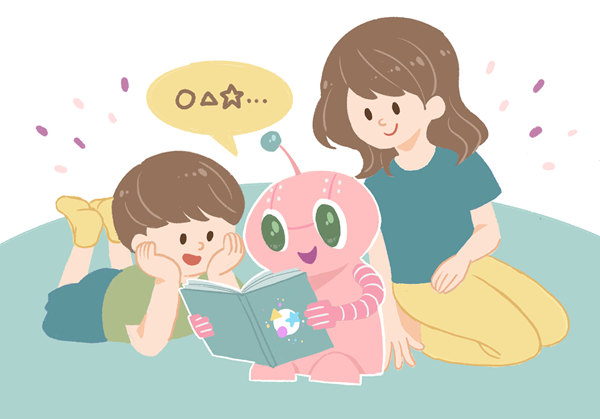
@学びの場.com
そして、これはネット社会になってからの問題でもありますが、今の子どもたちは情報を先生や大人ではなく、ネットから得ています。検索すればなんでもわかるので、場合によっては子どものほうが詳しいこともあるくらいです。もはや、「大人が教えてあげるから、言うことを聞きなさい」という理論は通用しなくなっているのです。
これまでは、親は子どもの手を引いて導いていく立場でした。でも、今では「この方向に行ったら?」と、子どもの背中を押す存在に変わっているのです。かつての親は知識があることで子どもから尊敬されていましたが、これからはどれだけ子どもたちを愛しているのか、家族を大事にしているのかという部分が見られるようになります。
教育現場では、先生たちはますます大変になっていくと思います。先生が間違えたときにも、AIに聞けばすぐに正解がわかってしまいます。先生の言うことを素直に聞かない子どももこれまで以上に増えていくかもしれません。特に中学生くらいになると知識も増えるので、先生も大学生を教えるくらいの気持ちが必要です。教室は子どもたちにとって「教えてもらう場」ではなく、「交流の場」となっていくのかもしれません。先生も「教えてあげる」ではなく、「学校に来てくれてありがとう」「一緒に学びましょう」という気持ちで向き合わないと、子どもたちも納得しないでしょう。知識ではなく、人間性やモラル、努力する姿勢などから子どもたちの尊敬を得ることが必要です。
今、人間は新しい出発点に立たされています。このAIによる変化は今後、止まることはないでしょう。子どもたちが大人になったとき、どの職業が残っているかは、もう私たちには予測できないのです。だからどんな変化にも強く対応できる子どもを育てなければいけません。変化を歓迎して、臨機応変に動けるような子です。
いつの時代も転換期には、人間は慌ててきました。電気が発明されたときには「ろうそくを作る仕事は無くなるの?」、車が登場したときには「馬の世話をしている人はどうなる?」と世の中は不安になりました。でも、大丈夫です。AIによって人間の仕事は減っていくかもしれませんが、AIによって空いた時間を使って人間はまた新しい何かを生み出すはずです。次の世代が必ず私たちをさらに素晴らしい未来に連れて行ってくれると信じています。

アグネス・チャン
1955年イギリス領香港生まれ。72年来日、「ひなげしの花」で歌手デビュー。上智大学国際学部を経て、78年カナダ・トロント大学(社会児童心理学科)を卒業。92年米国・スタンフォード大学教育学部博士課程修了、教育学博士号(Ph.D.)取得。目白大学客員教授を務め、子育て、教育に関する講演も多数。「教育の基本は家庭にある」という信念のもと、教育改革、親子の意識改革について積極的に言及している。エッセイスト、98年より日本ユニセフ協会大使、2016年よりユニセフ・アジア親善大使としても活躍。『みんな地球に生きるひと』(岩波ジュニア新書)、『アグネスのはじめての子育て』(佼成出版社)など著書多数。2009年4月1日、すべての人に開かれたインターネット動画番組「アグネス大学」開校。2015.6.3シングル『プロポーズ』release!!(Youtubeで公開中)
ご意見・ご要望・気になることなど、お寄せください!
「アグネスの教育アドバイス」では、取り上げて欲しいテーマ、教育指導や子育てで気になることなど、読者の声を随時募集しております。下記リンクよりご投稿ください。
※いただいたご意見・ご要望は、企画やテーマ選びの参考にさせていただきます。
※個々のお悩みやご相談に学びの場.comや筆者から直接回答をお返しすることはありません。
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 教育つれづれ日誌
教育つれづれ日誌 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望・気になること
ご意見・ご要望・気になること










