|
■「死への準備教育」ではない「いのちの教育」
「子どもといのちの教育研究会」会長で東海大学文学部教授の近藤卓先生は「いのちの教育」の目的や意味をこう話す。
「いのちの教育の目的を一言で表すならば、『世界の平和を目指す』ことなのです。こう言い切ってしまうことは、とても勇気のいる行為ですが・・・。この『いのちの教育』は、『死への準備教育』ではありません。『準備』という言葉は、何かをスタートすることを意味します。『死」はスタートではなく終点ですので、『死への準備』は必要ないと考えます。ですから、『死を通して生を考える』とか、『死を意識して命の大切さを確認する』ということはしたくありません。小さな子どもが楽しく遊び、明るく前向きに充実して生きているのは、『死を意識している』からではないと思います。生きていることそのものが楽しく価値あることだからです。そんな子どものような『いのち』を大切にしたいのです」
死、つまり終わる時はある時、突然起こるもの。だから「死」という言葉を避け、「生」に執着する。この近藤先生の考えに疑問を持つ方もいるかもしれないが、まだ幼い子どもたちの多くは「身近な死」を経験したことがないだろう。そんな子どもたちに「死」を通して考えさせるのではなく、まずは、楽しく健やかな自らの「生」を実感して欲しい。「生」は価値あるもの=毎日には価値がある大切なものだと気づいてもらえれば、自分のいのちを大切にし、無駄にするようなことはなく、さらには他者のいのちをも大切に思うことができるのではないだろうかと考えているのだ。
同研究会は今年で結成5年目を迎える。小中高の教諭、養護教諭、医療関係者、宗教者、研究者、カウンセラーなど約60名の会員の多彩なメンバーが集まっている。5年前に開催された全米ホスピス協会賞を受賞した絵本に関するシンポジウムをきっかけとして同研究会を発足、広報誌を発行し、隔月で行われる勉強会と年に一度の研究大会を催している。
■5年間の積み重ねを集大成
この日の勉強会は、文京シビックセンター和室にて行われ、高校や養護学校で「いのちの教育」に取り組んでいる先生方やスクールカウンセラー、近藤先生のゼミ生、教育関係会社の方など14名が集まった。お茶とお茶菓子を交えながら、和やかな雰囲気の中、進められた。
まずは全員の自己紹介。続いて、近藤先生が自ら編者となり、今年3月に出版した「いのちの教育~はじめる・深める授業のてびき」(実業之日本社)への道のりについて話した。
近藤先生が同研究会の今までの成果をまとめたいと考えていたところ、2002年度の研究大会に訪れた実業之日本社の藤田敏さんが、この活動に共鳴し、出版を企画したという。書籍の執筆は近藤先生をはじめ、会のメンバーなどが分担し、実践された授業を元に執筆した。大きく4つの章から構成されていて、「いのちの教育の理論」から始まり、「1時間からはじめるいのちの教育」、「つなげて深めるいのちの教育」では、多くの実践例が詳しく紹介されている。例えば、友だちの「いいとこさがし」を通じて、お互いのよさを見つめ、自分を肯定することからいのちの重さに気づかせたり、性やAIDS、臓器移植などをテーマに取り上げ「いのち」を考えるなど。ここでは、担任教諭や養護教諭だけではなく、外部講師を招いた事例も盛り込まれている。巻末には授業で使える絵本や生徒向け・教員向けの書籍、100冊を紹介した参考図書集もあり、「いのちの教育」を始めてみたい先生や、授業に行き詰まりを感じている先生に役立つ実践的内容が詰まっている。
■いのちを学び豊かな時間を
その後は、近藤先生と参加者とのざっくばらんな懇談によって進められた。参加者たちは、今感じていること、疑問に思っていることなどを自由に発言する。
「『一生懸命生きる』ことは何も全力でやることではありません。眠ることも一生懸命。『眠るカメ』がいたって構わないと思います。先日、高校の保健体育の教科書で『こころ』の部分について執筆を担当しました。そこで訴えたかったことは、『自己実現』です。実現の仕方は人それぞれ。一気に全力を出し切ったり、ゆっくり少しずつだったり、その人なりの一生懸命があると思います」近藤先生の話にうなずく参加者。
初めて参加する参加者から質問があがる。
「『死への準備教育』とはどのような背景があるのでしょうか?また、『いのちの教育』に取り組む時、『死』を前提とした教育と考えてもよいのでしょうか?」
それに対し、近藤先生が考えを述べる。
「ライフイベントとして『死への準備教育』が必要という考え方もありますが、『死』そのものには続きはありません。ヨーロッパでは、宗教的に『死のあとのつながり』が存在すると考えられているからではないでしょうか」
他の参加者からも「『死』を前提に置かなくても、子どもたちにポジティブな方法でアプローチできると思います」と同意する意見が。
「いのちの教育」と聞くとすぐに「死への準備教育」を結びつけて考える方も多いと思うが、必ずしもそうではない方法があることに気づく。
「『いのち』は教える側にとっても、マニュアルなどありません。共に考える時間を持つことが大切なのではないでしょうか?『いのち』を学ぶ機会が増えれば、より豊かな時間を過ごせるのではないでしょうか」藤田さんは話す。
■『いのちの教育』は思いを『共有』するチャンス
近藤先生は今後の活動についてこう話す。
「いのちの教育は子どもと子ども、子どもとおとなが、みんなで思いを共有するチャンスを提供するものです。心の問題、社会の問題、誕生から死までのあらゆる問題がテーマになります。どんなときにも、前向きに明るく楽しく、みんなで考えたり感じたりすることを中心に活動していきたいと思っています」
今後の勉強会では、現在、「いのちの教育」に取り組んでいる高校や中学校の先生による事例研究が行われる予定である。
(取材・構成:学びの場.com)
| 


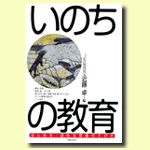

















 教育イベントリポート
教育イベントリポート 食育と授業
食育と授業 教育リサーチ
教育リサーチ



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望

