「子どもの貧困」に関して学校ができること
この1か月程、「子どもの貧困」に関する本を読んでいました。
特に冬休みに入ったこともあり、10冊以上の本を読みました。
そういった中で感じたこと、特にあまり一般的には言われていない小学校教員からの視点で「子どもの貧困」について書きたいと思います。
帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師 鈴木 邦明
「子どもの貧困は子どもの問題ではない」
本を読めば読む程、子どもの貧困についての問題は、「子どもに問題があるのではない」ということに気付かされます。
問題は「親」もしくは「社会(仕組み・制度)」にあります。
「親の発達障害」
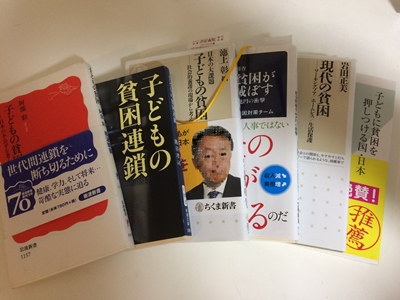
子どもは文科省の調査によると普通学級に発達障害の児童は6.5%いるとされています。
30人のクラスですと、2~3人いることとなります。
長年、小学校の学級担任をしていて、同様に親にも発達障害のある人がいるのではないかと感じます。
「モンスターペアレント」と呼ばれる人達もコミュニケーション能力の低さなどは、そういった可能性もあるのではと思います。
また、親が発達障害などである場合、行政などによる適切な支援が行えていなければ、経済的にも難しい状況である可能性があります。
不登校、高校の中退など学生時代の生きる上での難しさ。
コミュニケーション不足、注意不足など働いてからも難しさを抱えます。
そういったことを抱えたまま、子どもが産まれたとしたら、その子どもは厳しい状況となります。
LDなどである場合、行政の手続きなどもきちんとできない可能性があります。
障害者手帳が出る程度の障害であれば、行政などによるサポートがある程度されています。
しかし、そこまでではない場合は、行政などのサポートはなかなか得られないはずです。
クラスの子どもと関わる際、その子どもが「発達障害」であるとなれば、教師の意識もおのずとそのようになります。
ちょっと常識外れな行動をしても、理解できることが多いです。
親との関わりにおいても、同様の気持ちの持ち方をすれば、イライラが減るのではと感じました。
政府の統計などでは、大人の発達障害の割合などは出ていないようです。
しかし、ある程度の数はいます。
他の要素もあるのだと思いますが、そういったことと「子どもの貧困」が大きく関わっているように感じます。
「学校における支援の不十分さ」
「子どもの貧困」において、学校における支援の必要性は、様々な所で述べられています。
集金などの金銭に関すること、欠食や不衛生などの健康面に関すること、貧困が原因と思われるいじめなどのコミュニケーションに関する事などが挙げられています。
私が感じていることは、そういった事の中でも特に中学、高校などでの関わりの大切さです。
中学から高校の年頃は、その後、人生において、自分自身が貧困になり、そして、自分の子どもを貧困にしてしまうきっかけがいくつもあります。
具体的には、「高校進学、高校中退、望まない妊娠・出産、就職・離職」などです。
教育困難校と呼ばれる高校では、一年で1クラス分位ずつ生徒が辞めていってしまうということを聞いたことがあります。
あまり学習意欲の高くない子どもが中学の時よりも高度なことを学ぼうとしているのですから困難であろうということは想像がつきます。
また、高校の先生方の苦労も想像できます。
中学から高校の段階で、これまで以上に「人生について」考える時間を作ったらどうかと思います。
勿論、学習においてすべきことは定められています。
それは十分承知の上で、様々な工夫で、生徒が「どういったことが人生において大事なのか」「何をしたら自分にとって損なのか」「どうしたら幸せな人生を送ることができるのか」などを知り、考える時間を取るのです。
高校を中退してしまうのは、人生においてどれだけ損なのかということをそれなりに考えたことのある生徒は、中退したいと思っても行動に違いが出てくるかもしれません。
若すぎる結婚、出産によって、どれだけ苦労している人がいるのかを知ることも同様です。
若すぎる結婚におけるその後の離婚率、母子家庭率、貧困率などを具体的に伝えることで、少しは何かの役に立つかもしれません。
ポイントは「数値を用いて具体的に」という部分かも知れません。
教育には「適時」があります。
貧困の問題などは、中学校から高校の自分の人生を考える時期に行うのが最適でしょう。
「小学校の教員がすべきこと」
小学校の教員がすべきこととは、様々な基礎的な力を付けさせることでしょう。
小学校の2年生で学ぶ九九は、その後の算数・数学の基礎となります。
家庭での親の関わりが十分でない子どもは、九九の習得が完璧にならない場合があります。
小学校の学級担任は、家庭の状況なども分かります。
家庭でのフォローが十分でない家庭の子どもには、少し手間を掛けて、九九の習得を手伝うことなどが大事になります。
そういったフォローを行わないと、それが後々大きな影響を与えてしまいます。
九九が完璧でない場合、小学校の3年生や4年生で取り組む多くの単元で間違いが多くなります。
やり方は理解できていても、実際に計算をすると九九の不十分さから間違いになってしまいます。
そういったことが続くと、子どもは算数嫌いになります。
算数嫌いがきっかけで、国語嫌い、そして、勉強嫌いへとつながっていってしまいます。
小学校の教員がしっかりと九九などの基礎の定着を図ることで、子どもの勉強嫌いを減らすことができます。
学力を付けることが、貧困の可能性を減らす一番の要素だとされています。
中卒より高卒、高卒より大卒である方が、貧困になる可能性が低いという統計データもあります。
「税金「で」支える立場か、税金「を」支える立場か」
一字違うだけで大きな違いがあります。
今の子ども達が、将来、税金「で」支える立場になるのか、それとも、税金「を」支える立場になるのかは、今関わっている大人に掛かっています。
「子どもの貧困」に関することは、家庭に関わることも多いため、教員ができることが限られていることは事実です。
しかし、できることもたくさんあります。
できることをやっていくことが大事だと思います。
教育の役割とは、究極的には「子どもに幸せな人生を送ることのできる能力を付けること」だと思います。
不幸な思いをする人が減ることを願いいます。
鈴木 邦明(すずき くにあき)
帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師
神奈川県、埼玉県において公立小学校の教員を22年間務め、2017年4月から小田原短大保育学科特任講師、2018年4月から現職。子どもの心と体の健康をテーマに研究を進めている。
同じテーマの執筆者
-
兵庫県公立小学校勤務
-
兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)
-
大阪府公立小学校教諭
-
特定非営利活動法人TISEC 理事
-
兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭
-
岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任
-
福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝
-
大阪市立堀江小学校 主幹教諭
(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -
戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表
-
佛教大学大学院博士後期課程1年
-
明石市立高丘西小学校 教諭
-
木更津市立鎌足小学校
-
北海道公立小学校 教諭
-
東京都東大和市立第八小学校
-
東京学芸大学附属大泉小学校 教諭
-
東京都品川区立学校
-
岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭
-
神奈川県公立小学校勤務
-
寝屋川市立小学校
-
仙台市公立小学校 教諭
-
東京都内公立中学校 教諭
-
目黒区立不動小学校 主幹教諭
-
東京都公立小学校 主任教諭
-
尼崎市立小園小学校 教諭
-
埼玉県公立小学校
-
大阪府泉大津市立条南小学校
-
岡山県和気町立佐伯小学校 教諭
-
合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない































 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望








