前回から新年度の学級づくりについて、「整理整頓・掃除」の指導を紹介しています。今回はその2回目で掃除についての指導を紹介したいと思います。
掃除の指導は学級指導の要のひとつだと考えています。それは、環境をきれいにすることが児童の心の安定にもつながると思っているからです。雑然とした教室やゴミだらけの廊下では落ち着きません。環境の荒みが子どもの心の荒みとなって表れる場合もあります。そのようなことから、年度当初にはきちんとした掃除指導が必要だと考えます。
これまで担任してきた学級では掃除があまり得意でないことが多かったように思います。その原因として、「手順を知らない」ことと「掃除を一生懸命にやるモデルを知らない」ことが挙げられると感じていました。そこで、児童に掃除の手順をあらかじめ示し、教師も一緒にその手順で掃除を行うようにしました。一緒に掃除をしていると、児童をたくさんほめてあげることもできます。掃除の時間が貴重な児童とのコミュニケーションの時間にもなります。
また、掃除を一生懸命に行っている姿をモデルとして子どもたちに示すことも大切だと考えています。できれば、上級生の掃除の姿を生で見させるのがよいと思います。私の場合は中学生の掃除の様子をテレビで観させるようにしました。そのクラスでは、放課後に全員掃除を行い、一人一役の仕事を着実に行うようにしています。全員で一斉に行う掃除の姿は圧巻です。児童にその様子を見せることで、掃除をする素晴らしさを感じてほしいと思いました。
児童に掃除の手順や、中学生の掃除の姿を観察するための視点を示すために、年度当初から活用している「学級の教科書」を活用しました。内容は以下の通りです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<掃除活動の流れ>
1 そうじ場所に集合(役割の確認)
2 そうじ開始(もくもく!すみずみまで!)
3 そうじ用具のかたづけ
(かたづけまでがそうじです。)
4 用具の確認(きれいにかたづいていますか?)
5 反省会(今日のそうじについて反省会をしよう)
<そうじが上手な中学生の教室から・・・>
このビデオは中学校のあるクラスのビデオです。そうじの様子をビデオにとっています。このクラスは成績が学年で1番・運動も1番だそうです。そうじしているすがたからそのひみつを探ろう。
[児童の感想から]
・全員が自分の仕事をしっかりと行っていた。
・みんな真剣に掃除をしていた。
・みんなが一斉に動いているから、とてもスピーディーだった。
・あんなに早く教室掃除が終わるなんてすごい。
・教室がとってもきれいになっていた。
(『菊池学級教科書』26年度版より)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このように、掃除についての意味づけをしたら、あとは実践あるのみです。教師も一緒になって、毎日の掃除をやりきっていくことで子どもたちの掃除力が向上してくると思っています。

菊池 健一(きくち けんいち)
さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当
所属校では新聞を活用した学習(NIE)を中心に研究を行う。放送大学大学院生文化科学研究科修士課程修了。日本新聞協会NIEアドバイザー、平成23年度文部科学大臣優秀教員、さいたま市優秀教員、第63回読売教育賞国語教育部門優秀賞。学びの場.com「震災を忘れない」等に寄稿。
同じテーマの執筆者
-
兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)
-
京都教育大学附属桃山小学校 教諭
-
大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長
-
戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表
-
小平市立小平第五中学校 主幹教諭
-
西宮市立総合教育センター 指導主事
-
明石市立高丘西小学校 教諭
-
木更津市立鎌足小学校
-
東京学芸大学附属大泉小学校 教諭
-
愛知県公立中学校勤務
-
大阪大谷大学 教育学部 教授
-
神奈川県公立小学校勤務
-
寝屋川市立小学校
-
明石市立鳥羽小学校 教諭
-
千代田区立九段中等教育学校
-
大阪府泉大津市立条南小学校
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
「教育エッセイ」の最新記事














 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない



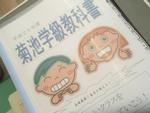
















 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望








