

全国各地で様々な授業研究会が行われています。教師にとって、他の先生の授業を参観することは何よりの勉強になります。
「自分だったらこの教材をどのように教えようか」
「この子をもっとのばしてあげる方法は無いのか」
など、考えながら参観することで、自分の指導に役立ちます。私もできる限り、研究会に参加し、授業を参観するようにしています。
しかし、いつも感じるのは、授業にいたるまでの経緯や、その先生がどのようなことを重点に指導をされてきたかということが見えにくいということです。もちろん、学習指導案に「指導観」や「単元計画」などが書かれており、文章で書き表されていますが、十分に伝わってきません。参観する方にとっては、1時間の授業のみから想像して、これまでの指導のあり方について考えることになります。このような状況を改善するために、授業を参観してもらう先生にもっと授業作りについて深く知ってもらう方法はないかということを考えてきました。
そのような中、1月31日に勤務校の研究発表会で国語の授業の担当をすることになりました。この機会に、参観される先生方に授業について深く知ってもらうための方法を考えてみることにしました。実践したいと考えていることは以下の通りです。
(1)授業実践パネルをつくって参観者の先生が、これまでのクラスでの指導の取り組みについてわかりやすくする。
→写真をたくさん盛り込んであるので、これまでの取り組みがビジュアル的にとらえられると思います。また、私の場合にはNIE(教育に新聞を)や辞書引き学習などの日々取り組んでいる実践についても知らせることができます。
(2)授業実践集をつくって、研究授業の時間にいたるまでの記録を参観者の先生に示す。
→児童のワークシートや授業の様子の写真を掲載することで、これまでの指導の流れが分かり、参観する授業を理解しやすくなると思います。
(3)学校のHPを活用して、事前の指導について発信する。
→授業参観をする前に授業の取り組みを知ることができ、当日参観をする視点を持つことができると思います。
これらの方法で、授業研究会をさらに実りのあるものにしていきたいと思います。

菊池 健一(きくち けんいち)
さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当
所属校では新聞を活用した学習(NIE)を中心に研究を行う。放送大学大学院生文化科学研究科修士課程修了。日本新聞協会NIEアドバイザー、平成23年度文部科学大臣優秀教員、さいたま市優秀教員、第63回読売教育賞国語教育部門優秀賞。学びの場.com「震災を忘れない」等に寄稿。
同じテーマの執筆者
-
兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)
-
京都教育大学附属桃山小学校 教諭
-
大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長
-
戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表
-
小平市立小平第五中学校 主幹教諭
-
西宮市立総合教育センター 指導主事
-
明石市立高丘西小学校 教諭
-
木更津市立鎌足小学校
-
東京学芸大学附属大泉小学校 教諭
-
愛知県公立中学校勤務
-
大阪大谷大学 教育学部 教授
-
神奈川県公立小学校勤務
-
寝屋川市立小学校
-
明石市立鳥羽小学校 教諭
-
千代田区立九段中等教育学校
-
大阪府泉大津市立条南小学校
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
「教育エッセイ」の最新記事














 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない



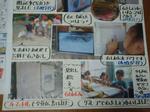
















 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望








