意外と知らない"21世紀型スキル"(vol.4)
"21世紀型スキル"とはどのような能力か? そして、どのように育成し、評価するものかについて、4回にわたり詳しく紹介するシリーズの最終回です。
協調的問題解決力とは
情報の分析を行ったり、解決策のアイデアを出したりする場合は、一人でやるよりも、違う視点を持った複数の人が集まってやる方が良い結果が得られることが多いと言えます。そこで「協調」能力が必要となります。
「協調的問題解決力」は次の五つの要素からなるとされています。
- グループ内の他の人の考え方を理解できる力
- メンバーの一人として、建設的な方法でメンバーの知識・経験・技能を豊かにすることに貢献するように参加できる力
- 貢献の必要性やどのように貢献すれば良いかを認識できる力
- 問題解決のための構造や解決の手続きを見出す力
- 協調的なグループのメンバーとして、新しい知識や理解を積み上げ、作り出す力
協調的問題解決力育成の様々な取り組み
問題解決力や思考能力、信頼関係作りの手法として使われるプロジェクトアドベンチャー(冒険体 験プログラム)を行う学校もあります。プロジェクトアドベンチャーでは、一人で考え、行動していては、いつまでたってもクリアできないゲームに取り組みま す。例えば、1本の長い丸太の上に全員がバラバラに上がって並んだ後、丸太から下りないで誕生日順に並び替えるという課題があります。しゃべれない人、目 隠しされている人などを設定することもあります。
調理実習を行っても、早く出来上がって食べられる班と、そうではない 班があります。うまく協力できたか振り返りをすると、次は改善することができます。また、状況に応じてその分野が得意な人を一時的にリーダーにしたり、 リーダーの人がフォロワーになったりする体験を積んでいくと、初対面の人とグループになっても、自然にうまく協力できるようになるそうです。
教室でできるゲームとして「月世界で遭難(NASAゲーム)」があります。生き残るために手元にある15種類のアイテムに優先順位をつけるコンセンサスゲームで、「砂漠で遭難」というバージョンもあります。正解と照らし合わせて、個人で出した結論と、その後グループで話し合って出した結論を採点して比較すると、8割以上がグループの得点の方が高いという結果になるので、「協調的」の効果を子どもたちも実感できます。
ジグソー(Jigsaw)法とは
ジグソー法は、あるテーマについて複数の視点で書かれた資料をグループに分かれて読み、自分な りに納得できた範囲で説明を作って交換し、交換した知識を統合してテーマ全体の理解を構築したり、テーマに関連する課題を解いたりする活動を通して学ぶ、 協調的な学習方法の一つで、協同学習を促すためにアロンソンによって編み出された方法です。教室の中で同じことを学んだとしても、「学びのゴール」は一つ ではない、教師が与えた答えだけが正解なのではなく、生徒同士が自分達で考え「納得のゆく答え」を出していくことが学びのゴールであると捉える学習観に基 づくもので、次のような手順で進めます。
- 答えを出したい問いを共有する
- 答えに必要な三つ(ほどの)の「部品(視点の違う資料や実験など)」を受け取る
- 小グループに分かれて、それぞれの「部品」の内容を理解する~〈エキスパート活動〉
- その上で、部品を担当したものが一人ずつ集まってその内容を統合する。統合して問いの答えを出す~〈ジグソー活動〉
- 答えが出たら、それを公表し合って、互いに検討し、一人ひとり自分にとって納得のゆく解を構成する~〈クロストーク活動〉
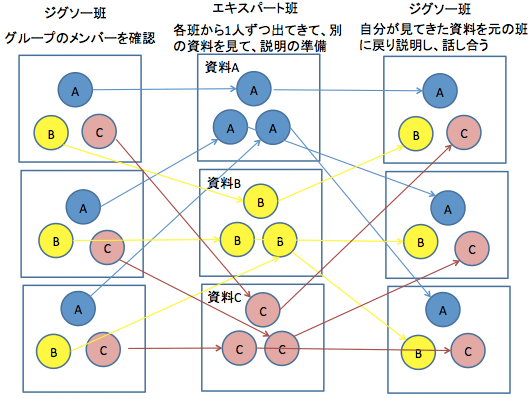
ICTを使った協調的問題解決
学習指導要領にはICTを利用した「協調的問題解決能力」の育成について明記されていませんが、PISA2015には、コンピュータを相手にチャットしながら問題を解決する問題が出題される予定です。
東北大学大学院情報科学研究科で、ある高校の2年生を対面で話し合う 群と、チャットで話し合う群に分けて議論をさせてアンケートをしたところ、チャット群から良い点として「対面より緊張しない」「会話ログを見直せる」、良 くない点として「発言のタイミングが難しい」「タイピングに時間がかかる」などの意見・感想があったそうです。ICTを活用した「協調的問題解決」を授業 に取り入れる試みは始まったばかりですが、企業現場では海外に生産を委託している場合など、チャットで遠隔地の人と協働的問題解決をすることは珍しくあり ません。
4回目のまとめ
参考資料
- 大学発教育支援コンソーシアム推進機構「ジグソー法の仕組み」
- 「教えて考えさせる授業」と「知識構成型ジグソー法」の実践
- 埼玉県ホームページ「子供たちの『わかった』を引き出す授業に-『協調学習』による授業改善-(教育ほっとニュース)」
- 三宅なほみ監訳『21世紀型スキル: 学びと評価の新たなかたち』P.9(北大路書房, 2014)
構成・文:内田洋行教育総合研究所 研究員 江本真理子
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事














 教育インタビュー
教育インタビュー 新刊紹介
新刊紹介 教材紹介
教材紹介



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望
