学校の風通しを良くする情報発信と"役割シェア"のススメー情報共有で教員をつなぎ、風通しの良い学校をつくるー(第1回)
多くの学校、特に規模の大きな組織では、学年や教科、あるいは分掌ごとで教育活動が個別化し、教員間の連携が希薄になりがちなことが共通の課題ではないでしょうか。私は、「同じ時間、同じ場所で、共通の教育目標の実現に向けて協働している」という意識を教員集団でいかに育むかに着目し、情報共有のあり方を意識し、実践してきました。
今回は、自分自身が実践してきた、学校全体の風通しを良くするための2つのアプローチと、その背景・理由も含めて説明します。一つは「意図的な情報共有」、もう一つは外部との関係性を活かした「役割のシェア」です。今回はそのうちの一つ目、「意図的な情報共有」に注目して話を進めていきます。
花園中学高等学校 社会科教諭 伏木 陽介
一体感を醸成するための「発信」の大切さ
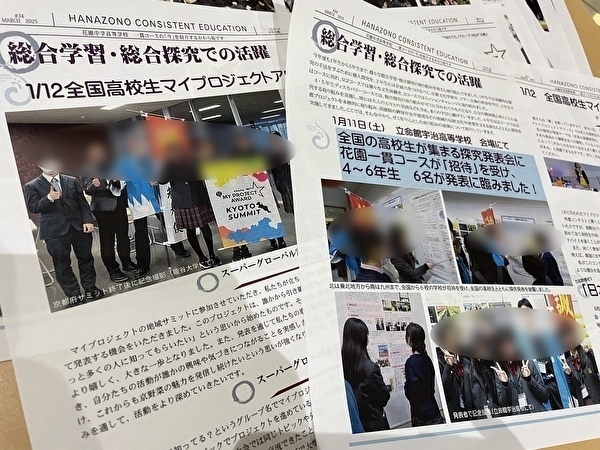
かわら版
私自身、生徒や保護者だけでなく、特に教員集団に向けて情報を発信することに力を入れてきました。「同じ時間、同じ目標に向かって教育活動を行っている仲間だ」という意識を、日常的に育むことを念頭に取り組みを進めています。
私は現任校で、中高一貫コース全体のコース通信として、毎月『一貫かわら版』という広報媒体を発行しています。A3サイズで毎月5枚。写真や生徒のルポ、感想なども入れ、デジタルとアナログの両方で発行。2022年ごろからの発行で、早いものでもう40号を超えています。
この広報誌で最も大切にしていることの一つに、「縦のつながり」があります。他の学年が今、何に取り組み、どんなことで盛り上がっているのかを互いに知る機会を作っています。「一体感」がそのキーワードです。
生徒や保護者にとっては、自分たちや近くの子どもたちの取り組みを知るだけではなく、「子どもたちはゆくゆくこんな活動をすることになるのか」「来年はこんな行事があり、成長があるのだな」と、学校生活の見通しを持つことにつながります。しかし、私がそれとともに大切にしている視点は、教員に向けたメッセージとしての「かわら版」の期待です。
紙面の主役は、教員ではなく生徒の声。普段関わることの少ない他学年の生徒の生き生きとした言葉や表情に触れることは、教員にとって新鮮な発見の連続です。「あの子、こんな一面があったのか」という気づきは、生徒理解を何倍にも深めてくれます。何より「この時期に他学年、他コースはこんな活動をしているのか」と教員も自分の視野からは見えにくい部分に視点を置くことができます。また教員それぞれの注力している分野以外の視座を提示することにもつながります。
また、「ライブ感」と「共時性(リアルタイム感)」を大切に、あえて毎月発行しています。そうすることで、個別化しがちな学年や教科の動きを緩やかにつなぎ、現在進行形で各コースや小さな取り組みの総和を互いが知ることができます。その積み重ねが、学校全体の一体感を醸成する媒体となることを目指しています。
ちなみに、生徒たちの声はGoogleフォームやGoogleドキュメントなどで提出してもらい、それをもとに作成しています。各学年の先生に写真提供を呼びかけることで、負担を分散することも可能です。
「探究ポータルサイト」の作成
もう一つの取り組みが、Googleサイトで作成している「総合探究ポータルサイト」です。ここには、生徒たちの探究活動の成果や日々の進捗が、写真や資料とともに蓄積されています。本校一貫コースではこのサイトを毎年作成しています。探究の伴走者や生徒にも適宜「共同編集者」になってもらい、それぞれの内容を持ち寄ることで、バラエティーある内容になるように工夫してきました。
そして、ポータルサイトのリンクを、私は全教員に共有するように段取りを組みました。いわば、探究活動の「ハブ(拠点)」です。
教員は、担当の生徒だけでなく、関心のあるテーマに取り組むほかの生徒の様子をいつでものぞきに行くことができます。サイトを眺めていると、「担当クラスの〇〇さんが、数学で学んだ知識を活かしてこんな分析をしていたのか」「物静かな〇〇さんが、こんなに熱い探究テーマを追いかけていたとは」といった発見が次々と生まれます。ポータルサイトを見た数学の教員から「〇〇さんの探究、この部分は数学の△△を使えばもっと深められるかも」と生徒に声を掛け、探究内容がさらに深まったこともあります。この経験は、生徒が教科学習の意義を自発的に見出すきっかけとなり、基礎知識の習得にもより意欲的になりました。
このように、ポータルサイトや「かわら版」のような存在は、授業の中で「そういえば、〇〇さんの探究、面白そうだね」と声を掛けるきっかけになったり、教科指導と探究活動を結びつけるヒントになったりします。先生方からのこの一言が生徒のモチベーションを高め、「多くの先生が見ているよ」というメッセージにつながります。このサイトは、生徒の学びを可視化するだけでなく、教員が生徒の新たな魅力に気づき、指導に活かすための貴重な情報源となります。さらに、直接探究を伴走していない先生にも「探究はこのように伴走するものなのか」「あの先生(の伴走)はこのような努力をしているのか」という理解が広がり、ほかの先生への理解もまた職員室に新しい風を吹き込むでしょう。
小さなアクションの積み重ねを大切に
今回紹介した実践は、特別な機材や予算がなくても始められることです。ここで大切にしているのは、同学年や同じ教科・分掌以外の広い教員間の関係性の構築に意識を向けること。そのために情報を発信・共有し、新しい関係性を構築できるようなプラットフォームを整えること。そして、このような小さなアクションを小刻みに重ねることです。
「自分はその立場にはいないから」という先生もいらっしゃるかもしれません。しかし、それは学級通信や学年通信、クラスでのポータルサイトの作成でもよいと思います。そして、できればデジタルを活用し閲覧の機会を増やす工夫をするとよいでしょう。あるいは、隣の学年やクラスの通信を読んでみる。自分のクラスの活動を一枚の紙にまとめて隣のクラスの先生に渡してみる。そんな小さな「発信」と「受信」から、学校の空気は少しずつ変わっていきます。
実際にこの40号の積み重ねの中で、私の周りでも、着実に発信の取り組みの大切さが認識され、実践する先生が増えています。そのような変化を感じるたびに、さらに新たな発信の意欲が湧いてくるのです。
このような発信による相互の交流が、結果的にはさまざまなきっかけを生み出し、より学校が風通しよく、創造的な場所へと前進すると思います。

伏木 陽介(ふせぎ ようすけ)
花園中学高等学校 社会科教諭/中高一貫(ディスカバリー)コース統括・ICT担当、東西探究交流会代表
長年にわたり、探究学習のプログラム策定や実践に携わってきました。
学校や授業の改革には何が必要かを考え、現場でのチーム作りや実践を重ねております。
また、大学などの「学術知」を中高の教科指導とどう結びつけるかを追求し、共通テストの分析やICTとの接続等の教材開発に取り組んでおります。
こうした経験を活かし、未来の学びの創造に貢献したいと考えています。
同じテーマの執筆者
-
京都教育大学付属桃山小学校
-
福岡工業大学附属城東高等学校 教務主任
-
北海道札幌養護学校 教諭
-
元徳島県立新野高等学校 教諭
-
栃木県河内郡上三川町立明治小学校 教諭
-
京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会
-
大阪市立堀江小学校 主幹教諭
(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -
大阪市立放出小学校 教諭
-
長野県公立小学校非常勤講師
-
浦安市立美浜北小学校 教諭
-
東京都東大和市立第八小学校
-
東京学芸大学附属大泉小学校 教諭
-
尼崎市立小園小学校 教諭
-
千代田区立九段中等教育学校
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事














 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない

















 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望









