意外と知らない"学習指導要領の改訂"(vol.2)

第2回は学習指導要領が、知識伝達重視から思考力・判断力・表現力育成重視へと変わっていった過程を振り返ります。まず、河野哲也『「こども哲学」で対話力と思考力を育てる』を参考に、思考力・判断力・表現力とはどのような力なのかを確認し、その後順に見ていきたいと思います。
【思考力】とは
思考力とは、「問題を発見する力」「予測・推測する力」「比較する力」「関連付ける力」「分析する力」「総合する力」など課題を解決するために必要な”考える力“です。
思考はそれまでとは異なった ものや新しいものに出会う驚きの経験から生まれ、異なったもの同士を関連づけ、意味づける活動です。すぐれた思考とは、批判的思考(それまで理由や根拠を 問うことのなかったものに、それらを求めていく姿勢。判断的。評価的)、創造的思考(新しいものを生み出す思考。実験的。前進的。構築的)、ケア的思考 (対象に配慮してそれを大事にする態度)の三つの側面を持った多元的な思考であると言われています。
各思考の要素(対話の評価項目例)
|
批判的思考
|
創造的思考
|
ケア的思考
|
|---|---|---|
|
|
|
【判断力】とは
【表現力】とは
表現力とは、考えたことを言葉や文章、図表やイラスト、絵、資料、身体、音楽、造形などによって、相手にわかるように説明することであり、対話や議論の基礎となるものです。
現代社会では、文化的な背景が異なる人々をまとめるために、理由に基づいた説明と説得・納得できる合理的な根拠が必要とされるようになってきており、対話や議論、コミュニケーション力が求められています。
なお対話とは、同じテーマに ついて異なった意見を関連付けていくこと、相手がどういう理由で自分と異なった意見を持つのか、その意見はどういう経験に裏打ちされているのか、自分の意 見と他人の意見がどういう点で同じで、どういう点で異なり、どういう関係にあるのか等を理解しようとすることです。相手と会話しながら思考を深めていく点 で、単なる会話や意見交換とは異なります。
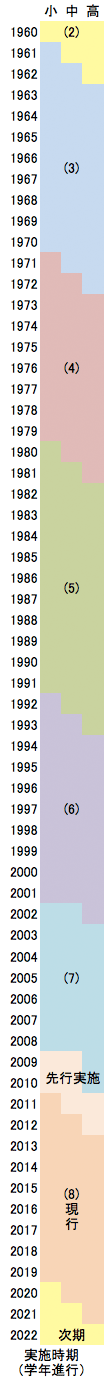
(5) 1977(昭和52~53)年の改訂:ゆとりある充実した学校生活の実現=学習負担の適正化
1973年には高等学校への進学率が90%を超え、このような状況にどう対応するか、また学校教育が知識の伝達に偏っている現状を改善し、自ら考え正しく判断できる力を持つ児童生徒の育成をどのように図っていくかということが課題となりました。
「知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童生徒の育成」「ゆとりある充実した学校生活の実現」「児童生徒の個性や能力に応じた教育の実施」の三つを柱とし、指導内容を精選・集約・中核化して授業時数を削減し、負担を減らすことで、地域や学校の実態に合わせて学校や教師が授業時数の運用に創意工夫を加えることができるようにしました。
(6) 1989(平成元)年の改訂:社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成
高度経済成長が終焉を迎える中で、情報化、国際化、価値観の多様化、核家族化、高齢化などの社会の変化、また、いじめや不登校、校内暴力の増加などの学校を取り巻く環境の変化に対応する観点から教育内容の見直しが行われ、21世紀を目指して一人ひとりの個性を活かし社会の変化に主体的に対応できるように、各教科において学ぶ意欲・学習の仕方と、思考力・判断力・表現力を育成することを重視した新しい学力観が打ち出されました。
これを受けて、体験的な学習や問題解決的な学習を重視して各教科の内容の改善が行われました。また、小学校1・2年生において社会・理科が廃止され、生活科が新設されると共に、国語の授業時数が増やされたり、隔週学校五日制が導入されたり、高等学校で世界史が必修となったりしました。
(7) 1998~1999(平成10~11)年の改訂:基礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」の育成
1996年の中央教育審議会の「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」の第1次答申では、「ゆとり」の中で「生きる力」を育むことを重視することが提言されました。「ゆとり」としては「完全学校週五日制の導入」を、また「生きる力」の重要な要素としては、「いかに社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力」、「自らを律しつつ、他人と共に協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性」、そして、「たくましく生きるための健康や体力」を挙げました。
これを受けて、各学校が地域や学校、児童の実態等に応じて、横断的・総合的な学習や児童の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を活かした教育活動を行う時間として、小学校3年生以上の各学年に「総合的な学習の時間」が新設され、合科的な指導を進めることができるようになりました。中学校では「選択」教科の時間を増やし生徒の個性を伸ばす仕組みが整えられました。
また、完全学校週五日制の導入で授業時数が削減されても「ゆとり」を持って学び、必要な教育内容を確実に身につけることができるように、教育内容の3分の1を「厳選」するとして全教科の内容の削減が図られましたが、学力が低下したとして後に論争が起こりました。
(7-2)2003(平成15)年一部改訂:学習指導要領のねらいの一層の実現
児童生徒の実態に合わせて学習指導要領に示していない内容も指導できることを明確化したり、個に応じた指導の例として小学校の習熟度別指導や小・中学校の補充・発展学習の例を追加したりしました。
また、総合的な学習の時間の目標について、創意工夫あふれる取組が増加したものの内容が明確でなく、検証・評価が不十分な実態等を受けて、各学年の目標・内容を含めて学校としての全体計画を作成する必要があること等が規定されました。
(8) 2008~2009(平成20~21)年の改訂:「生きる力」の育成、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力等の育成のバランス
教育課程実施状況調査、全国学力・学習状況調査、OECD生徒の学習到達度調査(PISA)、国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)の結果から、日本の児童生徒には次のような点に課題があることが指摘されました。
- 思考力・判断力・表現力を問う読解や記述式の問題、知識・技能を活用する問題
- 家庭での学習時間などの学習意欲、学習習慣・生活(読解力で成績分布の二極化が拡大)
- 自分への自信の欠如や自らの将来への不安、体力の低下
(小学校学習指導要領解説国語編 第1章総説「1 改訂の経緯」(PDF)より)
これを受けて、2006年に「教育再生」の第一歩として、教育の根本的な理念や原則を定める「教育基本法」が約60年ぶりに改正され、新しい時代の教育の目的(第1条)や目標(第2条)として次のような人間・国民・日本人の育成を目指すことが明文化されました。
- 知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって自己実現を目指す自立した人間
- 公共の精神を尊び、国家・社会の形成に主体的に参画する国民
- 我が国の伝統と文化を基盤として国際社会を生きる日本人
また、2007年に「学校教育法」が改正され、学力の三要素として「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「主体的に学習に取り組む態度(学習意欲)」が定められました(第30条2項・次期学習指導要領では、評価の観点を、現在の「知識・理解」「技能」「思考・判断・表現」「関心・意欲・態度」の4観点から、上記の3要素に沿ったものに改訂することも議論されています)。
これらを踏まえて、「ゆとり」か「詰め込み」かではなく、これからの社会において必要となる「生きる力」をより効果的に育成することを目指して、(1)小中学校における授業時数の10%程度増加、(2)記録、要約、説明、論述などの言語活動の充実、(3)中学校武道必修化などの伝統や文化に関する教育の充実、(4)1951年から言われ続けている道徳教育の更なる充実、(5)小学校5、6年生の外国語活動必修化などが図られました。
第3回・第4回は、学習指導要領改訂に向けて現在議論されているテーマについて、教科別に紹介したいと思います。(当記事は2016年3月末時点の情報をもとに構成しています)
参考資料
- 学習指導要領等とは何か?
- 新しい学習指導要領のねらい
- 初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について(平成15年答申)
- 学習指導要領のポイント
- 改正前後の教育基本法の比較(PDF)
- 新しい教育基本法と教育再生(簡略版)(パンフレット)(PDF)
- 学習指導要領データベース
- 光文書院 Vプレス Vol.12 (2012年発行)(PDF)
- int Web添削システムの紹介「6.思考・判断の評価について」
- 河野哲也『「こども哲学」で対話力と思考力を育てる』(河出書房,2014)P.8,28,41~44,81~91、205~206
構成・文:内田洋行教育総合研究所 研究員 江本真理子
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事














 教育インタビュー
教育インタビュー 新刊紹介
新刊紹介 教材紹介
教材紹介



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望
