第5回子ども環境学会「渡り鳥が飛来する地域の豊かな自然と田んぼ 人と自然の共生のかたち」/特定非営利活動法人GSP

地域社会は「生産の場」であり、生産を基盤に人と人とのつながりがある。このつながりそのものが、子どもたちにとっての豊かな学びの場なのではないだろうか──地域社会における自然と共生した暮らしにスポットを当て、特定非営利活動法人グローバル・スクール・プロジェクト(以下、GSP)が主催する「第5回 子ども環境学会」が実施された。
 菅原さんのお話に 聞き入る参加者 |
去る1月22日23日、特定非営利活動法人GSP(花井有美子理事長)主催で、宮城県北をフィールドに「第5回子ども環境学会」が実施された。1泊2日のエコツアーに、地元宮城県の小学校の児童をはじめ全国から、子どもと教育関係者、渡り鳥の専門家、地元の農家の方、大学生などの大人合わせて約40名が参加した。 「子ども環境学会」は、全国各地で環境学習に取り組む子どもと指導者の日常の成果を称えることを目的とし、各界の専門家および協賛者有志により毎年継続・運営されている。今回は、前回に引き続き宮城県北の伊豆沼周辺(栗原郡若柳町)での開催となった。伊豆沼は、ラムサール条約(正式名称・特に水鳥の生息地として重要な湿地に関する条約)に指定されており、その周辺は広大な田んぼが残っている日本でも数少ない湿地帯である。 ■多様な生物の生息地としての田んぼ 2日間のプログラムは、田んぼや渡り鳥、沼という宮城県の自然を通して、地域社会のつながりが体感できるように工夫されている。 まず、最初のフィールドとなったのは、冬の田んぼに水を張る「冬水田んぼ(冬期湛水・とうきたんすい)」という農法でお米をつくっている菅原秀敏さんの田んぼだ。もちろん、農薬や化学肥料は一切使っていない。さて、冬の田んぼに水を張るからには、それなりの理由があるはずである。 「冬の田んぼに水を張ると、イトミミズが増える。イトミミズは、トロトロした栄養のある土(トロトロ層)を作ってくれる。トロトロ層は、草の種を埋めてくれるので除草剤をまかなくても、雑草が生えるのを抑える働きがある。また、渡り鳥の寝床になったり、渡り鳥が落モミなどを食べにやってくるようになった。」と菅原さん。続いて、菅原さんの田んぼでイトミミズ調査を続けている高奥満さん(たかまん商事代表)より「イトミミズ」についての詳しいお話、同じく安蘇政樹さんより「田んぼで働く微生物」のお話があった。 この時の気温は、マイナス0.5℃。田んぼの水温はというと4.1℃と温かい。そして、田んぼの水の下の地温は5℃にもなる。当然、直接外気に触れている隣の田んぼの地温は、氷点下。田んぼに水があるおかげで、「イトミミズ」や「微生物」が活躍しやすい環境が作られ、冬の間に土を耕してくれているのだ。肌に突き刺さるような寒さの中、子どもたちは講師の方のお話に耳を傾けた。 お話の後、「生き物調査」としてトロトロ層に生息しているイトミミズの数を数えた。数値は夜のプログラムで明らかになるのだが、なんと5000㎡の田んぼ一枚に総数850万匹のイトミミズがいることが分かった。1㎡あたり1700匹生息している計算だ。実際に長靴を履いて田んぼに入った子どもたちは、イトミミズがつくり出したトロトロした土にズブズブッと足が沈む感覚を確かめていた。 ■水でつながる沼と田んぼのネットワーク 田んぼを後にして、次に向かったサンクチュアリセンターでは、伊豆沼・内沼の自然について館内を見学したり、スコープで沼の様子を観察した。日の入り近くになると伊豆沼のほとりに移動し、越冬中の数万羽のマガンがえさ場から一斉沼に帰る「ねぐら入り」を観察した。講師の呉地正行さん(日本雁を保護する会会長)から、「ガンがどんな降り方をするのかよく観察してみてください。そして、なぜそのような降り方をするのか考えてみてください。」と問いかけがあり、参加者はスコープをのぞきながら、四方から集まってくるマガンの姿を見つめた。その壮観な自然の営みには、いつも見慣れている地元の参加者からも歓声がもれた。 |
|
 トロトロ層に足をとられ、 転ばないように必死に歩く |
||
 日の入り近くになると、 数万羽のマガンが 寝床となる伊豆沼へ 帰ってくる |
|
夜は、宿泊場所のウエットランド交流館でお待ちかねの夕食だ。なんと言っても、やはり菅原さんの田んぼで収穫された農薬や化学肥料を一切使っていないお米の味が気になる。「水を張っていて、他の田んぼと違う菅原さんのお米を食べたかったので参加した」という地元の児童もいたほどだ。参加者からは「おいしい!」の声があがった。冬水田んぼでつくられたお米は、環境に配慮しているだけでなく、自然の恩恵をたっぷり受けた、わたしたちにもやさしいお米なのだ。 |
 夕食には、菅原さんの お米と、地域の伝統料理の はっとなどをいただいた |
 講師の呉地さんは、 プロジェクターを使って、 分かりやすくお話してくださった |
夕食後も、プログラムはまだまだ続く。成瀬 啓さん(宮城県教育研修センタ?)の指導のもと、昼間、菅原さんの田んぼで採取した稲株を顕微鏡で観察する。スクリーンに映し出されたプレパラート上には、珪藻やもっと小さな微生物が動いているのが確認された。 その後、講師の呉地さんから「水と鳥と田んぼ」のお話を伺った。「マガンは、広い沼と広い田んぼという湿地のネットワークがないと生きられない鳥である。90年前の宮城県北部には40の沼があったが、今残っている沼は伊豆沼を含め9つに減ってしまった。ガンの夜の休み場となる自然の湿地は各地で姿を消してしまったが、その一方でガンが利用できる水辺を提供する、冬水田んぼの農法に取り組んでいる農家の人たちが全国に増えてきた。今、その農家の人たちと一緒に、冬水田んぼのネットワークでガンの群れを全国へという取り組みをしている。皆さんは今、世界的にも貴重な沼で活動しているのだ。このような地域で生れ育ったということを大切にしてほしいと思う。」 ねぐら入りで観察した、マガンがヒラヒラと木の葉が落ちるような降り方のわけは、外敵から身を守るための知恵だそうだ。 2日目は、5時半に起床し、ねぐら入りしたマガンがエサを求めて周囲の田んぼに飛び立つ「早朝一斉飛翔」を観察した。 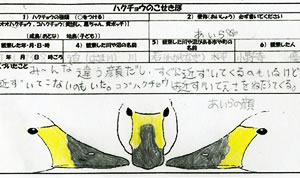 「ハクチョウの戸籍」には、一羽一羽の特徴が記録された
■地域社会の新しい価値への気付き 2日間のプログラムを通して、地元宮城県の児童は「去年勉強した、渡り鳥の渡りのルートを思い出した。今回参加して、マガンの降り方など初めて知ったこともあった。」と感想を話してくれた。また、東京から参加の児童は「沼やガンや田んぼがたくさんある風景がきれいだった。」「東京にもガンを増やしたいと思った。東京に帰ったら、洗い物をするときに、新聞紙で油を拭き取ってから流すなど、水をきれいにしたい。」と話してくれた。居住地は違うが、自然環境と共生した暮らしの価値を共有できたのではないだろうか。 また、参加した大人にとっては、水田でつながる地域社会の人と人の関係こそが、子どもたちの学びを育む豊かな未来の可能性を担っていることを再認識できたのではないだろうか。一連のプログラム後、大人の参加者には、若柳グリーンツーリズム研究会の千葉さんを囲んで、「グリーンツーリズム」を主題とした今後の地域外の参加者との関わりや、その意義について話し合う座談会が設けられた。 最後に、講師の呉地さんのご配慮により、CD制作中の「ふゆみずたんぼのうた」に、ここに参加した子どもと大人の元気な声が収録される予定である。
|
|
 スコープをのぞきながら、 マガンの一斉飛翔を 今か今かと待つ |
||
 思い思いのハクチョウの スケッチをする |
|
|
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事














 教育イベントリポート
教育イベントリポート 食育と授業
食育と授業 教育リサーチ
教育リサーチ



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望

