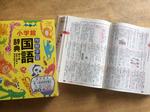

今日は、子どもの言語能力の育成をねらった実践の紹介です。
「辞書クイズ」と「言葉調べ」です。
小学校においては、3年生で国語辞典の使い方を学びます。
適切なフォローをしていかないと、多くの子どもがその後、ほとんど国語辞典を使わないようになってしまいます。
そこで、子どもが辞書や言葉に対して関心を持ち、言語能力の育成につながるような活動が大切になってきます。
一つ目は、私が「辞書クイズ」と呼んでいる活動です。
この「辞書クイズ」では、私が言葉の意味を読みます。
そして、子どもが色々と考えて、その言葉を当てるというものです。
写真にあるページでは、問題は次のようになります。
「水にすむ生物を集め、飼っておいて人々に見せる所」
この問題の答えは「水族館」です。
この活動をグループ対抗で行います。
取り組む上で、いくつかのルールを設定していきます。
「グループで相談している時に、他のグループに答えが聞こえてしまったら、1ポイント減点」
「教師に答えを伝える時に、他の人に聞こえてしまったら1ポイント減点」
こういったルールによって、上手な話し方の練習にもなります。
その他、細かいルールでは、「教師に答えを伝えに来る人は順番で変わる」などがあります。
回答できる回数は、問題のレベルによって変えていきます。
通常、一回目は導入で、盛り上げるためにもすべてのグループが正答できるような問題にします。
例えば、「公園などにある、子どもが高い所からすべりおりて遊ぶように作られたもの」などです。
これの答えはもちろん「滑り台」です。
こういったレベルのものは、回答できる回数を1回にします。
「時計の一種、ガラスの入れ物に砂を入れ、少しずつ小さい穴から落として時間を計る」
答えは「砂時計」です。
こうなってくると少しずつ難しくなります。
「色ガラスをはめ合わせて、美しい模様や絵を表した板ガラス。まどの飾りなどに使う」
答えは「ステンドグラス」です。
この位のレベルになると、間違えが頻発してくるので、様子を見ながらヒントを出します。
例えば、「頭文字は、『す』です」や「その言葉の文字数は4文字です」などです。
敢えて、ある子どもが活躍できるような出題をすることもあります。
サッカーを習っている子どもが少し友達とうまくいっていないという状況で、その子を活躍させるような問題を出すということです。
授業参観などで行うことも良いアイデアです。
親にも一緒に参加してもらうことで、親にとっても子どもにとっても意味のある活動になることがあります。
保護者の参加に関しては「授業参観における親の授業参加のすすめ」に載っているのでそちらをご覧ください。
もう一つは、「言葉調べ」です。
先に紹介した「辞書クイズ」は、遊びの要素も強く、定期的に行うようなタイプのものではありません。
私は、体育が雨で中止になってしまった際などにやったりします。
体育が出来なかった気持ちをうまく切り替えることにもつながるからです。
次に紹介する「言葉調べ」は、定期的に取り組んでいくタイプのものです。
私は金曜日に出し、週末に取り組む宿題という形でやっています。
内容は、国語の教科書などで今後取り組む教材文にある少し難しい言葉の意味を調べるというものです。
一週間に一回でも辞書を手にする機会を作ることで、子どもと辞書への距離感が縮まります。
辞書との距離感が物理的にも心理的にも近いことで、分からない言葉があった時の行動が違ってきます。
辞書を使い慣れていれば、すぐに「調べよう」という気持ちになり、実際に調べるはずです。
しかし、使い慣れていなければ、分からない言葉があった時に「まあ、いいや」という気持ちから、結局、調べずじまいになる可能性が高くなります。
そういったことの繰り返しが言葉の習得の積み重ねができないことにつながっていきます。
また、これまで書いてきたような紙の辞書を積極的に使う習慣が、中・高校生になってから電子的な辞書を上手に活用することにもつながります。
電子辞書やスマホなどに入っている辞書アプリなどは、便利な機能がたくさんあります。
小学生で紙の辞書を使い慣れた子どもは、中・高校生になってから電子辞書などを上手に活用し、力を伸ばしていくことが予想できます。
電子辞書は、読み上げ機能やリンクなどによって、一つの言葉から多くのことを学ぶことができます。
そして、その後のネットワークでの情報収集の基礎的な能力の育成へとつながっていきます。
情報収集などの学びの段階は、次のようにとらえることができます。
「紙の辞書」→「電子的な辞書」→「インターネットなどでの検索」
段階を踏んで、丁寧に取り組んでいくことで、それぞれの段階での学びの質が高まるのだと思います。
情報化された現在、高校生や大学生、そして、その後の生活において「情報を上手に収集すること」が、とても大事になります。
その第一段階として、小学生段階における「紙の辞書の活用」をきちんと取り組んでいくことが大事なのだと思います。

鈴木 邦明(すずき くにあき)
帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師
神奈川県、埼玉県において公立小学校の教員を22年間務め、2017年4月から小田原短大保育学科特任講師、2018年4月から現職。子どもの心と体の健康をテーマに研究を進めている。
同じテーマの執筆者
-
兵庫県公立小学校勤務
-
兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)
-
大阪府公立小学校教諭
-
特定非営利活動法人TISEC 理事
-
兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭
-
岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任
-
福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝
-
大阪市立堀江小学校 主幹教諭
(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -
戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表
-
佛教大学大学院博士後期課程1年
-
明石市立高丘西小学校 教諭
-
木更津市立鎌足小学校
-
北海道公立小学校 教諭
-
東京都東大和市立第八小学校
-
東京学芸大学附属大泉小学校 教諭
-
東京都品川区立学校
-
岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭
-
神奈川県公立小学校勤務
-
寝屋川市立小学校
-
仙台市公立小学校 教諭
-
東京都内公立中学校 教諭
-
目黒区立不動小学校 主幹教諭
-
東京都公立小学校 主任教諭
-
尼崎市立小園小学校 教諭
-
埼玉県公立小学校
-
大阪府泉大津市立条南小学校
-
岡山県和気町立佐伯小学校 教諭
-
合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
「教育エッセイ」の最新記事














 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない































 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望








