
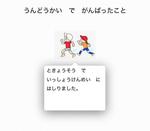
運動会での取り組み
写真は、ある日の運動会練習前のグランドから撮った一枚です。暑い一日でしたが、爽やかな風が吹いて、ちょっと不思議な虹が出ていました。そんな空の下で、子どもたちは元気いっぱい運動会練習をしていました。
この原稿を入力している2日後は、本校の運動会当日です。この原稿がアップされる頃には運動会が終わっています。今年度の運動会という小学校にとっては一大行事でiPadやiPhone等の端末がどのように活用されたのかを少し整理しておこうと思います。今回は大きく2つに分けています。
子どもたちの指導・支援
まずは、事前学習。本校では、運動会の練習が始まる前にほぼ全ての学年で事前学習が計画されています。いつ運動会があるのか、どんな種目に取り組むのか、誰と一緒に取り組むのか、練習は何回あるのか等、具体的に運動会までの学習の流れを確認する学習です。これは、視覚的な提示と具体物を用いての説明を組み合わせて行います。今年度の様子を見ていると、どの学年も視覚的な提示に端末が活用されているようでした。これはいつも活用しているKeynoteが主に使われていました。提示される内容もかなり厳選されて、子どもたちの理解を促すよう工夫されていました。また、一つの集団の人数が多くなっているところでは、子どもたちがより見やすいように映し出すテレビを二台にしたりと環境の工夫がなされていました。
次は、スケジュールの提示です。個別の練習スケジュールの提示にはアプリが活用されていたりしました。また、前回の練習の写真や動画をスケジュール提示に用いて、より具体的に練習をイメージできるよう工夫されている場面を見ることもありました。
また、練習の様子の動画は、学級に戻ってから子どもたち自身が端末を操作して見合ったり、帰りの会での一日の振り返りで用いられたりもしていました。
私の担当している子どもたちのグループでは、運動会後に「日記を書く」学習が計画されています。そこで、今回は、運動会の取り組みの様子を写真や動画を自分で見ながら文章を起こし、日記にしていこうと考えています。いま運動会の取り組みを一冊の本のようにまとめ、それを一人ひとりが見られるように準備しています。2枚目の写真はそのイメージの一部です。自分たちの活動の写真を端末でタッチすると、POPで文章が出てくるように作っています。写真や動画で活動自体のイメージが浮かんでくるのですが、それを実際の文章に起こす部分に苦手さのある子どもたちが、この作業を通じて、少しでも文章を起こしやすくできるようにサポートしたいと考えています。これはまだ取り組んでいない学習なので、その結果をお伝えすることができませんが、きっと成果が出るのはと期待しているところです。
教師の仕事
まず、一番使われていたのは写真撮影。練習の中で子どもたちが輝いている一瞬を逃さないよう先生たちは、すかさずシャッターをきっていました。特によく使っていた機能は、「連写」でした。あとは、外での活動が主ですので、逆光補正のできるアプリがよく使われていたようです。もちろん、通常のコンデジも数多く使われていますが、起動のスピードなどを考えて多くの先生たちは活動場面によって使い分けをしているようです。
私個人が使用していたのは、データを整理して持ち歩くことです。
行事は、とかくいろいろな部署からいろいろな書類が多く提案されます。その一つひとつをチェックしながら、自分に関わることから全体に関わることまでを把握していきます。経験年数的にも全体に関わる仕事が多くなっているので、全体の仕事を確認しながら自分の担当部署を動かしていく仕事が求められます。外での活動に数多くの書類をすべて持ち歩きながら子どもたちの指導に携わることは難しいですので、必要な書類はスキャンしたり、写真に撮ったりしたものを整理してデータで持ち歩くことにしました。
今回使用していたのは、「EVERNOTE」です。もう有名なものですので、皆さんご存知かと思います。
必要なデータを整理して、タグ付けしてすぐに活用できるようにしています。
もうひとつは、いつも使っているKEYNOTE。
総練習や運動会当日は、ボランティア等でお手伝いに来てくださる学生さんたちに用具配置等を説明する仕事があります。これは種目ごとに画像で整理して、必要なコメントを付けたものをKEYNOTEにまとめています。このKEYNOTEを使って、学生さんたちに説明をしています。ただ、屋外では、端末画面が見難いことがありますので、紙媒体も同時に用意して用いるようにしています。これは、できるだけ短時間で仕事内容を理解していただくことに役立っているように自分では感じていますので、次年度以降の引き継ぎ項目に加えていこうと考えています。
あと、本校では今年度活用できていませんが、他校では、運動会のBGMや競技種目ごとの音響にiPadを活用しているところが増えてきているようです。活用事例を見ているとかなり有効に思いますので、次年度以降、提案段階で検討できるよう準備できればと思います。

郡司 竜平(ぐんじ りゅうへい)
北海道札幌養護学校 教諭
小学校支援級、通常級と担当させていただき、現在は札幌養護学校小学部にいます。ここでは、私が取り組んでいる特別支援教育におけるICTの活用について具体例を交えながらご紹介していけたらと考えています。
同じテーマの執筆者
-
京都教育大学付属桃山小学校
-
福岡工業大学附属城東高等学校 教務主任
-
東京都立白鷺特別支援学校 中学部 教諭・自閉症スペクトラム支援士・早稲田大学大学院 教育学研究科 修士課程2年
-
東京都立南花畑特別支援学校 主任教諭・臨床発達心理士・自閉症スペクトラム支援士(standard)
-
富山県立富山視覚総合支援学校 教諭
-
東京学芸大学教職大学院 准教授
-
東京都立城北特別支援学校 教諭・臨床発達心理士
-
福島県立あぶくま養護学校 教諭
-
元徳島県立新野高等学校 教諭
-
東京都立港特別支援学校 教諭
-
栃木県河内郡上三川町立明治小学校 教諭
-
京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会
-
大阪市立堀江小学校 主幹教諭
(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -
大阪市立放出小学校 教諭
-
福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士
-
長野県公立小学校非常勤講師
-
浦安市立美浜北小学校 教諭
-
信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭
-
在沖米軍基地内 公立アメリカンスクール 日本語日本文化教師
-
東京都東大和市立第八小学校
-
静岡市立中島小学校教諭・公認心理師
-
寝屋川市立小学校
-
目黒区立不動小学校 主幹教諭
-
尼崎市立小園小学校 教諭
-
千代田区立九段中等教育学校
-
花園中学高等学校 社会科教諭
-
合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
「教育エッセイ」の最新記事














 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない






























 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望








