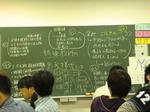
なんか怖いタイトルですみません(笑)。でもそんなに固い話ではないので、お付き合いください。
私は、この1年間教職大学院にて学んでいます。今回は、どのような授業が行われているのかをご紹介したいと思います。
まず、この教職大学院、学生構成が非常にユニークです。
大学4年間を卒業して、そのまま大学院に進んできた学生がいます。この学生たちを「ストレートマスター」といいます。なんだかかっこいい響きですが、長くて面倒なのか、「ストマス」と略されています。
そして、私たちのような学校現場から学びに来た、いわゆる「現職」の学生。
この「ストマス」と「現職」が、ともに同じ授業に参加し、学び合っているのが、この教職大学院の特徴なのです。
ここでは、グループワークとよばれる授業形態があります。
わかりやすくいえば、「班活動」です。学校でも「班ごとに、テーマについて考えましょう。」ということをよくやっていますよね。
このグループワーク、ストマスと現職の学生が入り交じって行うことにより、とても議論に深みが出ます。ストマスは現職の経験知ある発言に耳を傾け、現職はストマスの新鮮な発言に思わずうなってしまう、という相互のやりとりが生まれます。
さて、では授業でおこなったグループワークの一例をご紹介します。
先日の授業では、「授業改善を阻害する要因は何か?」というテーマでグループワークをしました。この日は、ストマスと現職合わせて6名の班で、議論をしました。
ストマスからは「現場が多忙すぎるから、先生方が授業改善をする余裕がないのではないか?」という意見が出されました。
「うんうん、もっともだ。」とも思いつつ・・・現職組は、はたしてそれが本当の「授業改善を阻害する要因なのか?」と、現場の経験を元にして考えてしまいます。
「確かに多忙だけど・・・じゃあ、もし先生たちが暇になったら、授業改善できるのか?」と。
全国の現職の先生方、いかがでしょうか?
ちなみに写真は、また別な授業。「熟練教師の思考様式とはどのようなものか?」というテーマで、グループワークしたときのものです。

増田 謙太郎(ますだ けんたろう)
東京学芸大学教職大学院 准教授
インクルーシブ教育、特別支援教育のことや、学校の文化のこと、教師として大事にしたいことなどを、つれづれお話しできたらと思います。
同じテーマの執筆者
-
東京都立白鷺特別支援学校 中学部 教諭・自閉症スペクトラム支援士・早稲田大学大学院 教育学研究科 修士課程2年
-
東京都立南花畑特別支援学校 主任教諭・臨床発達心理士・自閉症スペクトラム支援士(standard)
-
富山県立富山視覚総合支援学校 教諭
-
北海道札幌養護学校 教諭
-
東京都立城北特別支援学校 教諭・臨床発達心理士
-
福島県立あぶくま養護学校 教諭
-
東京都立港特別支援学校 教諭
-
京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会
-
福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士
-
信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭
-
在沖米軍基地内 公立アメリカンスクール 日本語日本文化教師
-
静岡市立中島小学校教諭・公認心理師
-
寝屋川市立小学校
-
目黒区立不動小学校 主幹教諭
-
合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
「教育エッセイ」の最新記事














 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 映画と教育
映画と教育 震災を忘れない
震災を忘れない


















 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望









