情報教育を、教科学習にいかに取り込むか 柏市立逆井中学校

「2005年までに全国の学校のすべての教室にコンピュータを整備し、インターネットにアクセスできる環境を実現する」という目標のもとに、全国で進められている「教育の情報化」。総合的な学習の時間では、インターネットによる情報収集、コンピュータを使ったプレゼンテーションなど、子ども達がコンピュータを日常的に使う姿もめずらしくなくなりつつある。しかし、通常の教科学習での利用となるとどうだろうか。 柏市立逆井中学校の取り組みにそのヒントを見た。(11/22)
 小菅由之先生    地域学習のための素材、指導計画、生徒の発表などを公開しているwebサイト 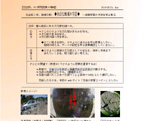 この授業の学習コンセプト 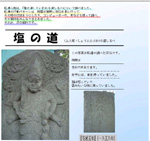 生徒たちの作品1 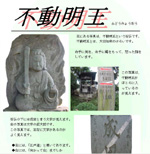 生徒たちの作品2  生徒たちの作品3 生徒たちの作品3  |
教科学習で情報機器を利用する場合、コンピュータ教室への移動、事前のマシン整備、トラブルによる授業の中断など、貴重な授業時間を侵食する要素も多く、「日常的にさりげなく」利用するにはハードルが高いと考える先生も多いのではないだろうか。
(取材・構成:学びの場.com)
調査した内容は、パソコンで原稿を書き、写真を貼り付けて編集する。写真などの画像データは、あらかじめ先生が撮ったものをインターネット上の素材集に保存しておく。そこまでするのは、「デジカメを生徒ひとりひとりに持たせられないし、画像処理といった作業は社会科の教科学習には直接関係がないから」だという。 「たとえば、“地図を作る”、“地域のことを調べてパンフレットを作る”という作業単元があります。教科書ではいまだに手描きの作例が掲載されていますが、これからはパソコンで作る時代ですし、今の子どもならできちゃうでしょう。そういう意味で、パソコンの指導も社会科の授業の一環だと思います。 |
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事














 教育イベントリポート
教育イベントリポート 食育と授業
食育と授業 教育リサーチ
教育リサーチ



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望

