|
平成22年度スーパーサイエンスハイスクール新規指定校となった横浜サイエンスフロンティア高等学校。同校独自の理数教育プログラムに「サイエンスリテラシー」がある。先端科学技術各分野の研究機関や大学、企業の研究者らに講義や実験指導を担当してもらう授業だ。今回はその一つ、日産自動車(株)による「燃料電池自動車」授業をリポート、併せて同校の理数教育への取り組みについて担当教諭に話を伺った。
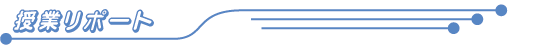
燃料電池自動車に“ほんもの体験”。
生徒の「なぜ」を育てる課題探究型学習
学年: 1年次生・生徒40名
教科・領域: 総合的な学習の時間(サイエンスリテラシーⅠ)
講座名: 燃料電池自動車
講師: 日産自動車株式会社
時間: 95分間
授業のねらい: 燃料電池自動車の仕組みについて講義、および模型製作を通してより深く理解すること
使用教材・教具: X-trail FCV 05モデル、燃料電池自動車実験キット
最前線技術のナマの情報に触れる
 日産自動車株式会社 総合研究所 EVシステム研究所 山梨 文徳 氏 「サイエンスリテラシー」は、1・2年次の「総合的な学習の時間」を使って行う課題探究型の授業。先端科学技術4分野(生命科学、ナノテク・材料、環境、情報通信)の実験実習等、“ほんもの体験”を通して生まれる「なぜ」「もっと知りたい」といった知的好奇心を育てるプログラムだという。
さて、本日は日産自動車株式会社の技術研究者たちによる「燃料電池自動車(FCV)」の講座が行われる。前半は、音響システムや大型スクリーン等が整備された350名以上収容可能なホールでの講義からスタート。日産の山梨文徳氏が映像を使って「FCVを取り巻く世界状況」や「FCVの原理」等の基礎知識から、現在の開発状況までを順を追って解説する。生徒たちは、これからの社会でのFCVの必要性、FCVの最新情報等がよく理解できたようだ。
「やはり第一線の研究者が教えてくれると違う。つい引き込まれる」
という生徒の声があった。自動車やエンジン、機械工学の分野に興味がある生徒にとって、たまらない講義と言えるだろう。
現場の技術研究者に直接質問する
講義後の質問タイムでは予定時間を延長するほど、多くの手が挙がった。
「将来は光触媒の技術を使って水素を作り出すことも考えていますか?」
「新しい燃料物質として、現在注目している物質はありますか? たとえばメタンハイドレートはどうでしょうか?」
「高分子膜以外に、コスト削減のポイントはありますか?」
「FCVが今後モータースポーツで活躍する可能性はありますか?」
「バイクや小型車への利用は?」
これらの問いに、山梨氏は
「新しい燃料開発にはバイオメタノール等も考えています。ただ水素はコストがかかる一方、いろいろな方法で作れるところにメリットがあって……」
等々と、次々に答えていく。やはり現場に携わる者の答えはリアル感がある。生徒たちも日常生活をイメージしながら聞けるので、より深く理解、納得できたはずだ。
講義の最後に山梨氏は、
「燃料電池自動車に興味を持った人は、ぜひ私たちの研究開発を継続してください」
というメッセージで締めた。
燃料電池自動車の実験模型を作る
 日産自動車株式会社 技術開発部 環境・安全技術渉外部 畑山 啓 氏 後半は場所を移して実験・実習に入る。2人一組になって「水分解式燃料電池キットカー」を作るのだ。
「実験用キットの箱を空けて中身を確認してください」
と、日産の畑山啓氏が声をかける。
「仕組みがわかった人はどんどん組み立て始めていいですよ」
との声に、すぐ何組かの手が動き出した。
 二人1組となって燃料電池自動車模型を組み立てる。「やはり手を動かす授業は楽しい」と生徒たち 構造自体はそれほど難しくない。車体上にある2本の小さなビーカーに精製水を注ぎ、燃料電池とつなぐ。そして水を電気分解し、発生した水素と酸素が装置内で反応、そこで生じた電力でモーターが回り、車を動かす仕組みだ。先生方と日産の研究者らが生徒に声をかけ、こまめに指導をして回るので、悩んでいた子も徐々に完成していく。
▲TOPへ
模型を実際に動かし、課題点を探る
 ソーラー電池で模型を動かす実験。天気はよいが、なかなか動き出さない キットカーが出来上がった組から中庭へ出てソーラー電池で実際に動かしてみる。日差しは強いが、なかなか動き出さない。しばらくすると、一組の車がトロトロと動き出す。ソーラー電池は発電に時間がかかることが実感できる。そのうちどの組も無事に動き出す。このキットカーは付属の乾電池を使っても動かすことができるので、そちらで実験する組もいる。
部屋に戻り、最後はまとめの時間。畑山氏が生徒たちに感想を聞くと、ソーラー電池で実験した組は、
「時間がかかり、しかも力も弱い」
といった答え。乾電池の組からは
「便利だけど、乾電池で発電させることに意味がないのでは?」
という疑問も上がる。それに対し、畑山氏が笑いながら答える。
「その通り。そういうことにも気づいてほしかったのです。ソーラー電池にはまだまだ課題がある。一方、乾電池はすぐに使え安定している。現実の技術開発でも既存のものの有用性を認識しつつ、同時に新たなエネルギーの開発を進め、両者をうまく組み合わせて利用することを考える必要があるのです」
という言葉に生徒全員が納得し、95分間の講座は終わった。
▲TOPへ
ほんものに試乗、驚きと感動を体験
 ほんものの燃料電池自動車に試乗する生徒たち。思わず興奮、知的好奇心が芽生える 今回は2台の燃料電池自動車が持ち込まれ、昼休みに各生徒が3分間程度の試乗を実施した。まず、実物を目の前にしながら、構造についての説明。ボンネットを開けて中を見たり、車下から発電によって排出される湿った空気を覗き込んだりして、さまざまな特徴を確認した。
いよいよ試乗。日産の担当者が運転する自動車に3人ずつ乗り込み、学校の周りを回ってくる。試乗を終えて降りてきた生徒のテンションが高い!
「スタート時の加速度がすごい」
「なんだか、“ぬるぬる”走っている感じ(笑)」
「加速する時、ジェットコースターっぽい」
等々、今どきの高校生らしい感想。記者自身も乗ってみると、確かに静かさと振動の少なさ、そして速やかな加速に驚く。
わずか数分の試乗とはいえ、ほんものの燃料電池自動車に触れることができた生徒たち。その興奮する姿から「なぜ」「もっと知りたい」といった驚きと感動、そして知的好奇心が次々に生まれていく様子を窺い知ることができた。
▲TOPへ
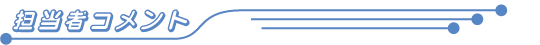
ほんものの科学の力を身につける教育を目指して
SSH指定により「サイエンスの学校にいる」という自覚が生まれる
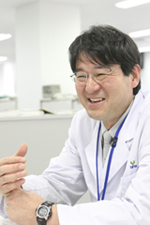 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 SSH事業推進主任者・理科主任・生物担当 溝上 豊 教諭 学びの場.com(以下、学びの場) 今年度、横浜サイエンスフロンティア高校(略称「YSFH」)は、文部科学省が指定するスーパーサイエンスハイスクール(略称「SSH」)になりました。それは狙っていたものですか?
溝上豊 教諭(以下、溝上) 学校創立当初からSSHを受けていく方針ではありました。昨年は開校したばかりで、1年生しかいませんでしたから申請できなかったのですが。
ただ、SSH事業の取り組み内容は、SSHを受けるために特別に作ったものではなく、もともと本校が理数教育で行うものです。先端科学4分野(生命科学、ナノテク・材料、環境、情報通信)を重視し、“ほんもの”に触れる体験をさせつつ高い学力を育成し、「科学技術立国・日本を支える世界レベルの人材を育成する学校」というコンセプトが、SSHの目的と合致したということでしょう。SSHを受けても受けなくても、やっていく内容なのです。
学びの場 とはいえ、SSH指定によるメリットもありますよね?
溝上 もちろん予算面が大きいです。本校の場合、初年度1,800万円支援されるので、実験費用、外部からの講師費用、生徒の海外研修費用……等々、計画に則って活用します。
また、SSH指定校として社会的に注目されることから、生徒にも教員にも「サイエンスの学校にいる」という自覚が生まれます。そして、他のSSH指定校との合同発表会が毎年あり、彼らとの交流や切磋琢磨により生徒のモチベーションも高まります。科学の進歩のためにはやはり競争は必要ですから。
▲TOPへ
徐々に効果が表れている、独自の理数教育プログラム
学びの場 本日の「燃料電池自動車」授業は、YSFH独自の理数教育プログラム「サイエンスリテラシー」の一つですね。
溝上 本校の教育方針は、先端科学技術の“ほんもの体験”や国際交流などを通じて「驚きと感動」を与え、知的好奇心を原動力に「知の探究」を深めていくというものです。
中でもサイエンスリテラシーでは、先端科学4分野の「ほんもの体験」をさせ、生徒の興味関心を高めることが目的です。生徒たちは知識として知っていても、実物を見たり触れたりする機会はなかなかありません。体験した中から各自が興味ある題材を掘り下げて学習し、校内外の発表会や科学オリンピックなどで成果発表してもらいたいと思っています。同時に、やりたいことを見つけ、明確な目的を持って大学へ進んでほしいという狙いもあります。
学びの場 サイエンスリテラシーの工夫点や課題点等は?
溝上 今回のように企業と連携をする際にはスケジューリングに気を使います。内容に関しては、授業の目標は絞ってありますし、企業側も一つのプロジェクトとして来てくれるので道具、人、進め方等についてお任せできます。本日の授業も、実験用キットの用意や、天候を考えてのソーラー電池と乾電池の両方の準備等、日産さんが考えてくれました。
また、費用面でも助かっています。サイエンスリテラシーの授業は、生徒一人につき年間5,000円の徴収と学校の予算で運営しますが、企業の方の場合には勤務時間内に来て下さるということで、謝金を辞退されることが多いです。おかげで低予算で質の高い授業が実現できています。
開校して2年目、まだ手探りの状態でやっていますが、3年くらい動かせば生徒の反応や効果もつかめますので、プログラム内容の改善等、具体的な検討に入れると思います。
学びの場 サイエンスリテラシー以外にも“ほんもの体験”できる仕掛けがありますね。
溝上 本校の常任スーパーアドバイザーの和田昭允・東京大学名誉教授に週1回来校していただき、生徒たちとお茶を飲みながら直接お話をしてもらう「和田サロン」や、ニュートン邸にあったリンゴの樹、メンデルが研究に使ったブドウの樹に由来する記念樹を学校の敷地内に植え育てる等、生徒の知的好奇心を刺激する工夫をいろいろ行っています。
ほんもの体験の効果は、私が担当する生命科学の授業でいえば、実験への意欲や理解度の高さとなって表れています。また、教えてくれた大学の先生の研究室に行きたい、あるいはその研究に近い分野に進みたいと考えるようになった子も見られます。それに、やはり和田先生レベルの方と定期的に触れ合えるのは、生徒にとって学問の核になるはずです。
▲TOPへ
卒業後の進路を支える取り組み、大学進学制度
学びの場 学校外の人々との交流が将来の進路志望にも影響を与えているわけですね。では、大学受験へ向けた対応はどうされていますか?
溝上 3年次には生徒個々の進路に合わせていくつかのコースから選択できるようになっています。本校は理数系の高校ですが、文系コースもあります。一学年240名全員が理系進学を希望するとは考えにくいですから。英語等、普通の高校より時間を多く取り、「理科の実験に時間をとられ受験に不利」ということはありません。さらに土曜日講習を行い、ついていけない子が出ないよう基礎的な部分をカバーしています。
学びの場 その他、卒業後の進路を支える取り組みはありますか?
 自然科学部の顧問でもある。「生物オリンピックの出場を目指し、高校教科書から少し外れた内容もやっています」 溝上 「横浜市立大学チャレンジプログラム」という、3年次に履修できるサイエンスリテラシーIIIの実験成果を市大の先生方に評価してもらい、総合的な判定により、国際総合科学部へ10名程度の進学を可能とする特別入学枠制度を設けました。これにより、受験で中断されることなく理科に集中して進学できる環境が可能になるでしょう。
世界を見ると、アメリカの高校ではどんどん大学レベルのことをやらせて、生徒のモチベーションを上げている。韓国も英才教育振興法により、生徒の大学進学を保証し、数学・科学分野の英才教育に専念できる体制を整えている。本校を作った目的も、世界レベルの理系人材を育成することですから、日本にもこのようなシステムが充実するといいですね。
▲TOPへ
将来、厳しい科学の道を究められる人材になってほしい
学びの場 YSFHの生徒さんはどんなタイプの子が多いですか?
溝上 成績で言えば、各中学校のトップ層もいますが、その次くらいの子も集まっている感じでしょう。性格的には、これは私の主観ですが、文武両刀のリーダータイプではなくて、やや大人しく理科好きな子という印象です。
中には、県西部から相当時間をかけて通学する生徒がいて、自然科学部に入部したいというので「帰宅時間は大丈夫か?」と聞いたら、本人は「この部活をやらなければ、ここに入学した意味がないです」と。また、私が指導の際「教わることばかりやっていくのではなく、教わらないことがいいこともある」という話をしたら、その生徒が「うちの父も『数学は公式で解くな、教わるな』と言っています」と言うのです。
そういう科学教育への意識の高い保護者を持つ生徒も多いほうだと思います。論理的な考え方ができる、自然科学の知識を持っている子は、やはり家庭環境の影響もあるようです。
学びの場 そのような生徒さんたちに、どのような将来を期待されますか?
溝上 本日の「燃料電池自動車」授業のような最前線の分野は臨場感があり、生徒を引き付けます。半面、今最前線のものは、あと5年、10年もすれば最前線ではなくなってしまいます。今後どんな科学分野が時代の中心になるかは誰にもわかりません。「今いいから」と飛びつくのではなく、人生は長いのだから自分が一番納得できて、満足できるものをやるしかないと、私の経験も踏まえて生徒には話しています。これから彼らは、このような厳しく、難しい選択をしていかなくてはなりませんから。
▲TOPへ
どの分野を選ぶにせよ、学問を最後まで追求・探究できる環境に行くのが幸せかなとも思います。海外で学ぶという選択肢もありますが、「博士研究員」という形で行くのが一番現実的でしょう。ただこれも、同じテーマについて常に成果を出していかなければならない、非常に厳しい道ですが。 そもそも研究の世界は競争ですから。競争に勝つと言っても受験とは違う、スピードや洞察力といった力が当然要求されてきます。そんな時問われるのが、実は気力と体力。徹夜でも平気で実験できる人には集中力があります。厳しい科学の道を究められるような気力・体力を持ち、将来世界で活躍できる人材を、本校の生徒たちには目指してほしいと思います。
記者は文系人間のため、前半講義における生徒と講師による質疑応答の内容には正直言って、ついていけなかった。まだ中学出たての高校1年生なのだが、なるほど、もともと理科好きな子であることは確かなようだ。ただ、この授業のどこがスーパーかと言えば、彼ら生徒たちのレベルの高さではなく、実用段階の先端技術と、それに携わる現場の技術者たちに直接触れる機会を提供したこと。そして今回の体験を通して生じた生徒たちの内面の変化(学習意欲だったり、目的意識だったり)を目の当たりにした点だ。この子たちの成長に期待したい。
取材・文:学びの場.com/写真:言美歩 ※写真の無断使用を禁じます。 | 















 教育イベントリポート
教育イベントリポート 食育と授業
食育と授業 教育リサーチ
教育リサーチ














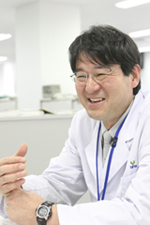






 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望

