シミュレーションゲーム教材は学校教育を変えるか?

数年来、学校教育でシミュレーションゲームを教材として活用する事例がふえつつある。ゲーム=娯楽というイメージが強く、学校現場ではまだまだ評価が低いシミュレーションゲームだが、その内容は刻々進化している。今回は、日本シミュレーション&ゲーミング学会を取材し、学校での実践報告を聞いた。
11月29日、「シミュレーション&ゲーミングにおける連携と拡大」をテーマに、お茶の水女子大学にて、日本シミュレーション&ゲーミング学会(JASAG)秋季全国大会が開催されました。
日本シミュレーション&ゲーミング学会は、1989年1月21日に、1980年代後半からのコンピュータ・テクノロジーの地球規模での革新の波を背景に設立。現在、「ビジネスシミュレーション研究部会(主査:黒沢敏朗)」「仮想経済ゲーミング研究部会(主査:出口弘)」など12の研究部会がありますが、今回は、「授業と教材研究部会(主査:三橋秋彦)」について取材してきました。
授業と教材研究部会の主査を務める三橋秋彦先生に、活動の背景をお聞きしました。
「シミュレーションゲーム教材は、開発に人的にも経済的にも大変コストがかかるものです。しかも実践には教師に高い技量を要求するものでもあります。ですが、ゲーム=娯楽という印象も根強く、授業で使用することに抵抗を示す方もいて、学校教育の場で正当な評価を受けていないのです。また、間違ったシミュレーションゲーム教材の理解や不適切な利用が平気で行われているという実態もあります。」
シミュレーションやゲーミングの手法を使った授業実践は、これまでにも学びの場見聞録で紹介してきました(川口市立芝西小学校 、田園調布雙葉中学高等学校、東京都中野区立第八中学校 )。が、どの授業でも思ったのは、事前の期待と実際の印象のギャップがかなり大きいということ。これは期待はずれというのではなく、まったく逆で、これらのゲームの面白さは、事前の説明や資料ではほとんど伝わらない。やはり実際にやってこそのゲーミング&シミュレーションなのです。この面白さを伝え、全国の学校で授業に取り入れてもらうには、今回のような学会で、地道に実践事例を発表していただくのが遠くて近道なのかも知れません。
さて、実際の発表の中で、印象に残ったものをいくつか紹介しましょう。
●埼玉県所沢市立荒幡小学校 ~情報モラルを学ぶ
発表者:寳迫芳人

寳迫芳人さん
小学校では、今のところ「情報教育」は教科として位置付けられていなません。しかし、実際には調べ学習などで子どもたちがインターネットやパソコンを使うことは日常的になりつつあり、それに伴って、インターネット上の間違った情報をうのみにしてしまう、悪質なサイトに引っかかってしまう、などのトラブルが発生しています。そこで、開発されたのが、「ネット社会の歩き方」。コンピュータ教育開発センター(CEC)のEスクエアプロジェクトの一環として開発されたもので、所沢市立荒幡小学校の寳迫先生も開発に参加しました。
個人情報の流出、チェーンメール、あぶない出会いなど、インターネットを使用するうえで気をつけなければならないことが、小学生から高校生まで、わかりやすく解説されています。これらの教材を使用した授業の指導事例集も公開されているので、さっそく授業に使ってみたい方にもオススメです。
●エコプラントゲーム(ボードゲーム)
発表者:社団法人環境情報科学センター調査研究室 仁井亮一

仁井亮一さん
化学物質は、私たちの身の回りにあって便利で快適な生活に欠かすことのできないものとなっています。一方で、適切な使用や処分が行われなければ人の健康や環境に悪影響をおよぼすという二面性を持っています。この二面性に対するバランス感覚を育成することを目的として、前環境省とともに開発したのが「エコプラントゲーム」。これは、小学校高学年から中学生を対象にしたもので、経済活動と環境負荷、校外の発生と環境対策について理解することをねらいとしています。

ゲームは、1クラスを5~6班に分け、各班で工場を1月ごと12ヶ月間経営して利益を競います。各班には毎月100万円の投資資金が与えられます。生産高を上げれば儲けも出ますが、環境負荷も上がっていきます。クラス全体の環境負荷が一定の値を超えると公害が発生し、環境対策を怠っていた班は環境浄化のための資金を払わなければなりません。投資資金を生産(=もうけ)と環境対策にどのように振り分けていくかがポイントのゲームです。
●ビオトープ・シミュレーター
発表者:兵庫県人と自然の博物館(岸田隆博 三橋弘宗 嶽山洋志) 株式会社A.R.C.S.(山下義弘)
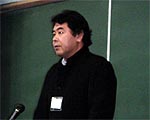
山下義弘さん
最近、自然体験学習の場として「ビオトープ」を設置する学校が増えつつあります。しかし、場所がない、維持が大変、などの理由から設置できない学校もまだまだたくさんあります。そこで開発されたのが、ビオトープ・シミュレーター。

ビオトープをつくろう!
初期画面で、里の学校か、街中の学校かを選択し、学校内のどこにビオトープを設置するかを決めたら、あとは池を作ったり、木を植えたり、植物を植えたりして自由にビオトープを設計します。設計が終れば景観画面に切り替えて、3Dで自分が作ったビオトープを確認。シミュレーションモードに切り替えれば、花が咲いたり、蝶が飛んで来たりなど四季折々の変化を楽しみながら、1年間のバーチャル管理を行うことができます。この過程で、動植物の名前や性質を覚えたり、生物どうしの関係性、食物連鎖、生態系といった自然の営みを学ぶことができるというもの。

自由なデザインで簡単にバーチャルビオトープができる
まだまだたくさんのシミュレーションゲーム教材が紹介されていましたが、最初にも述べたように、やってみると確かに面白い、使えそう!と思うのに、説明を聞くだけでは「なんだかわからない」ものも少なくありません。今回のような発表会や展示会で、ぜひみなさんも体験してみることをオススメします!
取材・構成:学びの場.com
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事














 授業実践リポート
授業実践リポート 食育と授業
食育と授業 教育リサーチ
教育リサーチ




 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望



