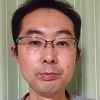『ファミリア』 「家族」とコミュニケーションを築く大切さ
映画は時代を映し出す鏡。時々の社会問題や教育課題がリアルに描かれた映画を観ると、思わず考え込み、共感し、胸を打たれてしまいます。ここでは、そうした上質で旬な映画をピックアップし、作品のテーマに迫っていきます。今回は『ファミリア』をご紹介します。
一番小さな「コミュニティ」である家族
人間が生きていく上で、最初に出会うのが『家族』という『コミュニティ』だ。最も身近で最も大切で、かつ最もひょっとしたら分かり合えない共同体。「ファミリア」はまさにタイトル通り(スペイン語で家族の意味)、そんな家族についての物語だ。しかもこの映画には、さまざまなファミリーが登場する。
まず一つ目は、役所広司扮する父親と吉沢亮扮する息子が織りなす家族。父の誠治は山里深くで、陶器を焼いて暮らしている職人だ。だが焼き物は決して金になるようなものではない。彼の妻は家計を支えるために懸命に働き、そのせいで体調を崩して亡くなった(と誠治は思っている)。一方、ひとり息子の学は一流企業のブランドエンジニアとして活躍中。赴任したアルジェリアで、難民の女性ナディアと出会って結婚した。
そんな学はナディアを連れて日本に戻って来た際に、このまま会社を辞めて、日本で誠治と共に自分も陶器職人として暮らしていきたいという思いを告げる。なんと父思いの優しい息子であろうか。
しかし誠治は学の考えを許さない。ナディアと結婚し、これから素晴らしい未来を築こうとしている息子に、自分と同じような人生を歩んでほしくないと考えたからだ。今のまま一流企業にいれば食うに困るなんてことはない。ナディアに迷惑をかける恐れもないからだ。学はそういった父親の考えを受け入れて再び赴任地のアルジェリアへと戻っていく。
ジャパニーズ・ドリームを信じたブラジル移民たち
もうひとつの家族はブラジル移民の家族。マルコスという男性と彼の幼なじみであり恋人となるエリカを中心とした家族は、家族だけではなくブラジル移民という大きなコミュニティにも焦点があてられる。そもそも彼らが日本に来たのは、ジャパニーズ・ドリームを信じたからだ。マルコスの父がリーダーとなり、日本に行って懸命に働けば金持ちになれると信じたブラジル系の移民たちは、懸命に働いた。しかしリーマン・ショックを皮切りに圧倒的に経済状況が悪くなった日本の会社は、南米の外国人労働者を大量解雇してしまう。
実際にリーマン・ショック以降、失業や生活困窮から日系人は母国へ大量帰国したという話がある。だがマルコスはその状況下でも帰国せずに日本で暮らすことを選択した家族だ。いや、選択の余地すらなく、帰れなかったのかもしれない。なぜならマルコスの父は自分が旗を振って日本に連れてきたことに、大きな責任感じ、投身自殺してしまったからだ。
かくして日本で懸命に生きてきたマルコスだが、様々な差別を受けつつ、低賃金で重労働を押しつけられている。そういった問題もはらみながら、ブラジルのコミュニティでは仲間内でパーティを開いたりしつつ、ポジティブに生きているのだ。
だがそんな中でマルコスを含め、若きブラジル人たちはある状況に追い込まれてしまう。それは同じブラジル人の男が半グレの榎本海斗(MIYAVI)から金を奪ってしまったことだ。もちろん盗んだ男も自分の愛する女性とその子どもに少しでも楽をしてもらいたいという出来心から金を盗んでいた。しかしそのせいで、若き在日ブラジル人が半グレたちの目の敵にされ、次々と悲劇が巻き起こっていく。
一方、在日ブラジル人を目の敵のように追う榎本海斗にもその理由があった。実は榎本は事故で愛する妻と子どもを失っていた。その事故とは酔っていた在日ブラジル人が起こした交通事故。今でも子どもが持っていたと思われる水筒を使っているほど、家族の死を超えられない榎本は、在日ブラジル人全般にその強い悲しみを恨みに変えてぶつけていた。だからこそ執拗なほど、ブラジル人たちを追い詰めていたのだ。
家族のように互いを思い、いたわり合うことの大切さ
こういった様々な家族を背景に抱える人間たちが、それぞれ交わりつつ物語を織り成していく。例えば実父を失っているマルコスは、榎本に追われた自分を助けてくれた誠治をいつしか父のように慕い、陶器の製作を学びたいと言い始める。誠治は誠治で、ある出来事が彼の身に起きた時は、彼の友達がまるで家族のように彼のことを親身になって支えてくれる。そういった支えを経て、最初はマルコスやブラジル系コミュニティに対して、誠治も決して乗り気ではなかったが、半グレとのトラブルを知る内に、誠治もマルコスを助けたいと思うようになっていくのだ。
要は誰しもが家族を愛しみ、その最低限のコミュニティを大切にする。時には家族ではなくても、赤の他人なのに家族のような関わりを持つことにもなる。それは人間の心の中には「相手を思いやる心」が存在するからだ。
だがその「相手を思いやる力」が欠如すると大きなトラブルが起きていく。例えば外国人労働者問題。もともと日本国内だけでは労働者がまかなえないと判断して、海外に向けて門戸を開いたのは日本政府だ。しかし経済的なトラブル後、はたしてその外国人労働者の問題を積極的に解決しているといえるだろうか。相手の立場、状況を少しでもかんがみたら、何かもう少しどうにかならないものなのかと思う。そこには「相手を思いやる力」が欠如しているからだ。
それは誠治の身にも起きる。ネタバレになるから細かいことは言えないが、ある出来事が起きた時の政府側の反応だ。家族としての気持ちを思いやれば、もっともっとやるべきことは多々あるはずである。だがそういった誠治の願いは政府側の意志により、無慈悲にもねじ曲げられる。
半グレの榎本にしたって、家族を失って悔しい気持ちはわかる。でも自分の家族を殺した犯人に向かうならまだしも、同じ民族に向けるというのは、江戸の敵を長崎で討つ…というもの。そんなことをしても亡くなった家族たちの無念さは払えない。ましてや暴力に暴力で対抗したって、何も生まれない。
今の時代に欠如している「相手を思いやる心」
つまりこの映画を見ていると、考えさせられるのは、いかに「相手を思いやれるか」ということなのだ。それは誠治が最終的に取る行動からも、また学ぶが取る行動からも、マルコスらが仲間たちのために取る行動からも、伝わってくるものがある。「相手を思いやる」気持ちが、とても大事なのだ。人間の根源は、元来はそこに根ざすものだからだ。
ちょっと想像してほしい。自分が自分のためだけに生きるだけなら人生は虚しくはないか。自分のためだけなら、食生活だって仕事だってなんだって、ほとんどのことが「いい加減」ですませることができるのではないだろうか。でも例えば好きな人ができたら、美味しいものを食べさせたいと思う。自分の好きなものを紹介したいと思う。そういう思いにあふれるのが家族の原点だ。だから両親は懸命に働くし、どうにか子どもたちを幸せにしたいと思う。子どものためなら、親は多くのことを我慢することができる。そういう「相手を思う」気持ちが、家族だけでなく、多くのコミュニティでも広がれば、「平和」というのは保たれるはずである。
しかし今の世界はむしろ逆になっている。相手を思いやれないから、平気で戦争が起き、様々な争いが起きる。相手を思うことができないということは、コミュニケーションの不足ということにも繋がる。今、どれだけの人がちゃんとコミュニケーションを取っているといえるのか。それは家族という最も小さなコミュニティでも壊れかけているといえる。
電車の中、乳母車に乗った子どもが泣いているのにスマホに夢中でいる父親。家族3人で朝食を取りにカフェに来たのに何も話さず、三様にスマホに向かっている親子。スマホの存在は恐ろしいほど家族を分断しているように感じる。また昔は、近所のおばちゃんやおじちゃんに「危ない」だの「何やってんの」だの、自分の子どもでもないのに怒ってくれた人達がいた。だが今思えばその「注意」には優しさがあった。愛情があった。でも今は自分の子どもにすら怒れない親が増えている。正しく叱ることも社会に子をなじませるための、ひとつのコミュニケーションではないのか。
このコミュニケーションの欠如は一体なんなのだろう。
もちろん他人を思いやったからといっても、誰もがハッビーエンドを迎えるわけではないことも、映画を見ればわかる。それでも「相手を思う」心は大切にすべきなのだ。心のあり方を学ぶためにも。だからこそ、今見るべき「ファミリア」なのだ。今作る意味があったのだろう。是非作品を見て、いろいろなことを考えていただきたい。
- Movie Data
『ファミリア』
監督:成島出 脚本:いながききよたか
出演:役所広司、吉沢亮、サガエルカス、ワケドファジレ、中原丈原、室井滋、アリまらい果、シマダアラン、スミダグスタボ、松重豊、MIYAVI、佐藤浩市ほか
配給:キノフィルムズ
年齢制限:PG12
(C)2022「ファミリア」製作委員会
1月6日(金)より、新宿ピカデリーほか全国ロードショー
- Story
陶器職人の神谷誠治は妻を早くに亡くし、ひとり山里暮らし。そこへアルジェリアに赴任中のひとり息子の学が、難民出身のナディアと結婚、一時帰国した。結婚を機に会社を辞めて、焼き物を継ぎたいと語る学。だが誠治は反対を。一方、隣町の団地に住むブラジル人青年のマルコスは半グレに追われた時に助けてくれた誠治に亡き父の面影を重ねていく。
文:横森文
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

横森 文(よこもり あや)
映画ライター&役者
中学生の頃から映画が大好きになり、休日はひたすら名画座に通い、2本立てなどで映画を見まくっていた。以来、どこかで映画に関わっていたいと思うようになり、いつの間にか映画ライターに。『スクリーン』、『DVD&ブルーレイでーた』、『キネマ旬報』など多数の雑誌に寄稿している。 一方で役者業にも手を染め、主に小劇場で活躍中。“トツゲキ倶楽部”という作・演出を兼ねるユニットを2006年からスタートさせた。
役者としては『Shall we ダンス?』、『スペーストラベラーズ』、『それでもボクはやってない』、『東京家族』等に出演。
2022年4月より、目黒学園で戯曲教室やライター講座を展開。
「教育エッセイ」の最新記事














 教育つれづれ日誌
教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 震災を忘れない
震災を忘れない



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事