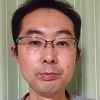『イン・ザ・ハイツ』 トニー賞やグラミー賞を獲得した不朽の名作が完璧な映画に!!
映画は時代を映し出す鏡。時々の社会問題や教育課題がリアルに描かれた映画を観ると、思わず考え込み、共感し、胸を打たれてしまいます。ここでは、そうした上質で旬な映画をピックアップし、作品のテーマに迫っていきます。今回は『イン・ザ・ハイツ』と『竜とそばかすの姫』の2本をご紹介します。
描かれるのはニューヨークのある地域に住む人々の物語
今回、まず紹介するのは『イン・ザ・ハイツ』というミュージカル映画だ。
もともとはブロードウェイのミュージカル。舞台版はトニー賞の作品賞、楽曲賞、振付賞、編曲賞の4冠を獲得しており、さらにグラミー賞のミュージカル・アルバム賞も獲得。傑作との呼び声高い作品だった。
それを映画化した本作は、映画ならではの表現を伴った、とても内容の濃いミュージカル映画に仕上がっている。なぜ内容が濃いと断言するかといえば、『差別』というものに対して真正面からブチ当たり、『差別』があるからこそ生まれるコミュニティのパワーを堂々と描き切った作品だからだ。
舞台となるのはニューヨークのマンハッタン島にあるワシントン・ハイツ。人種のるつぼともいうべきニューヨークは、ある意味、人間の人種に対する差別的感覚がハッキリと現れた街と呼べるかもしれない。例えば中国系アメリカ人が多く住むチャイナタウンがあるかと思えば、イタリア系アメリカ人が住むリトル・イタリーがある。またハーレムと呼べる場所ではアフリカ系アメリカ人が多く住んでいる(ちなみにこのハーレムは以前はオランダ系移民の住居地だった)。またニューヨークでは金持ちが住む場所と貧乏人が住む場所もハッキリと区別されている感があり、それは逆にいえば観光客の安全が補償される場所の限界を示したりもしていた。
実際、80年代に筆者も一度ハーレムに足を踏み入れたことがあるが、アジア人というだけで、来るべき場所ではない感を露骨に感じ、アポロシアターがあるいわゆる観光客もギリギリ訪れることが可能な125丁目より北にはとてもじゃないけど進めなかった覚えがある。
というのもその時はバスに乗ってハーレムに向かったのだが、マンハッタン島を北に進むにつれて、目に見えて街の荒れ方がすさまじくなっていったからだ。戦争でもあったのかといいたくなるほど壊れた、あるいは壊れかけたボロボロのビルが立ち並ぶようになっていき、歩いている人が極端に少なくなっていく。人種もどんどん有色人種へと変わっていく。同じマンハッタン島でもグリニッジ・ビレッジやソーホーなどの街の雰囲気とは明らかに違う。
ここ10年以上、ニューヨークには足を踏み入れていないため、情報不足ではあるが、現在はもう少し安全な地域が広がっているとも聞いている。街は生きているから、常にそこに住む人々の努力で街の表情は変わってくるのだ。
この街をいつか出たいと願う人々
で、舞台となるワシントン・ハイツだが、そこはマンハッタン島の最北に位置している居住区で、155丁目を起点とした約40ブロックにあたるという。もちろん実在する街であり、そこでは道端に置かれたカセットから、アパートの窓から、カーラジオから、常に音楽が聞こえてくる街なのだそう。現在はラテン系の移民が多く住んでいるが、古くからこのあたりは移民の街であり、以前はアイルランド系やイタリア系、ユダヤ系が占めていた。
映画を観る限りでは、本当にラテン系らしい明るさが占める街で、近所との繋がりもしっかりあって、互いに互いを気遣い合いながら生きている。でも経済的に裕福でないことは、街全体的から見てとれる。
映画はここに住む人達の群像劇となっているが、その背景に共通項としてあるのは、この街をいつか出たいという強い思いだ。ワシントン・ハイツを出て祖国に帰りたいと願う者、別の街で夢を追いかけたいと願う者…理由は様々だが、誰もが自分が置かれた状況から脱したいという夢を持っている。
その原因を作っているのが地価の高騰。住み慣れた我が家をやむなく追われる人が増えている経済的危機があり、誰もがこの地に安住するのか、それともどこかで夢を追うのかという葛藤を抱えている状況にあるのだ。
物語の語り部でもあるウスナビ(アンソニー・ラモス)もその選にもれない1人。
彼の夢は生まれ故郷のカリブ海の国に戻って、父の営んでいたBARを再建するということだ。その夢を叶えるために、彼は朝から食料雑貨店を営み、地味にお金を貯めている。
ウスナビには憧れの女性がいる。それがファッション・デザイナーを目指す女性、バネッサ(メリッサ・バレラ)だ。彼女は必死に美容院でネイリストをしながらお金を貯め、ワシントン・ハイツを飛び出し、170ブロック離れた界隈にあるファッション業界で働きたいと願っている。だがそんなステキな夢を、いきなり踏みにじってくるのが、なんと不動産業者。
ある程度のお金を貯めた彼女は、本気でアップタウンに引っ越そうとするのだが、不動産業者は彼女の人種を見ただけで、断ってくるのである。嫌な話だけど、この人種は泥棒系が多いとかいい加減だとか、そういう差別が存在しているからだ。その人種というだけでバネッサのように最初からどうにもならない…ということが現実にあるのだ。
そう、この映画のすごいところは、先程も述べたように素晴らしいラテンの香りがする楽曲がズラリと並んだ、とても楽しいミュージカルでありながら、人種差別など様々な問題に真っ向から取り組んでいるところ。
例えば他にもこんなシーンがある。それはウスナビの親友で、地元のタクシー会社の配車オペレーターをしているベニー(コーリー・ホーキンズ)の元彼女・ニーナ(レスリー・グレイス)がワシントン・ハイツに戻ってくるところから始まる。
プエルトリコ人である彼女は必死に勉強して、現在はこの街を出て、世界最高位の私立総合大学と言われるスタンフォード大学へと通っている。つまりニーナはニューヨークとは大陸を挟んで正反対にある、西海岸の大学に行っているのだ。ところが彼女もその大学で人種差別問題に遭遇する。
寮で暮らす彼女は、同室の友人がアクセサリーを失くした時、真っ先に犯人だと疑われたのである。理由は彼女がプエルトリコ人であり、家も決して裕福とは言えないから。ベニーが働くタクシー会社は、ニーナの父親が営んでいる会社なのだが、なんとそのタクシー会社の敷地を半分売ってまで、娘の学費を作りだしたのだ。しかし現実に西海岸へとやってきた彼女は、人種の壁や東海岸から来ていることも手伝って、全く友人ができず、その孤独さに負けてワシントン・ハイツに戻ることを決め込んでいた。
ところがだ。毎日ちゃんと勉強して有名大学へ通った彼女は、ワシントン・ハイツに住む人間たちから見れば希望の星。だからこそ彼女はそんな地元民からの羨望というプレッシャーも抱え込み、そのせいで大学をドロップアウトしたい欲求もなかなか口に出せずにいるのだ。親切で濃いコミュニティは、時にそういった弊害をも生んでしまう。
この映画を観たらアナタの生き方が変わるかも!?
しかも会社の土地を売ってまで、娘に大学に行かせたいと願う父の思いの根底には、それまでのカリブ海からアメリカへと移り住み苦労した親世代の移民たちの強い願望が絡んでいる。いわゆる自分たちができなかったことを、子供たちにはやらせてあげたい…という思いだ。
こういった世代による理想の生き方の違いなども、この映画ではしっかり描かれていく。
つまり見かけはとても楽しいミュージカルなのだが(往年のミュージカル映画を彷彿とさせるたくさんのシーンもある)、ひと皮剥くとそこには恐ろしいまでのビターな現実がどっかりと根を下ろしている。
移民たちの経緯など歴史的なことも踏まえていれば、切実な経済問題、そしてトランプ大統領により拍車がかかったであろう差別問題などが描かれているため、とてつもなく心に響いてくるのだ。
ネタバレになるのでこれ以上は明かせないが、とにもかくにも驚くべき展開を見せ、最終的には間違いなく大きな感動を与えてくれるのである。
といっても海外に住む気のない人は、この手の差別問題には無頓着を決め込んでいる人も多い。だが、最後までこの映画を見たならば、その考え方は大きく変わるかもしれない。
そのくらい強烈なインパクトがあるからだ。
さらにいうなら、この映画にはアナタ自身の生き方を変えてしまう可能性すら秘めているといえる。それはこの映画は「行動することの素晴らしさ」を訴えるものにもなっているからだ。自分から動かなければ何も変わらない…。その事実は人種問題にさほど関係なく生きている我々日本人にとっても、頭をガツン! と殴られるような衝撃を与えてくれるからだ。
ミュージカルはちょっと苦手という方でも楽しめる要素がふんだんだし、こんな素晴らしい映画を見逃す手はない。
- Movie Data
『イン・ザ・ハイツ』
監督:ジョン・M・チュウ
原作・製作・作詞・作曲:リン=マニュエル・ミランダ
出演:アンソニー・ラモス、コーリー・ホーキンズ、レスリー・グレイス、メリッサ・バレラ、オルガ・メレディスほか
配給:ワーナー・ブラザース映画
7月30日より全国ロードショー
(C)2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved
- Story
ニューヨークの片隅にあるワシントン・ハイツ。祖国を遠く離れたラテン系の人々が多く暮らすこの街は、いつも歌とダンスであふれている。そこで育ったウスナビ、バネッサ、ニーナ、ベニーの4人の若者たちは、それぞれ厳しい現実に直面しながらも夢を追っていた。だが真夏に起きたニューヨーク大停電の夜、彼らの運命は大きく動き出すことに…。
文:横森文
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
子どもに見せたいオススメ映画
『竜とそばかすの姫』
公開からわずか3日間で動員数60万人、興収8億9000万円をあげた大ヒット作
強いメッセージが光る音楽映画
この作品も音楽が非常に重要なポジションを占める映画となっている。ミュージカルとは違うが、とても素晴らしい音楽映画であり、と同時に『イン・ザ・ハイツ』同様、非常に強いメッセージが光る映画だ。
映画の背景にあるのは、誰もが自分のアバターを使って、ネット世界の中で違う人生を歩むことが普通になっている社会。そのネットの中での仮想世界は“U”と呼ばれ、“U”の中では人々は“As(アズ)”と呼ばれる分身となり、その世界を生きることができるのだ。
と聞くと人によっては、何やら遠い未来社会のように感じるかもしれないが、ゲームやネット世界に精通している人であれば、実はもの珍しくは感じないだろう。
例えばゲーム『どうぶつの森』シリーズに代表されるようなコミュニケーション・ゲームをやったことがある人なら、動物の主人公になって生活したり、いろんな人と喋ることはごく普通の事。他にもネットゲームなどには、チャットしながらモンスターと戦うゲームなども普通にある。今できるゲームでも充分に自分とは違う人生を体感できている感触を得られているから、そんなに斬新には思わないはずだ。
ただ“U”の世界が既存のゲームと少し違うのは、視覚や聴覚などもネットのコントロール下に入れてしまうというところ。つまり本人自身がその世界に入り込んだ、ヴァーチャル・リアリティのスーパー版みたいな体感ができるという点だ。
なんの変哲もない子がネットの世界で変身
そんな世界に入ることで変化するのが、主人公である、17歳の女子高校生の内藤鈴。特に美人というわけでもなく、どこというとりえがないからこそ自信が持てず、モヤモヤした人生を送っている。その現実を包み隠さずズバズバ突きつけてくる親友・ヒロちゃんに凹まされることも。そのヒロちゃんからすずは“U”を教えてもらい、アプリをダウンロードするのだ。
自分とは全く異なるタイプの華やかな女性キャラ・ベルとなったすずは、今まで歌いたくても自信がなくて歌えなかった自分から歌える自分へと変わっていく。さらにヒロちゃんのアシストもあって、ベルは“U”の世界で押しも押されぬスターシンガーとなり、たくさんの人々を虜にしていく。
この映画を見ていると自信を持って行動することで、どれだけ人生が変わるかがよくわかる。ちょっとしたことで、眠っていた力を発揮できる可能性を強く感じてしまう。
それは監督である細田守自身が、体験したあることが繋がっているのかもしれない。
細田監督は『時をかける少女』や『サマー・ウォーズ』などで、成功したアニメーション監督のひとりとなっているが、実は若かりし頃、アニメの仕事を辞めようかと思っていたことがある。そんな時に観たのが、ディズニー・アニメーションの『美女と野獣』(91年)だった。この作品にいたく感動した細田監督は、こんな素晴らしいアニメーションを作れるなら仕事を続けてみようと思ったのだそう。その後、様々な仕事で少しずつ認められるようになり、おそらくそれが自信に繋がっていったのだろう。かくして挫折せずにすんだ細田監督は次々と傑作アニメーションを生み出すことに成功したのだ。
この経験が『竜とそばかすの姫』に素晴らしく生きているというわけ。
ちなみに細田監督にとって、恩人ともいうべき『美女と野獣』へのオマージュが、この映画には驚くほどたくさん詰まっている。なにしろ主人公の名は『美女と野獣』と同じで“ベル”だし、“U”世界でお尋ね者扱いされている“竜”は、“ビースト”と呼ばれていたりする。その竜に会いにいく時のベルの出で立ちや、バラが出てきてしまうくだりなど、ありとあらゆるところで『美女と野獣』を彷彿とさせるシーンがあるのだ。それもまた映画好き、アニメーション好きにはたまらないめくばせとなっている。そして『美女と野獣』が美しい愛の物語であり、愛によって成長していく2人の物語であるのと同様、本作も愛と成長の物語として見事な発展を遂げている。ただし『美女と野獣』とはオチのつくポイントは異なるのもこの映画の素晴らしいところだ。
口で言うのは簡単だが、行動するのは難しいという事実
実はすずには、ずっと疑問に思っていることがある。それは自分が幼い頃に事故で亡くなった母の行動だ。母は増水した川の中に取り残された小さな子を助けようと、荒れた川の中に危険も顧みず入っていった。「行かないで!」と泣くすずを残し、「今行かないとあの子が死んでしまうから」と言って。結果、取り残された子どもを助けることができたが、母は亡くなってしまった。
その光景を目の当たりにしたすずの心には、ずっと疑問が渦巻いている。なぜ母はあの子を選んだのか。私と生きる人生ではなく、なぜ危険な川に入っていったのか…と。
それが彼女を縛る鎖のひとつ。彼女の人生を迷わせる要因ともなっている。だが“竜”を彼女が助けたいと思った瞬間、彼女の心の中でその答えが見つかってしまう。いや、明解に疑問が氷解したという言葉での説明はないのだが、ちゃんと伝わる表現となっていて、胸を打つのだ。
そして同時に思い知らされることが、口で言うのは簡単だけど、それを行動で見せるのは大変だということ。困っている人を見て、「可哀想」とか「救ってあげなきゃ」「助けたい」と言うことは誰にだってできる。でも実際に助けるには、とてつもない行動力と決断力、そして勇気が必要となる。そういったことも映画ではしっかりと描かれているのだ。
でも行動しなければ、決して何も解決はしないし、進展もない。自分の信じた道をどう進むべきなのか。信じて行動することの大切さを、この映画は訴えていく。
どうせなら、この映画はすずと同じ世代の、これから何をしていくべきなのか、悩んでいる高校生たちに是非観ていただきたい。行動することが、どれだけ運命を人生を変える力を持っているか、納得できるはずだ。
ちなみに本作でベルのキャラクター・デザインをしているのは、ディズニーのジン・キム。細田監督は2018年にロサンゼルスの映画祭にいった時、『塔の上のラプンツェル』や『ベイマックス』『アナと雪の女王』などを手がけていたキムさんと遭遇。その時にキムさんより「いつか一緒にやりたいね」と言われ、社交辞令で終わらせたくないと、「ぜひお願いしたいです」とプッシュし、今回のタッグに繋げていった。そういった監督の行動力からも、この映画に託された強いメッセージは伝わってくるはずだ。
原作・脚本・監督:細田守
声の出演:中村佳穂、成田凌、染谷将太、玉城ティナ、幾田りら、役所広司、石黒賢、佐藤健ほか
配給:東宝
現在公開中
文:横森文 ※写真・文の無断使用を禁じます。

横森 文(よこもり あや)
映画ライター&役者
中学生の頃から映画が大好きになり、休日はひたすら名画座に通い、2本立てなどで映画を見まくっていた。以来、どこかで映画に関わっていたいと思うようになり、いつの間にか映画ライターに。『スクリーン』、『DVD&ブルーレイでーた』、『キネマ旬報』など多数の雑誌に寄稿している。 一方で役者業にも手を染め、主に小劇場で活躍中。“トツゲキ倶楽部”という作・演出を兼ねるユニットを2006年からスタートさせた。
役者としては『Shall we ダンス?』、『スペーストラベラーズ』、『それでもボクはやってない』、『東京家族』等に出演。
2022年4月より、目黒学園で戯曲教室やライター講座を展開。
「教育エッセイ」の最新記事














 教育つれづれ日誌
教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 震災を忘れない
震災を忘れない



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事