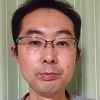『子どもたちをよろしく』 現代の子どもたちを取り巻く闇を描いた人間ドラマ
映画は時代を映し出す鏡。時々の社会問題や教育課題がリアルに描かれた映画を観ると、思わず考え込み、共感し、胸を打たれてしまいます。ここでは、そうした上質で旬な映画をピックアップし、作品のテーマに迫っていきます。今回は『子どもたちをよろしく』と『1917 命をかけた伝令』をご紹介します。
愛を育めない親の元に育った子どもたち
この映画を観終わった時、この映画のタイトル『子どもたちをよろしく』は誰に向けての言葉なのだろう……と、ふと疑問に感じた。
ここに出てくるのは、主に大人たちに翻弄されている3人の子どもたちの話だ。ひとりはデリヘル嬢を営む赤沢優樹菜。その優樹菜の義弟である中学生の赤沢稔。そんな稔の同級生で、実は父親が優樹菜の出迎えをする運転手をしている吉原洋一。この3人のそれぞれの人生が描かれる。
連れ子として赤沢家にやってきた優樹菜は、酔うとDV男に変貌する義父に性暴力を受けている。だがそれだけではない。男にすがる以外に生きる術がない優樹菜の母親は、そんな現実に目をつぶるばかりなのだ。つまり優樹菜には頼れる大人がいないということだ。
そしてその状況は義弟の稔にもあてはまる。稔と父親は血が繋がっているが、父親は稔のことは殴ったりどついたりが日常茶飯事だったりする。まだ中学生、色々なことに敏感な年頃の稔にとって、大人を頼りにできないということはかなりシンドい状況だ。唯一頼れるのは優樹菜だけだが、その彼女がデリヘルをしていると知った稔は、心が乱れに乱れてしまう。
さらに貞夫は重度のギャンブル依存症で、お金があればパチンコにつぎ込んでしまう。それは時に食費や洋一の給食代にまでも及び、何万という金額をアッという間にスッてしまう。しかも勝ったら勝ったで、それをスナックでの飲み代に使ってしまう。ホントに駄目な父親だ。
子どもは親の背中を見て育つというが、大人たちの歪みは子どもにしっかりと伝染していく。途中で洋一の父が感情を爆発させ、お前がいなければもっと良い人生を送っていたと叫んでしまう場面があるのだが、それがどれだけ子どもの心をえぐるか。だって自分の存在が重荷以外の何者でもないなんて、なぜ生きているのかと思いたくなる。
優樹菜の実母もそうだ。夫のDVにあらがえず、子どもたちのことを心配だと口では言うけれど、本気で守る気はサラサラない。
共通しているのは、洋一の父も優樹菜の母も結局は自分のことが一番可愛いタイプの人間だということ。本当に『愛情』のある人はその人を笑顔にさせたいと思う。喜ばせたいと思う。自分よりもまずは相手のことを考える。
そういう観点で見ていると、この映画はホントに『愛情』とは無縁の映画だともいえる。
元文部科学省の人間が企画&プロデュース
実は洋一は毎朝やってくる4人組の同級生たち(その中には稔もいる)に「ゴミオ」と呼ばれ、「臭い」と言われ、転ばされたり木に登らされたり、酷いイジメに遭っている。なぜ稔は洋一をいじめるのか。なぜ他の人も洋一をいじめるのか。それはこの映画ではハッキリとは言及されない。ただ同級生たちは「なんかムカつく」という言葉をくり返す。
だが『愛情』というものを失った人達という観点でいくと、4人組のリーダーである美咲と呼ばれる女子中学生も愛を味わっていないのではないかなと想像してしまう。美咲の家や両親は彼女の誕生日パーティーの場面で登場するが、父親は街の権力者(ゆくゆくは市長になるという話が出ている)で、そのパーティーでは政治家が挨拶し、子どもより大人たちの姿が目立つ。つまり子どもの誕生日をダシにしている感じがまるわかりなのだ。しかもその父親はデリヘルで優樹菜をコールしていたりもする(しかも父親は優樹菜の前だと素直になれるとも言っている)。もちろん両親は美咲を大切に育てているのかもしれないが、実際のところは子どもより建前などを大切に生きているのがにじんで見えてしまう。なるほど愛情の欠如が、いじめでしか相手を認識できないような、とんでもない化け物である美咲という人物を作りあげているのだろうなという想像がつくのだ。
だが最近はこういう余裕のない親が、結構多くなっているように感じる。例えば電車の中で乳母車にのった我が子が泣いているのに、ひたすら乳母車を前後に揺らすだけでスマホを観るほうを優先している父親。ドアが閉まりかけた電車に乳母車ごと突っ込んでくる母親……。この原稿を書いている際にも、パチンコに興じた両親が乳児を放置して死なせたという報道があった。
可愛いだの、心配だの、口先で言うことはいくらだってできる。でも行動がともなわなければ、人は敏感にその嘘を見抜く。嘘の愛情や愛の歪みを感じる。それが反面教師になればいいが、だいたいは残念ながら次世代へと引き継がれる。なぜなら歪んだ愛を受けて育つと、本人は歪んでいることすら気づかないことがあるからだ。自分が大事な人は、相手を愛することが表面的にできたとしても、心底からは無理という人が正直多い気がする。だから両親が無理なら、せめて近くにいる誰かが愛情というものを教えるべきで、それができないと他人を愛せない人間を創りだすことになってしまう。そんな人間形成の闇をこの映画はリアルに描き出している。
なぜリアルかといえば、それはこの映画の企画・統括プロデューサーとして関わったのが、元文部科学省官僚で長らく日本の子どもたちの実態と向き合ってきた寺脇研氏だからであろう。さらに元文部科学省官僚で現在は自主夜間中学のスタッフとして活動する前川喜平氏も企画に参加している。彼らが見聞きしてきたエッセンスがこの映画にはギュッと濃縮されており、正直観ているとやるせなくもなったりするが、目をそむけられない現実がそこにはあるのだ。
実際、洋一の貧困ぶりは並ではないが、今の日本では7人に1人の子が相対的貧困状態にあるのも現実だ。特にひとり親世帯の貧困率は50.8%と最悪レベルとなっているという。そういうところもちゃんと描かれているのが本作なのである。
他者と比較することがネガティブ感情を生む
ところで子どもたちがいう「なんかムカつく」という感情。これは一体なんなのであろうか。この映画を観ていて、何かその感情の発端がわかった気がした。
人は基本的に他者と比較する。人と較べて自分は劣っているのか、あるいは優秀なのか。そんなところから始まって、自分は貧乏なのか金持ちなのか、自分は美しいのかブスなのか……など、ありとあらゆるところで他者と比較する。
中でも日本人は、目立つことをそもそもあまり美徳と考えていない傾向がある。みっともないという言葉で片付けようとする。つまり自分たちと違うものは、みっともない=排除して良いというような感覚があるのだろう。
それがいじめを促進させているのではないだろうか。
他人と比較するからこそ、自分より優れたものを羨ましいと思ったりもする。自分が置かれた世界や状況を甘んじて受け、他者と比較せずに生きていけば、余計なことに振り回されて余計なネガティブな感情を抱え込まずに済むのではないか。そうすれば「なんかムカつく」という他者を蔑視するような感情も、湧かないのではないだろうか。
いずれにしてもそういったことをちゃんと大人が責任を持って子どもたちに教えられるかどうかが問題なのだろう。
無責任に誰かれとなく「子どもたちをよろしく」などと言ってはいけない。子どもを持つことは限りなく責任がつきまとう行為なのだ。それを忘れ、愛を忘れ、子どもを育てたらこうなるのだということを、この映画は静かに心に訴えかける。
- Movie Data
- 『子どもたちをよろしく』
▽コピーライト
子どもたちをよろしく製作運動体
監督・脚本:隅田靖 企画:寺脇研、前川喜平 出演:鎌滝えり、杉田雷麟、椿三期、川瀬陽太、村上淳、有森也実ほか 配給:太秦
- Story
- 北関東のとある街。デリヘルで働く優樹菜は、母親の妙子と義父の辰郎、辰郎の連れ子である稔と4人暮らし。DVの辰郎に稔は不満を感じ、優樹菜に淡い思いを抱いていた。一方、優樹菜が働くデリヘルの運転手・貞夫は、妻に逃げられ重度のギャンブル依存症に。息子の洋一は以前は稔と友人だったが、今は稔のグループが洋一をいじめの標的にしていて……。
文:横森文
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
子どもに見せたいオススメ映画
『1917 命をかけた伝令』
1600人の命を助けるために走れ!!
今年の映画で大きな話題を呼んでいる『1917 命をかけた伝令』。話題の理由は、その撮影の方法にある。119分の上映時間が、全編1カットという、驚異の映像で綴られているからだ。つまり撮影でもスタートしてしまえばそのシーンを撮り終わるまではストップできないし、後から編集でこのシーンはいらないなと思ってもカットすることができない。最初から計算しつくされた映像で、また役者たちはNGなしでキメないといけない舞台劇のような心持ちで望まなければならなかった作品なのだ。
その苦労は想像がつかないが、その末に完成した本作は、観終わった途端にほぼ全員が大きなタメ息をつくほど、主人公たちの旅路に寄り添った、臨場感に満ち溢れた作品となっているのである。
この類まれない臨場感で何を体験するかといえば、『戦争』そのものだ。
戦場にいるかのような圧倒的臨場感
描かれるのは第一次世界大戦。戦争が始まって3年が経過した1917年4月のフランス。前線に近い場所とは思えないようなのんびりとした花畑近くにいる兵士から始まるこの物語は、若きイギリス兵士のスコフィールドとブレイクに下された命令が発端となる。
西部戦線では長大な防衛戦をはさんで、ドイツ軍と連合国軍が睨み合い、激しい消耗戦をくり返していた。だがドイツ軍は撤退とみせかけて罠を仕掛けており、このまま追撃を仕掛ければ相手の思うツボとなり、兵士が壊滅する。そこでスコフィールドとブレイクは翌朝の攻撃中止命令を伝えるため、まだ敗残兵が残る中を必死に駆け抜け、伝令を伝えに最前線へとひた走ることになる。
話は本当にシンプルで、これだけだ。だが話はシンプルでも道は困難。いつどこで敵が待ち構えているかもわからない。ドイツ兵が遺したトラップもある。わんさかいる死体を乗り越えていく彼らが目撃するのは、戦争という地獄だ。
そして彼らが目撃した地獄は、その全編1カット映像の力で、まさにその場に居合わせるような錯覚を観客に味合わせる。兵士が感じる恐怖がダイレクトに観る側にも自然と入り込んでくる。それがこの映画の肝なのだ。
第一次世界大戦の話は歴史で勉強もしているし、知識としては知っている。戦争の話は祖父や祖母から第二次世界大戦の話を聞いたという人もいるだろう。けれどもそこで知ったことはあくまでも知識であり、体験ではない。映画というツールは、擬似体験をさせてくれる。他人の体験を自分のように感じることができる。つまり戦争というものはどういうものなのか。どんなことが起きるのか。どんなメンタルになってしまうのか。それを嫌というほど、この映画を観て味わうことになる。だから観た後は大きな疲労感に包まれ、タメ息のひとつもつきたくなるのだ。
この映画は中学生以上に是非観てほしい。今の子どもたちは、ゲームなどで体験している分、この映像を観てもさほど驚きはないかもしれない。しかしながら戦争がどんな無残なことをもたらすかは、この映画を見れば身に染みるはずである。だからこそ戦争はしてはならないということを痛切に感じるはずである。
アカデミー賞に作品賞を含む10部門でノミネートされたのも、伊達ではないのだ。
アンドリュー・スコット、コリン・ファース、
ベネディクト・カンバーバッヂほか 配給:東宝東和
(C)2019 Universal Pictures and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.
文:横森文 ※写真・文の無断使用を禁じます。

横森 文(よこもり あや)
映画ライター&役者
中学生の頃から映画が大好きになり、休日はひたすら名画座に通い、2本立てなどで映画を見まくっていた。以来、どこかで映画に関わっていたいと思うようになり、いつの間にか映画ライターに。『スクリーン』、『DVD&ブルーレイでーた』、『キネマ旬報』など多数の雑誌に寄稿している。 一方で役者業にも手を染め、主に小劇場で活躍中。“トツゲキ倶楽部”という作・演出を兼ねるユニットを2006年からスタートさせた。
役者としては『Shall we ダンス?』、『スペーストラベラーズ』、『それでもボクはやってない』、『東京家族』等に出演。
2022年4月より、目黒学園で戯曲教室やライター講座を展開。
「教育エッセイ」の最新記事














 教育つれづれ日誌
教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス
アグネスの教育アドバイス 震災を忘れない
震災を忘れない



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事